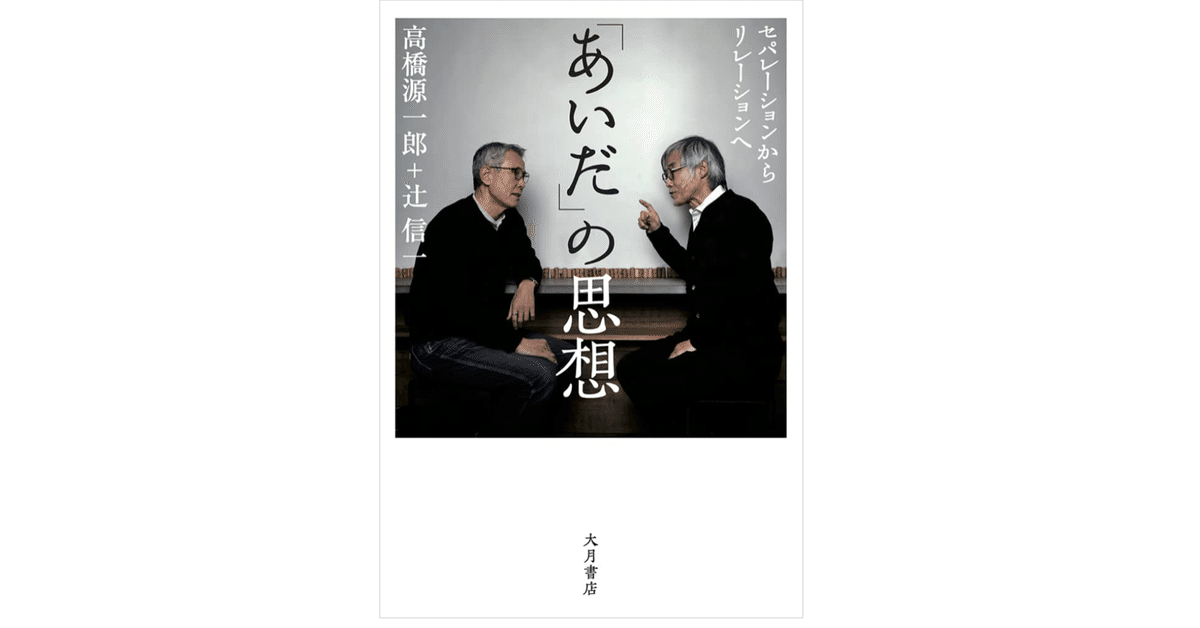
高橋源一郎+辻信一 『「あいだ」の思想/セパレーションからリレーションへ』
☆mediopos-2412 2021.6.24
すべては関係性のもとにあり
関係性を離れて存在するものはない
ひととひとの「あいだ」も
ひとと自然の「あいだ」も
ひとと世界の「あいだ」も
すべては関係性を離れては存在できない
しかし関係性そのものは
個別のものがあるからこそ生まれる
すべてが融合した状態においては
関係性そのものが生まれ得ない
「あいだ」の思想は
「分離」というプロセスゆえに
「つながり」のあり方を模索しようとする
依存と自立も
その前提にあるのは分離であり
個々の「つながり」方において
さまざまな有り様が生まれてくる
そのかたちのひとつとしてとらえることができる
ひとが生まれ育っていくということは
子どもが親から離れていくように
「分離」へのプロセスでもあり
そのうえであらたな「つながり」がつくられていく
「分離」がうまくなされないとき
「依存」のネガティブな側面が問題となり
過剰なまでの「分離」がなされるとき
「自立」がネガティブな側面を生むこともある
その「つながり」における
一人ひとりの「自由」のあり方に
「あいだ」からの自由を求める極と
「あいだ」への自由を求める極という
二つの極を考えることができる
「あいだ」からの自由を求めるのは
その「あいだ」において
ネガティブなものを見出し
「あいだ」への自由をもとめるのは
「つながり」において
ポジティブなものを見出すからだ
近代という時代は
とりわけ「分離」のプロセスの時代であり
そこで生まれてきたさまざまな
ネガティブな諸問題ゆえに
その「つながり」のあり方が
見直され始めているのだといえる
そして
あらたな「つながり」が模索される際は
「つながる」前提となっている
個そのものの有り様が見直される必要がある
そのとき
「人間、時間、空間、世間、仲間、中間、
居間、間柄、間合い、そして間という」
日本語特有の「あいだ(間)」において成立する
個とその関係性の可能性に目を向けることは
新たな「つながり」への視点を開くことにもつながる
本書では特に示唆されていないが
「あいだ」と相性がよさそうなのは
まさに関係性の宗教である仏教が示唆している
「中」というコンセプトでもある
依存も自立も
偏した極にあるとき
「中」であることはできない
自由もまた同様である
セパレーションもリレーションも
「中」であることで
それぞれの役割を果たすことが可能となる
「中」は動かない中心ではなく
動的な平衡としての統合力でもあるのだから
■高橋源一郎+辻信一
『「あいだ」の思想/セパレーションからリレーションへ』
(大月書店 2021.6)
(辻信一)
「世界には今、世界観の大転換が起こりつつあるとぼくは思っている。それは人と人との、人と自然との「あいだ」を隔てていた「分離(セパレーション)」を超えて、「つながり(リレーション)」へ向かう流れだ。(…)
国境をはじめとした種々の人為的な壁を越えてみるみるうちに世界順に広がったコロナ禍は、一方で、すでに着々と信仰してきた分断、格差、差別などを深刻化させることにもなった。しかし、だからこそ、世界のあちこちで近年沸き起こりつつあった「セパレーションからリレーションへ」の転換もまた、人々の中でより切実性と現実性を増しているようだ。人々はそれぞれの社会的な文脈の中で、さまざまな表現を通じて、共同の場としての社会、関係性としての生命、相互依存のネットワークとしてのコミュニティ、関係性へと開かれた人間、そして利己を超えた自分を希求している。「あいだ」をめぐるぼくたちの対話は、こうした世界史的なプロセスについての観察であり、思索である、と言えるだろう。
本書が「あいだ」という、一見あまりにも日常的でありきたりの日本語に秘められた豊かな可能性に、読者が思い当たるきっかけとなればうれしい。それは、和辻哲郎が『風土』で論じ、木村敏が『あいだ』や『人と人の間』で論じ、オギュスタン・ベルクが『風土の日本』で論じてきた哲学的テーマだ。それは、人間、時間、空間、世間、仲間、中間、居間、間柄、間合い、そして間というキーワードの中にも生きている。「あいだ」という概念の汎用性、その広さと深さ、そして豊かさにはほとんど限りがないと思えるほどだ。」
「われら近代人は長い間、西洋文明の中で育まれ、世界中に浸透した、利己的で、貪欲で、競争的で、疑い深く、暴力的な人間像を各自の意識の底部に住まわせてきた。ホッブズの「万人の万人に対する戦い」から、リチャード・ドーキンスの「利己的な遺伝子」に至る、暗く悲観的な性悪説が、現代世界の主流である経済学や政治学を支えている。そこでは、ホモ・サピエンスの「サピエンス」は「ずる賢さ」としての知へと貶められている。一方、ルソーに代表される性善説は、「楽観主義」「ロマンチシズム」「非現実主義」として、「幼さ」や「女々しさ」、「ナイーブさ」として批判や嘲笑に晒されることが多かった。
どうやら我々はいつのまにか、信じたくないことを信じさせられて、しまいには、そう信じることを自分が望んだと信じてしまったようなのだ。今や「知的」であることと、シニカルであることは切っても切れない関係にあるらしい。世界中にさまざまな「陰謀説」がはびこるのも無理はない。環境活動や社会変革運動の中にさえ、性悪説やシニシズムからくる絶望感が広がっている。
こうした自己否定の泥沼こそ、分離の物語が行き着いた場所だ。「進歩」と「発展」によって、地域、コミュニティ、自然生態系といった制約から一つずつ人間が解き放たれ、〝自由〟になって飛び立っていくという物語の結末----言い換えれば、「人間」ということばの「間」を取り除いていったことの結果だ。その果てに、人類はいよいよ存亡の危機に立たされている。
世界各地でベストセラーとなっている「ヒューマンカインド----希望の人類史」が教える通り、人間存在の本質を「愛」「親切」「友情」「助け合い」「信頼」といった関係性に見出す新しい時代の性善説が、今、生物学や人類学をはじめとしたさまざまな分野で勃興している。「あいだ」という非西洋近代的な概念の井戸から汲み出される思想が、「分離からつながりへ」の転換という人類史的な事業に寄与する可能性をぼくは信じ始めている。」
「ぼくはこれからは「自由」ということばを二通りに定義する必要があると思っています。一つ目はこれまで見てきたような、「あいだ」からの自由、「反・あいだ」としての自由です。それに対して、二番目の自由は、「あいだ」への自由。
(…)
これまで世界を席巻してきた一番目の自由は、自然生態系との関係、故郷との関係、コミュニティとの関係といったさまざまな「間柄」を断ち切って、そこから自由になることを目指してきた。つまり。「あいだ」を壊す自由です。それに対して、「あいだ」をつくり、育み、更新し、豊かにしていく二番目の自由があって、それがこれからの世界でとても大切な役割を果たすことになる、と考えたいんです。前者をファスト的な自由、後者をスローな自由、とも言えそうです。
とはいえ、「あいだ」からの自由を全面否定することはもちろんできない。やっぱり、どうしたって、困った関係性や断ち切るべき間柄はあるわけですから。そこでも問題なのは、「あいだ」からの自由と「あいだへの自由の、一方が個人主義的な自立」で、他方が前近代的で集団主義的な「依存」だとする二律背反の考え方だと思う。そもそも純粋の「自立」なんてあり得ないわけで、一つの関係から自由になるときには、必ず別の関係へと歩み出ているわけなんですよね。「自立か、依存か」という二元論じゃなくて、自立と依存とが絡み合った、さまざまな関係性の織物の中に生きている、という認識が基本でしょう。その基本さえなくなっているなら、まずそれを取り戻すことから、ですね。
中島岳志さんは、リベラリズムが、もともとカトリックとプロテスタントの悲惨な宗教戦争の末に生まれた宗教的寛容の原理から生まれたと言います。戦争「からの自由」は、同時に寛容「への自由」だったわけです。中島さんがよく依拠するエドマンド・バークも、制約や節度のないところに自由はない、と言っていた。先ほどのデニーンによれば、これまで支配的だった自由主義の自由は、本質的に「反・文化」なんです。文化とはさまざまな関係性で織りあげられた織物のようなものですから、その関係性を断ち切る自由というのは、反・文化にならざるを得ない。デニーンも保守思想家ですが、「反・自由」ではないんです。彼の本の最後の一説で、自由主義の後の「より深い自由」を創造し、打ち立てるべきことを彼は訴えている。それが人間にふさわしいほんとうの自由を証し立てることになる、と。その自由は、新しい文化と経済を創るための実践の中から生まれる。そして、その経済と文化の軸になるのは、家庭の手仕事と市民の公共生活だ、と。
ぼくも、「あいだ」への自由への動きが、今後、一種の文化運動になっていくんじゃないかと思っています.断ち切られてきた関係性を再発見したり、再生したり、つくり直したりして、共生の文化を創造する。ぼくは活動家として、この文化運動がエコロジー運動と一体のものとして展開される必要がある、と思っています。」
