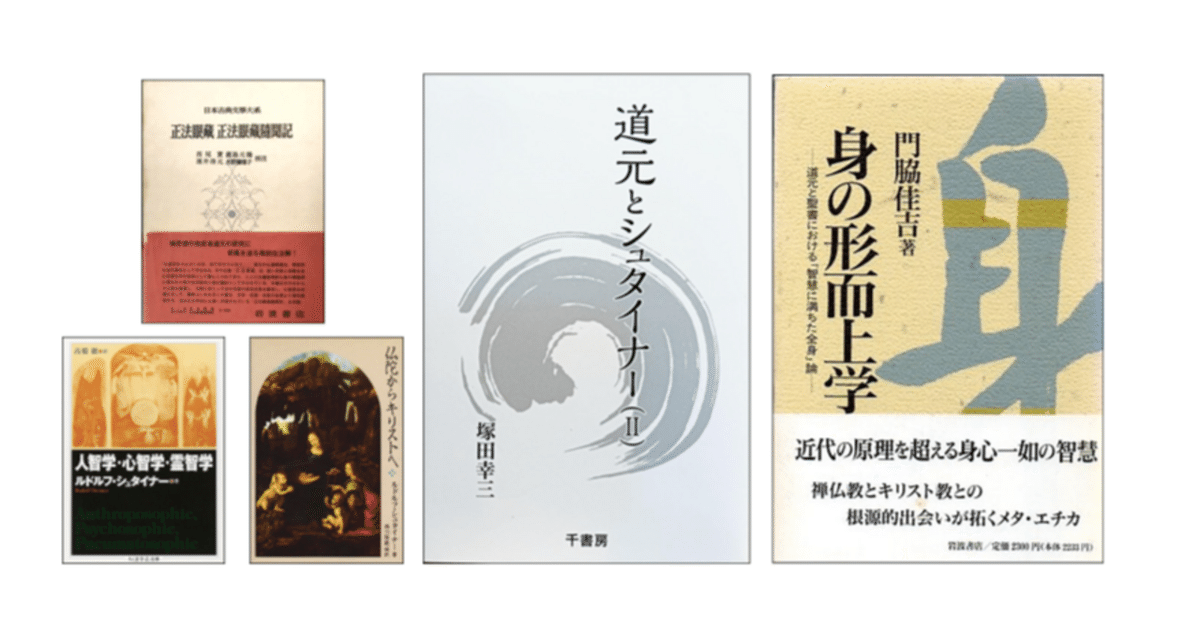
塚田幸三『道元とシュタイナー(Ⅱ)』/門脇佳吉『身の形而上学 道元と聖書における智慧に満ちた全身論』
☆mediopos3567(2024.8.25)
塚田幸三はルドルフ・シュタイナーを
道元・妙好人・池田晶子などと比較した著書を書かれているが
先日久々『道元とシュタイナー(Ⅱ)』という著書を見つけた
以前刊行されていた『道元とシュタイナー』(水声社)の続編であり
道元の「身心脱落・脱落身心」等について示唆されている
シュタイナーは一九一一年の講演で
「今日の霊学の内容は、浄飯王の子である菩薩が
仏陀となった時に説いた東洋の霊智と変わるところはありません」
と述べているが
いうまでもなくブッダの時代の後
キリスト事件が起こり
その衝動を通じ
人類は仏教とキリスト教の融合を経験しているが
人智学もそれを推し進める象徴的な動きでもあるだろう
ちなみに仏教においては
輪廻は無明から脱していないことになるが
道元においても
またシュタイナーにおいても
輪廻は否定的な意味でとらえられてはいない
キリスト事件において重要なのが
イエスにキリストが降りて「人の子」
つまり人間として身体をもち
死の後に復活したということであるように
そこでは身体が重要な鍵となっている
シュタイナーは
「なぜ私たちは最高の満足と最高の浄福を
受けとれるはずの天国にいながら、
あたかも牢獄の中に閉じ込められているかのように感じるのか
という疑問に対して、それは私たちの中に受肉している存在が
それほどに小さいからである、そのことに気づけば
私たちはさらなる地上生活を求めざるを得なくなる」という
道元もまた
「この法は、人人の分上にゆたかにそなわりといえども、
いまだ修行せざるにはあらわれず、証すせざるにはうることなし」
(「弁道話」)といい
自他力一如の身心脱落・脱落身心を説いている
仏教的な輪廻を脱する「解脱」ではなく
「身心一如」こそが重要なのである
そのテーマに関連して
禅とキリスト教を比較研究した神学者・宗教学者である
門脇佳吉(1926/1/6-2017/7/27)の
『身の形而上学』(1994)という
「道元と聖書における智慧に満ちた全身論」での示唆を
あわせてみておきたい
門脇佳吉は西洋にも智慧の思想の伝統はあったが
精神に宿る智慧であったため
「身心を完全に統一して「身」になしうるものではない」とし
「現代人の身心は合理主義の見えざる圧迫のもとに
分離しているにもかかわらず、精神に宿る智慧では、
この身心分離の深傷を医す力を所有していない」ため
「智慧に満ちた全身」としての
「身の形而上学(メタ・エチカ)」の思想を通じ
道元の『正法眼蔵』と同様に
聖書を宗教体験の書と解し
「人間と自然との宇宙論的一体性」
つまり「身心一如」を示唆している
道元が説いたように
仏道を学ぶとは「自己をならふ」ことであり
自己とは「尽十方世界真実人体」
(尽十方世界がそのまま真実人体である)という事実を
身体で実証していくことである
その身体とは
私たちのだれもが生きて死ぬ「生身」としての
「生死去来真実身体」だが
道元は「只管打坐」によって
世界と一である「真実人体」を
道の「活き」に満たされた身心一如であるべく
「證悟」することを説く
「自己をならふ」こと
そのために身心一如として生き
「智慧に満ちた全身」となること
シュタイナーの霊的認識の獲得も
たんなる知識ではなく
「智慧に満ちた全身」へ向けての
身心一如を示唆しているのだといえる
■塚田幸三『道元とシュタイナー(Ⅱ)』(千書房 2024/2)
■門脇佳吉『身の形而上学 道元と聖書における智慧に満ちた全身論』(岩波書店 1994/5)
■道元『日本古典文学大系 81 正法眼藏/正法眼蔵随記』(岩波書店 1965/12)
■ルドルフ・シュタイナー (西川隆範訳)『仏陀からキリストへ』(水声社 1991/5)
■ルドルフ・シュタイナー (高橋巖訳)『人智学・心智学・霊智学』(ちくま学芸文庫 2007/10)
**(塚田幸三『道元とシュタイナー(Ⅱ)』〜「まえがき」より)
*「道元もシュタイナーもいわゆる地上天国の建設を目指したわけではありません。地上天国はすでに実現している、というのが二人の立場です。 もっとも地上天国という言葉には矛盾があります。地上は天国ではないからこそ地上なのであって、それが天国になればもはや地上ではなくなってしまいます。泥水が真水になれば、もはや泥水ではありません。 釈尊が釈尊となって最初に説いたとされる仏教の根本教説・四諦――苦諦(人生は苦であるという真理)・集諦(苦の原因に関する真理)・滅諦(苦を滅した悟りに関する真理)・道諦(悟りに至る修行方法に関する真理)――に照らしても、その第一の苦諦が解消されてしまったら仏教は成り立たないでしょう。
また、仏道ないし宗教は知的営為ではない、という点でも道元とシュタイナーの認識は一致しています。重要なのは、難解な教義や堅牢な教団組織や壮麗な建物などではなく、いわゆる生きた信仰だというのです。
実は、それこそが「仏道をならうというは自己をならうなり」という道元の自己の立場の生命だと思われます。シュタイナーはさらに、今日求められているのは一人ひとりが従来のような師弟関係を結ぶことなく独自に歩むことのできる修行の道、誰でもまたひとりでも日常生活を営みながら取り組むことのできる行法だとして、西洋で秘儀とされてきた伝統的行法を著作や講演を通じて広く一般に公開しました。道元も和文による大部の『正法眼蔵』を撰述し、そのお蔭で現代の私たちもその教えに直に触れることができます。 本書はそのような言わば今日的な自己の立場に立って、シュタイナーを通して道元に対する理解を深め、またそうすることで併せてシュタイナーに対する理解も深めようとするささやかな試みです。」
**(塚田幸三『道元とシュタイナー(Ⅱ)』〜「第四章 「脱落身心」考」 四 脱落身心と歴史と自然法則より)
*「シュタイナーは一九一一年に「今日の霊学の内容は、浄飯王の子である菩薩が仏陀となった時に説いた東洋の霊智と変わるところはありません」(『仏陀からキリストへ』水声社)と述べています。これは道元の立場と同じです。
しかし、シュタイナーと道元には大きな違いがあります。それは、今日、人類は仏教とキリスト教の融合を経験しつつあるという、次のようなシュタイナーの驚くべき認識によります。——今日、二つの生命の流れが作用している。一つは智の流れ、すなわち仏陀の流れで、それは智と良心と平和の崇高な教えであり、その教えを全人類の心の中に浸透させるために必要になってくるのがキリスト衝動である。それに対して、第二の流れはキリストの流れで、それは審美的感情と洞察力によって人類を智かた徳へと導くものであり、そのキリスト衝動の最も偉大な師は弥勒菩薩である。彼は釈迦が悟りを開いてから五千年後、今から三千年後に弥勒仏になるまで何度も地上に受肉する。(シュタイナーが唱える)人智学の使命は諸宗教の統合であり、今日、その一つの型を仏教に、もう一つの型をキリスト教に見出すことができる。時代が進むにつれ仏陀とキリストが私たちの心の中で結びつくように、様々な宗教が結びついて行く。このような人類の霊的進化の過程において、諸文化・諸事象の理解を促すところに人智学の必要性がある。
シュタイナーは、「私たちは本来、いつでも天国の中で生きているのだ!」「不幸のどん底にいるときでさえ、そう言えなければならない」「この地上天国」と述べています(『人智学・心智学・霊智学』ちくま学芸文庫)。
この地上天国こそ、身心脱落・脱落身心の道元の世界だと思われます。それは、「この法は、人人の分上にゆたかにそなわりといえども、いまだ修行せざるにはあらわれず、証すせざるにはうることなし」(「弁道話」)という。修証一等の立場であり、自力・他力ということで言えば自他力一如の立場とも言えるでしょう。
シュタイナーは、なぜ私たちは最高の満足と最高の浄福を受けとれるはずの天国にいながら、あたかも牢獄の中に閉じ込められているかのように感じるのかという疑問に対して、それは私たちの中に受肉している存在がそれほどに小さいからである、そのことに気づけば私たちはさらなる地上生活を求めざるを得なくなる、と述べています。
道元のまた繰り返し輪廻に言及していますが、特筆すべきはそれが否定的な意味においてではなく、肯定的な意味においてであるという点です。それを踏まえて初めて、「おおよそ心に正信おこらば、修行し参学すべし。しかあらずば、しばらくやむべし。むかし(前世)より法のうるおいなきことをうらみよ」(「弁道話」)という言葉に納得が行き、道元の慈悲心を感じることができるものと思います。では、正信が起こらない人はどうすればよいのでしょうか。
シュタイナーは、肉体に閉じ込められた感覚的で心理学的な魂の領域から、超感覚的な霊の領域に進む必要があること、それには霊視・霊聴・霊的合一という段階があることを述べていますが、それは本当の自分、自分の本性を知るということです。道元も「仏道をならうというは、自己をならうなり」(「現状公案」)と述べていました。」
**(門脇佳吉『身の形而上学』〜「前書き」より)
*「本書「身の形而上学」では生態学的地球環境破壊をもたらす元凶・合理主義を克服する方途を示そうと思う。(・・・)われわれは、近代合理主義の元凶である理性・悟性を超え、さらに理性・悟性も包摂・統合する智慧にまで至ろうとする。西洋にも、プラトンのソフィアやトマスのサピエンチアなど、智慧の思想の伝統はあった。しかしそれらは精神に宿る智慧であるから、(・・・)身心を完全に統一して「身」になしうるものではない。現代人の身心は合理主義の見えざる圧迫のもとに分離しているにもかかわらず、精神に宿る智慧では、この身心分離の深傷を医す力(デュナミス)を所有していないのである。その上、「身」によってしか宇宙との一体感を快復しえないから、西洋的な智慧は近代の超克の原動力たりえないことは明らかである。
それに対して「身の形而上学(メタ・エチカ)」は神の霊とか仏法とか、メタ・エチカの「活き」によって身心一如を現成させるだけでなく、「智慧に満ちた全身」の思想を展開し、ポストモダンの新しい地平を切り拓こうと模索する現代人に、近代超克の方途を示し、未来げの展望を与えうるものと思う。
本書では創世記一章—二章を啓示の書とは取らない。むしろ、道元の『正法眼蔵』と同様に、宗教体験を表現したテキストと解する。啓示の書と取れば、ユダヤ・キリスト教の信仰を前提とするから、『正法眼蔵』と同じ次元に属さないテキストとなる。しかし、宗教体験の書と解するなら、『正法眼蔵』と比較しうる地平が拓ける。『正法眼蔵』の宗教体験と創世記のそれとは、その内容において非常に相違しているが、「智慧に満ちた全身」と、人間と自然との宇宙論的一体性を根拠づける点で共通していることは、本書の論究によって明らかになるであろう。」
*「**(門脇佳吉『身の形而上学』〜「第四章道元の「真実人体 2 悟りは身で得る」」より)
*「道元の心身一如を最もよく端的に表しているのは、『正法眼蔵随聞記』(三)の次の教えであろう。道元は「得道(本当の悟りをうる)は心で得るのか、身で得るのか」という問いに次のように教える。
仏教の他の宗派でも心身一如だから身をもって得ると言うが、なお「一如のゆえに」と付け加える。本当に身で得ることは確かではない。しかし禅宗では心身ともに得るとなる。そして、道元はさらに説く。
「心を放下して、知見解会を捨てる時、得るなり。見色名心、聞声悟道ごときも、なほ身を得るなり。しかれば心の念慮知見を一向に捨て、只管打坐すれば、今少し道は親しみ得るなり。しかれば、道を得ることは、正しく身をもて得るなり。これによりて、坐を専らにすべしと覚ゆるなり。」
道元の心身一如は他の宗派と根本的に相違する。他の宗派では悟りは心でするもので、心身は一如だから、身を悟るという立場をとる。道元の立場は次の二つの点で他宗派とは異なる。第一に、「一如のゆえに」という但し書きがなく、端的に身が悟る。第二に、悟るためには心を放下しなければならないから、心で悟るというよりは、第一義的に身で悟るのである。この場合、心が滅却されるわけではない。『身心学道』の前半では心をもってどのように道を学ぶかを述べているからである。心で充分道を学んだ上で心を放下して只管打坐すべきことを教えるのである。だから、心で学んだことは身学道の中で生きていると言えるだろう。いずれにしてもこの第二の主張は極めて道元的であり。道元独自の思想である。道元にとって證悟は何かの真理を対象的に悟ることではない。道の「活(はらたら)き」(本證とも呼ばれる)はもともと全宇宙に遍満し、修行者に内在し、坐禅させている。この本證に生かされて坐ることが本證の主体化でり、悟りを我が身に実現することである。この根本思想から「坐すなわち仏行なり」という思想が生まれる。また、歴代の仏祖から仏祖へ、祖師から祖師へ正伝されるのは心で悟った仏法ではなく、「兀坐」(ごつごつとした絶対の行)なのである。さらに本当に得道した人(仏)は、自分が仏(悟った人)であると覚知することをせず、むしろ行ずることによって身で「仏を證しもてゆく」ことに専念する。
この道元の徹底した身心一如論は、「道の形而上学」の観点から省察するとき、彼の立場がより鮮明になり、聖書の身体観との類似性が浮き彫りにされてくる。それは『身心学道』を読めばわかる。この巻で道元が主張することをまとめれば、次のようになる。仏道を学ぶとは「自己をならふ」ことである。その自己とは「尽十方世界真実人体」(尽十方世界がそのまま真実人体であること)を言う。従って、仏道とはこの「尽十方世界真実人体」の事実を身体で実証していくことである。
ふつう私たちはデカルトがそうしたように、自己を中心に据えて自分の身体を対象化して見るから、身体を限定された空間を占める物体とみる。そして世界を対象化して眺め、自分と世界は別のものと見る。ところが、道元は万物の根源である道(道元は仏の御いのちとも言う)から世界と身体を観る。道から観るためには、自己中心性を完全に捨て、道の「活き」と一つにならねばならない。そのために道元は上に引用したように、「心の念慮知見を一向捨てて只管打坐すれば、今少し道は親しみ得るなり」と説くのである。このように只管打坐する身体が「真実人体」なのであると説く。私たちの身体も世界も、道の「活き」によって生かされるから、道の「活き」の観点から観ると身体と世界は一である。従って、道の「活き」と一つになって只管打坐することは、世界と身体とが道の「活き」によって一である事実を身体で「実証」することなのである。世界と一である身体は、身心の二元論を超越した身体、端的に一なる身体である。それは道の「活き」によって統一されるから、形而上学的統一である。また、道元は「真実身体」を「生死去来真実身体」と言っているから、この「真実身体」は生死する「生身」の私たち一人一人を指す。しかも世界と一つであるような「真実身体」こそ道の統一力によって全人類とも一つであるような身体であることは間違いない。このような「真実人体」は道の「活き」に満たされ、充実した生ま身であるから、それは正しく「身」という日本語によって表現されるのに適しいと言わなければならない。
このように考察してくると、道元の身体観は、聖書の身体観と非常に類似していることがわかる。両者の類似をまとめると次の四点になる。①両者は人間が煩悩または原罪に苛まれる限り、身心は分裂しがちであるが、道の「活き」に満たされるとき、身心が端的に一に成る。従って、両者とも「身」と呼ばれるのに最も適しい。②従って身心の統一は哲学的領域の一致ではなく、神の霊、あるいは道(仏の御いのち)の「活き」による宗教的領域における端的な「一」である。③「真の身体」は個でありながら人類全体である。④両者とも形相・質料・存在の形而上学的カテゴリーで統一されるのではなく、道の形而上学的「活き」によって統一されるから、形而上学的一致説である。
両者のこのような類似性は、禅とキリスト教がともに道の宗教であることに由来することは言うまでもない。」
