
N°1 フランコフォニー文学の旗手、ファビエンヌ・カノールの代表作 『腐葉土』
今回は2016年にフランス・ガリマール社から刊行されたファビエンヌ・カノール著『腐葉土』の紹介です。
私がパリ大学で文学を専攻していた頃、授業の中でたまたま出会ったのが、この作品でした。まだフランス語で作品を読むことさえ必死だった当時、その「フランス語」の概念を覆すようなエクリチュールに頭を思い切り撃たれたような感覚を受けたのを鮮明に覚えています。
ショッキングで、詩的な激しさという魔力を持った作者渾身の一冊です。

キーワード
ポストコロニアル、アフリカ、アイデンティティ、人種差別問題、フェミニズム、移民、オラリティ
基本情報
Humus(腐葉土)
Gallimard より2016年刊行
著者紹介
ファビエンヌ・カノール(Fabienne Kanor)
マルティニーク出身の両親の元、1970年にフランスのオルレアンに生まれる。文学・社会学を学びジャーナリストとして複数のラジオ局に勤めた後、ドキュメンタリー映画制作を始める。2003年より作家として活動しており、二作品目のHumusは優れたフランコフォニー文学作品に贈られるRFO賞を2007年に受賞。英語とイタリア語に翻訳されている。これまで6作品がフランスで出版されている。現在はアメリカを活動の拠点とし、ルイジアナ州立大学でフランコフォニー文学を教えている。
内容要約
この物語は、作者ファビエンヌ・カノールがナント国立文書館で目にしたある文書から始まる。1774年、黒人奴隷船の船長が航海の最中に残した日誌である。そこに書かれていたのは、奴隷となった十四人の女性が海の中へ一息に飛び込み、そのうち何名かは鮫の餌食となり、八人の「損失」があった、という悲惨な事件についての簡潔な報告であった。何の前触れもなく囚われた女性たちは、名を与えられず、故郷を再び目にすることもなく、その存在を語られることもなく、歴史の闇へ葬られた。カノールはこの女性たちに声を再び与えることで、このたった数行の航海文書に現れていない「私」の物語を、彼女たち自身の言葉で語らせている。奴隷たちの呻き、声にならない叫び、死者への追想、海の咆哮、はたまた奴隷船の船員たちが故郷を想う唄…。様々な声や音に満ちた、女性たちの祈りにも似た語りの物語である。そして追憶の物語は時を超え、作者自身の面影を纏った現代の「私」に語りのバトンが渡される。
各章で語る女性たちは、生まれ育った場所も言葉も様々である。語り手たちの生きていた場所、名前、輸送された場所は具体的に記されていない。この匿名性の中でも、女性たちは自らのアイデンティティを探り続けている。作者は奴隷貿易という行為を改めて鮮やかに屈託なく読者の目につきつけるだけでなく、現代に生きる私たちと現代社会との紛れもない繋がりに目を向けさせる。
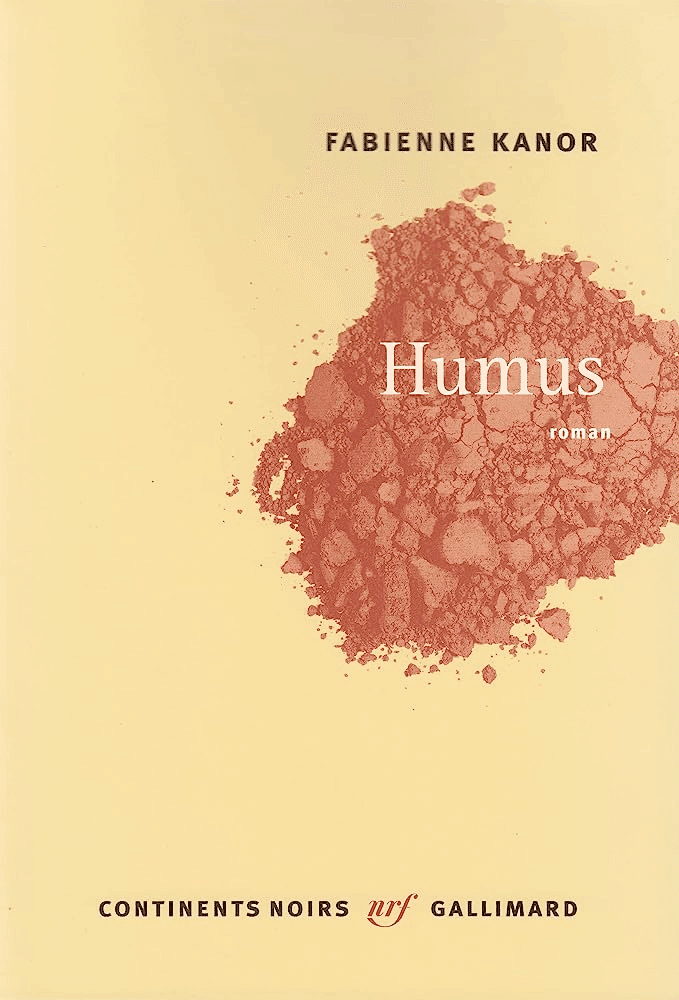
目次
序章 p.11-15
第1章 啞女 p.17-28
第2章 老女 p.29-56
第3章 奴隷女 p.57-78
第4章 女戦士 p.79-96
第5章 白の女 p.97-124
第6章 双子姉妹 p.125-140
第7章 雇われ女 p.141-154
第8章 少女 p.155-166
第9章 王妃 p.167-190
第10章 彷徨う女 p.191-216
第11章 母 p.217-228
第12章 遺された女 p.229-249
各章のあらすじ
第1章「啞女」
まだ幼く無垢な語り手は、ある日突然捕まり、あまりの衝撃に声を失ってしまう。故郷も家族も自分の名前すら分からない。別の商人に売られた後、海へ航海にでると他の奴隷たちと一緒に身投げをする。間一髪サメの牙を逃れ引き揚げられた少女は全ての希望が消えたことを悟る。がむしゃらに自分の名前を探していたある日、「世界を歩く者」という自分のアイデンティティを見出す。新しい主人と共にナントに到着した少女は、屋根裏への階段を上りながら船倉から海へ繋がる昇降口を思い出す。幼い語り手の拙い言葉遣いの中にも鮮明な痛みと悲しみがこめられている。
第2章「老女」
朝の支度が始まっていた穏やかな村は、侵略者によって一転して死で覆われた。家族の血が流れる中、語り手は老いた体に鞭打たれ連行されてしまう。牢屋では子を目の前で亡くした母親(十章の語り手)が一部始終を語り始める。老女は殺された娘に想いを馳せる。航海が始まると、奴隷の女性たちは身投げの計画を立て始める。決行の日、老女は皆に続き海に飛び込むも、引き揚げられ再び船倉の悪夢へと戻る。船はとある島に到着し、プランテーションでの厳しく理不尽な生活が始まる。ある夜、老女は主人の邸宅へ忍び込み、眠っている子どもを手にかけたいという念に囚われる。休息もない悪条件の中で労働の日々が続く。ある朝、奴隷のうち「家無し女」と呼ばれたひとりの美しい女性が首を括られて発見される。それを機に奴隷たちは動き出す。ハイチ独立前夜、奴隷たちの静かな怒りと死者への祈りに満ちた一編である。
第3章「奴隷女」
海のない小さな村ヌペ。ある日村が襲われ、首長の娘だった語り手は見知らぬ土地で奴隷となる。十二歳になると、ある王妃(九章の語り手)の召使となった。忠実な僕として仕えていたが、ある日突然砂漠の商人に売られてしまう。灼熱の太陽の下、水も食事も満足にないまま奴隷としての果てしない旅が続く。ある嵐の日、山の上でアッラーの教えを説く不思議な男と出会う。キャラバンから一人抜け出し、イスラム教徒となって町から町へと漂流の旅にでる。ある夜、奴隷商人に捕らえられ再び奴隷となり、船へと乗せられてしまう。同乗した奴隷の中にかつて仕えていた王妃を発見し、彼女の下僕として自分の存在意義を再び見出す。本章の語り手は常に奴隷として生きることを強いられている。「わたしはヌペの娘」というフレーズを繰り返しながら、流浪の日々の中に自分の存在を見出そうとする語り手の葛藤が描かれている。
第4章「女戦士」
ヒョウの娘、ソシ。そう自称する語り手は恐れを知らない戦士であり、故郷を去ってダホメ王国の女戦士団に加入する。意気揚々と戦いに備えていたある夜、自分の村を襲う夢を見る。翌朝、それが現実になると知ったソシは内密に故郷の人々を亡命させ、僻地へ一人旅立つ。ある日、狩の最中にヨボ(白人)に捕まってしまうが、生まれながらの戦士である語り手は奴隷となってもなお闘争心を失わない。出航後身投げをすることを他の女達に提案し綿密に計画を練る。しかしヨボへの宣戦布告は数人の仲間の死とともに失敗に終わる。自由を手に入れられなかったソシは島に到着するやいなや逃亡し、ひとりの男と出会い双子の男子を生む。故郷に戻ることを依然諦めない語り手は、家族を残し海に乗り出す。荒れ狂う波に死を予感するが、魂が故郷に帰ることを願う。場面が変わり、語り手はどこかの島に辿り着いたようだ。夢想か死後の世界か。語り手はヒョウに変身し、もと居た場所へ帰ってきたのだと確信する。
第5章「白の女」
白の女————白人に見初められた語り手は、奴隷たちから皮肉まじりにこう呼ばれていた。良い待遇を受け、白人の男を愛することすら覚え始める一方で、かつて母親の男に性的な暴力をふるわれていたことを思い返すようになる。そんな中、とうとう白人の子を孕ってしまう。ソシ(四章の語り手)に子を堕ろすよう説得され、身投げ計画のことも耳にするが、決断できないでいた。ある日、男に妊娠を伝えると、以前の優しさとは裏腹に容赦無く追い返されてしまい、語り手は身投げに加わることを決意する。作戦決行後、船乗りによって引き挙げられたが、以来完全に正気を失ってしまう。自分を売った母の仕打ち、愛していた父の死——過去と現在の境なく想いが彷徨う。そのうち白い肌を持った娘が生まれるが、間もなく亡き者となってしまう。再び「鼠たち」が頻繁にやってくる。苦しみ、痛み、大量の出血、体が粉々に砕かれる感覚。つきまとって離れない鼠の影に語り手は抵抗の叫びをあげる。
第6章「双子姉妹」
セネガル河の果てに住む双子の姉妹はいつも一緒だった。妹は姉とそっくりになろうと言動を全て真似ていたが、ある日を境に自分は姉と違うという事実に気がつき、姉を憎み始める。そんなある日、姉妹が村の外から帰ってくると、村が火に飲まれていた。逃げるのも虚しく、二人は囚われてしまう。河を下り海に出ると他の奴隷たちと一緒に船倉に詰め込まれ、身投げの計画を耳にする。妹は泣きながら反対するが、姉妹は他の奴隷と身投げをする。姉だけがサメに食われてしまい、残された妹は心の中で姉と言葉を交わす。双子だが異なるアイデンティティを持つ姉妹の言葉が複雑に交差する。
第7章「雇われ女」
船頭の父をもつ語り手は奴隷船の雑用係として生きていた。いつか舵を取ることを夢見ていた彼女は、船がアフリカ大陸に帰還した後、機を伺ってソレイユ号に乗船する。モワゾニエ船長から船の監視役を任された彼女は、出航の前日から女戦士(四章の語り手)を中心に奴隷たちの間で何やら計画が立ち上がっていることに勘付く。出港後、女たちを監視するため初めて船倉に降りた彼女は、そのおぞましさに唖然とする。恐ろしい光景に心が揺らぎながらも雇われの身として役割を果たそうと船長へ報告する。しかし時既に遅く、十三人の女たちがまさに飛び込まんとする姿を目にする。これまで命令にのみ従って生きてきた語り手の心で何かが壊れる。その瞬間、彼女は自らの意志で躊躇なく海に飛び込んでいた。海の為すまま身をまかせながら、雇われ女は再び船の夢を見る。
第8章「少女」
少女は囚われの身となったが母の手の温もりが恋しい。ある時、「白の女」(五章の語り手)と皆が呼ぶ女を姉のように慕うようになる。白の女は少女のことを妹のように大事にし、事あるごとに注意を促したり物語を話して聞かせてくれた。しかし夜は船乗りのもとへ行ってしまう。ひとりになった少女はこれから辿り着く島の夢を見る。
ある時、戦士の周りで謀反の計画が上がっていることを知ると、自分はもう小さくなんかないと女たちを説得し仲間に加わる。身投げに加わるものはだんだんと増え、毎晩輪になってそれぞれの国の話を語り合った。謀反の時、戦士の言葉を合図に皆と一斉に飛び込む。しかし少女は泳いで故郷に帰るにはやはり幼すぎたことを知る。
第9章「王妃」
語り手は王の寵愛を受け何不自由なく暮らしていたが、なかなか子宝に恵まれないでいた。遂に王が別の妃を迎えることになると、彼女より先に子どもを産もうと子宝の薬を得て、新しい妃が身篭った子の命を摘んでしまう。語り手は双子を授かるが、うち一人は出産時に亡くなってしまう。妃として母として、再び栄光の地位に君臨したが、生き残った子を憎むようになり、遂に暗殺してしまい、真実が明らかになると奴隷として売られてしまう。王妃が奴隷牢に入ることに我慢できないでいるが、肌が黒いものは皆同じ価値だと奴隷商人に言い捨てられ、王妃としての自分の姿を見失ってしまう。出航が近づくと謀反の計画があることを知る。その輪の中に自分を見つめる者(三章の語り手)がいるが誰なのか思い出せない。そしてかつての王妃は波に叩かれ海深く飲み込まれる。女王から奴隷へ、皮肉な運命を辿る語り手が、自分が何者なのかを自問自答する姿の中に、美しい日々へのノスタルジーが垣間見える。
第10章「彷徨う女」
語り手は霊力の持ち主である。魂は夜になると船倉を離れ、外の世界を目にする。故郷のナントを想う奴隷船船長。ナントの邸宅で夫の帰りを待つ妊婦マリー。語り手の魂は魚や鷲に次々と姿を変え、ハイチに辿り着くと、奴隷の反乱に怯える白人達を目にする。次に魂は山を登り、逃亡奴隷マカンダルと出会い、反乱を画策する。語り手の呪いに苦しめられるマリーの腹からは、奴隷を飲み込んだ海を示唆するかのように、大量の水と共に無数の黒人が流れ出す。魂は奴隷船に引き戻され、ひどい嵐の末にハイチに到着する。語り手はマカンダルと再会し、ハイチでの黒人反乱が幕を開ける。「彷徨う魂」の奇怪な語り口から、船乗りや植民者たちの恐怖や悲しみが初めて明らかになる章である。
第11章「母」
語り手は奴隷商人連行される間も背中におぶった赤ん坊に必死で話しかけている。ある日、船に乗り換える際、足元がふらつき赤ん坊を海の中に落として亡くしてしまう。船上で厳しい日々を過ごしながら、亡くなった子に依然として語りかけているが、かつて子がいた胸には男が乗るようになる。ある日、停泊していた海辺の牢で同郷の老女(二章の語り手)と出会い、村での懐かしい思い出を語るうち、子を救えなかった後悔の念に強くかられる。子どものいる場所へ行きたい一心で、奴隷仲間と共に身投げをし、サメに食われてしまう。子に語りかける声は次第に力がこもり、暗く臭いサメの腹から不気味な子守唄をくちずさむ。
第12章「遺された女」
身投げの事件から二世紀後、語り手はナイジェリアの海辺のホテルにいた。モニエ船長の航海文書を目にしてから、事件をめぐる物語に取り組もうとしていたところ、ふとした手違いで受け取った葉書をきっかけにバダグリーへの旅を決意したのだ。島巡りのドイツ人観光客、サメ料理を得意げに振舞うレストランのシェフ。かつての出来事を全て忘れたかのようなこの地で、語り手だけは、「彼女たち」が遠い島から故郷に戻る姿を見る。語り手はこの「不在の者たち」の記憶を取り返すかのように、全てが始まった場所で思いにふけり、やがて意識は奴隷たちのそれと重なる。文章を書き出せず、女たちのイメージだけが頭を駆け巡る。ソレイユ号、彷徨う女(十章の語り手)の耳打ち、ブロンド女の微笑み、アフリカに到着したばかりの溌剌としたモニエ船長の姿…雨季のひどい湿気の中、様々な幻を見るようになる。パリに戻った語り手は、書き上げた作品を前に、蓋をされていた亡霊たちが本となって蘇ることを確信する。語り手は明らかに作者自身であるが、かつて生きていた女性たちを代弁する「後継者」として作品の一部となっている。
特徴と読後感
エクリチュール
この作品の最大の特徴はエクリチュールの特異さにある。原文はフランス語で書かれているが、スタンダードな言葉とは程遠く、奇天烈な表現やぶつ切りにされた文章などが多用されている。これにより、狂気に満ちた場面や語り手たちの激情をメタテクスト的に表現している。同時に、鋭いリズムに満ち、複雑ながらも心地よい音楽性を含んでいる。おとぎ話や詩、各章の間に挟まれる船乗りの唄など、オラリティも重要な要素のひとつである。
時間と空間の曖昧さ
女たちの語りの言葉は、時間と空間の境なく彷徨う。鎖で繋がれた語り手たちの姿と対照をなすように、彼女たちの想いは自由に時空を行き来する。夢か現かもわからない話と、大胆な思考の旅に、読者は面食らうかもしれない。特に最終章は他章とまったく異なる時間軸で語られる。マルティニークにルーツをもつ作者は、この物語の主人公たちの「子孫」であると同時に、存在を認識されてこなかった彼女たちの「代弁者」でもある。そのため、1773年の身投げ事件に関わる者として、この物語の一部を成している。最終章では語り手である作者が、できあがった作品を目の前にして幕が閉じる。そして、それを読み終えた読者の手にはまさにその作品が残っている、というわけだ。この不思議な入り子構造が、時間と空間の感覚をさらに曖昧にする面白さを生んでいる。
登場人物
物語はソレイユ号に居合わせた女性たちの語りによって成り立っている。ある章の語り手が別章でも現れることがあり、読み進めるうち立体的に物語が象られていく印象をうける。また、奴隷だけでなく、奴隷商人、船乗り、プランテーションの主人たち、船長とその妻も、この物語にとって重要なピースである。カノールは白人対奴隷という安易な構造で奴隷制を批判しているのではなく、身投げ事件を取り囲んでいたであろう人々の姿を浮き彫りにすることによって、歴史の中で語られてこなかった黒人奴隷貿易の側面を明らかにしようとしている。
メタファー
木、海、空、雨などの自然物がまるで意思を持った生き物のように描かれ、語り手たちの心情のメタファーとして頻繁に現れる。特に語り手たちの多くは「海」という存在を奴隷になって初めて目にする。海は、奴隷たちの暗い航海のシンボルであり、同時に生者と死者の対話の場所、また女性・母性のシンボルとしても表れている。その他、本作品中の複雑なメタファーの中には、ありありとしたイメージが映し出され、時に心臓を突くような描写もある。
日本における受容予想
本作品は、日本の読者にとって必ずしも受け入れやすい作品ではないかもしれない。第一に、黒人奴隷貿易というテーマの関係上、目を覆いたくなるようなシーンは避けられない。また、黒人奴隷を描いた映画や文学はたくさん存在するが、日本社会においてこの言葉が話題に上がることは多くない。さらに、原文のエクリチュールが特殊であるため、邦訳での読みづらさを感じる読者もいるだろう。
しかしこのような課題がありながらも、本作品は人々が国境を越えて行き交いアイデンティティの定義づけが難しくなっている現代において、重要な問いを投げかけている。この点で、社会派の文学として受け入れられてもらえるだろう。また、既成の作品でもあまり焦点が当てられない女性奴隷からの目線で語られているため、フェミニズム文学としての重要度も高くなるだろう。
この作品は、日本の読者がほとんど知らないであろう文化的歴史的コンテクストが織り交ぜられており、読者にとって読解が難しくなる可能性もあるが、脚注などを丁寧につけることによって解決可能である。
翻訳難易度
上で述べたとおり、原作のフランス語は標準から大きく逸脱しており、フランス語母語話者でも読解に時間を要する。翻訳に取り組むには十分な時間と、文学に通じたフランス語母語話者の協力が得られる環境が必要である。また、アフリカ諸言語も所見されるため、複数のアフリカ言語の辞書にアクセスできる環境、もしくは協力者が得られる環境も必要となるだろう。また、アフリカの歴史文化の知識が必要な語には適宜丁寧な脚注をつけられることが望ましい。
非標準的なフランス語の原文を翻訳する際、日本語でもかなり違和感のある文章になる恐れがあるため、明確な方向性を決めて翻訳を開始することができると良い。
