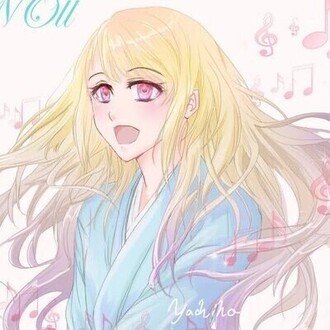「花の寺」 桃源郷ならぬ桜園郷!
九重(ここのえ)に、咲けども花の八重桜、幾代の春を重ぬらん。
然(しか)るに花の名高きは、先づ初花を急ぐなる近衛(このえ)殿の糸桜。
見渡せば柳桜をこき交(まぜ)て、都は春の錦燦爛(さんらん)たり。
千本(ちもと)の桜を植ゑ置き、其の色を所の名に見する。
千本(せんぼん)の花盛り、雲路や雪に残るらん。
「九重の都に咲いても、八重の桜、どのくらい春を重ねたことであろう。
花の名所はまず、永和4年頃、足利義満が近衛道嗣(このえみちつぐ)邸の枝垂桜(糸桜)を所望して、室町御所に移植したと伝えられる桜で、京都屈指の名花である。
見渡せば柳の緑に色添えて、京都の桜は春の錦といわれるほどのきらびやかに織りなしたようである。
千本もの多くの桜を植え、その美しさをそのまま所の名にあらわした千本通りの花盛りは、雲路を辿るや雪中を行くようである。」
これは能の「西行桜」という演目に使われる謡曲です。実際のそのお寺を見た後で、この小唄の詩を読み返すと思わず頷きたくなります。
桜とほんの少しの赤い椿が咲いていました。
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?