
不登校を3回経験│たどり着いた『親も子も自分を生きよう』に込められた思いとは?
不登校は、子どもだけでなく、親にとっても大きな転機 となります。
「どうすればいいの?」「このままで大丈夫?」—— そんな不安を抱えながら、日々お子さんと向き合っているお母さんも多いのではないでしょうか。
そんな方々に向けて、実際に不登校を経験したお母さんたちのリアルな声をお届けするインタビューシリーズを始めました。
子どもとの関わり方、悩み、気づき、そして親としての変化——。さまざまなエピソードを通じて「ひとりじゃない」と思えるきっかけになれば嬉しいです。
第1回ゲスト:カオラさん
記念すべき第1回に登場してくれたのは、3回の不登校を経験し、不登校支援カウンセラーの資格を持つカオラさん。
不登校を通じて、何を感じ、何を学び、どのように変わったのか——。
その想いを、じっくりお聞きしました。
◆プロフィール
長男:大学1年、次男:中学3年の2児の母。
「親も子も自分を生きよう!」 をモットーに、noteやX(旧Twitter)で不登校の子を持つ親御さんや働くママへ向けて、生きるヒントを発信中。また、『ありがとうスペース』(不登校をテーマにしたXのスペース)の主催や、『NPO法人こずえのつぼみ』での不登校おはなし会の開催など、幅広く活動している。
■不登校のはじまり
ーー不登校について、お話できる範囲で経緯などをお聞かせください。
長男が小学4年のとき、季節の変わり目にぜんそくが悪化することはよくあったのですが、その年は追い打ちをかけるように溶連菌にもかかってしまったんです。やっと熱が治まって「これで登校できる!」と思ったものの、長男の体調がなかなか回復せず「まだしんどい、だるい」と。
その後、なんとか登校しはじめたものの、保健室に行く回数が増え、朝から体調を崩すことが多くなっていきました。
ある日、ご近所のママから「長男くん、大丈夫?」と声をかけられたんです。「何のこと?」と尋ねると、どうも長男は担任の女性の先生から目をつけられていたようで、教室の外にまで響く金切り声で怒鳴られたり、廊下に立たされたりしていたと聞かされました。
ある日、長男が悔しそうな顔で帰ってきて「濡れ衣を着せられた」と。それ以上、何があったのか話してはくれませんでしたが、このあたりから長男の顔から徐々に笑顔が消え、毎日のように体調不良を訴えるようになりました。
ーーそのとき、カオラさんはどのような心境だったんでしょうか?
そんな状態でも「行けそうな時は行かせなくちゃ!」と思っていました。
ある時、連絡帳に「昨夜少し微熱が出ましたので、体育は見学させてください」と書いて、長男を学校に送り出したんです。ところが、体育の見学をさせてもらえなくて。聞くと、最近は体調が悪くしんどいと訴えても、保健室に行かせてもらえないと。
それを知って、やっと「休ませるしかない」と決断しました。
ーー学校には相談したんでしょうか?
ちょうどその頃、会社の先輩のお子さんが朝起きられず、夜寝られない『起立性調節障害』という状態であることを知ったんです。
「もしや」と思い、検査をしたところ、長男も『起立性調節障害』だということがわかりました。
担任の先生に話してみましたが、あまり理解してもらえず、教頭先生に相談することにしました。教頭先生は寄り添ってくださり、話もたくさん聞いてくださいました。
小学5年に進級すると、長男の親友が一緒のクラスになり、若い男性の先生が担任になりました。たぶん、教頭先生が配慮してくださったんだと思います。
■もっと早く頼れば良かった

ーー学校以外にも相談しましたか?
臨床心理士の資格を持つ友人が、親と子の両方をカウンセリングしてくれるメンタルクリニックを紹介してくれて、そこに通うことにしました。
私自身、カウンセリングの内容はあまり覚えていないのですが、最初の数回はずっと泣いていた記憶があります。気持ちを吐き出せる、唯一の場所でした。
長男のカウンセリングを担当してくださったのは、若い男性の臨床心理士さん。長男にとっては、一緒に遊びながら話を聞いてくれる「頼れるおにいさん」のような存在で、あっという間に懐いていました。
もっと早くカウンセリングに通う決断をしていたら、もっと早く第三者に助けを求めていたら、長男の傷はもう少し浅かったのかもしれない。そんなふうに思うこともあります。
ーー他にも頼れる人はいましたか?
塾の先生にとても助けられました。実は、長男は発達障害の診断はつかないものの、発達に凹凸があるタイプ。IQは比較的高めで、理解力は高いのに処理速度が遅いという特性がありました。
そんな長男を見て、塾の先生がこう言ってくれたんです。
「長男くんは、教えた時の理解や反応が他の子にはないものがある。まだまだ粗削りだけど、光る原石だと思います。学校がしんどくても、塾で初めて知ることを学んでいる時は非常に楽しそうです。塾がそういう場になってくれたらいいなと思っているんです」
長男の可能性を見抜き、導いてくださった先生には感謝しています。
そして、長男が6年生、次男が2年生になった頃、やっと長男は自力で歩いて登校できるようになりました。次男は、大好きなお兄ちゃんと一緒に登校できてとても喜んでいました。
■『起立性調節障害』を再発
ーー不登校は3回ご経験されているということですが、2回目の不登校についてお聞かせください。
長男は中学受験をして、私立の中高一貫校に進学しました。学校までの道のりは約1時間。最初は順調に通っていたものの、電車の中で寝過ごすことが増え、遅刻する日もだんだん多くなっていきました。
さらに体調も崩しがちになり、中学1年の2月には、ほぼ完全に登校できなくなっていました。完治したと思っていた『起立性調節障害』が再発したんです。
ーー『起立性調節障害』は再発することがあるんですね。
「まさか2回目なんてあるはずない」と私も思っていました。ところが、検査の結果、「起立性調節障害 体位性頻脈症候群(POTS)」ということが判明したんです。
その後は治療を続けながら、2週間に1回くらい、保健室の隣りにある学習室に通うようになりました。長男にとって、学習室は「安全地帯」でした。
そして、中学2年の3学期に、新型コロナウイルスのパンデミックが発生。学校が閉鎖され、授業は動画配信に切り替わりました。そのおかげで長男は、自宅で1年ぶりに授業を受けることができたんです。
分散登校が始まっても教室に戻ることはできませんでしたが、動画配信のおかげで学習意欲が戻り、高校に進学することができました。
■今度は次男が不登校に
ーー差し支えなければ、次男くんのお話もお聞かせください。
次男は明るくてムードメーカー的な存在で、元気に学校に通っていました。小学5年のとき、コロナ禍の分散登校が始まってしばらく経ったある日、突然「学校に行きたくない!」とボロボロ泣き出したんです。
その瞬間、ついに来たか…と思いました。
実は、次男には繊細なところがあり、もしかしたら我慢しているんじゃないかとずっと思っていたんです。学校に行けないお兄ちゃん、怒るお父さん、辛そうな私を見て、「僕はみんなを笑わせるんだ」って、明るく元気に振る舞ってくれていたんです。
ーー次男くんにはどんな言葉をかけましたか?
泣きじゃくる次男を抱き締めて、こう言いました。
「全然いいよ! 休もう! ここまで休まずきたんだから、今度は堂々と休んでいい! 心配しなくていいよ!」
実は、コロナ禍後、次男のクラスは学級崩壊のような状況だったんです。担任のおじいちゃん先生のことも「怖い」とよく言っていました。
学校を休みがちになり、何とか別室に登校すると、先生から 「今頑張らなきゃ、もう来られなくなるよ! しんどくても、頑張らないといけないんだ!」 と熱心に説得されるんです。
悪気はなかったのかもしれませんが、エネルギーがゼロの状態の次男には、その言葉が重すぎました。
これ以上、無理をさせるべきではないと判断し、しばらく学校を休ませることにしました。
ーーそのとき、長男くんはどのような反応でしたか?
長男は「がんばれ」とか「大丈夫か?」と声をかけるわけでもなく、次男をそのまま丸ごと受け止めていました。
家に2人でいるとき、どんな話をしていたのか、詳しくはわかりませんが、お互いの存在が安心感になっているのは伝わってきました。
兄弟仲良く、優しくて、自慢の息子たちです。
■動き出した子どもたち
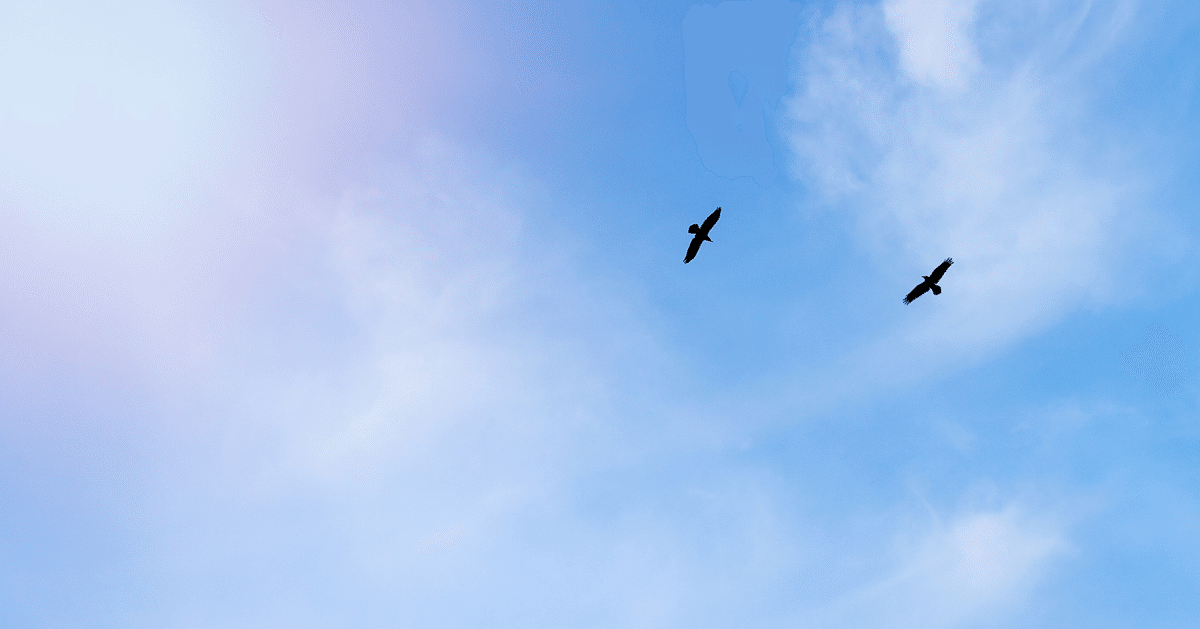
ーー現在はどのような状況でしょうか?
長男は高校生活を無事に終えて、大学に進学しました。今は、大学生活を楽しんでいます。
次男は小学6年で別室登校、中学では月に1回ほど適応指導教室に通いました。そして、昨年末に通信制高校への入学が決まりました。
ーー再び動き出せたのは、どうしてだと思いますか?
長男は「満足した」というか、「もういいな」と思ったみたいです。
何もしていない不安から、一時はゲームの世界にどっぷりハマっていました。でも、それも次第に飽きてきて、「これが一番楽しいことではない」とわかったようでした。ゲームが、彼にとっての“一番”ではなくなったんです。
ーー次男くんはどうでしょうか?
次男は、今も中学校には通っていません。だから、ずっと「高校には行かない」と言うんじゃないかと思っていました。
ところが、ある時「高校には行きたいな」と。近所に住む友人から受験の話を聞き、そんな風に思ったようです。それなら、と一緒にいろいろ調べて、全日制ではなく通信制高校を選びました。
「友だちが欲しい」という言葉も次男から聞きました。
長男が高校で友だちをつくった姿を見て、次男も高校に希望を持てるようになったのかもしれません。
ーー「高校に行きたい」という言葉が出るまで、カオラさんはどのように接していたのでしょうか?
私からは何も言いませんでした。
ぐっとこらえて、ひたすら我慢していました。
ーー何も言わないのは、大変ですよね。
本当に大変でした。でも、我慢していたからこそ、次男が自分から言い出してくれたのかなと思います。
とはいえ、何が正解かはわかりません。子どもによって、タイミングによって、その時々で変わってくるのかなと思います。
ーー不登校について、今はどのように受け止めていますか?
今は、落ち着いて受け止められるようになりました。学校に行っても行かなくても、楽しい人生を送ってくれたらいいなと思っています。
ーー「受容過程の5つのステージ」(注1)の受容の段階ということでしょうか?
一旦は「受容」ということになると思います。とはいえ、不安になることも、心が揺れることもあります。ひとつひとつ、受け入れながら進んでいくのかなと思います。
(注1)アメリカの精神科医キューブラー・ロスが提唱した、人が大きな喪失や変化を受け入れるまでの心理的プロセスのこと。
①否認②怒り③取引④抑うつ⑤受容の5段階とされる。
■「親も子も自分を生きよう」に込められた思いとは?
ーーカオラさんのアカウント名「親も子も自分を生きよう」には、どのような思いが込められているのでしょうか?
親と子は、別々の人格であることを常に意識しています。私の発信は「不登校」が中心ですが、子どもが「不登校」かどうかにかかわらず、親の思い通りに成長する子の方が、むしろ少ないと思うんです。振り返ってみれば、私自身もそうでした。
親と子が別々の人格であるということは、子どもが抱える課題と、親が抱える課題も違うということ。乗り越えなければならない課題は、人が違えば違うはずなんですよね。
親と子は違う人間であり、違う考え方や価値観を持っています。だからこそ「親も子も自分を生きて欲しい」と願っています。
ーー「課題の分離」は頭では分かっていても、なかなか難しいですよね。
そうですね。距離が近ければ近いほど、見失いがちになります。親子の距離感って、本当に難しいと感じます。
例えば、「学校に行けなくても、家にいてもいいけど、友だちだけでもいてくれたら…」と思ってしまったり。
本来、友だちとの関係は子どもの課題のはずなのに、親の方が気にしてしまう。どうしても、子どものことは「自分ごと」として捉えてしまうんですよね。
ーー確かに友だち関係は、親にとって大きな悩みのひとつですね。
子ども自身が求めていなくても、親は子どもに対して「せめて友だちが1人でもいてくれたら」「他の人と関わりを持ってくれたら」と思ってしまう。
それは、大人である私たちが知っているからです。
自分がひとりで生きてきたわけじゃない。
人はひとりでは生きられない。
親は、子どもより先にこの世からいなくなります。そのとき、子どものそばに誰もおらず、困った時に助けを求められる人がいないままだったら…?
そんな不安が、どうしても頭をよぎってしまうんですよね。
また、大人である私たちは、「人間関係の中で得られる、かけがえのない経験」 を知っています。だからこそ、「同じような幸せを、子どもにも感じてほしい」 と願ってしまうのではないでしょうか。
子どもの課題と、親の課題は違う。だから、本来は分離して考えなければいけません。でも、この件に関しては「課題」ではなくて、親の「願い」なんだなと思います。
ーーなるほど。「課題」ではなく「願い」なんですね。
とはいえ、親の「願い」を子どもに背負わせるわけにはいきません。親が「課題」を与えるのは避けたいですよね。だから、こう思うようにしています。
親が自分の心の中で願うことは自由!!
そこまで自分の感情を抑える必要はないんですから。
■ゼンタングル®の講座を本格始動したい!

ーー今後の目標があればお聞かせください。
2024年にゼンタングル(注1)の認定講師資格を取得しました。
ゼンタングルは、瞑想のような効果があり、シンプルなパターンを繰り返すことで完成するため、ASD傾向の子どもたちにも楽しんでもらえるのではないかと考えています。
「親が楽しめる時間」、「特性があるお子さんも楽しめる時間」 を目指し、最近、試験的に講座を開催しました。本格始動に向けて、現在、準備を進めています。
(注1)ゼンタングル®(Zentangle) とは、シンプルなパターンを繰り返し描くことで、美しいアートを生み出す手法。瞑想のようなリラックス効果があり、「描くマインドフルネス」 とも言われている。

ーー素晴らしい講座になりそうですね!それでは最後に、今、お子さんに伝えたいことはありますか?
もーーっと楽しんでいいんだよ。『どうにかなる』じゃくて、『どうにでもできる』と伝えたいです。
X(旧Twitter) x.com/kaora2314?t=W6P6zq7m-Zm36M4KmFhOIQ&s=09
instagram https://t.co/nAdRE4zzpn
インタビューにご協力いただき、ありがとうございました!
カオラさんのお話を聞いて、不登校は「親子がともに成長する時間」なのだと改めて感じました。
そして、インタビューの最中、長男くんが飛び入り参加!
そのときに残してくれた言葉が、とても印象的でした。
「なんとかなったから、ええねん♬」
シンプルだけど、たくさんのことを乗り越えてきたからこそ言える言葉。
この一言に込められた想いに、胸が熱くなりました。
「親も子も自分を生きよう」—— その言葉のとおり、さまざまなことに挑戦されているカオラさん。
これからのご活躍を、心から応援しています!
最後までお読みいただき、ありがとうございます!
この記事が少しでも役に立ったと思ったら、シェアやフォローをしていただけると嬉しいです。
次回のインタビューもお楽しみに!
#不登校インタビュー
いいなと思ったら応援しよう!

