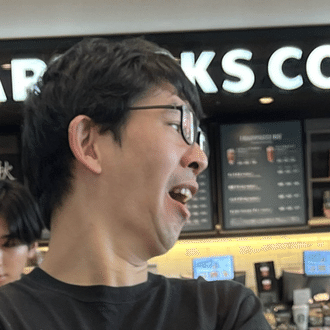書評「Google流資料作成術」
このブログを読んで、早速購入してみました。
紹介元のブログにも書いてありますが、タイトルだけ読むと、小手先だけの資料作成本だと思うかもしれませんが、そうではありません。
本書「Google流資料作成術」は、データを元に多くの人に理解してもらう資料を作るにはどうしたらよいか。特に「どうやったらデータを使って人を動かすのか」について詳しく書いている書籍です。
本書に書かれていることは、以下の6点です。
1.コンテキストを理解する
2.相手に伝わりやすい表現を選ぶ
3.不必要な要素を取りのぞく
4.相手の注意をひきつける
5.デザイナーのように考える
6.ストーリーを伝える
データを見せるために大切なのは「コンテキスト」
僕が本書を読み終えて印象に残ったのは、最初に「コンテキスト」の大切さを説明していたことです。
誰に、何を、どう説明するのか。
どんな資料でも、コラムを書くときでも、当たり前のように意識しなければならないことですが、いざデータを取得して人に説明しようとすると、当たり前のことを忘れがちです。
そして、データもあくまで人に理解を促すための要素の一つであり、最大限効果を発揮してもらうためには、コンテキストに沿って採用することが大切だということを、本書は分かりやすく説明しています。
「グラフの書き方」について説明した本ではこれがベスト
本書には、データを「どう見せればよいか」「どんなグラフを使えばよいか」「グラフの書き方」について、分かりやすく書かれています。グラフの書き方については様々な本が出版されていて、いろいろと読みましたが、実戦に使える本としては、これがベストかも知れません。
なお、本書に書いてあるデータ視覚化のデザインについては、THE GUILDの @goandoさんがわかりやすくまとめているので、こちらもおすすめです。
本書を読み終えて、さっそく自分が仕事で作っているグラフを見直しました。日々グラフを作って資料を作っている方は読んで損はない書籍です。
いいなと思ったら応援しよう!