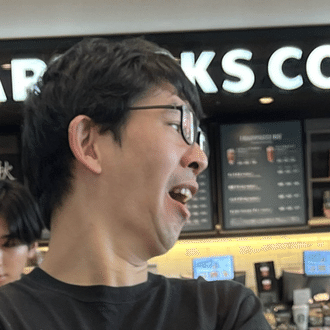書評「ナーゲルスマン流52の原則」
この本を読んだ感想が他の人と違いそうなので、書評を書いておこうかと思います。
本書はホッフェンハイムでのブンデスリーガ史上最年少監督としてデビューし、RBライプツィヒをクラブ初のCL 4強へと導き、そして2021年に就任したバイエルンでは悲願だった自身初のタイトルを獲得。順調にキャリアを積み上げているユリアン・ナーゲルスマンの戦術や考え方について書かれた書籍です。
多くのサッカーファンは本書を読んだとき、ナーゲルスマンの戦術や設定している原則に注目すると思うのですが、僕は本書を読み終えたときこんなことを感じました。
「この本はベンチャーで成果を出したマネージャーがレガシー企業に転職してDXに苦労している現在までの道のりをまとめた本だな」と。
ナーゲルスマンの戦術や原則の考え方は斬新かもしれません。ただバイエルン・ミュンヘンの監督に就任してからのナーゲルスマンは、チームが求めていることと自分がやりたいことのすり合わせに苦労している印象を受けています。
ナーゲルスマンが得意なのはDXです。チームの仕組みを変え、考え方を変え、より成果が出るように作り変えることです。ただホッフェンハイムやRBライプツィヒといったベンチャーでは通用した手法が、レガシー企業とも言えるバイエルン・ミュンヘンで通用するかどうかは別だと僕は思っていました。バイエルン・ミュンヘンのレガシー企業っぽい経営者が期待するのはトロフィーの獲得ですが、たぶんDXまでは求めていないはずです。なぜならDXを実施したら、自分の居場所までなくなる可能性があるのですから。
それは選手も同じのような気がします。結果は欲しい、でも変化はいらない。そんなどこかレガシー企業っぽい選手のマインドとナーゲルスマンがどう向き合っていくのか。ナーゲルスマンのような監督が成果を出すには、彼をバックアップする歳上の意思決定者が不可欠ですが、バイエルン・ミュンヘンの動きを眺めていると、ナーゲルスマンを心からバックアップしようとしている人はいるのか気になります。
本書はベンチャー企業で成果を出してきたマネージャーがレガシー企業のDXにどう立ち向かうのか。その過程を描いた本だと捉えるととても面白い本です。グアルディオラやクロップが成功しているのは、彼らが経営者のバックアップを得ているからです。さて、ナーゲルスマンはどうでしょうか。
いいなと思ったら応援しよう!