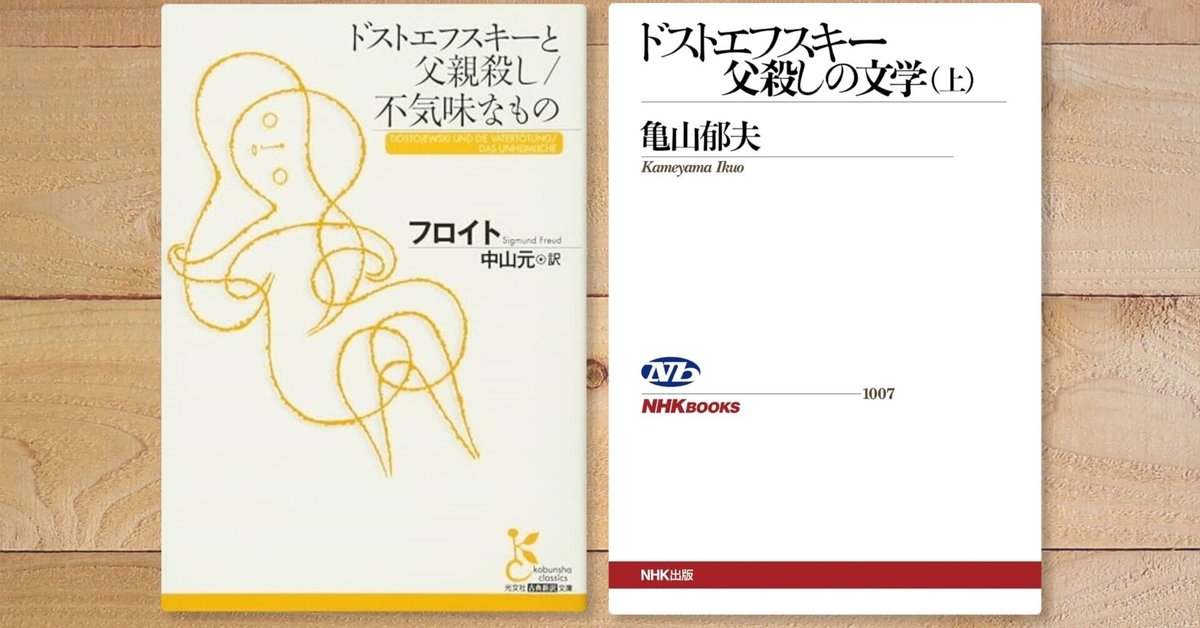
『カラマーゾフの兄弟』は本当に父殺しの小説なのだろうか本気で考えてみた
ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』は言わずと知れた世界文学の金字塔です。私も20代前半にこの作品と出会い、私の僧侶としての道を決定づけるほどの衝撃を受けることになりました。(※詳しくは以下の記事でお話ししています)
『カラマーゾフの兄弟』はドストエフスキーの晩年に書かれた生涯最後の作品です。
ドストエフスキーはこの作品で生涯変わらず抱き続けてきた「神と人間」という根本問題を描いています。
ただ、この作品においては様々な見方もされており、最近では「『カラマーゾフ』は父親殺しの小説である」という説がメディアなどを通して語られることも多く、その影響力は見過ごすことができません。
こうした「カラマーゾフは父親殺しの小説である」という説は元々フロイトによって提唱された説でありました。
フロイトは1928年に『ドストエフスキーと父親殺し』という作品を発表していて、これが現代でもその根拠として語られています。
この作品はドストエフスキーに彼の父殺しの理論、エディプス・コンプレックスの理論を適用し、『カラマーゾフの兄弟』も分析していくという作品です。
まずはじめに私の立場をお伝えします。
私はフロイトのドストエフスキー論には賛同できません。なぜなら彼の理論には根拠がなく、彼がこの作品で根拠として持ち出したものはすでに研究者によって否定されています。フロイトは自分が収集した情報を基に自分の想像を語り、それを事実として語ります。そしてドストエフスキーの生涯や性格をすべてエディプス・コンプレックスの観点で分析し、サディスト・マゾヒストと断言し、『カラマーゾフの兄弟』においても父殺しの衝動が彼にそれを書かせたと結論づけます。
彼の語る物語は読む人を惹きつけます。ですが、根拠がなく史実がないがしろにされた内容なのです。
フロイトの説は正しいか正しくないかは問題ではないのです。
「一気に読ませる」ようなストーリーを展開できてしまうその言葉の力、物語生成能力こそフロイトの最大の特徴です。
私はフロイトを全否定しているわけではありません。100年近く前に発表された著作に対して「事実と違う」と批判するのはナンセンスなのも重々承知です。ですが、このフロイトの説が未だにドストエフスキーの事実として紹介されていることに対して私は心を痛めています。こうした記事を書くのは正直心苦しいのですが、私はあえてこの記事を書くことにしたのでした。
フロイトの説のどこに問題があったかはこの記事では長くなってしまうのでお話しできませんが、詳しくは以下の記事で紹介しています。
項目としては以下の通りです。ひとつひとつ根拠ある資料に基づいてお話ししていますのでご安心ください。
フロイトが根拠にあげるひとつひとつの事例を丁寧に見ていきますと、ドストエフスキーへの父殺し理論の適用は非常に厳しいことは明らかです。
ドストエフスキーがエディプス・コンプレックスに一生縛られ、それによって『カラマーゾフの兄弟』が書かれたというのは事実と異なります。
フロイトがドストエフスキーの伝記や『カラマーゾフの兄弟』をどのように読むかは自由です。作品は作家の手を離れた瞬間に読者の自由となると言われるように、出版された本をどのように読むかは個人の自由です。
フロイトは持論のエディプス・コンプレックスは正しいという立場から『カラマーゾフの兄弟』を論じました。
「作品をどう読もうが読者の自由」という原則に当てはめれば、これは何の問題もない行為です。
ですが、フロイトはその自由な解釈を作者のドストエフスキーにまで当てはめてしまいました。そして彼の解釈したドストエフスキーこそ真のドストエフスキーだと断言したのです。上で見た通り、「ドストエフスキーは強姦をした」とまで断言し、彼の人格を決めつけ、ドストエフスキーの作家人生はエディプス・コンプレックスによるものだと単純化して論じました。
私がフロイトのドストエフスキー論になぜここまでこだわるのかというと、まさにここに理由があります。
フロイトは対象となる人物の生涯や時代背景、文化を無視してエディプス・コンプレックスという持論のみで解釈しようとします。
フロイトはこの作品のはじまりでドストエフスキーについてこう述べています。
ドストエフスキーが道徳的な闘いにおいて最終的に到達した段階もまた、名誉のあるものではない。個人の欲動を充足させたいという願望と、人間社会のさまざまな要求を和解させようとして、激しい苦闘を経験したのだが、結局のところは後戻りして、世俗的な権戚と宗教的な権威に屈服したにすぎないのである。ツァーとキリスト教の神に畏敬の念を捧げ、ロシアの狭量なナショナリズムに屈するのであれば、ドストエフスキーほどの才能は不要だし、彼ほどの苦闘も不要なのである。これはこの偉大な人格の欠点なのである。
ドストエフスキーは人類の教師や解放者になり損ねて、人類の牢獄の看守になり下がったのである。未来の人類の文化が、ドストエフスキーに感謝すべきものは何もないのである。おそらく神経症のためにこのような蹉跌の運命にあったということは、証明できるかもしれない。あれほどの高い知性に恵まれ、あれほどの高い人類愛に燃えている人物には、もっと別の、たとえば使徒のような人生が開けていてしかるべきだったのである。
ルイス・ブレーガーによるフロイト伝『フロイト 視野の暗点』によると、フロイトは無神論者で宗教に対して激しい批判を加えていました。そして彼はオーストリアを拠点としていましたのでロシアのことはほとんど知りません。彼が知るキリスト教はカトリックとプロテスタントです。
ロシアのキリスト教は同じキリスト教といってもロシア正教というカトリックやプロテスタントとはかなり異なる文化を持った宗教です。
ドストエフスキー自身もロシア正教の立場からカトリックやプロテスタントへの批判をしています。
ロシアの専門家ではないフロイトはロシアの歴史や文化、宗教には詳しくありません。ドストエフスキーがどのような時代背景で育ったかも、彼が読んだ資料の範囲でしか知りません。さらに言えばただでさえ強固な無神論者を任ずるフロイトが、ロシア正教の教えや思想を理解していたかは疑問です。
そしてドストエフスキーがどういう思想的な流れを通って『カラマーゾフの兄弟』を執筆したかもフロイトは知りません。フロイトは自分に都合のよい情報しか得ようとしません。フロイトは自らの理論を基に自分に都合のよい情報を使って「『カラマーゾフ』は父殺しの小説である」と断言しました。
そもそも結論ありきで小説を読んでいくのですからそうなるのも当然です。
たしかに小説の中で父殺しは書かれています。
フロイトがそれを『カラマーゾフ』の主題として読むのは自由ですが、だからといって『カラマーゾフ』が父殺しを主題にした小説であるとは限らないのです。
これは一見些細な違いなようにも見えますが、決定的に違います。『カラマーゾフ』は宗教や政治、思想、文化、当時のロシアの時代背景など様々な要素が複雑に絡み合ってできています。そしてドストエフスキー自身がどんな思いでその作品を書いたのか。それすらもフロイトの言う「『カラマーゾフ』は父殺しの小説である」という単純化された理由で無視されてしまうのです。
作品をどう読むのかは自由。ですがその自由な解釈を作家にまで当てはめて断言してしまうのは問題です。
ただ、一般読者がそれを個人的にする分には何の問題はありません。
しかしフロイトのような権威ある大学者がそのように断言してメディアで積極的に宣伝したらどうなるでしょうか。フロイトはメディアを使った宣伝が非常に巧みだったと伝記『フロイト 視野の暗点』にも書かれていました。彼が自分を礼讃する人間を集め、積極的にフロイト理論礼賛のキャンペーンを張っていたことは有名です。
こうして大々的にフロイトのドストエフスキー解釈が世に広まることになります。
それにそもそも、ドストエフスキーの専門家でなければわざわざドストエフスキーが本当に「父親殺し論」に当てはまるかどうかの検証はしません。多くの読者の関心はその小説が面白いかどうかです。そこに学問的な正確さは求められません。
「フロイトがそう言った」と言ってしまえば、「そうなんだ!面白い!」となってしまうのは当然です。なにせフロイトは面白い物語を紡ぎ出す天才ですから、面白くないわけがありません。彼の語る物語はショッキングでセンセーショナルで、キャッチーなものがほとんどです。
フロイトのドストエフスキー論でもまさしくそうした見事な物語が語られます。「なんか、言われてみればそれもありえそうだな」と思ってしまうような物語です。
物語としては筋が通っているのです。ですが事実とは違うのです。ここが何とも難しいところです。
ただ、現代において語られるフロイト理論はあくまで彼の創作、物語であり、それを科学理論のように当てはめて対象を解釈していくのは危険であると私は考えています。それは確かに面白いかもしれませんが、事実からは遠ざかっていくのではないでしょうか。
SFや小説を「事実と違うからけしからん」と否定するのはたしかに問題があるかもしれません。フロイトの物語もそうした面があるのはある意味否定できません。ですが、フロイトにおけるドストエフスキー論は言い過ぎです。父殺し理論の補強のために、「ドストエフスキーは強姦をした」とまで断言するのはさすがに問題があります。そしてこの本ではそれらに対する注もありません。フロイトがそのように想像するのは自由ですし、フィクションとしてそれを作品化するのも自由です。そしてそれをある種の創作物語として読者が楽しむのも自由です。ですが、ドストエフスキーに関しては一線を越えているのではないかというのが私の思いです。
最後にもう一度強調しますが、私はフロイトを全否定しているわけではありません。あくまで、フロイトが言っているドストエフスキー論には根拠がないという点を明らかにしたかったというのが私の思いです。
ドストエフスキー作品を読んでどう思うかは人それぞれ自由です。そしてドストエフスキーがこれだけ世界中の人に愛されたのも、様々な解釈を許容する懐の広さがあるからこそだと私も思います。
世に膨大なドストエフスキー論があるのもまさにその証拠です。トルストイ論よりもドストエフスキー論の方が圧倒的に多いのです。それだけ多様な解釈が生まれやすい作家なのだということでしょう。
ですので、何度も言いますが私は『カラマーゾフ』を読んで「それが親殺しの小説である」という説自体は問題だとは思っていません。ですがそこから拡大してドストエフスキー自身にまでその説を拡大し、根拠のないドストエフスキー像を面白おかしく語るのはどうなのだろうかと思う次第であります。
出版不況の中、まずは認知されて売れなければしょうがないという事情もわかりますが、事実を歪曲してゴシップ的に語るというのは事情を知らない読者に対して道義的に問題があるのではないかと私は考えています。
ドストエフスキーに関するこの辺りの問題に関しては以下の本で詳しく語られているのでぜひ私はおすすめしたいです。
私はロシア文学の専門家ではありませんが、ドストエフスキーを愛する者として昨今の現状には思うことがありました。
この記事は元々2022年に公開した以下の記事を再構成したものになります。
私がドストエフスキーを本格的に学び始めたのは2019年のことでした。そしてその年の秋に今回の記事でお話ししたフロイトの問題とぶつかったのです。私はその時ドストエフスキーにこのようなレッテルを張った説に対して強い怒りを感じました。そしてこうしたフロイトの説が本当に正しいのか、それに対してどう反論できるのかと私は猛烈に本を読みこむことになりました。
今思えば、こうした怒りが私のモチベージョンになっていたのでしょう。どうしても認められない、乗り越えなければならない問題が目の前にあったからこそこうして必死で取り組めた。研究を終えて冷静になった今となってはむしろこの問題と向き合えたことに感謝しています。
以下、私が参考にし、かつおすすめできるドストエフスキー参考書の一覧記事のリンクになります。ぜひ参考にして頂けましたら幸いです。
また、『カラマーゾフの兄弟』がどのようにして書かれたのか、そしてその主題は何だったのかについてお話ししたのが以下の記事になります。今回の記事と合わせて読んで頂くとよりわかりやすいと思います。
以上、「『カラマーゾフの兄弟』は本当に父殺しの小説なのだろうか本気で考えてみた」でした。
関連記事
