
雨宮哲監督 『SSSS.GRIDMAN』 : 作中世界の「親友」
作品評:雨宮哲監督『SSSS.GRIDMAN』(2018年・全12話)
放映当時、一大ブームを巻き起こした作品である。まず、目を引くのは「作画」レベルの高さだ。
(1)絵がきれいで描き込まれている。
(2)キャラクターデザインやメカデザインが魅力的。
(3)戦闘シーンが「アニメのロボットもの」と「実写特撮もの」の良さを兼ね備えている。
つまり、作画においては、ほとんど文句なしで、特にメインの2人の美少女キャラ(アカネと六花)は、単なる見た目の良さだけではなく、含みのある性格や感情の動きなどが繊細に表現されていて、とても魅力的に仕上がっていた。
したがって、放映当時に大人気となったのは、単に絵面が良かったというだけではない。今どき、それだけなのであれば、あれほど騒がれはしなかったのである。

本作の「戦闘シーン」の素晴らしさは、やはり、「ウルトラシリーズ」で知られる実写特撮の老舗「円谷プロダクション」の製作(実際にアニメを「制作」したのは、アニメ制作会社「トリガー」)ということが大きいだろう。
また、そもそも本作は、円谷プロがかつて制作した実写特撮ドラマ『電光超人グリッドマン』のアニメ化作品なのだから、「実写テイスト」が盛り込まれるのは、いわば必然なのだ。
例えば、本作『SSSS.GRIDMAN』の、グリッドマンと「怪獣」との市街地での戦闘シーンには、それまでのアニメではほぼ無視されていた「電柱・電線」が巧みに描き込まれていて、グリッドマンや怪獣の巨大感を、実写特撮以上に見事に表現している。


しかしまた、当然のことながら、単に実写特撮的な戦闘シーンを、アニメ表現に移しているだけではない。
本作の戦闘シーンでは、明らかに、テレビアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』や実写特撮映画『シン・ゴジラ』などの庵野秀明作品が参照されているのだが、周知のとおり、庵野秀明その人が「特撮ファン」なのだから、本作『SSSS.GRIDMAN』の場合は、「実写特撮→アニメ」という流れが「複層化」されており、その分、洗練度を高めてもいるのである。


だが、肝心なことは、本作『SSSS.GRIDMAN』は、単なる「実写特撮ドラマの(忠実な)アニメ化」でもなければ、「作画が素晴らしい」というだけの作品ではないという点だ。
原作の『電光超人グリッドマン』の世界観を踏まえながらも、キャラクターや物語などは、全くのオリジナル作品として作られており、しかも、全12話を通しての「仕掛け」に満ちた作品となっていて、いやが上にも、見た者を、謎解きの「考察」へと引き込むような、凝った作りの作品になっている。

そんなわけで、ここからは、本作『SSSS.GRIDMAN』の「世界観」についての考察が中心となるので、本編を未見の方には、まず「シリーズ全編を鑑賞し終わってから、本稿をお読みください」と、「ネタバレ注意報」を出しておきたい。
そこまでして、本稿を読む気がないという方には、「本稿は読まなくても良いから、是非とも『SSSS.GRIDMAN』は見ろ」とオススメしておこう。
『SSSS.GRIDMAN』が、「歴史的な傑作」だとまでは言わないけれども、見る価値は十分にある「89点」の作品だとは、保証しておきたい。
だから、作品本編を見た上で、もしその気になれば、本稿に示した作品解釈と、それに基づく「滅点」理由を知った上で、各人がそれぞれに本作『SSSS.GRIDMAN』を採点していただければ、本作のファンとして幸いである。

○ ○ ○
【以下で、本作『SSSS.GRIDMAN』のネタを割りますので、未見の方はご注意ください】
本作の「仕掛け」とは、ひとことで言うなら、「メタフィクション」的な世界観を持った作品、だということになろう。
と言うのも、原作である実写特撮ドラマ『電光超人グリッドマン』(1993〜1994年)という作品自体が、「電脳空間」での戦いを描いた、その意味では、すでに「メタフィクション」的構造(額縁構造)を持った作品であり、早すぎた「サイバースペース」アクションだったのだ。

ちなみに、パソコンが一般家庭にまで広く普及するきっかけとなったのは、OS「Windows95」の発売が1995年であり、間接的にではあれ「サイバースペース(電脳空間)」を描いた先駆的な作品として知られるのが、日本の劇場用アニメ『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』(1995年)。そして、同作の影響下に「サイバースペース」の「仮想世界」を映像化してみせたのが、アメリカ映画『マトリックス』(1999年)で、こうした歴史を考え合わせるならば、『電光超人グリッドマン』の「世界設定」の試みが、いかに先駆的なものであり、ある意味では無謀な冒険だったのかも理解できよう。
今の時代の人ならば、「サイバースペース」の物語だと言われても、「ああ、そうですか」というくらいにしか感じられない。なにしろ私たちの生活のかなりの部分が「SNS」という「サイバースペース」上で行われているのだから、もはや「サイバースペース」とは「異空間」ではなくなってしまったわけなのだが、『電光超人グリッドマン』の頃には、「スマホ」はおろか、「パソコン」さえ一般には普及していなかったのだから、「電脳空間」と言われても、多くの人には、ファンタジー的な「異世界」と大差のないものとしか理解されておらず、説明されてもチンプンカンプンな人が大半だったのである。

だが、本作『SSSS.GRIDMAN』が作られた「2018年」には、すでに学生たちの間にもスマホが当たり前に普及して、もはや体の一部にも等しいものとなっている。
したがって、『電光超人グリッドマン』が描いたような「電脳世界(サイバースペース)」をそのまま描くだけでは、むしろ「原始的」にさえなってしまうのだから、そのあたりで必然的に、本作『SSSS.GRIDMAN』は、今日的に「バージョンアップ」された「複雑な世界観」を描いている。
そして、その「世界観」の種明かしが、物語後半から徐々になされてゆき、最後の最後で「すべての真相」が「暗示」されて、物語は幕を閉じるのだ。
つまり、一応の「説明」はなされているのだが、それがすべて「言葉でわかりやすく説明」されているわけではないので、見終わった視聴者の多くは「ああ、そういうことだったのか。一一でも、では、あのへんはどういうことになるのだろう? 結局あれは、なんだったのだろう?」という疑問が、少なからず残ってしまう。そのために、『SSSS.GRIDMAN』は、見終えた段階から「理解しようとする考察が始まる」といった作品になっているのである。
そんなわけで、この作品を論評するためには、どうしても本作の世界観や作品構造を、すべて明かした上でないと、そこから先を語ることが出来ない。
したがって、本稿も、ここからは、まず「作品世界の構造」を説明し、その上で、残された「謎」についての考察を進めるという段取りになるので、もう一度、ここでも「警告」を発しておきたいと思う。
【本作『SSSS.GRIDMAN』の「作品構造」をバラしますので、ご注意ください】
本作は、ごく簡単に言うと「夢オチ」の作品である。
だが、無論、単なる「夢オチ」ではないし、「夢オチ」だから「くだらない」ということでもない。
本作のオープニング主題歌「UNION」(作詞:大石昌良 / 作曲:大石昌良 / 編曲:Tom-H@ck / 歌:OxT(オーイシマサヨシ・Tom-H@ck))の歌詞が『目を醒ませ』から始まっているのも、物語が、主人公の少年・響裕太(ひびき ゆうた)の覚醒シーンから始まるのも、この作品が、「夢」というものと切っても切れない関係にあることを如実に示している。
では、この「夢」は「誰の見ている夢」なのかだが、それは裕太の高校のクラスメートで、『周囲からは才色兼備な好人物として認識されている』が、
『裏では自分の意に沿わない人間を怪獣で殺害し、その様子に狂喜する残虐性をもつ(※ 少女)。(※ 裕太たちがしばしば屯する)「JUNKSHOP絢」の隣にある豪勢な一軒家でひとり暮らしをしているが、邸内は大量のごみ袋と怪獣フィギュアで埋め尽くされており、私生活は破綻している。』
(Wikipedia「SSSS.GRIDMAN」)
そんな美少女・新条アカネの「夢」であったらしいことが、最終話(第12話)の最後の「実写シーン」で示されるのだ。
つまり、アニメ『SSSS.GRIDMAN』に描かれた「アニメ」の世界は、すべてこの最後に登場する「新条アカネ」と思しき「実写の少女」の見ていた「夢の世界」だと言えるのである。
だが、そんな『SSSS.GRIDMAN』の「アニメ内世界」で説明される、その世界の成り立ちは、もっと複雑だ。
その「謎めいた世界」設定を、端的に示す、第1回「覚・醒」と第2回「修・復」の「あらすじ」を見てみよう。
第1回「覚・醒」
『響裕太は、自身の名前を含めあらゆる記憶を喪失した状態で、(※ クラスメイトの)宝多六花の家であるジャンクショップ(※ 「絢」)で目を覚ます。そして裕太は、店に陳列された古いパソコンに宿ったグリッドマンなる存在から、自分の使命を果たすように促される。翌日、同級生の内海将や新条アカネに助けられながら日常を送る裕太だったが、放課後、突如として怪獣グールギラスが街に現れる。裕太はグリッドマンに導かれるがまま彼と合体。実体化したグリッドマンは六花が(※ パソコン通信で)送った内海の指示によってグールギラスを撃破する。』(前同)


第2回「修・復」
『グールギラスを倒した翌日、裕太たちは被害を受けたはずの学校(※ や街)が修復され、さらに同級生の問川ら数名のクラスメイトがいないことに疑問を抱く。裕太たちはサムライ・キャリバーを名乗る(※ 味方らしい)男とクラスメイトの家を周り、問川たちが既に(※ ずっと以前に)亡くなっていること(※ になっていること)を知る。一方、怪獣を生み出した張本人であるアカネは、今度は(※ その態度が気に障った)学級担任を殺すために(※ パソコンの中から話しかけてくる怪人)アレクシス・ケリヴと共に怪獣デバダダンを作り出す。裕太は被害を抑えるため、(※ データ量を)最適化され(※ 動きの良くなっ)たグリッドマンと合体。グリッドマンは光線を弾くデバダダンに苦戦するが、キャリバーが変身した(※ 武器)グリッドマンキャリバーを用いることで勝利を収める。』(前同)
このように、本作の「世界」は、裕太が覚醒し、さらに古いパソコンの中から呼びかけてくるグリッドマンの求めに応じるところから、「作品世界」が幕を開けるのだ。
言い換えれば、「裕太とグリッドマン」の干渉以前からあったらしい(物語開幕以前の)世界こそが、新条アカネが、その願望のままに創造した世界なのである。

だが、勘違いしてはならないのは、ここで言う「新条アカネ」とは、最終話で初めて登場する、シルエットの「夢から醒めた、実写の少女」のことではなく、あくまでも、アニメの中のキャラクターである「新条アカネ」のことである。
「実写の少女」と「新条アカネ」とのつながりは、最終話で「宝多六花(たからだ りっか)」がアカネにプレゼントしたパスケースが、現実の少女の部屋に置かれていることから、一見すると、アカネが「現実世界」に持ち帰ったかのように思えるが、しかし、元から現実に持っていたパスケースが「夢」の中に登場したのだとも考え得るから、そう単純に「新条アカネ→実写の少女(そのもの)」と決めつけるわけにもいかないのである。


さて次は、こうした「(実写部を含まない、アニメ)作中の世界観」が明かされる第6回「接・触」のあらすじを紹介しよう。
第6回「接・触」
『裕太は校外学習でのアカネの問いかけから、彼女が(※ 裕太ら3人以外は失っているはずの)怪獣の記憶を持っていると推察するものの、周囲に相談する機会を逃し悶々としていた。そんな折、裕太は怪獣を名乗る少女と遭遇し、押し切られる形で行動を共にする。裕太は少女からツツジ台の外には何も存在しないこと、怪獣を生み出す人物がアカネで、彼女が(※ この「ツツジ台」)世界の創造主であることを告げられる。一方、グリッドマンが裕太であるとアカネから知らされたアンチ(※ アレクシス・ケリヴが創造した、自我を持つ怪獣で、日頃は人間の少年の姿をしている)は、(※ 怪獣)少女と別れた直後の裕太を襲撃するが、(※ グリッドマンの仲間で、裕太らを守る四人組「新世紀中学生」の、うちの2人)キャリバーとマックスによって阻まれる。アンチは彼らに裕太を殺すと(※ 宿敵認定している)グリッドマンを倒せなくなる(※ という)矛盾を指摘され、やむを得ず撤退する。』(前同)

つまり、ここで明らかになるのは、主人公の響裕太をはじめ、メインキャラクターである、クラスメートの内海将(うつみ しょう)や宝多六花なども含む作中の「人間」は、すべて新条アカネが創造したキャラクター、「理想のクラスメート」や「ツツジ台の隣人」でしかなかった、という事実である。


ところが、そんな、自分の作った「理想のクラスメイト」「理想の街(ツツジ台)」も、アカネにとっては、常に「完璧なもの」ではあり得ない。
それはたぶん、なんの不満も感じない他人とは、当然、すべて似たり寄ったりになってしまい、それはそれで、個性のない人々として面白みがなく、満足できない存在だからではないだろうか。
つまり、「理想のクラスメイト」とは、じつは「欠点やクセのある人物も含めて」のことなのだが、若い新条アカネは、そのことに気づいていない。
だから、彼女は、この「理想のツツジ台」世界を、そこに住む人々を含めて「作っては削り、作っては削り」の一部修正を加え続けていたのであり、その意味で彼女は、その見かけとは裏腹な「荒ぶる破壊神」でもあったのだ。
本作では特に印象的な「街の彼方に見える怪獣の影」とは、アカネが創造したこの「ツツジ台世界」を修復管理する「管理機構」のようなもので、アカネが不必要だと思ったものは取り除き、取り除いたものな関する記憶を抹消するといった一切の作業を請け負った存在で、いわゆる「怪獣」として暴れることはない。
では、どうしてそんなものが「怪獣」のかたちをしているのかと言えば、それはアカネが女子には珍しい「怪獣オタク」だからであろう。だから、世界の管理機構に、仮初のカタチとして「怪獣」の姿を与えたにすぎないのだ。



したがって、オープニングをはじめ、作中でもしばしば描かれる「街の彼方に見える怪獣の影」は、当初は「ツツジ台」の住人たちの誰にも見えてはいない。
もちろん、アカネには見えているが、アカネ以外で、最初にその「怪獣の影」に気づくのは、「外部からやってきたグリッドマン」の影響を受けた裕太であり、その後、悠太の影響で、親しい友人の内海将や宝多六花にも、それが見えるようになり、世界改変の記憶も残るようになる。
さて、こうしたことからわかるのは、少なくとも「グリッドマン」は、作中の(アニメの)新条アカネが生み出したものではなく、アカネの生んだ「ツツジ台世界」の外からやって来た存在だ、ということである。
そして、もう一人の「外からの来訪者」とは、アカネが作った粘土細工の怪獣を、(アニメの)作中世界で「実体化」させる謎の怪人アレクシス・ケリヴだ。アレクシスは、見るからに「悪役の異星人」キャラなのである。

アレクシスは、グリッドマンと同様、当初はアカネのパソコン画面に登場し、そこからアカネに親しく話しかけ、アカネに怪獣を作るように促し、アカネの作った粘土細工の怪獣を実体化させる。
なぜ、このようなことをするのかというのは、今ひとつ分かりにくいところなのだが、ただ、ひとつ言えることは、アレクシスはアカネの「憎悪」を煽る存在だということだ。つまり、アカネの中にある「不全感」的なものを煽って「憎悪」にまで高めることをしているのである。

で、ここまで来れば、アレクシスの狙いは、おおよそ見当がつくだろう。要は、彼は、人間(など、知的高等生物)の「憎悪の念」を摂取して活動している、非肉体的な不死の存在なのだ。だから、彼は、「大きな不全感」を抱える人間にとり憑いて、その憎悪を煽り、人の心を蝕みながら、その力を増大させる、「悪」の存在なのである。
そしてここからは、ほとんど推測だが、新条アカネは、作中ではハッキリとは描かれない何らかの理由によって、現実世界に大きな「不全感」を抱えており、そのために「理想の世界」を作ってその世界の中に引き篭もろうとしていたのようなのだ。
だが、そうした彼女の弱さにつけ込んだのが、外から来たアレクシスだった、というようなことのようである。
では次に、本来「人間」であるはずの新庄アカネは、「(虚構の)ツツジ台世界」を「どこに」作ったのだろうか? 一一その答えは、第7回「策・略」で、絵的に示される。
第7回「策・略」
『裕太は怪獣少女から告げられた(※ ツツジ台世界の)真相を内海や六花に話すが一笑に付される。放課後、裕太は(※ アカネ)本人に直接話を聞こうと決心するが、その矢先に自室に侵入したアカネと邂逅。アカネから手を組むように勧誘され、アレクシスの存在を知る。そんな時、アレクシスがアンチの頼みで生み出したUFOが夜の街に現れる。グリッドマンはいくら倒しても再生するUFOに苦戦するが、(※ 「新世紀中学生」の一人ヴィットの本来の姿である、グリッドマンの援助メカ)スカイヴィッターと合体したスカイグリッドマンになることで、上空でUFOを操る怪獣ヂリバーとアンチを発見し、2体を撃退する。戦闘後、内海たちはグリッドマンが戦闘中に見た上空の街の存在から裕太の(※ ツツジ台は、アカネの作った虚構世界であるという)話を信じることとなり、裕太はただ街を救うだけが使命でないと自覚する。一方、アンチは用済みと判断され、アレクシスに処分されかける。』(前同)


ここで『上空の街』として示されるのが、実写の原作『電光超人グリッドマン』の戦闘シーンの舞台となる「(都市的な)電脳空間」である。
つまり、アカネが「ツツジ台」を作ったのは「サイバースペース」内であり、要は、彼女は、パソコンによって、パソコンの中に、彼女の「ツツジ台」と作ったのだ。
当然、その中にいる者には、その世界内主観からして、そこが十全にリアルな世界に見えているが、実際のところは「第6回」に登場した「怪獣少女」が、その世界観を説明した際に(イメージ動画として)示された「パソコンゲームの世界」のような「小宇宙」にすぎないのである。
さて、ここまでをいったんまとめれば、こんな感じになるだろう。
一一現実世界に馴染めず「不全感」抱えている新条アカネは、パソコンの中に、自分の理想世界としての「ツツジ台」を作り、その世界の神として暮らしていたのだが、そんな彼女の心に、「外」から来たアレクシス・ケリヴがとり憑いて、彼女の「憎悪」を煽り立てていた。
そこへ、そうしたアレクシスを追ってきたグリッドマン(ちょうど『ウルトラマン』第1話の、ベムラーを追って地球にやってきたウルトラマンに相当する)が、アカネの作った「ツツジ台」に入ろうとした際、そこでデータ容量などで問題が生じてしまい、グリッドマンの記憶自体が失われて、さらに彼の能力の一部が別物として外部化されてしまうということにもなるのである(それが、アシストウェポンの擬人化である「新世紀中学生」の4人)。



中段が、左からサムライ・キャリバーとマックス。
下段が、ヴィットとポラー)
そんなグリッドマンの本来の目的とは、アレクシスの捕獲逮捕であり、そのために、アレクシスからアカネを解放して、アカネを救うことでもあったのだが、その記憶が失われてしまい、ただ、わずかに残された本能的な記憶に従って、グリッドマンは悠太と合体して、「ツツジ台」を襲う怪獣たちを退治していたのである。
さて、ここで、今更のように打ち明けるが、私は本作の原作である『電光超人グリッドマン』の方は見ていない。
だから、同原作について持っている知識といえば、本作『SSSS.GRIDMAN』の放映当時に、その原作と知って、主題歌をカラオケで歌ったので、そのカラオケ映像を見た程度。
あとは、今回、本稿を書くために「Wikipedia」を読んだくらいである。
つまり、大筋は理解しているつもりなのだが、しかし、なにしろ本編自体は見ていないから、その理解に確たる自信まではないのだ。
ただ、本作『SSSS.GRIDMAN』は、「原作を見ていなくても楽しめる作品」として作られているので、本作は本作として、独立した作品として評価するのが、ある意味では、作品評の本道ではあろう。
無論、原作の『電光超人グリッドマン』の方も知っていれば、本作の作り手が、原作のどのあたりを採用し、どのあたりを捨てたかがわかるので、作品を理解しやすくはあろう。だがそれは、半ば「裏情報」に類することなので、作品理解のための情報としては、あくまでも二次的なものだと言えるから、私はそうした情報を、自明の前提とはしないという立場で、この論考を書いているのである。
さて、そんなわけで、ここまでの説明で、本作『SSSS.GRIDMAN』という作品の「メタフィクション」的な基本構造というのは、おおよそのところはご理解いただけなのではないかと思う。
つまり、「アニメ『SSSS.GRIDMAN』に描かれる、悠太たちの街・ツツジ台」を、本作の「表層世界」だとすると、その下には、より「現実に近い世界」が、下のように、階層的に存在しているのだ。
(1)「アニメ『SSSS.GRIDMAN』に描かれる、悠太たちの街・ツツジ台」
↓
(2)「アカネの作ったパソコン内のツツジ台」
↓
(3)「サイバーワールド」
↓
(4)「アカネらしき実写の少女の夢」
↓
(5)「実写の現実」
↓
(0)「『SSSS.GRIDMAN』を鑑賞する私たちの現実」
最後の「『SSSS.GRIDMAN』を鑑賞する私たちの現実」を(0)としたのは、これはもう「作品外の現実(そのもの)」だから、作品とは別物としたためであり、『SSSS.GRIDMAN』の作品世界とは(1〜5)までである。
だが、このように整理した上で、ここで考えていただきたいのは、作中での「作中世界の説明」(第6話)の中心となる(1〜2)は、じつは、「ウルトラシリーズ」にはよくあるパターンであり、その意味でもっともらしくはあるものの、しかし実のところ「自己言及のジレンマ」を露骨に含んでいる、という点である。
つまり、作中のアニメの新庄アカネは、新条アカネのパソコンの中の「ツツジ台に存在する、作られた新条アカネ」なのか否か、という問題だ。
新条アカネが、パソコンの中のアレクシスと話しているシーンがほぼ毎回あるのだが、この時、アレクシスの顔が映っているディスプレイ画面の付いたパソコンの中に、アカネが作った「ツツジ台」の世界が存在しているのだろうか?
そうだとすると、パソコンの前に座っているアカネとは、パソコンの中の作られたアカネの「創造主」としてのアカネなのか、それとも被造物としての「ツツジ台の一部のアカネ」つまり「創造主としての(大文字の)アカネを投影した、(大文字の)アカネによって作られた(小文字の)アカネ」なのだろうか?

そろそろ読者の頭も混乱してきたと思うが、私がここで言いたいのは、パソコンの前に座っている新条アカネは、「作った方のアカネなのか、作られた方のアカネなのか」は、たぶん「決定不可能」だということである。
つまり、この問いにおいては、次のような無限循環を止めることができないのである、
(1)→(2)
↑ ↓
(2)←(1)
したがって、この問題を解決するためには、(1)と(2)の世界内部には、「真の創造主たる人物」は存在しない(自己完結していない)、ということになる。
つまり(1)と(2)は、実は「2つ合わせて1つの世界(創作物)」であり、それが置かれているのが(3)の「サイバーワールド(パソコン内世界)」だと考えれば良いわけだ。
しかし、そう考えると、今度は(1)の世界の外部である(2)の世界を描いているはずの「第7回」で、『上空の街』として(3)が登場するのは、これまた「自己言及のジレンマ」を含んでしまうことになる。
なにしろ(1〜2)の外部にあって、(1〜2)の世界からは見えないはずの(3)の世界が、「ツツジ台の外の上空の街」だとは言え、裕太たちに見えてしまうというの、おかしい。
つまり、上の図を少しいじると、こうなる。
(1〜2)<(3)
v Λ
(3)>(1〜2)


そんなわけで、この物語が、完全に「矛盾」を孕まないようにするには、「アニメ」の外の、隔絶した特権的外部世界を描かなければならなかった。
それで、アニメの中には存在し得ないものとして、必然的に「実写世界」を導入せざるを得なかったのではなかったか。
そしてまた、この「実写世界」も、「フィクション」であり、これが実写特撮ドラマである、原作の『電光超人グリットマン』と同階層の世界であることにおいて、本作『SSSS.GRIDMAN』は、その特異な作品世界を、閉じることができたのではないだろうか。
○ ○ ○
さて、ここまでは、もっぱら「作品の形式」という側面に注目して『SSSS.GRIDMAN』という作品を見てきたが、ここからは、この「多層構造」が、何を意味していたのかについて、「物語の内容」に即して考えてみよう。
その場合、作中での「現実」とは、「目覚めた実写の少女」の「現実世界」だということになるから、(1〜3=4)ということになるだろう。つまり、アニメ部分である(1〜3)は、すべて「実写の少女」が見た「夢」としての(4)だということになる。そして(4)は(5)の一部だ。
では、この(5)の世界に住む「実写の少女」の見た(1〜3=4)の世界、つまり「アニメの世界=夢」とは何なのかといえば、もちろん、「実写の少女が見た、アニメの夢」ということになる。
だが、「そんな夢を見る奴なんているのか?」と普通は思うだろうし、その疑問は、至極もっともなものだと思う。
仮に「実写の少女」が「怪獣オタク」だったとしても、わざわざ「アニメ」の夢を見ることはなく、「怪獣の登場する、実写風の夢」を見るだろうから、この点については本作『SSSS.GRIDMAN』の「弱点」ではないかと、私は考える。

すでに説明したとおり、作品の「多重構造」を完結させるためには、最後に、アニメとは文字どおり「次元」を異にする「実写の世界」を導入することが必要だったのだろう。だが、そのために「実写の少女」が「アニメの夢を見ていた」という無理が生じたのである。
だが、こうした「形式的な無理」を踏まえた上で、無理にでもそれを正当化する理屈をつけるとすれば、「実写の少女」が抱えていた「現実世界」(5)での不満は、「実写」的なものでは叶えられない種類のものであった、ということにでもなるのではないだろうか。
一一例えば、新条アカネは「薄紫色の髪」であるけれども、それは「アニメ」では自然でも「実写」では、いかにも「作り物」くさく、嘘くさい。リアリティが無い。
つまり、「実写の少女」が願望した「理想世界」とは、「アニメ」的に、非現実的なまでに抽象化され理想化されてはいても、しかし「特撮実写ドラマの薄紫色髪の少女」みたいな「作り物くささ」や「嘘くささ」は認められないという、「矛盾した世界」だったのではないか。

これは、あくまでも「形式的矛盾」を孕んだ「実写の少女の理想」とジレンマという話だが、これは「実写の少女」の抱えるジレンマの「性質」を示していると考えることも出来よう。
つまり、アニメ本編が暗示しているように、「実写の少女」が「新条アカネ」に託した夢とは、「親のいない家庭」や「誰からも愛される才色兼備の人気者である自分」、それでいて、「エンディング映像」で示される当たり前の学生服(ブレザー)を着て、親友のように仲の良さそうな「宝多六花」との個人的な関係、さらに最終回で示される「六花の友情」ということを考えれば、「実写の少女」は、たぶん「家庭での親子関係」に問題を抱えており、かつ学校でも浮いた存在で、親友と呼べるような存在もいない、あるいは、六花に当たる親友の喪失経験などの、「孤独」を抱えていたのではないだろうか。




だから、そんな「実写の少女」が、自分の現実から逃避するためには「自分の理想世界を創造する、神のごとき新条アカネ」というアニメキャラクターの夢を、見なくてはならなかったのではないだろうか。
「現実の自分」が、少なくとも「外見」的にはほとんど反映されることのない異質な世界で、自分の理想世界を作る少女という「(ビジュアル的に)アニメ化された自画像の夢」を見なくてはならなかったのではないか。
一一以上は、多分に強引な「深読み」ではあろう。だが、ひとつの解釈としては、必ずしも間違ってはいないと思う。
仮に「特典映像」的なもので「実写版の美少女・新条アカネ」が登場したとしても、それは本編最終回の最後に登場した逆光によるシルエットの「実写の少女」とは、別物だと考えるべきだと、私は思う。
彼女はきっと、もっと「平凡な少女」なのである。だからこそ、こんな「極端に非現実的な夢」が必要だったのだ。
また、私が聞いていない、番外編的な「ボイスドラマ」などで示されたらしい世界観と、私が以上で示した世界観が一致しなくても、そもそも、その世界観は、一つである必要はないのではないだろうか。
なぜなら「実写の少女」が見る「夢」は、「毎回」通じて守備一貫したものだとは考えられないからである。
○ ○ ○
なお、最後に本作のタイトル『SSSS.GRIDMAN』の意味を考えてみたいと思う。もちろん問題は「SSSS」の部分だ。

検索してみると、この「SSSS」の部分が何を意味するのか、引っかかった人は少なくないようで、それに対しては、もっともらしい、いくつかの説明が、すでになされている。
その最も「現実的」な意味合いは、原作『電光超人グリッドマン』のアメリカ版タイトル『スーパー・ヒューマン・サムライ・サバイバー・スクワット』の略だというものだ。たぶん、そのとおりなのだろう。
だが、基本的には、そこから採られたものだとしても、こうしたタイトルには「多重の意味」が与えられていることも、ままあるだろうし、そもそも、アニメのタイトルに「原作のアメリカ版タイトル」を冠しなければならないという理由はない。
ならば、本作アニメ版に「特有の意味」も、そこに附与されていると考えても良いのではないだろうか。

そこで私が思いついたのは、一一「SSSS」の「S」は、じつは英語ではなく、日本語の「セカイ」の頭文字なのではないだろうか。
つまり、「SSSS」とは、『スーパー・ヒューマン・サムライ・サバイバー・スクワット』という意味を持ちつつ、同時に、アニメ版特有のものとして、「多重世界」を描いた作品だとの暗示であり、その意味するところは、この『SSSS.GRIDMAN』が、ある意味では「セカイ系」の作品だということだ。
では、ここで言う「セカイ系」とは、何かといえば、
『東浩紀らの定義によるセカイ系
インターネット上で流通した「セカイ系」という言葉が、活字出版物上に現れるようになったのは2004年頃からだとされているが、これ以降はインターネット外でも様々に論じられるようになる。その際、盛んに参照されたのは、サブカルチャーを論じる批評家として注目を集めていた東浩紀を中心に発刊された『波状言論 美少女ゲームの臨界点』編集部注によるもので、前島賢もこの同人誌の編集者であった。それによればセカイ系とは「主人公(ぼく)とヒロイン(きみ)を中心とした小さな関係性(「きみとぼく」)の問題が、具体的な中間項を挟むことなく、「世界の危機」「この世の終わり」などといった抽象的な大問題に直結する作品群のこと」であり、代表作として新海誠のアニメ『ほしのこえ』、高橋しんのマンガ『最終兵器彼女』、秋山瑞人の小説『イリヤの空、UFOの夏』の3作を挙げ、肯定的な評価を与えた。』
(Wikipedia「セカイ系」)
もちろん、『SSSS.GRIDMAN』は「きみとぼく」の二者世界ではないから、その意味では、オーソドックスな「セカイ系」の作品だとは言えない。
しかしながら、「セカイ系」という言葉に、決まった「定義」などは存在しないのだから、もう少し緩い意味で『SSSS.GRIDMAN』も、「セカイ系」少女の内面世界を描いた作品として、「セカイ系」の作品と考えることもできるのではないだろうか。
また、『SSSS.GRIDMAN』の場合の二者関係とは、じつのところ「アカネと六花」の関係なのかもしれない。

では、本作『SSSS.GRIDMAN』においては、「実写の少女」における「セカイ系」性は、制作者から、どのように考えられていたのだろうか。
私が思うには、それはやはり当たり前に、「目を醒まして、もう一度、身の回りの現実世界(社会)を見つめ直してみよう。そんなに悪いものでもないはずだ」といったことなのではないだろうか。
アニメで描かれた「神としての新条アカネ」が、最後は、自分の被造物であるはずの宝多六花に、これまでのことを謝罪し、六花に励まされて、その「自作世界」を去り、自身の「現実世界」に目覚めるという流れは、そのことを示しているように思う。
アニメでも実写ドラマでもそうだが、そうした「フィクションの世界」は、「現実世界」への絶望のせいで死なないための、生きるための「避難場所」として、時に機能する。
しかし、それでも、そこは「一時的な避難場所」でしかなく「永住の地」ではあり得ない。
そして、そのことを教えてくれる「親友」とは、「フィクション」の世界のキャラクターであってもかまわないし、フィクションのキャラクターにも、人を励まし、人の一生を変えるような「親友」性があるということを、「新条アカネと宝多六花の別れのシーン」は語っているのではないだろうか。
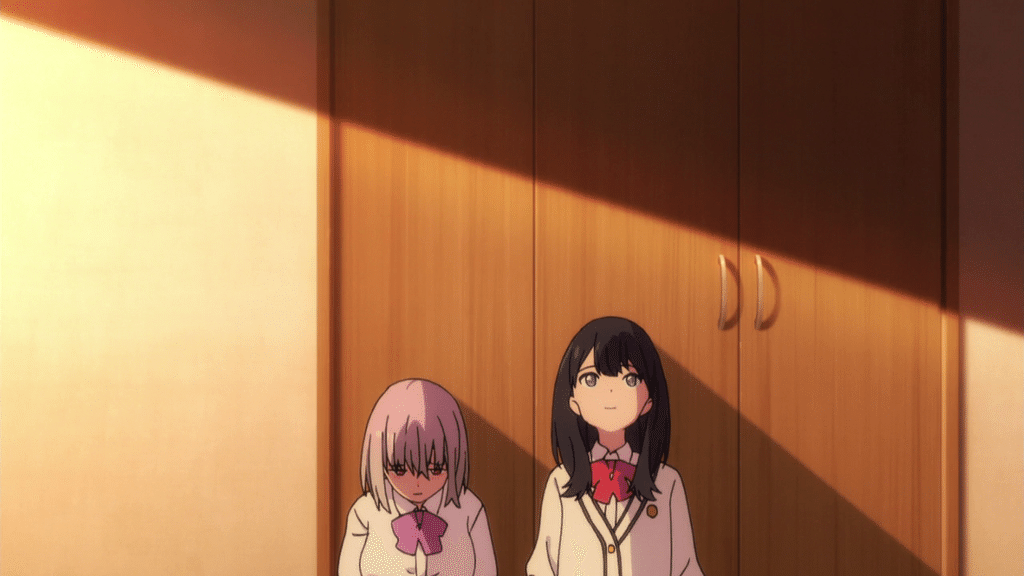
また、だからこそ、自身の被造物だとは言え、あれだけ多くの人を殺したアカネが、最終回でのグリッドマンの「フィクサービーム」で、あっけなく「まともな人間」になってしまうのも、「フィクサー」とは、「浄化」ではなく「調停役」という意味だからだろう。
つまり、この場合はアカネだが、「フィクサービーム」とは、それを浴びた人が、それで浄化されて「変わる」のではなく、その人が変わるための、世界との「調停をする」だけ、なのではないか。
つまり、変わるのは、最終的には、やはり当人の意志なのである。
そして、「夢」の中では暴虐のかぎりを尽くした「実写の少女」も、思うにまかせない現実を生きるひとりの少女として、「夢の中の親友」から、世界との和解をうながされ、その機会を与えられた、ということだったのではないだろうか。

(2024年11月29日)
○ ○ ○
● ● ●
・
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
