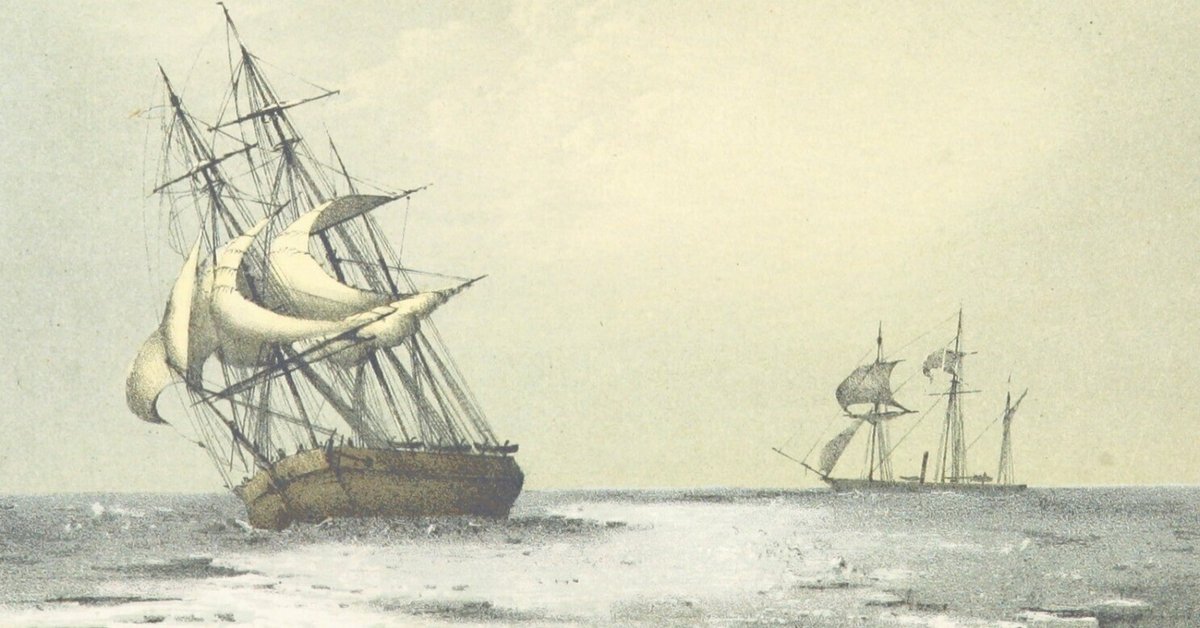
大海を照らす灯台 ジョン・サザーランド『若い読者のための文学史』
ジョン・サザーランド『若い読者のための文学史』(河合祥一郎∥訳、すばる舎、2020)
すべての作家に敬意を表しますが、以下、敬称略
著者はイギリスの現代英文学の名誉教授であり、著名な作家であり文学評論家である。また、本書の目的は全世界の文学および作家を網羅的に解説することではなく(原題はA Little history of literature『文学小史』、2013)、著者の言葉を借りるなら「『多くの人が大切だと思ってきた作品なので、あなたもそう思うかもしれないが、最後は自分で決めてください』式の助言』、「文学をざっくり概観するのが目的」のものだ。
従って、短いチャプター1~40までの中に神話や叙事詩から今日の世界文学、そしてそれを取り巻く出版界や文学賞事情までを、イギリス流のユーモアをたっぷり含んでぎゅっとまとめているため、扱われるのは主に西洋の作品だ。日本の作家はグローバル化の文脈で村上春樹が出てくるだけ(あとがきを抜いて367ページのうち、1ページ分にも満たない。川端や大江ではないのだ)。訳者の方も、「スタンダールとかサマセット・モームとか完全に無視?」とあとがきで驚いてみせている。けれども、もう一度言うと、本書は古代から現代までの文学の概観を示し、自分なりの文学の楽しみ方を見つけられるようにするためのものだ。
簡潔な概説書をさらに要約するのは困難なので、まずはチャプタータイトルを列挙する。
1. 文学とは何か(C・Sルイス/ディケンズ)
2. すてきなはじまり 神話(ホメロス/キーツ/ハーディ)
3. 国民のために書く 叙事詩(ホメロス)
4. 人間であること 悲劇(アイスキュロス/ソフォクレス/エウリピデス)
5. イングランドの話 チョーサー(チョーサー/ガウェイン詩人)
6. 街頭演劇 ミステリー劇(『第二の羊飼いの劇』作者)
7. 詩聖 シェイクスピア(シェイクスピア)
8. 本の中の本 欽定訳聖書(ティンダル)
9. 縛られぬ心 形而上詩人(ダン/ハーバート)
10. 国民の興隆 ミルトンとスペンサー(ミルトン/スペンサー)
11. 文学は誰のもの? 印刷・出版・著作権(グーテンベルク/キャクストン)
12. フィクションの家 (ボッカチオ/ラブレー/セルバンテス/バニヤン/ベーン)
13. 旅人の法螺話 デフォー、スウィフト、小説の興隆(デフォー/スウィフト)
14. 読み方 ジョンソン博士(サミュエル・ジョンソン)
15. ロマン派の革命家たち (キーツ/バイロン/ワーズワース/ブレイク)
16. 研ぎ澄まされた精神 オースティン(オースティン)
17. あなたの本 変貌する読者層(リチャードソン/フィールディング)
18. 巨人ディケンズ (ディケンズ)
19. 人生文学 ブロンテ姉妹(シャーロット/エミリー/アン・ブロンテ)
20. 毛布の下で 児童文学(キャロル/トウェイン/トールキン/ローリング)
21. デカダンスの華 ワイルド、ボードレール、プルースト、ホイットマン(ワイルド/ボードレール/プルースト/ホイットマン)
22. 桂冠詩人 テニソン(テニソン)
23. 新しい土地 アメリカとアメリカの声(ブラッドストリート/ホイットマン/トウェイン)
24. 偉大なる悲観論者 ハーディ(ハーディ)
25. 危険な本 文学と検閲官(フローベール/ボードレール/D・Hロレンス)
26. 帝国 キプリング、コンラッド、フォースター(キプリング/コンラッド/フォースター)
27. 不運な国家 戦争詩人(サスーン/オーウェン/ブルック/ローゼンバーグ)
28. すべてに挑戦した年 1922年とモダニストたち
29. 彼女自身の文学 ウルフ(ウルフ)
30. すばらしき新世界 ユートピアとディストピア(ブラッドベリ/ハクスリー/オーウェル)
31. 仕掛けの箱 複雑な語り(スターン/カルヴィーノ/オースター)
32. ページを離れて 文学と映画、テレビ、舞台(オースティン/ミッチェル)
33. 不条理な人生 カフカ、カミュ、ベケット、ピンター(カフカ/カミュ/ベケット/ピンター)
34. 壊れた詩 ローウェル、プラス、ラーキン、ヒューズ(ローウェル/プラス/ラーキン/ヒューズ)
35. 色とりどりの文化 文学と人種(ナイポール、エリソン、モリスン)
36. マジック・リアリズム ボルヘス、グラス、ラシュディ、マルケス(ルヘス/グラス/ラシュディ/マルケス)
37. 文学の共和国 境界のない文学(ラクスネス、モー、村上春樹、シンガー)
38. 罪悪感のある快楽 ベストセラーと金儲けの本(リチャードソン/スコット/ユゴー)
39. 誰が一番? 賞、採点、読書グループ(パステルナーク、ソルジェニーツィン)
40. 文学とあなたの人生 そしてその向こう(マクルーハン/ギブソン)
タイトルに出ていない作家も本文中では触れられている。わたしの興味の範囲でいえばチャプター15以降が胸躍るけれど、チャプター1~14のおかげで、すべての文学がそれまでの積み重ねの上に、加えたりひねったりしつつ新しいものを生み出してきたことがわかる。一直線に“進歩”や“成長”してきたような文学史観はない。
冒頭の「文学とは何か」が、児童文学を例にして書き出されるのが嬉しいところだ。サザーランドも20章で言うように、文学の中で「子ども」は19世紀に発見された。そこから児童文学は誕生し、現在では年齢の垣根を越えて楽しまれている。「文学とは何か」で言及される『ナルニア国物語』シリーズでは、第二次大戦最中に疎開してきた四兄妹が、異世界に通じる洋服箪笥をくぐり抜けてロンドン大空襲の悪夢から逃れる。しかし、その異世界ナルニアとて危険に満ちた場所なのだ。ナルニア国物語に限らず、優れたファンタジーはアレゴリーだ。子どもに直接教えることが難しいことでも文学なら可能になる、という捉え方もできるし、本書の他の章で解説されるように、厳しい検閲・統制をかいくぐるために文学的表現が磨かれたという側面も併せ持つ。
チャプター16では、著者はウルフと並んで1960年代以降の第二波フェミニズム運動で高く掲げられたオースティン作品の内容について、フェミニズムという観点からは懐疑的だと述べる。(というか、「男性を女性より上に考える見方を一度たりとも問題視していない」と書いている。そうか?という疑問は数あるオースティン批評に任せる。)それでもなお、オースティン自身が皮肉を交えて「象牙の2インチ四方ぐらいの小さなところに、とても繊細な筆で描くのです」と喩えたことを引用しながら、著者は「オースティンの小説によって、文学作品は偉大であるために大きなものでなくてもよいということが、すごくよくわかる。2インチの象牙に何が含まれ得るか。天才の手にかかれば、書くに値することはすべて含まれ得るのである。」と章を締めくくる。神話や叙事詩といった大きな物語で始まり男性的権力を帯びていた文学だが、女性の手によって小さな世界観ですべてを描いてみせたのは、十分フェミニズム的事実ではないかと思う。逆に、近代化の中で学問としての権威を高めるために文学の科学性と男性性を強めていった過程についてはイーグルトンが詳細に説明してくれていたと思うので、また今度記録を書きたい。
対照的に、チャプター23では、アメリカ文学は女性(アン・ブラッドストリート)の声(「本質的に新世界の詩」中略「まったく新しい声だ―アメリカの声であり、さらに言えば、新しい国を作っているアメリカ人の声だ」)から始まること、そして英国文学とは反対にテーマが大きいことを説明している。英文学と米文学のテーマ性の違いについては、翻訳家の柴田元幸がある短編集のあとがきでも書いていた。柴田元幸つながりで思い出せば、『中国・アメリカ謎SF』では近年の作品を扱うが、同じ大陸かつ大国同士でも、問題を抱えながらも急成長している中国と、もはや新しい国ではなくパクスアメリカーナも過ぎ去ったアメリカとでは、こんなにも作品のトーンに違いが出るのかと驚いた記憶がある。
話は逸れるが、『ジェイン・オースティンの読書会』(原題:The Jane Austen Book Club、2007年、同名ベストセラー書籍の映画化。原書は未読)というのがあって楽しい映画だった。少しネタバレになるけれど、オースティンを読んだことがないのに参加することになってしまったSF好きの青年が、SFを軽視する主人公にル=グウィンを紹介するのがナイスだった。トロイア滅亡後の英雄の遍歴を描く、ウェルギリウスによる古代ローマの叙事詩『アエネーイス』を、その妻の視点から捉え直した『ラウィーニア』(初版2008)などは、消された女性の声を聞こうとする昨今の潮流にも良く合うものだと思う。『ハムネット』や『存在しない女たち』、『アダム・スミスの夕食を作ったのは誰か?』などもおいおいこの読書記録にまとめたい。(なお、本書には、ル=グウィンは高学歴で高い地位についた女性作家としての紹介しか登場しない。ハリー・ポッターが大ベストセラーになった当初、魔法使いの少年の児童書が大人気だと聞いてゲド戦記が再び流行っていると勘違いしたという彼女のエピソードをエッセイで読んだことがある。そんな彼女なら憤慨するかもしれない。いや、憤慨する暇なんかないわ、大切なことを考えるのに忙しくて、かも。)
(ウェルギリウスつながりで話は逸れるが、ラース・フォン・トリアー監督『ハウス・ジャック・ビルド』原題The House That Jack Built、2019という映画がある。自身の過去作品と真摯に向き合う努力を、一方で小馬鹿にしたというかおちゃらけムードで包んだ印象の映画だった。日本版公式サイトの惹句は「ゾッとするほど、魅力的」で、検索すれば、芸術の葛藤が描かれる、誰でもシリアルキラーになりうるなど様々なインタビューや考察や推薦コメントが見つかる。しかしながら!謎の語り手が後半に主人公と対面し、ウェルギリウスであると明かすのだが、すなわちその後二人が向かう地獄はダンテの神曲の世界なのだが、そこに触れた記事が公開直後ほとんどなかったことが残念だった。技師としては有能であったジャックは、サイコパスだったために建築家≒芸術家にはなりきれなかった。結末も踏まえると、露悪趣味や女性蔑視、殺人では素晴らしい芸術は創造できないというシンプルな主張の映画だったと思うのだけど。死体で作られた家というのは、グロテスクだが魅力的な芸術という比喩ではなく、ありあわせのもので作った二流以下の作品ということではないのか。ネタバレすみません。でも、エンドロールの曲もHit the road Jack だし、“魅力的”じゃないよジャックは。)
(話はもっと逸れるが、本書ではオースティンのチャーミングな翻案に映画『クルーレス』原題:Clueless、1995年を挙げている。若きアリシア・シルバーストーンが超絶可愛い!エマの翻案ではあるが……どちらかというと90年代後半からゼロ年代のファッション変身&人間成長もののノリに近しいと感じた。ミーン・ガールズとかシーズ・オール・ザットとかキューティ・バニー原題House Bunnyとかキューティ・ブロンド原題Legally Blondeとか。キューティ・ブロンドはセクハラの告発や「女子学生にばかりお茶くみさせるのよあの教授」みたいな台詞がさらりと入っている。Y2Kファッションがトレンドの今年、どれもそこまで古臭さを感じずに楽しめる。)
さて、チャプター29では、ウルフの『自分自身の部屋』を「フェミニズム文学の礎となるテクスト」だと述べている。ウルフとブルームズベリーの紹介とともに、彼女らを取り巻く当時の社会情勢を皮肉交じりに語るのだが、章の最後はヴァージニアの入水自殺(第二次世界大戦中、簡単にフランスを制圧したドイツの英国侵攻を危惧したウルフ夫婦は、慎重に自殺を計画していた)で終わる。「イングランドはそれよりも長く生きて、さらなる文学を、国をあげて生み出し続ける。モダニズムの時代の最大の女性作家には、そうすることはできなかったのである。」という一文が表す深い悲しみを、わたしは再現することができない。ぜひ本書を読んでほしい。
最後に
とりとめのない読書記録になってしまったが、最後に、これからの文学や書籍の行方について著者がとても前向きな展望を示していることが興味深い。紙の書籍が電子書籍に取って代わられる点については、グーテンベルクを引き合いに、とくに賛成とも反対とも言わない。(紙の本に似せてあるのが不気味だとは述べていた。マクルーハンがいうところのバックミラー主義だと。)未来の人にとって問題になるのは、お金ではなく時間だろう、と言う。現在は、プロジェクト・グーテンベルク(日本の青空文庫のようなもの)のような無料の電子図書館のおかげで、読める本の選択肢は無数に増大した。加えて、ひとつのデバイスから文学以外の多数の娯楽にアクセスできる環境の中、どれくらいの時間を読むことに費やせるだろうか、という懸念を示しながらも、全身参加型・インタラクティブな読書の可能性やファンフィクション(文学の流動性の復活)の存在を例に出して、将来的には「作り手であれ、読み手であれ、ある種の『一体感』を取り戻すだろう」と述べる。そして、「どのような新しい形に変化しようとも、永遠に私たちの人生の一部となって、人生を豊かにしてくれるはずだ(中略)私たちと言ったが、あなたたちと言うべきだろう――そして、あなたたちの子どもたちと。」と締めくくられる。
現在、実際には電子書籍へのアクセスは、地域によって、また経済状況によって平等ではない。電子書籍化されるかどうかは著作権と売上実績に左右されるだろうし、売上を左右する世界文学になれるかどうかという点は、いまだ英語で書かれたか(もしくは英語に翻訳されるか)だろう。本書のチャプター36マジック・リアリズムの紹介では、大部分がラシュディに費やされていた。日本でマジック・リアリズムといえば南米文学ブームを牽引したマルケス『百年の孤独』が代表作というイメージが個人的には勝手にあったが、これもラシュディがイギリス在住かつ英語で書いたからだろう。(英国の旧植民地政策が主題だというのも関係があるだろう。)
とは言え、繰り返しになるが本書は現代英文学の名誉教授であり、著名な作家・文学評論家が若者のために西洋の文学史を概観したものだ。長らく母国語で文学を生み出せなかった国々においても、現地語で書くことを選択する作家が増えてきたと聞くし(出典忘れました)、ノーベル文学賞も多様性・多言語を重視するようになってきたというし、ここら辺の事情については最近買った『「その他の外国文学」の翻訳者』(白水社、2022)を読んでみて、また感想をまとめられたら、と思う。
いつまでも文学が私たちとともにありますように!
詳細はこちら↓
『若い読者のための文学史』
※わたしの文章は”書評”ではないので、専門家による書評を望まれる方は、2021-04-18 読売新聞 朝刊 掲載 評者: 栩木伸明(早稲田大学教授・アイルランド文学者)を読まれると良いと思います。これを書ききってから栩木さんの書評を読んでみたら、コンパクトなのに何も失われず、わかりやすすぎるうえに希望と期待に満ちていて感動しました。
