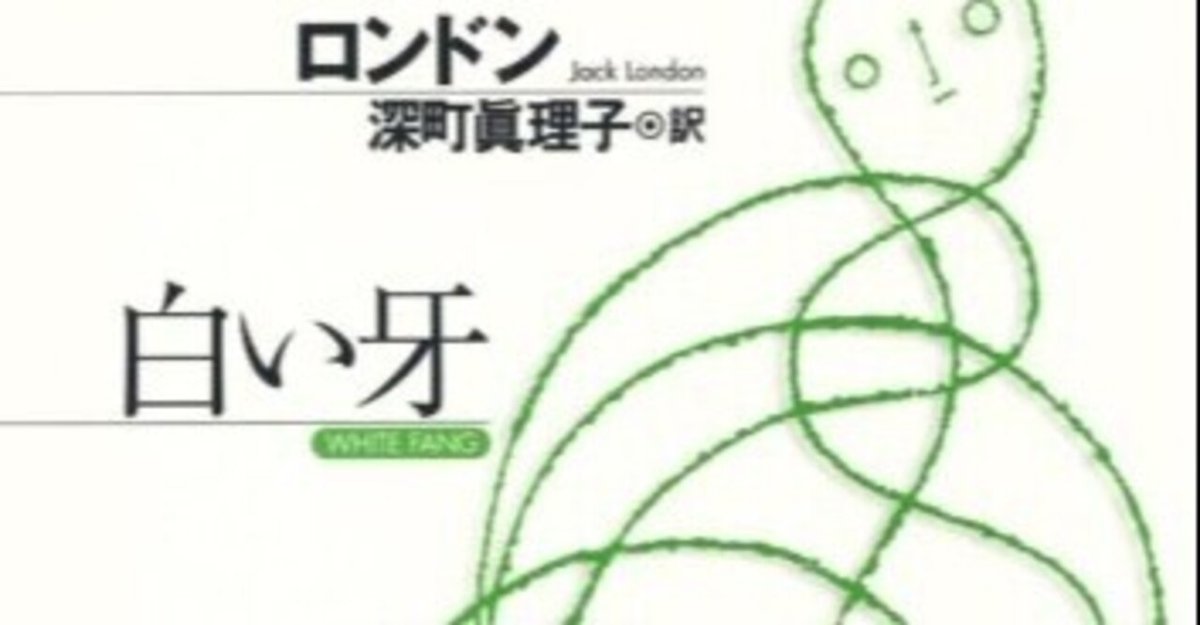
名作で繋がる縁と人生の幸福を問う『白い牙』
犬の血を引いた荒野に生きるオオカミの物語と聞いて、『ごんぎつね』みたいな感じかなあ?ちょっとこども向けかしら。それともオオカミが擬人化されて喋る『BEASTARS』みたいな感じかな?と思いつつ読み始めたのですが、みくびっていました!やはり名作と呼ばれている本は、食わず嫌いせずに一度は手に取ってみるものですね。
『白い牙』 ジャック・ロンドン
犬の血を1/4引く、北国の荒野で育ったオオカミ犬ホワイト・ファング。厳しい荒野を生き、そして人との出会いによって変わりゆく彼の瞳には、一体なにが映るのか。

最近アニメばっかり見ているせいか、冒頭こそ『ゴールデンカムイ』や『不滅のあなたへ』が脳裏をチラつきましたが、第2部に入る頃にはすっかりシャック・ロンドンの無骨でいて鮮明な描写、映像が立ち上がってくるような物語の魅力にぐんぐんと引き込まれていきます。
次第にホワイト・ファングという一匹のオオカミ犬の一生を通して、もっとも原初的なレベルでの生きるということの意味について考えさせられていきます。生きていることの奇跡的な幸運を感じ、生を全うし、充足や幸福を得ることのできる生き方とは、なんなのか。
荒野に生きる頃にホワイト・ファングが狩をすることを通して感じ得た、生の実感。
それは
”この世界における自らの存在意義、それを彼は実感し、そのためにこの世に生まれてきた行為 ーつまり、肉を屠ること、それを屠るために闘うことー を実行しているのだった。彼はこうして己の存在を正当化していた。たんに生きているだけでは、これ以上に偉大なことを成し遂げることはできない。生命がその頂点をきわめるのは、本来そうするように力を授かっているその行為を、せいいっぱい成し遂げたときにこそ、なのだから。”
と、ジャック・ロンドンは書きます。
しかし紆余曲折を経て愛する主人と出会い、荒野を離れ、自らの意識を持って人間の世界へと居を移すホワイト・ファング。愛する主人と時間を共に過ごすことで、かつてない幸福感、そして愛というものを得られる一方、人間社会で生きていくことは、野生のオオカミとして与えられた本能をすべて捨て去ることを意味するのです。
荒野で狩りをし、自身の存在意義を全うする生き方か、それとも持って生まれた本能を抑え込み、愛する人のために忠実に生きることか。ホワイト・ファングにとっては一体どちらが幸せだったのでしょう。卑小な比較かも知れませんが、やりがいを感じる仕事に一生を捧げるべきか、それとも自分のやりたいことを曲げてでも、愛し愛される幸福に生きるべきか、という人間社会でも多分に議論される主題と近しいものを感じました。しかしなにを選ぶことが幸せなのかは、自分で選んで生きてみることでしかわからないことなのでしょう。
この本を読んで犬好きの人の気持ちが前よりわかるようになった気がします。著者がどれほど野生の生態について正確に書いているのかはわかりませんし、実際オオカミの気持ちなんて分かり得ないものなのですが、ジャック・ロンドンが書くホワイト・ファングの描写がとても写実的で、目の前で本当にオオカミの仕草を見て、オオカミの感じていることを一緒に聞いているような気持ちになり、自然と愛着が湧いてくるのです。オオカミ犬の忠実さには胸がキュッとします。
言われてみれば、犬と人間の共存とは、なんと不思議な関係なのでしょう。その関係は、馬や牛や羊とはもちろんのこと、猫との関係とも違っているように感じます。この本を読んでいると、遥か昔にオオカミが人間の熾す火の元へやってきて、共に生きることを選んだことが、オオカミにとって幸福な選択肢であったと思わせてほしいと切に願わずにはいられません。
ところで、ちょうどこの本を読んでいた先週、撮影の仕事で本好きのフランス人の男の子と一緒に働いたときのこと。2ヶ月ほど前に一緒に働いたとき、村上春樹の『騎士団長殺し』を読んでいて、人生のベスト10に入るかも知れないくらい名作だ!と言っていた彼。それから森山大道の写真と日本的な美意識についての議論になり、それなら是非と谷崎潤一郎の『陰翳礼讃』をオススメしていたら、この2ヶ月の間に本当に読んでくれていました。なんて良い子なんだ。『騎士団長殺し』も人生のベスト10に入るくらい面白かったと言うことで、バイブルと言える本は何か聞いてみると、偶然にもオススメしてくれたのが、ジャック・ロンドンの『マーティン・イーデン』。『白い牙』の解説に書かれていたロンドンのバイオグラフィーに興味を持っていたのですが、『マーティン・イーデン』はまさにロンドンの実体験を元に書かれた小説なのだとか。これはズバリ読みたいと思っていた内容ではありませんか!本を通した小さなセレンディピティに、とっても嬉しくなります。
ロンドンは貧しい家庭に生まれ、家計を支えるために10歳で新聞配達の仕事を始め、牡蠣の密漁をしたり、ゴールドラッシュに参加するものの病気で帰郷を余儀無くされるなど、文学的特権階級とはかけ離れた人生を送っているのですが、帰郷後に借金を抱える家族を養うため著述業で身を立てることにするのです。
借金で首が回らないときに、一体全体、本を書こう!なんて思えるものでしょうか?私なら日銭を稼ぐことだけで頭も回らなくなるだろう思うのです。貧しても鈍しない、こんな状況で著述業に身を投じ、本当に一流の名作家になってしまうのですから、なんと非凡な方なのでしょう。ますます『マーティン・イーデン』を読みたくなります。
前述の本好きの彼、他にもナボコフの『ロリータ』やメルヴィルの『白鯨』をオススメしてくれました。お恥ずかしながらどれも未読の名作古典。若い男の子なのですが、ちゃんと名作文学を読んでいるってなんだかそれだけでしっかりした良い子なんじゃないかと頼もしく感じてしまいます。犬好きが「犬を飼っている人に悪い人はいない!」なんて言っているのを聞くと、「いやいや犬飼ってる猟奇的犯罪者もいるでしょ」なんて斜に構えてしまいますが、本好き、しかも文学作品を読んでいると言われると、途端に人を見る目が甘くなって、ついつい「文学好きに悪い人はいない!」なんて思ってしまいます。
