おやじカウンセラーのダジャレ的つぶやき3 ー 心残りは心の「こり」
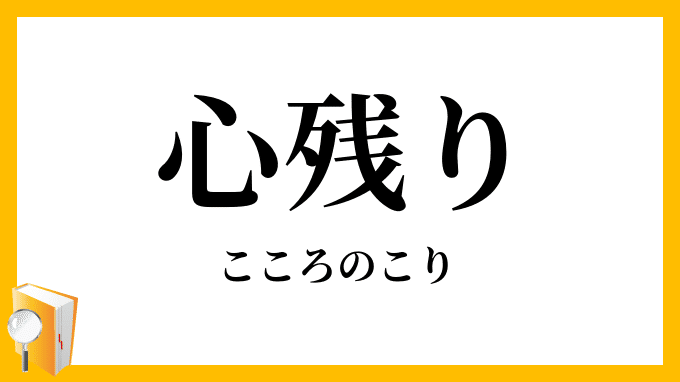
https://kokugo.jitenon.jp/word/p17470
みなさん、こんにちは。
今日は少し空いて、3回目の書き込みをさせていただきます。
前回は「ブタが仏陀(ブッタ)」ということで、すべての人の中には「仏」のような存在がいて、という話をさせてもらったのですが、今日からは、それでも日々いろいろ「不測の事態」がある中で、どんなふうにすれば心をほぐしながら生きていけるのか?ということについて、書かせていってもらえたらと思っています。(前回はちょっと長すぎたような気がしますので、今回からはもう少しコンパクトにまとめさせていただきます)
ということで、今日のダジャレは、
心残りは心の「こり」
になります。
わたしたちは「思い」を持ちながら生きる生き物です。
わたしたちは毎日、いろいろな「思い」を持ちながら生きています。
その中で、「あれをしたい」「これをしたい」「あれが欲しい」「こうなったらいいな。。。」というふうに、いろいろな願望もわいてくるものです。
「おいしいものが食べたい」「温泉に行きたい」「あの人に会いたい」「オリンピックで金メダルを取りたい」。。。
ある意味でわたしたちはそういう「願い(欲)」を持つからこそ、生きていけるということもできるでしょう。
「欲」というのは、わたしたちが生きるエネルギーなのです。
(英語で「欲求」というのはneedといいます。つまり満たす「必要がある」ものなのですね。)

「願い」はすべてはかなわない。
ただ、残念なことに、わたしたちの「願い(思い)」は、すべてはかないません。
たとえばいまも、コロナ禍のために、わたしたちはいろいろなことができなくなって、いろいろなことを我慢しながら過ごしているわけです。
生きているのは自分だけではないので、わたしたちは常にまわりとやり取りしながら(折り合いをつけながら)、生きていかなければならないのですね。。。
では、わたしたちの中からわいてきた願望というのは、その思いが満たされなかった場合は、一体どこに行ってしまうのでしょうか???
それは、願いがかなえられないと、また一旦心の中にもぐって、再び出てくるチャンスをうかがう、ということになると考えられるのですね。
「欲求不満」というかたちをとって。。。
そしてまた、いつかチャンスが来たら、その思いが浮かび上がってきて、行動を起こして、願いがかなうこともあれば、最初のものとはちょっとちがうけれども、似たような願望を満たしたりすることで、元々の思いをかなえられたことにする、という感じで、わたしたちは自分の気持ちをやりくりしていっているのです。
がまんがつのると。。。

ただそれで、ある程度の時間のうちに、わいてきた欲求がなんらかのかたちで満たされて、その欲求不満が解消されればいいのですが、それがすごく長引くとか、全然うまくいかない、ということになってくると、場合によってはちょっと困ったことが起こってきます。
気持ちを押さえようとするのですが、だんだん収まりがつかなくなってくるのですね。。。
わたしたちの心から一度出てきた「思い」というのは、消えるものではありません。
「食い物の恨みはおそろしい」ということを言ったりもするのですが、「願望」という心のエネルギーは、決してなくなるものではなく、その実現を求めて、納得がいくまで、その行き場を求めて心の中に留まり続けて、「心に念が残ってくる」のですね。
「心残り(残念)」とは、そういうことなのです。
そして、その思いがずっとかなえられずに、心の中に押し込められたまま、ということになってくると、その「心残り」が、だんだんこり固まってきて、心の「こり」(コンプレックス)をつくってしまうことがあるのです。
「心残り」が、心の「こり」になってしまうのですね。。。
心の「こり」にも良性と悪性が。
ただ、この心の「こり」にも良性と悪性があるようで、良性の場合は、「どこまでも夢をあきらめない」根性や「ハングリー精神」を生み出して、後の成長や成功につながっていく場合があります。
「悔しさ」をバネに!!となる場合や、「こだわり」をもって努力と工夫をかさねて!!となる場合ですね。。。
では、悪性の場合はどうなるのでしょうか???
よくない心の「こり」としての「心残り」は、場合によっては、精神的なしんどさにつながっていきます。
満たされない思いが、押さえて(抑えて)いるのだけれども、頭をもたげてきて、他のことに集中するのを邪魔してきたり、ずーっとモンモンとしてしまって、心が晴れない、とか、いつもなにかイライラしてしまっている、というような感じのことがでてきてしまったりするのですね。
こうなると、コンプレックスが、「障がい」としてはたらいてしまうようになるのです。
心が固くなって、こってくると、体の方もこってくることがあります。
肩こりや首のこり、偏頭痛や腰痛なども、いろいろな心理的な無理が続いて起こってくることもあるので、注意が必要です。

カウンセリング(心理療法)と「心残り(心のこり)」
そして、カウンセリングや心理療法を受けに訪れる方の多くは、この悪性の心の「こり」のようなものが、ちょっと自分だけでは触れられない、心の深いところにできてしまって、一体どうしたら?ということでやってこられることがすごく多いのではないかと僕は思っています。
過去からの積み重なってきた「心残り」を取り扱いながら、心の「こり」をほぐす仕事が「カウンセリング」だということも、できるかと思います。
では、その心の「こり」の部分は、いったいどういうふうに扱っていけばいいのでしょうか???
そういう「こり」というのは長年月かけてできてきたものであることが多いので(場合によっては雪だるま式にふくらんでしまっている場合もあります)、「すぐに一発解消!」というふうにはなかなかいかないものです。
でも、ゆっくり時間をかけてほぐしていくうちに、だんだんほどけて(溶け出して)、よくなっていく可能性があるものなのです。
体にするマッサージとはちょっとやり方が違うのですが、次回からはその心の「こり」とのかかわり方について、また少しずつお伝えさせていってもらえたらと思っています。
ただ長くなるので、今日は、「心にいろいろ思い残しをしてしまうと、それは心の『こり』になってしまうことがある」というところまでお伝えをして、終わりにさせていただきたいと思います。
続きはまた次回から、ということで、どうぞよろしくお願いします<(_ _)>

大切な「願い」や「思い」
それにしても、人はなぜ、「体」だけではなく、目に見えない複雑で高度な「心」も持つようになったのでしょうね???
そして、人はなぜ「願い」や「思い」というものを抱く生き物なのでしょうね???
僕もまだよくわからないのですが、やっぱり生命の進化の過程で「心」というものが生まれてきたのには理由があって、その「心」から生まれてくる「願い」や「思い」というのは、かなえられるべきものとして生まれてくるのではないか?という気がするのですが、みなさんはどう思われますか???
たとえ小さな個人の「願い」でも、一つの「願い」はこの世に生まれてきたかけがえのない一つの「願い」ですし、小さな「願い」もつながって集まれば、「大きな願い(思い)」になっていきます。
一人の人というのは、「この世に生まれてきた一つの『願い(希望)』の種」だということもできるのではないでしょうか?
自分の心の声に耳を澄ましながら、日々のささやかな「願い」や「思い」を大切にして、なるべく「心残り」がないように生きていきたいものですね!(^O^)/

https://koimemo.com/article/10479
