
自炊モチベを高める方法
こちらのnoteでは自炊モチベーション、やる気を高める方法について書いています。
内容としては脳科学や心理学に関する内容を含みますが私はそれらについては素人であり、参考文献をもとに今回のnoteを執筆しました。
自炊大変ですよね
献立作成~食材の買い出し~調理~食卓の準備~後片付け。
毎日3度の大仕事お疲れ様です。
疲れたり、嫌になって自炊したくないって思うときもあるでしょう。
ここではそんなあなたをやる気にさせて自炊モチベを高める方法をお伝えします。
お話の流れとしては脳科学と心理学の側面からまず「やる気」を考えます。
その後、料理系サイトや料理家さんの本などに書かれている自炊モチベを高める方法について見ていきたいと思います。

脳科学で考える「やる気」
とにかくやる
まずは脳科学でのお話です。
「やる気」はどのようにして起こるかわかりますか?
実は脳の側坐核と呼ばれる部位が意欲の中枢とされており、そこが刺激されることで「やる気」が沸き起こるのです。
もう少し細かなお話をするとその側坐核で放出されたドーパミンがやる気を起こしてくれるのです。
後ほど詳しくお話しますが、ドーパミンは達成感などを感じた時に放出される快楽物質である一方でやる気を起こしてくれる側面も持っています。
では何をすれば側坐核を刺激することができるのでしょうか?
ずばり、「考えてばかりいないで動く(部屋の片づけやウォーキングなどをする)」。
これなんです。
「あれもしなきゃ、これもしなきゃ。わ―、やりたくないよう(´;ω;`)」
これで結局行動を起こさず考えているばかりならやる気は起きません。
こんな時でも少し面倒でもとりあえずやるんです。
言いたいことは分かります。
「やる気が出ないから行動に起こせないんだ(# ゚Д゚)」
その通りだと思います。

ただ私の立場からはこうお伝えするしかできません。
騙されたと思ってやってみてください。
参考文献通りのことしか言えませんが、元々やる気がなくても行動を起こすとやる気が沸いてきます。
もしそれでもやる気が沸いてこなければ休息が必要だという証拠のようです。
ちなみに、この様にやる気が沸いてくることを「作業興奮」というようです。
ドーパミンをコントロールする方法
先ほど少し触れましたが、部屋の片づけやウォーキングなどこれから取り掛かろうとしている自炊に直結することでなくても構いません。
散歩などで歩くことは脳への血流をよくしてくれます。
また、これから取り掛かろうとしている大きな課題を「これならできる」と言える小さな課題に細分化し、スモールステップでこなしていくことがコツになります。
例えば夕食を作ろうと考えているなら「献立を決める」、「食材を買う」、「炊飯器のスイッチ入れる」・・・。
このように細かく分けて捉えてもらえればいいでしょう。
これでもまだハードルが高ければもう少し細かくしてみましょう。
最終的に課題が終わったときには達成感を噛みしめましょう。
達成感を噛みしめることでドーパミンが放出されます。
すると、脳が「またこの快感を味わいたい」と思いその行動にまつわる脳の部位が活性化するそうです。

他にも作業に取り掛かる前に「これから〇〇をする」と自己暗示をかけることもよいそうです。
以前はドーパミンは快楽物質として捉えられており、達成感が得られたときに放出されるとされていました。
しかし、今では報酬(達成感など)が得られるタイミングが近づくと放出されることが知られています。
そのため事前に自己暗示をすることで以前の成功体験から事前にドーパミンが放出できるようになるのです。
制限時間を設けてみる
また、これはやる気というよりも集中力を高める方法ですが、時間を制限して作業に取り掛かるのもよいそうです。
調理作業というよりは献立を考えるようなシチュエーションを思い描くと分かりやすいと思います。
時間に制限を設けることで集中できるのではないでしょうか?
脳は起きていても覚醒状態に向かっている時と睡眠状態に向かっている時があるそうです。
当然覚醒状態にある方が頭がシャキッとしており集中して作業に取り掛かることができます。
献立を考えるような作業は脳が冴えている時間に行う方が良いでしょう。
時間の制限以外にウォーキングなどの適度な運動や部屋の片づけなどの作業をすることで集中力を高めることができます。

心理学で考える「やる気」
自分で決めたから頑張る
次は心理学からやる気を見てみましょう。
心理学では「内発的動機付け」と「外発的動機付け」と呼ばれるものがやる気に影響しています。
内発的動機付けとは「自分で決めたから頑張る」という意思です。
外発的動機付けとは「自分以外の外部の要因がきっかけでそれを行なう(周りから強制されている、ご褒美があるからやるなど)」場合です。
また、他者からの期待に応えるということもやる気に影響しています。
ただこれは日本人にとっては内発的動機付けとして扱われますが、外国では外発的動機付けとして扱われているようです。
この二つの動機付けですが外発的動機付けよりも内発的動機付けをきっかけとした場合の方がやる気は長続きします。
つまり、周りからやるように言われてやるよりも自分からやりたいと思ってやる方がやる気が出るということです。
子どものころ親に言われてやっていた勉強と大人になってから自分で取りたいと思った資格のためにてやっていた資格勉強(職場から取るように言われてやっていた資格の勉強ではありません)ではどちらがやる気が強かったでしょうか?

期待×価値理論
期待×価値理論という考え方があります。
これは内発的動機付けをコントロールする方法のひとつです。
これからやろうとしていることのハードルを高く設定せず、そのことに価値を見出すのです。
期待とは「やろうとしていることが成功できそうだと期待できる」ということです。
価値とは「やろうとしていることが価値のあることである」ということです。
そして、これらはを掛け合わせたときに大きくなるほどやる気は大きくなるという考えなのです。
足し算ではありません。
期待、価値のどちらかが0ならやる気も0になってしまいます。
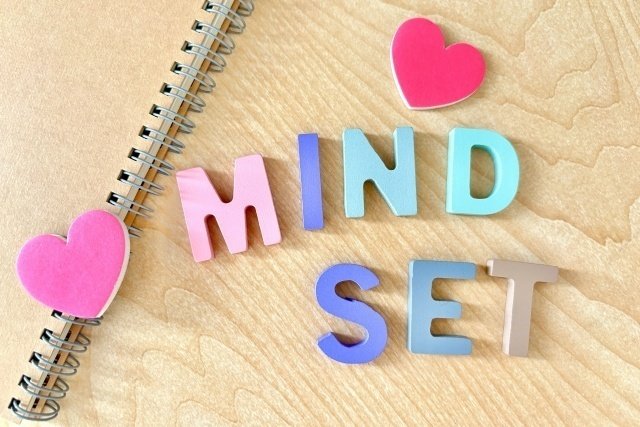
例えば、料理初心者の方を想定してみましょう。
「彼女を家に呼んで手作りのフルコースをごちそうしたい」と思ったとしましょう。
この場合、成功すれば料理ができるという事をアピールできる絶好のチャンスです。
しかし、料理初心者であればそれを実現するまでに料理の勉強などやらなければならないことが多くハードルが高くなってしまいます。
つまり、そのごちそうが成功できる可能性は低くなってしまいます。
これらの掛け算の結果がやる気として現れます。
同じ料理初心者でも「彼女と一緒にお鍋を囲みたい」と考えてみればどうでしょうか?
手作りのフルコースをごちそうするよりも成功できそうに思え、やる気が沸いてきませんか?

このように期待と価値のどちらかが低ければやる気は高まらず、両方の掛け算の結果がやる気の大きさを表すというのが期待×価値理論です。
価値に着目すると「家族の中で決められた料理当番だから嫌々料理をする」と捉えるよりも、「家族の健康は自分が守っているんだ」と意識することでそれまでよりも自炊が価値の高い行為になるのではないでしょうか?
ここまで脳科学と心理学の側面から「やる気」についてお話をしました。
本noteの執筆のために調べた脳科学、心理学の文献では他にもいろいろなことが書かれていました。
しかし、ここでそのすべてに触れてしまうと煩雑になってしまいます。
そのため、料理系サイトや料理家さんの本などに書かれている自炊モチベを高める方法を紹介しながら関連する脳科学や心理学のお話をしていきたいと思います。

ここから先は
¥ 300
サポートありがとうございます😃 かかりつけ管理栄養士の中野です。 サポートされたお金は栄養・食・健康関連の情報発信のための資料代として大切に使わせていただきます。 今後も情報発信だけでなくスキル販売、コンテンツ販売に力を注いでいきます。 ぜひとも応援よろしくお願いします🙏
