
SaaSビジネスのプロフェッショナルサービスことはじめ(反省編)
■ これは何
・「#SaaSLovers 秋のブログ祭り」16日目、Repro伊藤のプロフェッショナルサービス立ち上げについて書いたドキュメントです(記事というよりは反省文です)
・昨年執筆した前作「SaaSビジネスのプロフェッショナルサービスことはじめ」を読んでいることを前提として書いておりますので、まだの方は先に前作を読んでいただくとより楽しく読めるかと思います👐
・SaaSLovers、昨日のAlp伊藤さんの記事はこちら
■ どんなことが書いてあるか?
・SaaS企業Reproのプロフェッショナルサービスの一つ「ASO(App Store Optimization: アプリストア最適化)支援事業」の立ち上げから、ある程度事業として安定するまでにやったことを反省とともにつづっています
・フェーズ的には0→1、1→10でそれぞれの反省とあるべきをまとめました
・「前の記事読んだけど具体的に自社で立ち上げる際のイメージまで湧かなかった😶」という方や「実際何が大変だったのか知りたい」という人はぜひ読んでみてください。あと採用目的で書いてるのでRepro興味ある方も読んでください絶対!
・ご多分に漏れず今回の記事も15,000字くらいと長いので、お忙しい方は目次から気になるところだけ読むのがお勧めです📖
■ 前提
・リサーチを主とし、そこに自身の経験を付加してSaaSビジネスのプロフェッショナルサービスにおける一般解を導こうと試みた前作とは異なり、今作はあくまで「ReproというイチSaaSベンチャーでPS事業の責任者をやっていた当事者としての失敗とその振り返り」がメインテーマです。
・一般解ではなく特殊解。というか成功と胸を張って言えないので、解ですらないです… 🙁
・なので、事業立ち上げ等の経験が豊富な諸先輩方や普通に仕事ができる人からしたらレベルの低い悩みや失敗が多いと思います🤕 読み進めて期待値と違ったらそっと閉じてください。映画も記事も「名作の続編は駄作」と相場は決まっています。
・また、自分が立ち上げたのがプロフェッショナルサービス分類(下図参照)で言うところの「b-2. 顧客のツール活用以外の領域を支援、課題解決することによって支払ってもらう売上」なので、「b-1.ツールの利活用に紐づくPS」を中心にやられている方にとっては事情が違うところが多々あると思います🤔

・「定型化したコンサルサービス売り」という意味では代理店にお勤めの方やもともとPS主体でツールをあとから作りはじめたSaaSベンダーにお勤めの方とかのほうが親和性は高いかもしれません😶
・あと、「その悩み・課題についてだったらこの書籍・この記事おすすめだよ📚」というのがあれば教えてください!前作と異なりリサーチを全くもって怠っているので、良いリファレンスもらえたら本ドキュメントに記事urlを随時足してゆきます🙇
…と本題に入る前から予防線張りまくりですが、つらつらと書いていきます✋
TL;DR
お忙しい方向けに、下記に本稿のエッセンスをまとめました📝
TL;DR
■ プロフェッショナルサービス 0→1フェーズ編
・PSの0→1、つまり立ち上げフェーズではマーケもセールスも受注後の運用も全部自分でやりましょう👐 まだ事業の不確実性が高いので、すべての領域で自分が最前線に立ち、勝ち筋を見つける検証を行いましょう。
・0→1フェーズの採用は「放っておいても学べる」「ハードワークできる」このAND条件を満たす人だけ取りましょう。+αで業界経験あれば尚よし。
・よっぽどのスーパーマンではない限り、他チームを兼務しながら立ち上げやるのは止めましょう。必ずどちらかにラストマンシップが持てなくなるよ
TL;DR
■ プロフェッショナルサービス 1→10フェーズ編
・1→10のフェーズでは解像度を上げるべき未来の時間軸およびそこに紐づく自分のリソースの使い方が0→1フェーズの時と明確に変わります。少なくとも1-2年先の事業の未来の解像度を上げる業務に自分のリソースを割きましょう。0→1フェーズでの伸びをもとに事業計画作ると死にます。
・具体的には市場や競合状況のリサーチ、プロダクトとの戦略のアラインメント、組織デザインetc。これと採用にリソースの半分くらいは割きましょう。現業のマネジメントはサブマネをさっさと登用して権限委譲すること。
・SaaS企業である限り、どんなにプロフェッショナルサービス事業が伸びようと主体はプロダクトです。プロダクトとの機能面での連携、それが難しければプロダクトの持つ事業KPIや施策レベルでの連携は絶対諦めちゃだめです。
ここまで読んで、まだお時間ありそうだったらお進みください👇👇
そもそもなぜASO支援事業をやることになったのか
そもそも自社SaaS「Repro」の解決する領域とは関係ないASO支援事業をなぜやることになったかというと、当時行っていたコンサル案件からの派生です。
現在もありますが、Reproにはマーケ、セールス、CSなど一般的なSaaS企業にあるファンクション型の組織とは別に、コンサルチームという「お客さんの成功のためなら何でもやってやるぜ!」という部隊があります。
新規リリースするアプリの事業計画書作成、リサーチのプロジェクト、実店舗やデジタル広告領域も含めたデータ分析などなど、ゼロベースから与件ヒアリングして個社ごとに異なる提案をします。
ソリューション営業でもPSを売るわけでもなく、ふつーにガチガチのコンサルです。(※もちろんパッケージ化されたソリューションを組み合わせて提案することも多々あります)
そこのチームのボスにコンサルの化身、社長の平田と並んでKing of クライアントファーストなマインドを持つCSOの越後という役員がいるのですが、当時マーケの管掌役員も兼ねていた彼がある日、

👨「直樹君さー、クライアントワークもやりたいって前に言ってたじゃん?こないだ○○社と△△社にASO提案したら発注してもらえたからさ、これ君がやりなよ」
👦「!!!! まじですか!!!!!!! やります!!!!!!」
そんな「唐揚げ1つ余っちゃったから、これ君が食べなよ」みたいなノリで事業立ち上げタスク振らないでほしいな~とは思いつつ、返事は「ハイ」か「YES」か「押忍」しか教わっていないのが地獄系SaaSの第二新卒。
当時はASO? 阿蘇かな?🌋 越後さん今日いつもより顔怖くないな?くらいしか考えていなかった気がしますが、成長機会という餌につられて僕のPS奮闘記が始まったのでした。
というわけで前作にも書いたのですが、当該事業の成長性や「売上の柱となる新規事業を作ろう」と考えて始めたわけではなく、目の前のクライアントが困ってたからやるぞ!!!!!!という感じで始まったのがReproのプロフェッショナルサービスの一つ、ASO支援事業でした。
(余談ですが、この越後さんは本当に凄くて自分の基礎的なビジネススキルや仕事に対するスタンスはほぼ全て越後さんから教わったと言っても過言ではないです。良い師匠に恵まれました🙇)
0→1フェーズは"JUST DO IT"
プロフェッショナルサービスの0→1フェーズは、1→10のフェーズと比べるとめちゃくちゃシンプルです。
「ぜんぶお前がやれ」
以上。
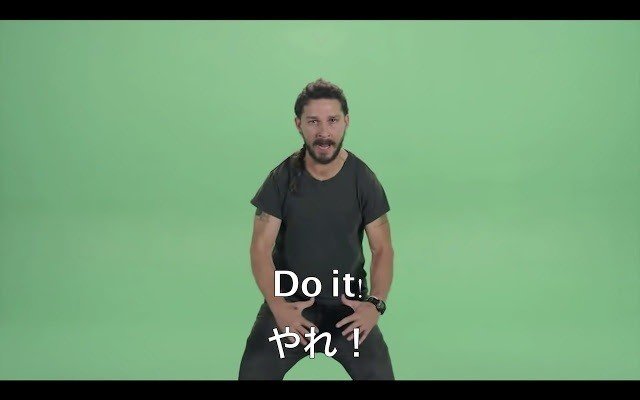
これです。マジでこれ。
NIKEでいうと "Just Do It"。
ブルース・リーでいうと "Don't think! Feel."
「つべこべ言わずやれ」
以上。
職務領域ごとのtipsもほぼ無いのでまとめて書きます✋ 具体的に何をやったかは1→10パートにて後述します。
・マーケティング…お前がやれ
お前が記事書け。お前がLP作れ。お前が訴求テキスト書け。お前がセミナーの企画考えて登壇しろ。お前がアンケート作れ。お前がリードのクオリファイしろ。お前がアポ取れ。
・セールス…お前が売れ
お前が全部のアポ行け。お前が提案書書け。お前が価格交渉しろ。お前が契約まけ。毎回セールストーク変えろ。
・受注後の案件…お前がやれ
お前が運用レポート作れ。お前がメール/チャット対応しろ。お前が定期訪問で喋れ。お前がアップセル/クロスセルしろ。解約阻止になるならソリューション変えることを厭うな。
・メインプロダクトとの連携…余裕があればやれ
いったんはReproとのシナジーとか考えすぎず、User Acquisition(UA)のニーズがある顧客に売れるか、満足してもらえるかにフォーカスしろ。プロダクトとのシナジーはUAとCRMの両方にニーズがあるクライアントに提案書作るときに嫌でも考えることになる。
・採用…余裕があればやれ、余裕がなければHRに任せろ
「放っておいても学べる」「ハードワークできる」このAND条件を満たすやつ以外は採るな。たとえデジマ経験者でもハードワークできないシニアとか絶対に採るな。特にASOのような死ぬ気で2~3ヶ月もやればだいたいキャッチアップできるソリューションで経験者を採るの無意味。
ゼロイチの頃はまだ事業の不確実性が高いので、すべての領域で自分が最前線に立ち、勝ち筋を見つけるための検証を行う必要があります。
オールユーニードイズ "GRIT"、やり抜く力。
ラクスルの田部さんも最近のtweetで同じようなことをおっしゃってました。つまりは事業責任者自身がハイパフォーマーたれ、そういうことです(˘ω˘)
サービスの立ち上げ期において圧倒的なハイパフォーマーの存在は重要。1人で戦局を変える売上の大半を作るユーザー価値に対して強烈な課題設定ができる。こういう人材をパフォーマンスさせる仕組みを作ることも大切。拡張期では属人化は排除すべきだがゼロイチはたった1人の熱狂から生まれることも多い
— 田部正樹@運用型テレビCMならノバセルbyラクスル (@tabemasaki1) October 16, 2020
当時はやり抜き力、ラストマンシップは持っていたかなと思う一方で、0→1フェーズでのもっとも大きな反省は自分以外へのメンバーにも無理を強いてしまったことと、兼務していたマーケチームを手放す判断をもっと早く経営と相談するべきだったことです😢
・立ち上げ時の痛みと現業への悪影響。
立ち上げ時はそのプロフェッショナルサービスを売ったりコンサルする専属チームなど無いので往々にして立ち上げた本人が兼務となり、業務が2倍(かそれ以上)になって死ぬ。
自分の場合、半年弱はマーケをやりつつのASO事業立ち上げだったため自身の負荷もさることながら当時のマーケチームのメンバーに多大な迷惑をかけてしまった。ついでに立ち上げを手伝ってくれたASO事業側の社員とインターンにも結構な無理を強いてしまった。皆様ごめんなさい、この場を借りて改めてお詫びします。
『SaaSビジネスのプロフェッショナルサービスことはじめ』より抜粋
CAの藤田さんもわざわざブログにしてます。兼務ダメ絶対🙅三木谷曲線。
楽天三木谷社長の著書に「三木谷曲線」というのが出てきます。最後の0.5%の粘りが大半の結果の差を産み出してしまうというグラフです。
99.5%まで仕事をする人はいくらでもいるので差がつかないのです。
何かを兼務している人は、自分は抜かりなくやっているつもりでも、無意識に0.5%の余った時間をもうひとつの仕事に振り分けてしまうものです。
成果に大きな差がつくのは残りの0.5%を努力できるかどうか。真理すぎますね…🤔
ReproのPS「ASO支援事業」 1年間のあゆみ
そんなこんなで始まったASO事業ですが、細かいプロセスをすっ飛ばして結果を先に書いてしまうと、数字的にはなかなかに伸びました。
<案件数と人員数>

・立ち上げ時の2017年8月と集計時の2018年11月を比較すると人員は1人→8人に
(※アルバイトとインターンは週2~4の3~6時間勤務が多かったので、フルタイムの人員換算で言うとインターンとバイト5人で正社員2人分くらいの稼働)
(※グラフが11月までと半端なのは年末に社内向けの報告会があったからです)
立ち上げ当時の2017年秋はiOS10から11へのアップデートでストアの仕様が大きく変わり(≒アプリストア最適化のゲームのルールが変わる)、アプリマーケ業界内でもASOに再び注目が集まりました🔍
プッシュ通知など他のテーマだと参加者10~20人程度の少人数セミナーも50人を超えたりと毎回盛況。
そんな時代の追い風もあり、成約数は次々と増加。
業務過多で死にそうになり慌てて社内で兼務できるメンバーを無理やりアサインし、ハードワークできると意気込むインターンも採用。
その後は採用のミスマッチなどもあり増えたり減ったりしつつも、2018年の春あたりからはメンバーもほぼ固定化し、この頃から本格的に組織化、つまり0→1から1→10のフェーズになっていきました。
8人態勢になった時点での平均年齢は25.2歳。全員男。社員よりインターンとバイトのほうが多く、自分以外の社員二人は元ホストと元フリーター。社会人経験あるやつゼロ。
徹夜しても僕が提案書ボコボコにフィードバックしても、たまの打ち上げで焼肉おごってやればみんな鬼のモチベーションで働く若きソルジャー。
夜の「今日どうする?」という会話は「家に帰らず社宅に泊まるか?」の意味でした。そしてだいたい泊まる。帰れよ。

たまの焼肉がすべてを救う🐄🐖🐓🥩🍖
若さと勢いだけが取り柄の未熟なチームでしたが、彼らが事業の礎を築いてくれました。バイトさん含め、よくまあハードワークとラーニングができるメンバーが集まったなと思います。
<MRRと単価>
売上もまあ伸びました。(こちらはさすがに実数は伏せます)

(※単位同じ「万円」なのに2軸にしてるのグラフのお作法に反すると思いつつ、見やすさの観点からそうしてます🙇)
MRRは立ち上げ時の10倍以上。受注単価も実績を積み上げながらじわじわとプライシングを上げ倍以上。当時のRepro全体の売上のなかでも期待される事業に育ちました🌱
案件数減っても売り上げ減ってないのはプライシングのおかげ。ソリューションの型もできたしここからさらにスケールできるぞ~🚀
…と数字だけ見ると「順調そうじゃん😦」という風に見えなくもないのですが、全くもってそんなことはありませんでした。事実このあと、売上は少し停滞します。
というか、この「0→1立ち上がったぜ!」「数字の上では順調!」という状態が自分の目を曇らせ、本来事業責任者としてやるべき役回りが全くできていませんでした。
ここから総論、各論という形で1→10フェーズの反省を書いていきたいと思います(ここからようやく本題。長い🙄)
いったい何が問題だったのか(総論)
いま振り返る、当時の自分にもっとも欠けていたこと。
それは0→1と1→10のフェーズで明確に違うのは解像度を上げるべき未来の時間軸、およびそこに紐づく自分のリソースの使い方だったが、そこが全くわかっておらず「強いプレイングマネージャー」としての業務にとどまってしまったことです。
0→1のときは前述の通りGRITを信条に現在~向こう数カ月先くらいまでを確かなものにする業務に時間を使って良いが、1→10になったら少なくとも1-2年先の未来のあるべきを具体化し、そこから逆算して今何に時間を使うべきかを決めなければいけない。
特にb-2型のようなメインプロダクトと別のニーズをとらえてソリューションを提供しているようなプロフェッショナルサービスの場合、そのPS事業の肌感もあってあるべきを解像度高く考えることができるのは、会社のなかで自分しかいないからです。

■ 脳みそ・リソースをいちばん使うところ🧠
0→1
・0→1では前述の"Just Do It"パートの通り、「この事業、顧客に刺さるのか?」「どういう売り方ならいいのか?」などを自分が最前線に立って検証を行うこと、目の前の売上を作ることにリソースを全振りしてよい。ただし自分が持てる商談数や案件数に限界はあるので、最低限の業務標準化やオンボーディング環境は整えておくこと
1→10
・1→10では「この事業、同じやり方で10xするのか?」「ReproというSaaSの企業価値を上げるためのASO事業の立ち位置は?」「市場は今後もあり続けるのか?」などを少なくとも1年先、理想は2~3年先までクリアにしておく必要がある。
・なので具体的にやることとしては市場や競合状況の改めてのリサーチ、メインプロダクトとの戦略のアラインメント、それを可能にするための提供ソリューションや組織のデザインetc,etc。これを経営陣や各事業部の責任者クラスとディスカッションしながら固めていくことにリソースを割く
・事業と組織のスケールに耐えうるためにドキュメントやオンボーディング、採用プロセス整備などの仕組化に時間を割くのは1→10フェーズでやるべきこととして悪くはなかったが、その業務は事業の現在~せいぜい半年後までの直線的な成長を担保するためのものでしかないので、そのあたりはサブマネ候補の社員に一通りのスキルトランスファーを終えてあとは任せるという動き方をするべき
ということで、某社のバリューにある「10xから逆算して考える」が全然できていませんでした🤕 ストレングスファインダーで未来志向けっこう高いはずなのに…😥
当時、社長やCSの責任者だった佐々木さんに「僕の課題なんですか」と聞くといつも即答で「積み上げ思考。」と返ってきて、そうだよな改善せねばな…と意識はしていたのですが、いま振り返ってみると何も改善できていなかったです。
というか自分が逆算の思考を働かせている時間軸は数週間~せいぜい数か月先までで、より先の未来に関しては考え無しだったのだなーと思います。反省しかないです…
未来の解像度が低いと起こる問題
では、未来の解像度が低いと何が起こってしまうのか?
未来の解像度が低くても、足元の数字を固める事業運営には問題ありません。1→10のフェーズでは人が増え、リード獲得~受注~運用までの勝ちパターン、ワークフローがある程度完成しているからです。
最大の問題は来期計画の策定時に訪れます。
数年先のあるべきから逆算せず現状の延長線上で売上/採用計画を立ててしまうため、Fond福山さんがおっしゃっているところの「Excel経営の罠」にドハマりしてしまうのです。
福山:Excelを見ながら「ここを2倍にしたら2倍成長できる」といった計画立てを、僕自身も何度か犯してしまったのですが、そうすると「成長レバーの順序」を見失ってしまう。会社の成長にあたっては...(以下略)
成長率の罠にハマるな。SaaS経営者が考えるべき戦略と戦術[Fond・福山太郎さん] #SaaSTokyo
(このpodcast、本当に学びが多く金言の宝庫なのでまだ聴いてない方がいらっしゃったら今すぐこのnoteは閉じてこっちを聴くほうがいいです…(˘ω˘) )
どういうことか理解を深めるために、具体的な例を挙げます。
上からざっくり「来期のASOチームの売上目標を作ってね」と言われて自分が出した案件数と人員数の目標はこれ。

MRRと案件単価の目標はこれ。

上記を実現するための案件運用体制はこれ。

・当時3名1ユニットのスリーマンセル制で5~6件は案件を運用できていた
はい、積み上げ思考のお手本のようなクソ事業計画です。
自信持ってこれを提出してるのヤバすぎる。こんなの計画でもなんでもない。
というかこの1年ちょっとで案件数もMRRも直線的には伸びてこなかったのを分かっているはずなのに、なんでこんな「一次関数習いたてです👦」みたいな計画出せるんや…🙄
しかも経営者が陥る「Excel経営の罠」よりもタチが悪いと個人的に思うのが、1→10フェーズのPS責任者は現場の肌感はあり、現状の顧客のニーズは完璧に捉えていること。
事業計画を作っている自分自身がまだ何割かのリソースをセールス活動や案件対応など「顧客に会う」活動に充てているため、「このソリューションはまだニーズがある」「勝ちパターンはわかったのでまだ伸びる」と信じ切ってしまう。
結果、現状の売上の延長で直線的な成長目標を引き、2x、3xの達成を目指す。事業のグランドデザインは描けていないのにもかかわらず。
これを摺合せている最中に自分が再度マーケチームに移籍するという話になり上記の計画自体は半分白紙になるのですが、仮に自分がASOに残り続けていたとしてもうまくいかなかったでしょう。
結局のところ問題は、事業に対する未来の解像度が低いことに起因しているんです。売上や採用数など数値上の目標しか経営と摺合せておらず、例えば以下のようなことを考え、ディスカッションする時間をほぼとっていませんでした。
・そもそも今後数年先も一次関数的な売上増加が見込める市場・ソリューションなのか?
・iosとandroid、両アプリストア上でプラットフォーマー主導の独善的なゲームチェンジは将来的に起こらないのか?
・競合環境はどうで、自社のポジショニングはどうしていくつもりなのか?
・Reproというプロダクトと併せてどういうチームで、どう売っていくつもりなのか?
プロダクトが主、PSは従
10x思考以外に当時の自分に欠けていたものとして、「SaaS企業である限り、どんなにプロフェッショナルサービスが伸びようと主体はプロダクトである」という考え。
これ。プロダクトがキング/SaaSビジネスサイドでのプロダクトとの向き合い方 #SaaSLovers Day3|こが @kg_yt7 #note https://t.co/jf03dRY6Qx pic.twitter.com/TgVBFEAIej
— Naoki Ito(Repro Inc/㈱銭湯ぐらし) (@n_11o) October 6, 2020
#SaaSLovers 3日目の古賀さんの記事にかぶせてドヤってますが、恥ずかしながら本当にそう思い始めたのはここ2年くらいな気がします。お前SaaS業界5年目ちゃうんかい(˘ω˘)
ASO支援事業は本稿の冒頭で分類した「b-2. ツールに紐づかないプロフェッショナルサービス」であるため、何もしなければメインプロダクト「Repro」との関連性は全く起きません。
お客さんにReproの説明しなくても支援はできるし、成果もあげられるし、お金ももらえる。Reproの管理画面を一生触ることなく入社~卒業することだってできる。
しかしながら、プロダクトとの機能面での連携、それが難しければプロダクトの持つ事業KPIや施策レベルでの連携。これは絶対に諦めてはいけません。諦めた瞬間にそのPSは死にます。短期的に成功しても中長期でどこかで壁にぶちあたります絶対。
・クライアントから共有してもらったアプリストアまわりのデータをプロダクトに生かせないのか?
・ASOからプロダクトへのスマートなクロスセルの方法は?
・両方受注しているクライアントには定期訪問のレポートをCSと一緒に作れないか?
etc
ほんの一例ですが、これらを考えて業務に落としこまないと、SaaSのプロダクトに何も紐づかないプロフェッショナルサービスなんて所詮傍流で終わります。だって究極、Reproでやる必要ないですもん。
前作で「支援領域の違う事業を立ち上げることはone team感が薄れるリスクがある」と書きましたが、その一因は間違いなく自分のマインドセットにありました。
・SaaSスタートアップの強さである「one product, one team」感が薄れるリスク。なぜならプロフェッショナルサービスがプロダクトと別領域の課題を解決している場合、そのチームは普段の業務で自社サービスと直接関わりを持たないのでプロダクトへの関心が薄くなる。関心が薄れるとコミュニケーションが減る。コミュニケーションが減ると組織は…💀
当社も一時期プロフェッショナルサービスの部隊だけサテライトオフィス勤務の時代があったが、サテライトに行く側からすると傍流感は拭えないし、物理的な距離が離れたことで本体側のbiz/devメンバーとの交流はさらに薄くなった。メインオフィスと比べてサテライトオフィスの雰囲気が悪いと問題視されたことも
『SaaSビジネスのプロフェッショナルサービスことはじめ』より抜粋
プロダクトとの業務的な関わりやRepro本体のMRRに貢献している仕組みを作れれば、傍流感など感じなかったはずです。働いているオフィスが分かれてしまったことはそれほど問題ではない。
むしろこの時の自分は「まあ目標のMRRは超えてるから問題ないか」と経営や他チームへのレポートも本当に最小限にとどめてしまい、現場間で他チームとの交流を生むような業務も生み出さず(たまにメインオフィス↔サテライトオフィスの交流ランチやってたくらい)、ASOチームを独立小国家のようにしてしまいました。
閉鎖的な小国家の繁栄が長くは続かないのは歴史が証明していますね…💀🏰
もう一度言います、「プロダクトが主、PSは従」。現在SaaS企業でPSやっている方は毎日唱えてください👹
引き継がれないフェータルな事業課題
事業の未来に関するグランドデザインが描けていないので、当然後任に引継ぐ際も中長期の展望や将来的なリスクに関する話は共有されません。
当時の引継ぎ
「チームミーティングは週一回で、ドキュメントを置いておくディレクトリはここで〜」
「セールスフォースの案件管理方法はこれで〜」
「メンバーの勤怠管理は~」「1on1と評価は~」
「受注決まったあとのメンバーのアサイン方法は~」
こんなの引き継ぎでもなんでもないです。
担当者レベルならOKかもしれないですが、責任者レベルでやるべき引き継ぎではない。
特にまずかったなと思うのは、すでに顕在化はしており、この先もボトルネックになり続ける可能性が高い課題に対して明確な打ち手を示す前に引き継いでしまったことです。
ASO支援事業の場合、具体的にはこの2つが積み上げ思考の自分でも認識している課題でした。
1. チャーンの高さ
・push通知の運用や広告の運用と比すると、ASOは継続的に人的リソースを割いてやるほどのものではないと考えているアプリ事業者が大半。
・なので1案件あたりの継続月数は平均5~6か月。Repro SDKの最低契約期間が1年~と考えると明らかに短いし、月々の運用案件数のボラも高かった
・そういったASOの商材特性に対して最低契約期間の再設定やApple Search Ads(ASA)へのスライドなど部分的な対処は行っていたものの、マーケ面で「ASOも広告と同様に担当をつけて運用するべき」というメッセージをより大々的に啓蒙・浸透させるとか、チャーンは高いドアノック商材と割り切ってプライシングや提供内容を設計し直しASO支援終了後は必ずSDKのクロスセルにも繋げる戦略にするとか、そういう上流の意思決定をしていなかった
2. ASOを売るセールス機能が自チームに内包されていない
・事業計画で掲げた運用案件数の目標は当然ASO支援チームとSalesチーム両方で達成するべきものだが、ASOに限らず全ての商材の新規案件を獲得する役割/責任はSalesチームにあった(※伊藤は0→1フェーズでも1→10フェーズでも自分で商談行ってはいたが、成約した場合の売上はSales組織と同席したSales担当個人に紐づいていた)
・新規案件獲得数に対する責任範囲が自チーム内に無いので、運用案件数・金額の目標が未達だったときにチーム内で対策がしにくいし、どうしても他責になる。
・また、採用が先に進んでしまった場合に案件数に対して運用コンサルの人数が過剰になる(≒暇な人が増える)が、そうなるリスクを踏まえて非正規雇用中心の採用にして彼らでも回る体制にするとか、手が空いた場合に別の業務を用意しておくとかを充分できていなかった
・セールスからしても、入社後ずっと売ってきたRepro SDKに比べてASOは経験が少なく、売りにくい。ニーズが違うので2つのソリューションがカニバることはないが、「何も与件がない時にどちらの説明を優先するか」と問われたら当然売りやすく、受注金額も高いSDKを優先してしまう
1∼2年先は見えていなくても、せめてこれらの顕在化している課題は引き継いだ責任者にしっかりと伝え、ディスカッションするべきだったと思います。
引継ぎに関してまとめると、次クォーターから半年先くらいまでの未来を自分無しでも回せるための業務標準化や権限委譲はできていたが、未来の解像度を上げる業務を全くやっていなかったので、起こりうるリスクや将来的な方向性などについてまったく引き継げていなかった、というかその考えすら無かったのがやばいところです。
…ここまで書いていて、自分では「ASO支援事業は0→1を突破してもう1→10のフェーズだぜ」と思っていたのですが、上記チャーンの高さや案件数をアンダーコントロールにしていないというフェータルな課題を残したまま引き継いでいる時点で、ゼロイチすらやり切れていなかったのではないかという気持ちになりました。つらい😔
今ならどういう時間の使い方をするか
では、上記の反省を踏まえて今同じ状況に置かれたらどういう時間の使い方をするか?
ざっくりの分けではありますが、自分のリソースを100%として当時と今考える"あるべき"の時間配分をグラフにしてみました。

重要視するところは「 脳みそ・リソースをいちばん使うところ🧠」で書いていることと同じです。
■ フェーズごとの時間の使い方⌛
0→1(当時)
・前述の"Just Do It"パートの通り、8割以上のリソースをマーケ・セールス・受注後の運用に割いていた。余った時間で管理部門ぽい仕事をやるかんじ
・今思えば案件の運用をハンズオンでインターンにスキルトランスファーしていたのと同様に、マーケやセールスも2人目を採用して自分が手を動かす部分を減らしていく動きをするべきだった
1→10(当時/あるべき)
・1→10でも相変わらず5~6割はマーケ・セールス・受注後の運用に割いていた。これはダメ
・マーケなら大きめのセミナーでの登壇、セールスなら難しいクライアントの最終クロージング同行など自分ならではのバリューが出る業務は残しつつ、積極的な権限移譲を図るべきだった
・案件運用も後進の育成や現場感のキープのためにゼロにすべきではないと思っているが、もっと減らせた
・ピンクの部分は当時で5%と書いているが、業務の中身は管掌役員と週次で行うKPI確認、案件進捗のmtgで、本稿で再三にわたり反省している「未来の解像度を上げるための業務」は全くできていなかった。今なら全リソースの四分の一くらいは使うべきと考えてるがそれでも少なすぎるかも
・HR系の業務は主に「攻めの採用」がぜんぜんできていなかった。入社オンボーディングや評価などは着手していたが自らリクルーティングするとか採用関係のブログ書くとか何もやっていなかった。これも25%では少なすぎるかも
・業務標準化(ドキュメント整備、提案資料の標準化etc)は時間を使って悪かったとは思わないが、前述の通りサブマネージャー的な人を採用してその人に任せる、でよかった。ここに割く時間はもっと減らせた
という感じです。嗚呼、タイムリープしたい…⏲
時間の使い方に関しては、LayerXの福島さんがとてもシャープな回答をされていました。(前田ヒロさん @djtokyo のpodcast聴きすぎ説)
前田:「1回目の起業(Gunosy)の時と2回目の起業(LayerX)の時で自分の働き方、時間の使い方で変わったことってある?」
福島:「かなり語弊がある言い方かもしれないですが、誰でもできることはやらなくなった。
昔は誰よりも長く働いていて、サーバーに障害が起こったら自分が一番最初に直しに行っていたし、ユーザーインタビューも自分が聴きに行くとか、カスタマーサポートも自分で返していて、それが美徳とさえ考えていた節もあった。」
(そういったことも)もちろん必要は必要だが、大前提として経営者のリソースはすごく希少なので、本当にそれをいま自分がやるべきか?」というのは(2回目の起業の今は)すごく考えるようになった」
(中略)
福島:「例えば僕カスタマーサポートとしてめっちゃ優秀かもしれないですけれど、CSとして出せるαっていわゆる一般のCS担当の方よりもせいぜい10%生産性が高いとかそれくらいだと思うんですよ。
もしかしたら2~3倍くらいは出せるかもしれないけれど100倍、1,000倍のパフォーマンスは出せない。なので変な美意識で細かい作業をすることは止めようと」
ソフトウェア産業の勝ち方が変わってきている ~ LayerX 福島 良典
(※podcastの37分ころから上記のお話をしています。このpodcastも学びが多く金言の宝庫なので、まだ聴いてない方がいらっしゃったら今すぐこのnoteは閉じてこっちを聴くほうがいいです…(˘ω˘) )
ちなみにExcel経営のところで紹介したFondの福山さんも同podcastでCEOが何に時間を使うべきかについてお話しており、そちらもすごく参考になります📻
1企業の事業責任者が経営者とまで思う必要はないかもしれませんが、時間は誰にでも平等なだけに、組織のフェーズや自分のその時の役回りによって常に意識し続けなければいけないなと強く感じています…🙁
おわりに
もともとはプロフェッショナルサービス立ち上げに際し未熟ながらもやったことを具体的に書こうと思い筆を執ったのですが、マインドセットや時間の使い方など根本的なレベルでの失敗が罪深すぎて反省が1万字を超えてしまい、施策レベルでの取り組みや反省まで書ききれませんでした…
ここから総論、各論という形で1→10フェーズの反省を書いていきたいと思います(ここからようやく本題。長い🙄)
って書いてたのに各論どこいったんや😠
各論ではこのあたりについて詳述するつもりでした。
・事業KPIとしてどこを見ていたのか
・具体的にどういうマーケ施策を行ってリードを獲得していたのか
・社会人経験ゼロのメンバーをどうやって育成していたのか
・代理店さんに売ってもらうの難しい問題
・マネージャーはどこまでクソジーコになるべきなのか
etc
このへんなどは次回作『SaaSビジネスのプロフェッショナルサービスことはじめ(実践編)』にて書こうと思います! (って言ってずっと書かないやつ←)
この反省文を読んで各論のとりとめもない話も聞きたい方、少しでもReproに興味を持ってくれたそこのあなた、ぜひご連絡ください~🍵 Twitter、FBでもOKです📧
つまりはこういうことです🔥 ご連絡お待ちしております!!

他にもちょこちょこSaaS関係のドキュメント書いてるので、よろしければそちらもお願いします📖
いいなと思ったら応援しよう!


