
真鯛 食べ鯛 捌き鯛
はじめに
好きな魚は何ですか?と聞かれるとおそらく、マグロ、カツオ、タイ、ブリ、ヒラメ、アジなどなどいっぱい出てくると思います。魚は日本人にとって昔から貴重なたんぱく源です。近年では日本での魚の消費量が少なくなり、農水省が魚をいっぱい食べましょうとPR活動をしています。20年ほど前に流行った「おさかな天国」もそういった経緯で作られた曲で、20年から魚離れは問題となっていました。その当時の鮮魚売り場では「お魚天国」がよく流れていました。今回は魚の中でも日本人になじみ深い鯛を取り上げます。自粛期間で鯛から得たことや思ったことを2回に分けて書いていきます。
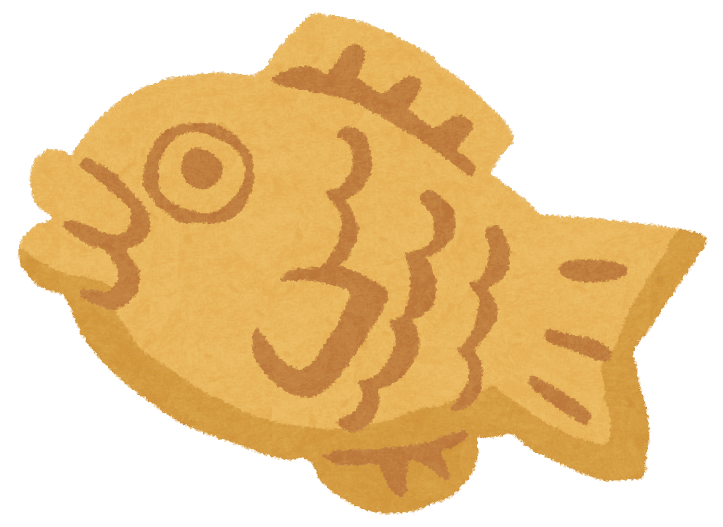
鯛を捌き鯛
鯛はスズキの仲間の白身の魚で、鯛にも様々な種類がありますが、一般的なのは真鯛です。鯛は色や形が綺麗なこととさらに鯛と「めでたい」をかけて祝い物として用いられます。アマダイや金目鯛のほうが真鯛より高級ですが、見た目や形からおめでたい席では真鯛が出てきます。お相撲さんが優勝したときやお正月のにらみ鯛などでおめでたい場面でよく登場します。さらに鯛は良い物の例えであり、「腐っても鯛」や「海老で鯛を釣る」といった言葉に使われます。日本人にとって鯛は単になじみ深い魚といだけでなく、良い物として認識されています。
日本人にとってとてもなじみ深い魚である鯛を食べたことがないと言う人は非常に少ないはずです。よく口にする魚ではありますが、実際に一から捌いたことがある人は食べたことがある人より少なくないと思います。魚を捌く話をしながらそれにまつわる話をしていこうと思います。
魚を捌くときにまず鱗を引きます。鱗を引くのは鱗が口の中に入ると生臭さが残るのと口を切ったり喉を傷つけたりするからです。生きた魚を丸呑みするアザラシでさえ、魚を食べるときは頭からしか食べません。その理由は鱗と反対の向きに食べると喉を傷めたり、最悪の場合、窒息してしまったりするからです。人間は道具を使う動物なので、包丁や鱗取りで鱗を引いて食べやすい状態にすることができます。写真のは三徳包丁で捌きましたが、出刃包丁で捌くのがベストです。このときはまだ出刃包丁を買っていませんでした、、、

そして、次のエラと内臓の除去です。エラは魚が酸素を取り入れる部分なので、血が多く残っている箇所であるため、エラが残っていると生臭さが残り、寄生虫がいることもあります。そして、内臓を取るのは寄生虫の除去です。寄生虫を人間の体内に取り込むと体調不良だけでなく、命にかかわる事態に陥ることもあります。外国で生魚を食べない方がいいと言われる理由は下処理がテキトーであることが多いため、寄生虫を体内に取り込んでしまうからです。処理されていない魚を早めに処理しないと寄生虫が内臓以外の身に移ってしまうことがあります。
肉食獣は獲物を捕らえたときに内臓から食べます。その理由は栄養が一番あるからです。あれ?内臓が一番栄養あるなら魚の内臓を食べてもいいのではないかと思われますが、寄生虫も同様の理由で内臓に寄生しています。内臓にある栄養よりも寄生虫を体内に取り込むリスクを考えると栄養を捨ててでも体を守ることが重要と判断した先人の結果なのかもしれません。
鱗引きとエラと内臓の除去は一種のリスクマネジメントです。鱗が残っていると魚自体の風味に影響を与えるだけでなく、危害を及ぼします。内臓やエラについても、同様で鱗以上のリスクを回避するために行います。こういった作業にしっかりとした意味があり、その意味を考えると動物の体の構造やそれを取り巻く環境が分かります。研究者が動物を解剖するのはそういったことを調べるためです。魚を捌く場合には鱗や内臓やエラは食べられないので捨てます。
鯛を食べ鯛
鱗やエラや内臓を取ることを下処理と言い、ここから三枚におろしたり、二枚におろしたり、姿焼きにしたりします。次の工程をどうするかはどんな料理を作りたいかによって決まります。塩焼き用の切り身を作りたいなら二枚おろしで十分ですし、刺身とアラ汁を作りたい場合は三枚におろさないといけません。鯛丸々、刺身で食べたいと思ったとしましょう。そうなると三枚におろすことになります。両面の身を背骨から切り離し、中骨をすき、皮も引きました。こうなると中骨の付いた部分や皮は不要な部分になります。
じゃあ、これをそのまま捨てるのかとなると思います。そこは自由ですが、せっかく鯛一匹丸々食べるのであれば、食べたいですよね。実はこの中骨の部分や皮についても、どんな料理をするかで要不要が決まります。刺身しか食べないという人はそれらの部分はゴミですが、そういった部分を料理する人はそれらの部分は大事な材料です。決まった物だけを作るのが料理ではなく、その過程で出たものを使うことも料理なのです。この部分は料理の大事な技術の部分でもあります。その最たる例がアラ汁やアラ煮です。アラのように食べにくい部分をあの手この手で食べようとして工夫した結果だと思います。料理ができるというの単に美味しい味付けができることだけでなく、手元にある物でどういったものが作れるかでもあります。

単に包丁さばきが上手であったり、味付けがうまかったりすることだけが料理ができるのではなく、余った物をどう使うかも料理です。プロの料理人は無駄なものをほとんど出さないと言います。お客さんに提供する料理で使わない物があることはありますが、だからといって捨てることはありません。それをまかない料理にしたり、それで出汁を取ったりします。これが技術の問題と思われるかもしれませんが、知識の問題です。魚であれば身は食べることができても、大きい背骨や頭を食べることができないと思うかもしれません。しかし、アラ汁やアラ煮という料理を知っていれば食べることができます。魚を捌いて料理して思うのは使えなさそうな所であってもちょっとした工夫次第では料理ができるので、そういった意味ではスーパーフードだと思っています。アジを三枚におろしたときにできる背骨に唐揚げ粉を付けてあげるとちょっとリッチな骨せんべいが出来上がります。魚を料理するときにどんな料理ができるの考えながらするのも楽しいです。
おまけの方で料理についてざっくり触れています。気が向いたら読んでみてください。
