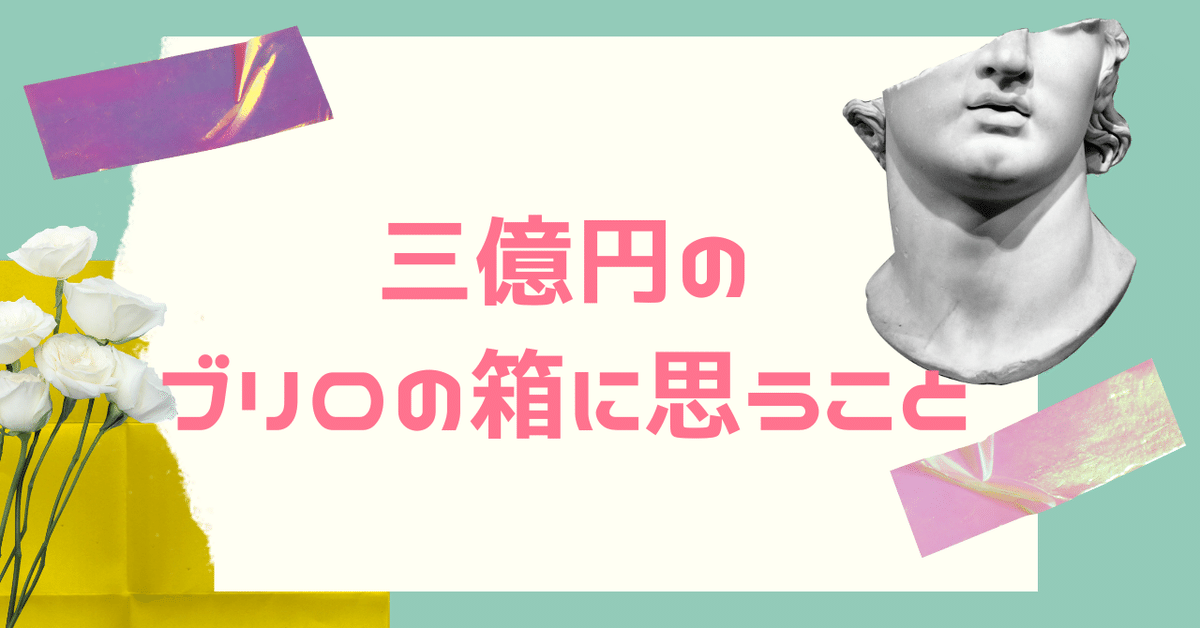
三億円のブリロの箱に思うこと
こんにちは。特別支援学級教員13年目のMr.チキンです。
寒い日が続いています。学校の用務員さんは
「だんだんと衣替えする子が増えてきて。こういう季節が一番廊下にホコリがたまるんですよ。」
とつぶやいていました。
そういう季節の移り変わりの感じ方もあるのだな。人と話して初めて気付かされることもありますよね。
さて、今日は、巷で話題のアンディ・ウォーホルの作品についてお話をさせてください。
アンディ・ウォーホルの三億円の箱
鳥取県が三億円の”ブリロの箱”を購入というニュース
こちらの記事でもお話ししている通り、実は中学校・高等学校の美術の教員免許を取りました。
ですから、美術関連のニュースはとても気になっています。
今、巷では、鳥取県がアンディ・ウォーホルの作品を三億円で購入したことが話題となっています。
しかし、購入した作品の金額が物議をかもしている。その額はなんと…
鳥取県民A:
3億円…
鳥取県民B:
言葉が出ないですけど。
県民もびっくりのお値段約3億円。
県が購入したのは、アメリカ製タワシのパッケージに似せて作られた「ブリロの箱」という作品。作者は“ポップアート界の巨匠”アンディ・ウォーホル(1987年没)だ。
ウォーホルは“スープ缶”やマリリン・モンローの肖像画で知られ、モンローの作品には2022年オークションで約250億円の値がついた。
県民の間では、「三億円分の観光収入は期待できるのか」などの批判の声が上がっているということでした。

この箱に、三億円をかけたこと、皆さんはどう考えられるでしょう?
アンディ・ウォーホルってどんな人?

アンディ・ウォーホルは、言わずと知れたアメリカン・ポップアートの巨匠です。

こちらの”マリリン・モンロー”は有名すぎるほど有名ですね。
この作品の作者が、アンディ・ウォーホルです。
シルクスクリーン技法と呼ばれる技法を用い、「ファクトリー」と呼ばれる工房で、スタッフを雇って制作をしていました。そのことにより、既存の写真イメージを、何度でも、大量に、短時間に、反復生産できることを可能にしました。
アンディ・ウォーホルは、ネオ・ダダの流れを引き、アメリカン・ポップアートをけん引した人物として有名です。(ネオ・ダダについては後ほど解説します。)
彼の才能はグラフィック・デザイナーのみではとどまらず、映画監督やミュージシャンのプロデュースなど、幅広い芸術分野で活躍しました。
アメリカン・ポップアートへ至る歴史的な流れ
アメリカン・ポップアートが、ネオ・ダダの流れを引いて成立したと言われています。ネオ・ダダ?なんだそれ?と思われる方も多いと思われますので、ごく簡単に流れを説明しましょう。
ダダイスム
ネオ・ダダの前に、”ダダ”についてお話をします。
ダダというのは、一つの芸術運動の総称です。
時代背景は第一次世界大戦中から大戦後にかけて。

実は、芸術において、第一次世界大戦というものは大きな意味を持ちます。
私が大学の頃に学んでいた国文学史の教授は
文学史は、第一次世界大戦前と第一次世界大戦後で明確に分けられる。
とおっしゃっているほどでした。
第一次世界大戦は、戦闘機や戦車が用いられた初めての大規模な戦争でした。それまでの歩兵などが中心となる戦争から大きく様相を変え、たくさんの人が亡くなりました。
人々は
人はここまで人を殺せるのだ。
ということに気付かされたのです。
その気付きは、アート運動に昇華されていきます。
第一次世界大戦に対する抵抗やそれによってもたらされたニヒリズムを根底に持っており、既成の秩序や常識に対する、否定、攻撃、破壊といった思想を大きな特徴とする。

ダダイスムの根幹には極端なまでの反戦があり、その表現方法には、反芸術がとられたのです。
ネオ・ダダ
時代は変わって第二次世界大戦後のアメリカ。
ロバート・ラウシェンバーグやジャスパー・ジョーンズといった芸術家たちは、既存の芸術的価値への抵抗を、ダダの手法を取り入れて表現しました。

これは、ジャスパー・ジョーンズの「旗」という作品です。この作品は、そこにアメリカ国旗があるだけです。
今までの絵画は、「ほかの何かについて」が描かれている物でした。この作品は、みんなが知っている記号としての”旗”を表現しており、あえてそれ以外のメッセージ性を排除しています。
メッセージ性を排除していることが、逆にメッセージ性を際立たせているのです。
この、物事を記号として捉えて表現するというネオ・ダダの手法は、のちのアンディ・ウォーホル率いるアメリカンポップ・アートにつながっていきます。
アメリカンポップ・アート
戦後のアメリカは、「豊かな時代」として捉えられました。
そして、ネオ・ダダの成功は、その「豊かな時代」を表現しようとする多くのアーティストに影響をあたえました。

ロイ・リクテンスタインの「どうにもならない」は、漫画の表現方法を拡大して用いました。ベンデイ・ドットという、陰影をつけるための網点が作品の存在感を引き立たせています。

クレス・オルデンバーグは、日常的な器具や家具をモチーフとして制作を行いました。
アメリカンポップ・アートは、当時のアメリカ社会の大量生産・大量消費という社会背景をそれぞれのアーティストが、時に肯定的に、時に皮肉的に表現の場に引きずり出したアート運動という一面もあります。
アメリカンポップ・アートへの批評
ただ、アメリカンポップ・アートには、厳しい批評もあります。
美術批評家のクレメント・グリンバーグという方は1960年代のポップアートなどを「ノヴェルティ・アート」と呼び、
「低いレヴェルでの楽しみ」であって「キャンディのように小さくなってしまう」もの
であると批判しました。
アメリカの「豊かな時代」を表現したアメリカンポップ・アートではありますが、当時から様々な批判があったことが分かります。
美術館に高価な作品を取り入れること=観光資源 なのか
”ただの箱”であるということと、”ただの箱であることが重要”ということのジレンマ
さて、冒頭の”鳥取県の美術館が三億円の作品を購入した”という話に戻ります。
おそらく、県民の方々は、驚かれたと思います。

ブリロの箱は、本当に”ただの箱”に見えるからです。
ただ、一方で、美術史を紐解いてみると、アメリカンポップ・アートの中では、”箱が箱としてそこにあるということ”自体がアートの価値であるということも分かるでしょう。
そして、そこに三億円の価値を見出せるのかどうか・・・ということも。
今回の県民の皆様の困惑は、”ただの箱である”ということと”ただの箱であることが重要”であるというジレンマの渦中にあるということにおいて、すでにアンディ・ウォーホルの掌の上にあるのかもしれません。
大学の授業でならったこと 「大家族」を宇都宮美術館が購入した例
大学の頃、美術の科目を受講していた時のことです。
その時の教授が、ディベートのテーマを提示しました。

宇都宮美術館が、ルネ・マグリットの「大家族」を三億円で購入しました。
それについて、皆さんはどう感じるか。
というものでした。
私を含む学生からは
作品的価値があるので、購入は必然である。
全ての人にとって価値のあるものではないので、税金を投入することには反対だ。
という二分された意見が出ました。今の鳥取県と同じ構造です。
教授は、「確かに、この作品に価値があるかどうかには、評価が分かれる。」としながらも、
では、この作品購入経費である三億円を、宇都宮市民の人口で割ったらどうだろう。
当時の宇都宮市の人口は50万人ほどでした。
一人当たり600円ほどになります。
実際に、このマグリットの作品を見るとなったら、ヨーロッパやアメリカへ行く必要がある。
600円で、ヨーロッパに行けるだろうか。
ホンモノの作品が身近にあるという強みは、実はそういうところにあるのかもしれませんね。
奇しくも、宇都宮市の人口と鳥取県の人口、そして作品の市場的価値がほぼ同様のケースでした。
アンディ・ウォーホルのホンモノがそばにあるという価値は、単なる観光資源なのだろうかという視点は必要かもしれません。
教員の視点から 自分が鳥取県民なら、どうやってブリロの箱を授業に使おう?
最後に、学校教員としての視点から考えてみましょう。
実際に、気軽に行ける場所にホンモノの芸術作品があったら、どんな授業ができるでしょう。
ポッと思いついたものをいくつか。
低学年:箱の中には何が入っているかな?~想像をふくらませよう~
中学年:三億円で何をしよう?~鳥取県は箱を買った!~
高学年:三億円の箱のパッケージを考えよう~自分とホンモノのギャップ なぜ、この箱に三億円の価値が付いたのか~
こんな授業をしてから、美術館に足を運んで、ホンモノを見てみたら・・・子どもたちはどんな反応をするだろう?
と、想像をしてしまいました。
三億円というのは大きなお金です。それをアートに使って良いのだろうか?という議論も含め、みんなで話をしていく必要はもちろんあります。
みんなで鳥取県の議論に注目していく・・・それも一つの経済効果かもしれません。
"買ってよかった"と思える議論となれば良いなと考えています。
では、またね~!
