
超個人的な思い入れをつめすぎた| #名刺代わりの小説10選
深夜にビールの泡をなめながら、Twitterのハッシュタグとそれに付随するTLをスイーッと親指でスクロールして流すのが好きだ。変なやつかもしれないけど。いつもは眺めるだけで終わるのだけど、うっかり、単純に「いいじゃん」と思うと指を滑らせてしまったりして、ツイートボタンを押してしまうことも、まあ、しばしばある。
#名刺がわりの小説10選
部屋の明かりをつけて、自分の本棚を眺めて、トトトッとタップしたツイートがこちら。
こころ
— まりさん (@marisaaan27) June 22, 2019
吾輩は猫である/夏目漱石
きらきらひかる
抱擁、あるいはライスに塩を/江國香織
重力ピエロ/伊坂幸太郎
モモ/ミヒャエル・エンデ
ミドリのミ/吉川トリコ
エヴリデイ /デイヴィッド・レヴィサン
ジヴェルニーの食卓/原田マハ
最果てアーケード/小川洋子
#名刺代わりの小説10選
「趣味は読書です」と誰にも、自分にも後ろめたい思いをせずに言いたくて、すがりつくように本を買い込み、かじりつくように読んできた。決して大きくはない本棚にさしてある本たちには、1冊1冊思い入れと感想がある。
ツイートした10冊だって、"わたしの名刺”というワードに沿うように選んだ。けれど、タイトルだけでそれって伝わりきれるのかな・・・?140字しか伝えられないことがちょうどいい場合がTwitterには多いのだけど、今回ばかりは、140字じゃ足らない気がするし、考えていたら、選んだ10冊をもっと言葉を足して紹介できれば、"わたしらしさ”が見えてくるような気がした。
ということで、noteに補足を書くことにする。Twitterで紹介した10冊+αを、わたしらしく書いてみた。断言するが、これが本当に書きたかった、 #名刺代わりの小説10選 である。
*見出しと内容がミスマッチなところがあるかと思います。
あらすじなど、気になる作品は調べていただくか、
Twitterなんかで、ぜひ気軽に聞いてください。
恋が罪悪なら、この憧れはなんですか|夏目漱石『こころ』
鎌倉の海岸で、学生だった私は一人の男性と出会った。不思議な魅力を持つその人は、“先生”と呼んで慕う私になかなか心を開いてくれず、謎のような言葉で惑わせる。やがてある日、私のもとに分厚い手紙が届いたとき、先生はもはやこの世の人ではなかった。遺された手紙から明らかになる先生の人生の悲劇――それは親友とともに一人の女性に恋をしたときから始まったのだった。
(引用:新潮社 『こころ』)
高校生のときに夏目漱石という作家に出会い、彼に心をベシャベシャにされた人間は、(わたしだけであってほしいけど)わたしだけじゃないと思う。物語が身体に馴染みすぎると、日常に戻ってくることが難しくなる。彼の文章は、まさにそうで、教科書用に編集された『こころ』を読んで、戻ってこられなくなった。
戻ってこられなくなった理由としては、漱石の使う日本語が、恐ろしいほど美しかったことと同時に、思想家に初めて出会ったことが大きい。漱石本人もそうだが、『こころ』で“先生”と呼ばれる彼もまた、作中で思想家と紹介されたりする。はじめて出会った思想家が発した「恋は罪悪ですよ」という言葉の、あまりに残酷な響きと、そしてその言葉の後ろにある過去の告白のマリアージュに、メロメロになった。いまでも深酒するとベショベショに泣きながら「なぜわたしは漱石が生きてた時代に生まれなかったのか」といい始めるようぐらいには、心奪われつづけいるので、いまだに戻れていないのかもしれない。
余談だけれど、高校生のわたしは、戻ってこられなくなった結果として、人生ではじめて国語教師に喧嘩を売り、4000字のレポートを提出し、5000字の赤字を食らった。思い出深いな。
趣味欄に「人間観察」って書くひとの必読書|『吾輩は猫である』夏目漱石
大学を卒業できたのは、猫のおかげだ。
『我輩は猫である。名前はまだない。』という書き出しは、一般教養テストで問題になるに値するほど、簡潔かつ美しく、洗練された1文がすぎると思う。
というようなことを2万字書き連ねた論文と、猫の好きなシーンを切り取って朗読原稿を作り、舞台上で読み上げて、卒業制作として提出。単位不足などない、真面目な学生だったものの、漱石の猫でなければ、飽き性を発揮して卒業できない事態に陥っていたことも容易に想像できる。
猫の目を通して読んだ人間の世界は、ちょっと時代錯誤を感じる部分もあるが、新鮮で、痛快で、重々しさなどなく続く、わたしが生きる"日常”と重なってくる。
この作品のおかげで、黒猫を見ると、みんな作中の猫と同じように世の中を皮肉りまくっているんだと思い込むに至った。いつか土砂降りの日、川辺で猫を助けたいとすら願っているので、目撃情報お待ちしております。
中学教師苦沙弥先生の書斎に集まる明治の俗物紳士達の語る珍談・奇譚、小事件の数かずを、先生の家に迷いこんで飼われている猫の眼から風刺的に描いた、漱石最初の長編小説。
(引用:新潮社 夏目漱石『吾輩は猫である』)
性癖の露呈、といっても過言ではない|『きらきらひかる』江國香織
アル中の妻と、ゲイの夫と、その恋人(青年)、そして彼らを取り巻く人々が織りなす”普通の恋愛小説”。たぶん、恋や愛を意識しはじめたばかりの高校生で読んでしまったばっかりに、恋愛の指針、みたいなものをこの小説で培ってしまって、今後もきっとそれは続く。最近失恋したのをきっかけに読み返して思った。積極的に勧めないけど、読んだ人と出会うと、なんとなく、”うん、ね・・・”という同志っていうか、頷きあいたい気持ちになる。
幸せな閉鎖空間。愛すべき日々。ここは、わたしの理想形。
「お前たちのことはよくわからんが」
ばかみたいに喋り続ける息子をじっとみてからコーヒーに口をつけ、
「でも、私には笑子さんも銀のライオンにみえるよ」
と言って、またひっそりと笑った。
恋や愛を意識しはじめて、ようやく10年経ったが、ようやくわかった。
この作品の主要登場人物、同性の恋人を持つ夫、睦月が好きだ。どタイプだ。「どんな人が好み?」と聞かれて、いままで、まったく答えられなかったけれど、今後は大きな声で言いますね。わたしの好みのタイプは『きらきらひかる』の睦月です。潔癖症未満のきれい好きで、ずぅっと苦笑みたいに微笑みながら、ひどい優しさで人を傷つけたり、誠実のためになんでも犠牲にしてしまったり、真面目が故に肝心なことに気が付かず、全部を取りこぼしてしまいそうな、そんな睦月が好きなのだ。
物語のような人生でありたかったのに、|『抱擁、あるいはライスに塩を』江國香織
幼い頃(この”幼さ”は、世間を何も知らなかった頃のこと)西洋の、お城みたいなお屋敷で暮らす人たちに憧れていた。少し成長して、そんな素敵な閉鎖空間の中で、自分たちの幸福を守るために、どうしようもなくなっている物語が好きになった。この作品からは、家族という枠組み(空間)から、少しずつ足を出し、それぞれが苦労をみせびらかさずに生きるひとたちの、痛々しくも繊細で、なおかつ美しさが匂い立つ。あるいは思慕と執着、家族の歴史かもしれない。
お城みたいなお屋敷、他人の侵略をたやすく許さない、居心地のいい場所で、ずっとたゆたっていたいよ、ほんとはね、きっとわたしだけではなく、だれかもそうだ。
上巻・下巻と分かれている、長い長い物語なのだけど、上巻が好きだ。青天の霹靂として、ずっと心に残る言葉に出会い、目がさめるから。
そういえば、個人的に、江國香織さんは短編の名手だと思っていて、エッセイも最高なのだけど、そういう人の書かれる長編小説は、文句なく最高なのだ。わたしの読書の好みと癖の話だけれど、だいたいはじめて読む作家にふれるとき、短編から入る。そういう癖があったことに、いま気がついたや。
「小説や映画にでてくるみたいなことが、ほんとうにあると思ってたんだから」
そう続けた彼女の浮かべた笑みは、しかし自嘲そのものだった。
ぼくらの正義はここにある|『重力ピエロ』伊坂幸太郎
春が二階から落ちてきた。
この一文に、軽く脳震盪を起こす。そして、これほどまでに起承転結があざかやな作品に、わたしはまだ出会えていない。
この物語の中で、家族の定義とその関係は、遺伝子に依存せず、それ越える。静と動、それぞれの気性をもつ登場人物たちの一挙一動。レイプや放火、売春、ストーカーといった、もう、事件しかない時間軸を背景にして、淡々とそれでも際立つように営まれる兄弟、家族の時間。そしてその存在感。
出される答えは、世間様にとっては正義ではないけれど、この作中の家族と、作品を好む読者の中では、かなり絶対的に、正義だったんじゃないか。
わたしの正義は、この中にある。そう思う作品が本棚に眠っていることが、明日も強く生きる根っこのひとつになる。
物語をまたいで出てくる登場人物がいることは、伊坂作品の醍醐味でもあるけれど、同級生はだいたい「黒澤さんが好き」って言ってて、わたしはふーんって適当に相槌を打っていた。誰かの好きに乗っかるものか、と意地をはっていたせいだけど、思い返すと、私も黒澤さんが好きだった。ほんと、そういうとこ。
時間を惜しまず、誰が好き?っておしゃべりしたい|『モモ』ミヒャエル・エンデ
児童文学、とても好きだ。岩波少年文庫を愛読して長い。
ミヒャエルエンデの代表作として、有名すぎる『モモ』は児童文学の中でも代表作と言っても過言ではないほどに、多くの人に愛される有名作ではないか。
きっと、あなたにはあなたの、『モモ』がある。
多彩な登場人物の中で、みんな誰が好きだろう。ちょっといま思ったんだけど、登場人物って、物語だと(とくにファンタジーにおいては)、人でなくても、熊やドラゴンであっても、登場人物と呼べるのって、寛容で、ひどく柔軟で、いいな。
わたしは、カシオペア(亀)が好き。(背中に文字を光らせて、ゆっくりとモモを導くシーンは何度読んでも美しい。)
それでは、ねえ、あなたは、だれが好き?
余談ではあるのだけど、この夏、岩波少年文庫から特別カバーデザインの『モモ』が発売されているのだけど、びっくりするほど可愛いので、ごきょうみあればぜひどうぞ。
心の声(ふつうふつうって、うるせーな!)|『ミドリのミ』吉川トリコ
本のジャケ買い、ってするひとですか?
これ、「結構“賭け”だよね〜」って言われがちで、表紙につられてみたら、内容が全然自分に合わなかった、みたいなことがちらほら起きるそう。いつもそう聞いては、「そっか、そうだよね~」と答えていたけど、ごめんなさい。わたし、ぜんぜん、「そうだよね~」って思わずに返事をしてきた。
ちょっとした自慢なのだけど、わたしはジャケ買いで失敗したことが、ほぼない。見た目がきになる本は、中身もきになる本だ。いままで、ぜんぶ。
『ミドリのミ』も完全にビジュアルから入った。
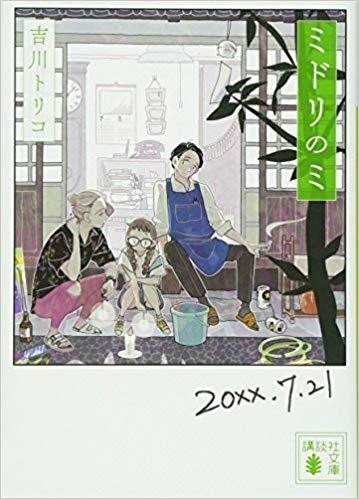
何回眺めてもおしゃれでかわいくて、でも絶対的になにかさびしい。
とはいっても、心構えとしては、サラッと読めるアットホームコメディみのある作品かなと思ってたのに、予想はことごとく覆されて、とにかくすごく”ぶわっ”とくる作品だった。びっくりして、3回ぐらい繰り返し読み返した。
よくもわるくも、わたしにとって、"ふつう”は大事な判断基準だ。
できるだけ外れたことはしたくないし、目立ちたくもない。
でも、”ふつう”って何で、どうして”ふつう”にこだわるのか。
なんで“ふつう”じゃないとだめなの、って聞かれると、ちょっと、ぜんぜん答えられそうにない。途方にくれる。それでも。
小学三年生のミドリちゃんと、父親の広とその恋人の源三と、別居中の母親・貴美子。はじめは、ぜんぜん気持ちがわからない、相容れないと思っていた登場人物たちが、読みすすめるたびに愛おしくなり、全員に"居場所”を持ってほしいと切に願ってしまう。
”ふつう”が好きだ。好きなひとたちが幸せになれる”ふつう”を、わたしはいっとう大事にしたい。
重田ミドリ、小学3年生。今一緒に住んでいるのは父の広とその恋人、源三。母親の貴美子とは別居状態だ。夫の突然の心変わりがなかなか受け入れられず、離婚話もなかなか進まない。
ミドリも楽しそうに過ごしてはいるが、色々と抱えているものがあって――。(引用:講談社BOOK倶楽部『ミドリのミ』)
「あなただから好き」って、顔の話?魂の話?|『エヴリデイ』デイヴィット・レヴィサン
「知ってたかも知れないけど、好きで、付き合ってほしい」
はじめて告白をされた時に、わたしは困惑して(そもそも、知らなかったし)、1時間ぐらい相手とずっとにらめっこしていた。
なにをもって、好きなのか。
恋や愛を前にして、いま、わたしは性別は超えられるだろうな、とぼんやり考えている。いままでの経験値からのみ出される"可能性”だけで話すなら、異性愛者なのだろうけど、わたしにもだれにも、これから先はわからない。
ただ、じゃあ超えられないものも、あるんじゃないだろうか。例えば、理由を上手につけることもできない、”生理的に無理”とか。
レヴィサンの『エヴリディ』は、2019年の初読了本で、読み終わったあとしばらくグルグルした1冊だ。
主人公は14年間、毎日違う、見ず知らずの少年少女のからだで目覚め、その子として一日を過ごす暮らしを、ずっと続けているA。この名前すら、便宜上、つけた名前というのもグッとくる。ある日、恋をしたAは、必然的に、あらゆる子に成り代わりながら、同じ子を思い続けることになる。男だったり女だったり、デブだったり痩せっぽちだったり、ヤク中だったりいじめられっ子だったりしながら、同じ子を思う。AはAだけど、外側はいつも違う。
恋することは簡単だけど、恋されることは簡単じゃない。
その上、Aの恋は、他人の人生と生活を変えることになる。それは、、やっちゃいけないことだけど、じゃあ、どうしたらいいんだろう、どうするんだろう、と最後の方はもう、ずっと悲しい。
わたしは、なにをもって好きだと思うんだろうって、ずっと考えることになった。性別とか見た目とか、関係ないって思ってたけど、本当にそうだろうか。ずっと考えている。いまも。
わたしは、天才の目になりたいです|『ジヴァルニ-の食卓』原田マハ
中学の時、美術部に所属していて、一番好きだった活動が、美術準備室で埃をかぶった、有名画家の代表作図録をみる、だった。
わたしは、印象派の画家たちだ好きで、夕日が入る埃っぽく、油絵の具のにおいが染み付いた、せまい部屋の中で何度も何度も大きなページを捲り続けた。
東京に暮らしていて嬉しいことは、いろいろあるけれど、なかでも、すぐいける距離に美術館があるっていうのは、かなり、グッとくる。実家が田舎にあるので、美術館っていうのは、1日かけて行く小旅行のうちの1つだったし、だから、ずっと図録で我慢をしてきただけに、ほんとうに嬉しくて、価値がある。
図録をみていても、美術館で展示される本物の絵をみていても、思うことはいつだって同じだ。
この画家の目になって世界をみたい。それが無理なら、彼らのそばで同じ目線でみて、知り得ることができたらどんなにいいか。
どちらも不可能な話なのだけど、いまだって思う。
『ジヴァルニ-の食卓』に出てくる、モネ、マティス、ドガ、セザンヌは大好きな印象派の画家たちで、なおかつ語り手となる女性たちは、わたしがなりたかった(いまもなりたい)存在にほかならない。
「太陽が、この世界を照らし続ける限り。モネという画家は、描き続けるはずだ。呼吸し、命に満ちあふれる風景を」
そうだ、わたしは、職業を画家にするしかなかった天才に、ずっと憧れている。だから、美術館で泣く。彼らが向き合い続けたキャンパスの、その向こうの景色をみたくて、また泣く。
何回も初めてみたいな顔して、レジに持っていく|『最果てアーケード』小川洋子
うっかり、同じものを買ってしまうことってある。
まだ残っているのにお醤油を買っちゃうとか、弟と共有している漫画の、同じ巻数をふたりとも買ってしまったとか。家に帰ってみると、「ええ、あったっじゃん・・・」と呆然として、そのあとちょっと笑ってしまう。
先にいうと、小川さんの『最果てアーケード』を、わたしは4回、買っている。実家に1冊、自宅に1冊、残りの2冊はひとにあげた。2012年に文庫版が発売されたのだけど、そこから、数年おきに1冊買う、みたいにやらかして、いまにいたる。
毎回、新鮮な気持ちで買うのだ。ああ、こういうの読みたかったんだよね、という気持ちで。小さなアーケードで、ささやかに身動きがとれなくなっている、うつくしいひとやものたちに焦がれて購入し、自宅についてから驚くのだ。4回やってる。たぶんあと2回ぐらいやる気がする。
個人的に、夏の空気をまとった作品だと思う。いや、毎回夏にやらかしてきたからかもしれないけれど。
そういえば、百科事典の話を読むと、『博士の愛した数式』を思い出すの、わたしだけだろうか・・・?と思ってAmazonレビュー見たら、同じこと書いてるひとがいて、やっぱりそうだよね、と随分励まされたことがあります。
使用済みの絵葉書、義眼、徽章、発条、玩具の楽器、人形専用の帽子、ドアノブ、化石……。「一体こんなもの、誰が買うの?」という品を扱う店ばかりが集まっている、世界で一番小さなアーケード。それを必要としているのが、たとえたった一人だとしても、その一人がたどり着くまで辛抱強く待ち続ける――。(引用:講談社BOOK倶楽部 『最果てアーケード』)
いいなと思ったら応援しよう!

