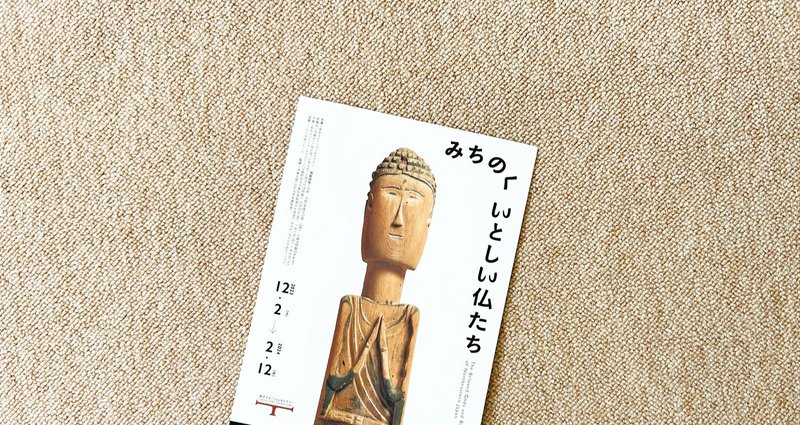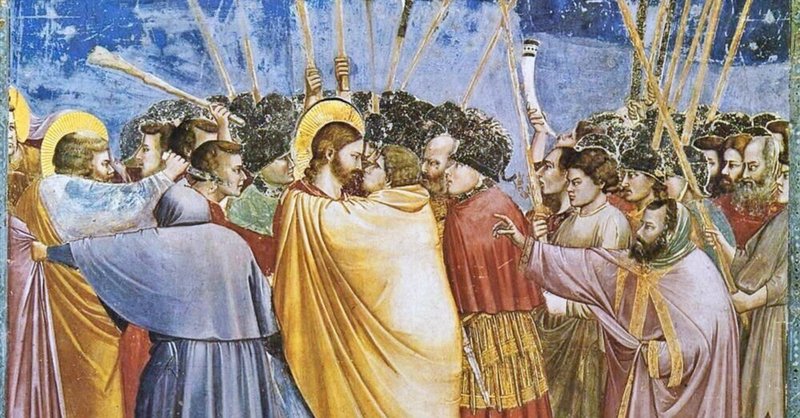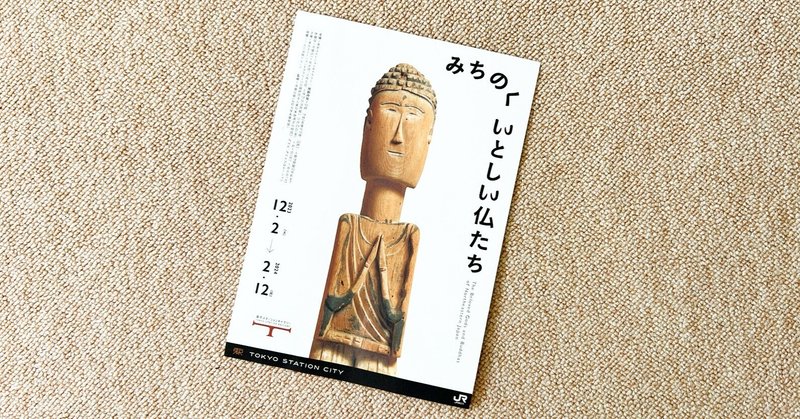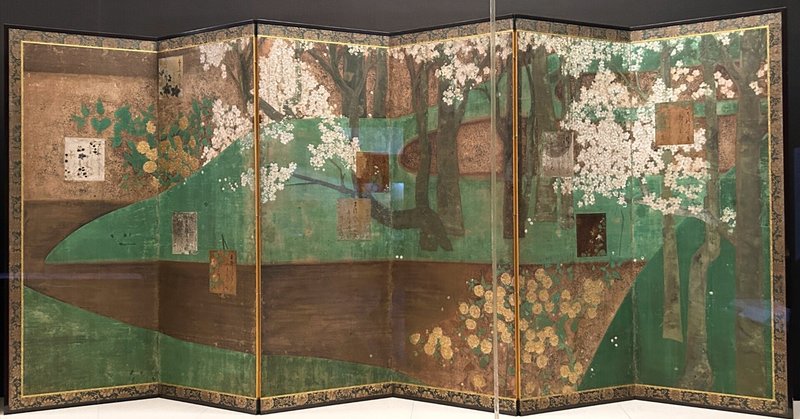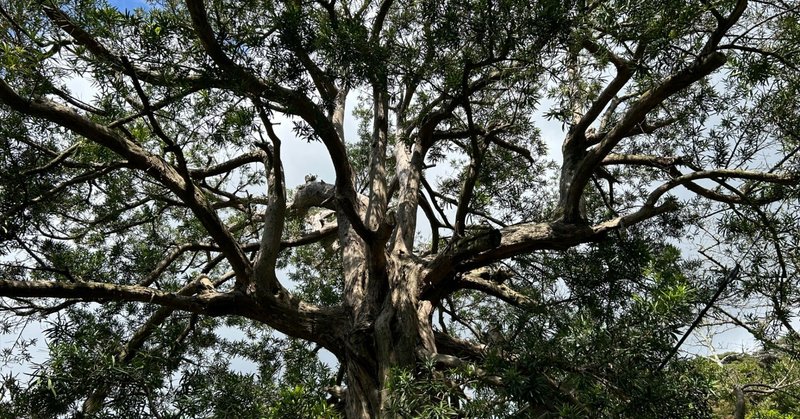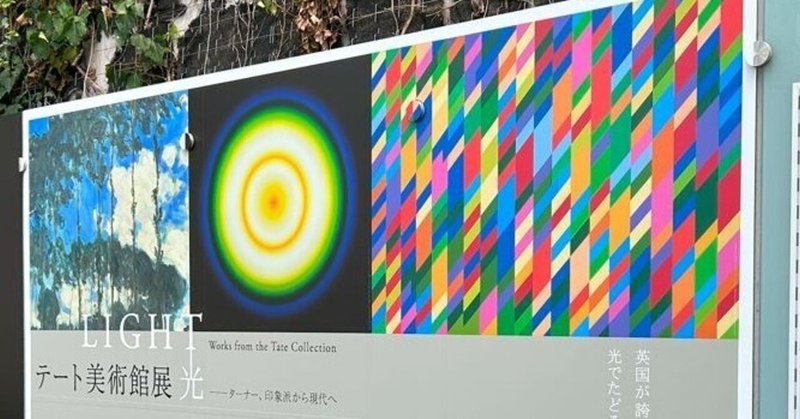#芸術

[理系による「アート」考察] 東京BABYLON(1990~1993) ➡"魔法少女まどか☆マギカ"を、それより20年前にBL(Boys' Love)でやったCLAMPの凄さ
会社の後輩(20代後半)に強く強く勧められて"魔法少女まどか☆マギカ"(アニメ版)を見ました。 自身は、萌え系の絵に強い拒否反応があり、最近のアニメは全く見ないのですが、あまりにも後輩が薦めるのと、エヴァを知らない最近の若い世代のカルチャーに強い興味があったので(その後輩はエヴァを見たことがない…)、食わず嫌いかもしれないと思い立ち、12話を一気に見ました。 初めは、予想通りの拒否反応がでて、このアニメを見ることが苦痛で苦痛でしかなかったのですが、修行だ!、と思い耐えてい