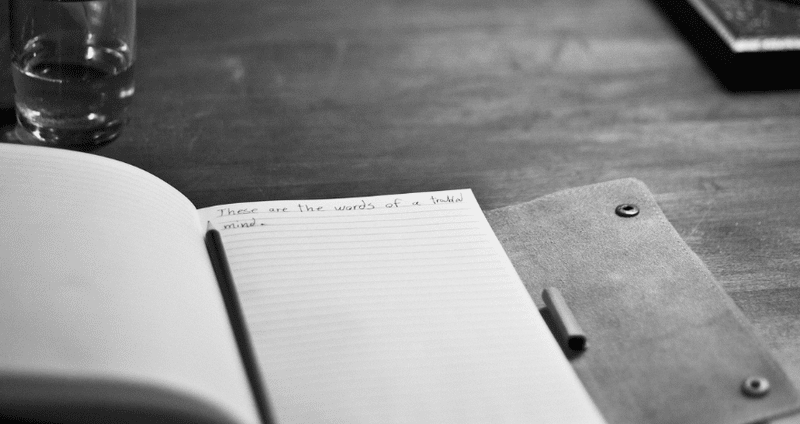#読書日記
作家の心もちに震えた『禁忌の子』
鮎川哲也賞受賞という看板をひっさげて登場し、話題になっている『禁忌の子』
作家は経験がなくたって様々な事を描けなければならないけど、それでも「よく書けたな!!」というものがあります。
この作品はその逆。受賞作だけあって、冒頭に受賞の言葉が入っているのですが、”1歳の子どもの声を聞いている”というフレーズを読み終わったときに思い出し震えました。
この作家の心持ちたるや。
救急医の元に運ばれてきた
「「「「のスピードに圧倒された『死んだ木村を上演』
メフィスト賞受賞という実績をひっさげて登場して話題になった『死んだ山田と教室』。本編と同じくらい驚いたのが、ページの最後に続編告知が出ていたことでした。
その続編が『死んだ石井の大群』。
さらにその『石井~』の最終ページには『死んだ木村を上演』の告知が。
デビュー作にして3部作。誰の度胸がすごかったって、出版社の度胸がすごいわ。それだけ「絶対話題にする」という強い意志も感じましたが、売り手側の
『対馬の海に沈む』に人間の業の深さを感じた
久しぶりに、朝の出社時の読書で「山手線をこのまま一周してこようかな」と思いました。これはスゴいノンフィクションです。
先日、自爆営業はパワハラだと厚生省が指針を出したというニュースが出ました。自腹でノルマを達成することを示す「自爆営業」。とはいえ、会社員たるものそういうノルマや過度にストレッチされた目標にさらされた経験がある人は少なくはないでしょう。
そのノルマを助けてくれる人が近くにいたら
崇高なまでのくだらなさに巨匠の仕事を見た『カーテンコール』
出版不況だ出版不況だと言っているうちに、本を出すこと、売ることが一世一代の大イベントみたいになってきてしまいました。
こうなると、書く方も売り出す方も無駄なまでに肩に力が入ってしまう。そんな書き手側の裏側の悲壮感が見えると、読む方も力が入ってしまう。。。
『カーテンコール』を読んでまず感じたのが、「あぁ、これよこれ、この力の抜け方よ」という脱力感でした。
なんて書いたら当事者に怒られそうだけど、
どろぼんが盗んだ一番大きなものは読者の心かも『どろぼうのどろぼん』
ブックセラーズ&カンパニーが「一読三嘆」という企画を始めたというニュースを読みました。
「みんなで1冊の本を売る。」それで多くの人に届ける。私も過去何度も取組んできたし、今も離れられないテーマです。言葉にするのは簡単なのだけれど「売る」以上に「みんなで売る本を1冊決める」というのがどれほど大変な事か。
本屋大賞だってその”1冊”の決め方を真剣に考え考え、考え抜いた結果できたようなもんです。
こ
『難問の多い料理店』は、まさに”真相をお話します”だった
『#真相をお話しします』を大ブレイクさせた著者の最新作。
あれだけ売れたあとだと、何かと大変だろうなあ…と売り手側としても、読み手としても勝手な心配をしてしまうのですが、新作はこちらに『#真相をお話しします』というタイトルがつけられていても納得してしまうような謎解きでした。
Uber Eatsを思わせる「ビーバーイーツ」の配達員たちと、都心部にあるゴーストレストランのシェフが連作を繋ぐ存在です
行間になにを見るか、作家の凄みがわかりました『ぼんぼん彩句』
よく「この句を読んで、著者の思いをこたえなさい」みたいな問題があるじゃないですか。
そうすると、目をつむったら浮かんでくる家族の情景とか、子どもの笑い声とか、その背景に美しい景色。みたいなものを想像しがちですよね。
”散ることは実るためなり桃の花”
という句を見て、私が想像した景色は、宮部さんにかかるととんでもないサスペンスになり、サイコパス家族みたいな人が出てきて怖ーい話になっていました。
舞台装置のすべてにドキドキできる『檜垣澤家の炎上』
エビデンスが難しそうなNo1が惹句だのオビだのに並んでいるので、大丈夫?不当表示って言われない?ってちょっと心配しながら手に取りました。
永嶋恵美ってことはミステリなんだろうし、ミステリと書いてはあるけれど、まず目に飛び込んでくるのはある富豪の一族の家に住むことになった妾の子の姿です。
これが主人公のかな子ちゃん。
富豪の妾の子なんていったら、悪役令嬢ものシリーズでもしょっちゅう出てきそうな設定だ
心のどこかに持ち合わせているかもしれない黒さを描いた『黒い絵』
今『異邦人』を読み直したら「太陽が眩しかったから」って言っちゃう気持ちとかが理解出来ちゃうかもしれない。って思えるくらいの暑さが続いていますね。
というこんな時期にはちょっと怖い本、ノワール小説が似合うということで、原田マハさんの『黒い絵』
原田さんの新境地ということで、すべての短編が何らかの犯罪や背徳行為にまつわるお話です。それについては皆さん賛否あるようですが、私はたまにはこういうのも良い
シリーズ化も楽しみな『惣十郎浮世始末』
信頼する読み手の何人もが発売前から絶賛していたので「これは読まねば」と決めていた本でした。
いわゆる捕物帖です。ですので、謎解きがメインのミステリなのですが、力が入っているのは家族や親子の業の部分だったり、お上からの締め付けに辟易しながらも楽しみを見いだしながら日々一生懸命生きる江戸の人たちを描く本であったり、その顔は色々。
肝心の謎自体は「もしかして、黒幕というか犯人はこの人なんだろうか」と途
世の中の争い事は全部”グリコ”で解決することにすればいいのに『地雷グリコ』
タイトル聞いたとき、地雷原みたいなところでグリコをやって人がどんどん死んでいくですゲームみたいな話?
って思ったんですよ。『バトルロワイヤル』みたいな。
そのイメージで、各賞を総ナメと言われながらも手を出さずにいたのですが、直木賞ノミネートと聞いて腰を上げました。
そして第1章の『地雷グリコ』を読んだ段階で「世の中の争い事、全部グリコで解決すればいいのに!考えた人天才じゃないのよ」という感想に大
読みはじめ30ページで涙腺崩壊『死んだ山田と教室』
読み始めて30ページのところですでに泣けました、といったら「なに言っちゃってるんですか」と言われると思います。
なんたって、30ページといったらあらすじに書いてある事しか起こってないんだもの。
「人気者だった山田が死んで、なのに声が教室のスピーカーから聞こえてきた」というそこまでに、山田がどういう人で、ここがそこそこの偏差値の男子校で、色々あるけど概して仲の良いクラスだった二年E組。
でももしか
サラリーマンが竜崎に憧れる理由について改めて考えてみた『一夜:隠蔽捜査10』
なぜ、人は竜崎に憧れるのか。
多分「正しい事を真っ直ぐ言えるから」なんじゃないかと思うのです。それくらい「正しい事」を言うのって難しいことなのですよ、きっと。
サラリーマンをやってると、多かれ少なかれ日々何かを飲み込んで生きてるわけで、空気を読まずにそれを口に出せる強さがあるかどうかの違いくらいしかないんじゃないですかね。
それくらい「わかっていても出来ないこと」は多く、それに気づかずに正義の