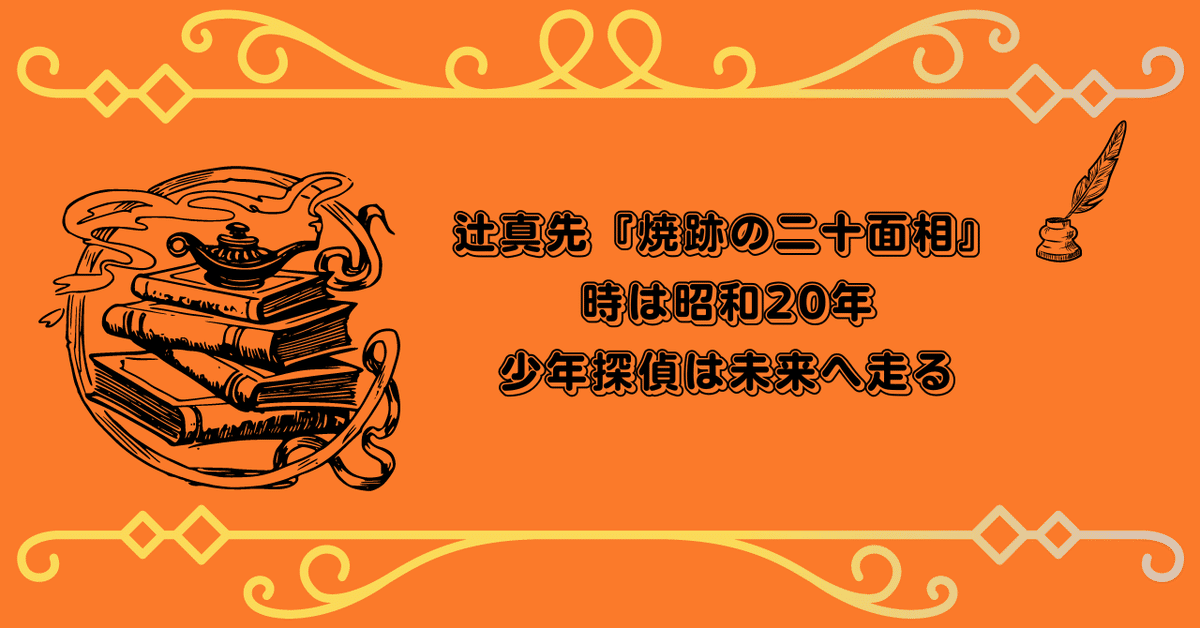
辻真先『焼跡の二十面相』 時は昭和20年 少年探偵は未来へ走る
いまや遠い昔になってしまった感もある昭和。その昭和育ちの多くの方が親しんだであろう怪人二十面相が帰ってきました。焼け野原になった東京に再び現れた二十面相に対し、応召されていまだ帰国しない明智小五郎に代わって挑むのは、小林少年――名手が送る痛快なパスティーシュであります。
昭和20年8月――敗戦の混乱冷めやらぬ中、それでも明日への希望を胸に、明智小五郎の留守を守って懸命に生きる小林少年。ある日、買い出しに出た彼は、警視庁の中村警部が輪タクを追う現場に出くわし、その後を追うことになります。中村警部が追っていたのは、輪タクに乗っていた隠匿物資のブローカー・伊崎。しかし追いついてみれば乗っていたのは替え玉――しかも彼以外いないはずの走る車中で、その替え玉は何者かに刺されて死んでいたのであります。
早速走る密室の謎を鮮やかに解いてみせた小林少年ですが、伊崎は行方をくらましたまま。そしてその後に友人を訪ねた田園調布で偶然輪タクの運転手を目撃した小林少年は、その場所が戦争中に巨万の富を築いた四谷重工業の社長宅であることを知ります。中村警部と一緒に調査に向かった小林少年ですが、そこで見つけたのは、なんと二十面相の予告状――四谷重工の社長が密かに隠匿しているという秘仏・乾陀羅の女帝像を狙った大胆不敵な犯行予告だったのです。
戦時中ヨーロッパに渡り、いまだ帰国の目処が立たない明智小五郎に代わり、小林少年は二十面相の犯行を阻むべく行動を開始するのですが……
名探偵・明智小五郎とそのライバル・怪人二十面相、そして明智探偵の助手・小林少年の名は、仮に彼らが登場する作品に直接触れたことがない方でもよくご存じでしょう。戦前の昭和11年に登場して以来、戦争を挟んで昭和の半ばに至るまで、数々の奇怪な事件を引き起こした二十面相と、彼に敢然と挑んだ明智探偵と小林少年、そして少年探偵団は、私も子供の時分に大いに心躍らせた懐かしい存在であります。
本作は、そうした名探偵vs怪人の世界を、終戦直後の東京を舞台に忠実に蘇らせてみせた物語。そのシチュエーションだけでも心躍りますが、それを描くのが、今なお『名探偵コナン』などで活躍する名脚本家にしてミステリ作家、そしてその時代を実際に生きてきた辻真先なのですから、面白くないはずがないではありませんか。
かくてここに展開するのは、初めて目にする、しかし懐かしさが漂う(全編ですます調で展開するのも嬉しい)物語。かつてあの名探偵が、そして怪人が大好きだった身にとっては、その時のときめきを――作中で二人の帰還を信じて待つ、小林少年と中村警部のような心境で――思い出しつつ、ただただ夢中にページを繰ることになりました。
とはいえ本作は、ノスタルジーのみに頼った作品では、もちろんありません。まず本作ならではの魅力の一つとして、本作の主人公として二十面相に、そして劇中で起きる怪事件に挑むのが、明智小五郎ではなく小林少年であるという点があります。
明智小五郎の助手として、そして少年探偵団のリーダーとして、常に大人顔負けの活躍を見せてきた小林少年。しかしそうではあっても、やはり少年――物語の中では、明智小五郎の庇護の下、師に一歩譲る役回りでありました。ところが本作においては、名探偵不在の中、怪人を向こうに回して一歩も引かない活躍を見せて小林少年が大活躍。これは、かつて自分たちの代表として小林少年に憧れた世代には、たまらないものがあります。
しかし、本作で小林少年が戦うのは二十面相だけではありません。その相手となるのは、二十面相などよりもある意味もっとたちの悪い、我欲に駆られた悪人たち――そのような美学も理想もない連中を前にしては、さすがの小林少年も、分が悪いように思われます。が、その小林少年の前に思いもよらぬ意外な同盟者が登場、痛快な共同戦線を張ることに――と、これ以上はここではナイショにしておきましょう。
そしてもう一つ、本作において決して忘れてはならないものがあります。それは、敗戦直後という舞台設定そのものであります。
輝かしい文化の数々――その一つにほかでもない、探偵小説があったわけですが――は愚かな戦争によって失われた末、誰もが明日の夢よりも今日の飯を追い求めることを余儀なくされた、敗戦直後の日本。本作はその姿を、リアルタイムでそれを目撃してきた者ならではの目で、克明に描き出します。(例えば、爆撃で真ん中が、そして焚き付けにされて根本が失われ、天辺だけがブラブラと残った電柱、などという奇怪な風景など、その最たるものでしょう)
そんな世界に蠢くのは、浪漫と稚気、そして美学に溢れる怪人とは全く異なる種類の人間たち――戦争を利用して私腹を肥やす大商人、敗戦したと見るや米軍にすり寄って儲けようと企むブローカー等々、厭な「大人」たちであります。敗戦直後という夢も希望も文化も誇りも失われた世界、怪人や探偵にとっては空白の時代には、あるいはそのような人間たちが相応しいのかもしれません。しかしそれでも本作が、そうした焼跡にあえて乱歩の世界を復活させてみせたのは――これは作者らしい強烈な異議申し立てだったのではないでしょうか。
作中で繰り返し繰り返し描かれる、当時のそして戦時中の世相、そしてそれを仕掛けた人々とそれに流された人々に対する皮肉。時に読んでいて些か鼻白むほど痛烈なその皮肉は、先に述べたように、リアルタイムでその世界を知る作者ならではのものというべきでしょう。しかし本作はそうした直接的な皮肉以上に、さらに強烈なカウンターパンチを、現実に喰らわせるのです。戦争というバカバカしい現実にも負けずに鮮やかに復活し、現実を翻弄してみせる怪人の存在によって。そしてそれに挑む、正義と理性の徒である探偵の存在によって。
そしてまた、こうした焼跡の物語だからこそ、現実の愚かな「大人」たちを相手にするからこそ、本作の探偵は、未来と希望の象徴である「少年」でなければなかったと感じます。目の前の現実に翻弄されて右往左往している大人たち、現実の中にどっぷりはまって小狡く立ち回っている大人たちを後目に、明日を夢見て奮闘する少年に……
さらに言えば、本作で描かれる痛烈な皮肉が、決して舞台となった時代に対してのみ向けられているわけではなく、今我々が生きるこの時にも向けられているであろうことを思うと、小林少年の活躍は、かつて少年だった我々に対するエールとも、発破ともいえるのではないかと感じるのです。
と、小難しいことをあれこれと申し上げましたが、やはり本作の基本は良くできたパスティーシュであり、痛快な探偵活劇であることは間違いありません。終盤の逆転また逆転のスリリングな騙し合いのたたみかけは見事というほかなく、何よりも思いもよらぬ(それでいて乱歩とは全く無関係というわけではない)ビッグなゲストまで登場するサービス精神にはただ脱帽であります。そしてここで語られるこのゲストの戦争中の行動については、なるほど! と納得するほかなく――そしてそこから生まれる「名探偵」同士の爽やかな交流に、胸を熱くせずにはいられないのです。
そして、ラストの小林少年の言葉に思わずニッコリとさせられる――怪人二十面相と少年探偵団の世界、探偵小説という世界への愛に満ちた本作。かつてその世界に胸躍らせた我々にその時の気持ちを甦らせると同時に、空白の時代に活躍する彼らの姿を描くことにより、我々の胸に新たな火を灯してくれる――そんな快作であります。
