
寒暖差疲労とは?-日常生活での影響と対策-
気温の変化が私たちに与える影響とは
すぐと日中の気温差が季節が大きくなると、なんとなく疲れやすかったり、気分が不安定になったりすることはありませんか?
特に7℃以上の気温差あると、私たちの身体はその変化に対応するためにフル稼働し、自律神経が乱れやすくなります。
寒暖差疲労は、肩こりや疲労感などの身体の症状だけでなくイライラ、感情や不安といったメンタルヘルスにも影響を考えることができます。にどう対処すればいいのか、詳しく見ていきましょう!
寒暖差疲労とは?日常生活での影響と対策
寒暖差疲労(Temperature Gap Fatigue)とは、気温の急激な変化によって自律神経が乱れ、身体や心に不調を感じる状態のことです。特に春や秋など、日中と朝晩の気温差が大きい季節に起こりやすい症状ですが、冷暖房が効いた室内と外の気温差が激しい夏や冬でも発生することがあります。
実は、7℃以上の気温差があると自律神経が疲労しやすいと言われています。この寒暖差が日常生活のさまざまな場面で起こり、知らないうちに体に負担をかけているのです。また、この寒暖差疲労は、身体だけでなくメンタルヘルスにも大きな影響を与えます。

寒暖差が日常生活で起こる場面
寒暖差疲労の原因となる気温差は、自然環境だけでなく、私たちの日常生活にも潜んでいます。以下は、よくある寒暖差の例です:
通勤中
冬の暖房が効いた電車から冷たい外気に触れる瞬間や、夏の冷房が効いたオフィスから暑い外に出る瞬間など。
外と室内の温度差が激しいため、自律神経が頻繁に切り替わります。
自宅内での温度差
冬場、暖かいリビングと寒い寝室や廊下との行き来で体がストレスを受けます。
お風呂上がりに温かい浴室から冷えた脱衣所に移動するのも典型的な例です。
買い物や外出
スーパーやショッピングモールなど、冷暖房が強い施設に出入りするたびに寒暖差が発生します。
寒暖差疲労の主な症状
寒暖差疲労の症状は人によって異なりますが、以下のようなものがあります
慢性的な疲労感
頭痛やめまい
手足の冷え
肩こりや筋肉のこわばり
イライラや不安感
これらの症状が続く場合、放置するとさらに体調を崩す可能性があるため、注意が必要です。自分の体調に表れる症状が何なのか、一度考えてみてください!
ちなみに、上記の動画のチェックリストのうち、3つ当てはまると要注意だそうですよ!
寒暖差疲労への具体的な対策
①衣類で温度調節をする
朝晩の気温差が大きい場合、カーディガンやストールを持ち歩き、体温調節を心がけましょう。
冬は冷暖房での急激な温度変化を防ぐため、マフラーや手袋を使いましょう。
②体を温める
日々の生活で湯船に浸かる習慣を取り入れることが効果的です。入浴中に副交感神経が優位になり、疲労回復が促進されます。
温かい飲み物やショウガを使った料理も体を内側から温める助けになります。
③適度な運動をする
軽いストレッチやウォーキングは、血流を促進し、自律神経のバランスを整えます。
特に朝の運動は、1日の体温調節能力を高める効果があります。
④十分な睡眠を取る
睡眠不足は自律神経の乱れを悪化させるため、毎日一定の睡眠時間を確保することが重要です。
⑤栄養バランスを整える
疲労回復を助けるビタミンB群やミネラル、抗酸化作用のあるビタミンCを積極的に摂取しましょう。
ビジネスパーソンへのアドバイス
特に忙しいビジネスパーソンは、気づかないうちに寒暖差疲労をため込むことがあります。オフィスでは空調による寒暖差が発生しやすいため、以下のポイントに注意しましょう!

デスクにカーディガンやひざ掛けを常備する
定期的に立ち上がり、軽いストレッチをする
会議の前後に温かい飲み物を飲んでリフレッシュする
寒暖差がメンタルヘルスに与える影響
寒暖差による自律神経の乱れは、以下のような形でメンタルヘルスにも影響します。
ストレスの増加
自律神経が頻繁に切り替わることで、体が常に緊張状態に陥り、ストレスホルモン(コルチゾール)が過剰に分泌されます。になります。
睡眠の質の低下
自律神経の乱れは、睡眠を司る副交感神経の働きを考えて、眠りが浅くなったり、不眠が原因になります。睡眠不足が続くと、精神的な疲労感が増し、気分の緊張につながるあります。
感情の起伏の激しさ
気温の変化に体が適応できないと、交感神経が優位な状態が続き、気分の浮き沈みが起こることがあります。 特に寒暖差が激しい季節には、細やかなことで気分が不安定になることもあります。
季節性前向き障害(SAD)の悪化
季節性優先障害は、特定の季節に起こるうつ症状のソフトで、日照時間の減少や気温の変化が引き金になることがあります。 寒暖差がこれに当てはまると、症状がさらに悪化する可能性があります。
日常生活で寒暖差と健康をケアする方法
寒暖差疲労がメンタルヘルスに与える影響を軽減するために、以下のような工夫が効果的です。
規則正しい生活リズムを整える
毎日同じ時間に起きて寝ることで、自律神経を安定させることができます。 特に睡眠をしっかり取ることは、メンタルヘルスの基盤を整えることが重要なポイントです。
リラクゼーションを取り入れる
湯船に浸かる、深呼吸をする、ヨガや瞑想をするなど、副交感神経を活性化させる習慣を取り入れましょう。これにより、ストレスホルモンの分泌を抑え、リラックスした状態を保てます。
適度な運動をする
ウォーキングや軽いストレッチなど、気軽にできる運動は血流を促進し、自律神経を整える効果があります。また、運動によるエンドルフィン分泌は気分を高めるのに役立ちます。
ビタミンDを意識して摂取する
日光浴やビタミンDを含む食品(魚、卵、きのこなど)を摂ることで、季節性優先障害の予防につながります。
寒暖差を大事にする工夫
室内外の温度差をできるだけ小さくするために、エアコンの設定温度を調整したり、衣類でこまめに体温を調節しましょう。
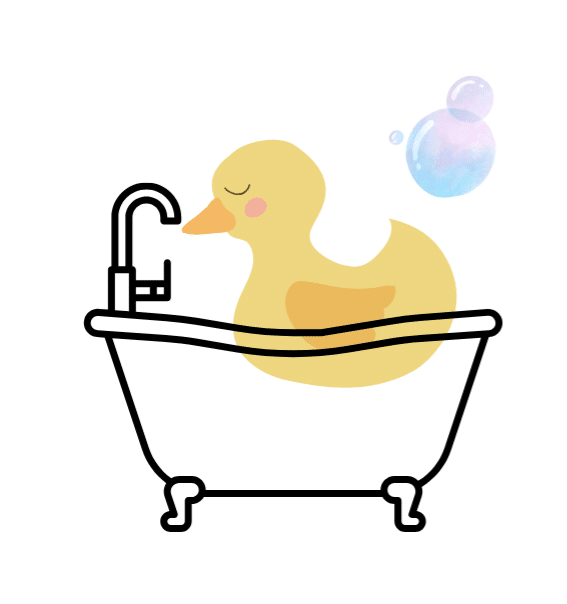
健康に影響を感じたときのサイン
寒暖差疲労がメンタルヘルスに影響を与えているサインとして、以下のような状態に気づくことが大切です:
イライラしやすい
変換ができない
慢性的に疲れていると感じる
食欲が減り、逆に過剰に食べてしまう
これらのサインを感じた場合、専門家のアドバイスを受けることも選択肢の一つです。
結論
寒暖差疲労は、身体の不調だけでなく、ストレスや不安感、さらには睡眠不足などメンタルヘルスにも影響を考慮する可能性があります。 気温差が激しい季節には、自分自身の体調と心のバランスに目を向け、生活習慣を工夫することで、寒暖差疲労を予防・軽減できます。
この記事が、日々の心身のケアの参考になれば幸いです!
