
劇伴音楽を巡るあれこれ
「音楽の現場」
スタジオ・ワーケーション──その実態を「裏の裏」まで知る人であればお判りではあろう。確かに「予算の範囲内」ともなれば、これは劇伴に拘らずあらゆる「音楽作品」へとつきまとう労苦的挿話ながら、表現を如何に凝らすかは造り手らの「時々」による都合と、それらが収斂による謂わば「結晶」であるは言うを俟たない。
例えば「大河ドラマ」より一つ挙げてみよう。
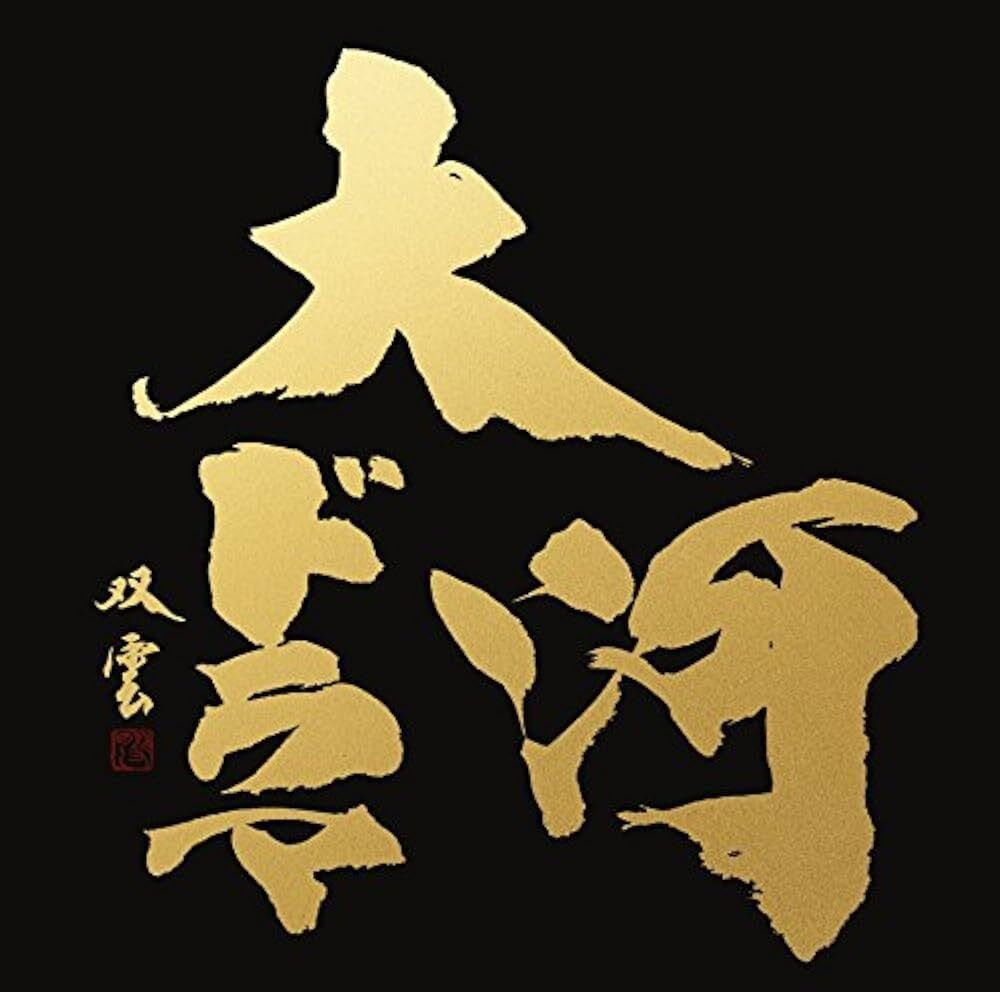
メイン・テーマは、もう長いことNHK交響楽団が、折節のシェフを迎えて録れている。当然、比較潤沢なる予算を誇る大河ドラマであれば、四管編成以上の大オーケストラに、特殊楽器や合唱、あるいはソロ・ピアノなどを採用するも容易い。
尤もそれも、まさに予算加えて「条件次第」ではある。
実際のところ、ドラマ本編では作曲者(大抵の場合は、ピアノを得手とする)がリードせる、より小規模なアンサンブルが場面へと応じて様々に表現をするのであるが、例えば80年大河「獅子の時代」では、音楽の表看板として宇崎竜童が起用をされるも、彼の場合、クラシカルなオーケストラル表現は聊か不得手なれば、サブ(とはいえ、寧ろアドヴァイザー的役割を担うに能う「上手」)が助言、否、寧ろアレンジャーとして効率的に音楽を総括監督している。
結果、この年の大河については従前的「管弦楽表現」及び「アンサンブル表現」の一端へと宇崎らが合流をし、メイン・テーマなどはある意味「エレキ・ギター協奏曲」的色合いを醸すものとなる。

一方で宇崎も、このワーケーションが結果として(オーケストラルなスタイル云々は措き)その「音楽表現──パレット」をより拡げるに到る機へと与る。メイン・テーマ自体も、宇崎渾身の「クラシカル・スタイル」になる楽曲であるが、この時代など、余程クラシカルな素養を有するミュージシャン(例えば細野晴臣とか坂本龍一)でなければ陥りやすい典型的「三部形式」となるはご愛嬌。それでも相対的には見事にも構築されているは、流石「宇崎」と言明してよかろう。
「音を巡り」知悉する職人であるか否か
そもより遥か前の、例えば放送なる「ワーケーション」にては、あらゆるジャンルに対応し得る「現場人」が求められていたのであるが、こうなると何より「潰しが利く」は、音大などにて専門的に修学をせる人々となる。勢い時代から推して猶、冨田勲をも含め「クラシカルな音楽を血肉とせるか否か」が鍵を握る。
実際のところ、80年以前において冨田は確か、複数の大河ドラマを担当しているやに記憶するが、この時代には明確ながら、冨田勲は「現代日本が誇るオーケストラル・アレンジメント」の第一人者であり、そんな彼ゆえ「可能性──その伸び代を求めて」シンセサイザー表現を切り拓くべく、と理解してよろしいのやもしれない(尚、冨田自身は慶應義塾出身であるが、周囲周辺にはジャンル問わず様々な楽人がいたためか、スロウスターターながら声楽表現〜管弦楽法までほぼ独学でマスターしている)。

冨田はレアケースであるにせよ、戦前以前の「契約的」空気が未だ拭えぬ時代にあって、入野義朗の弟子でもあった宮内國郎(ニッポン放送にほぼ専属するプロダクションつまり下請け企業に所属)や冬木透(東京放送社員)らが、何より放送あるいは時に映画などにおいて「潰しの利く」手練手管にて様々に劇伴を手掛けていたのである。
さりながら──。
では「劇伴」の「究極的それ」は如何であるかが枢要。
斯く意味にてストラヴィーンスキー「兵士の物語」こそ、今日的「劇伴音楽」の嚆矢でありまた究極である。

「楽器の数を」勘案する以前に求められるセンス
耳の良い人向けに──シャスタコーヴィチのアニメ劇伴音楽「僧侶とその下男バルダの物語」などは、例えばラジェストゥヴェースキーになる「編曲」とトーマス・ザンデルリンク(クルトの息子。ザンデルリンク兄弟の一人)になる「オリジナル・スコア」版を比較衡量しつ聴いてみるがよい。
況して「音楽を知る」人であれば──。
斯く意味からするなれば、やはりシャスタコーヴィチが映画音楽「アローン──女ひとり」を巡り、やはりラジェストゥヴェースキーになる「編曲版」と、リカルド・シャイーになるオリジナル・スコア版を如何に捉えるかであろう。

否、もっと謂えば──。
ストラヴィーンスキーがバレエ音楽「火の鳥」のオリジナルと1919年版をば聴き比べてみたまえ。
「譜面も読め」かつ思い入れもある人なれば、そうよさね⋯⋯「話はそこからだろう」と。
劇伴音楽に纏い着こうある種の「根源的セオリー」を理解しているか否かで、話題の「行く先き」も転変しようが、基本は「その音楽が如何なる条件なり契約の許に成立したか」をも問われる。斯く状況下に措いて如何に効果的な「表現」を生み出し得るか。
なれば「兵士の物語」は「究極的」表現ではあろう。
