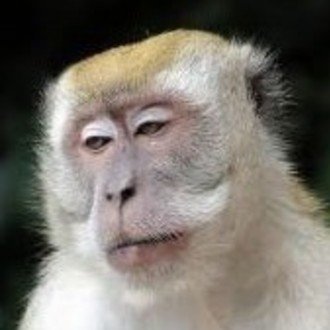ピエモンテ・ワイナリー紀行#5/霧の葡萄
前職のとき、とてもお世話になった先輩がイタリアワイン党だった。僕はその頃から原則フレンチしか飲まなかったからね。彼には酒の席で、よく弄くられた。その彼が言った言葉を、今回の旅行で唐突に思い出した。
「ネッビオーロはな。語源はラテン語のネブラnebulaなんだ。霧のことだ。ネッビオーロは霧の中に佇む葡萄の木だから、ネッビオーロと呼ばれるようになったんだ」
霧の中に佇む木? その時は、全く意味が分からなかった。しかし今回のピエモンテ・ワイン紀行で、立ち昇る朝靄の中に佇むネッビオーロに出会って、僕にもようやくその意味が分かった。...
「Nebbia di mattina è sospiro di Bacco。だから他の葡萄とは違うんだ。特別な葡萄なんだ。だからネッビオーロという名前が付けられているんだ。」
先輩は酩酊すると、よくその話をした。
なるほど。神の吐息に育まれた葡萄ねぇ。神に愛でられし"特別な葡萄"ねぇ。
・・それはこの地に立って、朝靄の白濁したスープの中に沈むネッビオーロの木々に出会わなければ、生まれてこない感動だね。
ガリアの地の人々は、ピノノワールを。シャルドネを。キリストが最後の晩餐の日に飲んだワインであるという。
ならば僕の先輩が、ネッビオーロはワインの神・バッカスが最も愛している葡萄だと云っても、これは"なるほど"というしかない・・と思う。
しかし、今回は彼のこの説に、ちょいとチャチャを入れたい。
朝靄に沈むネッビオーロを見つめながら、これを愛でたのは、バッカスでない「他の神」ではないか?と思ったからだ。
そんな話をしたい。
いうまでもないことだが。。バッカスBacchusはローマ神話の中に登場する豊穣の神。ワインの神である。英語読みをすると"バッカス"だが、ラテン語読みだとバックス。もともとBakkhosは、ギリシャ神話の中に出てくるディオニュソスの別名で、これをラテン語読みにしたものがバックスBacchusである。
ディオニュソスは、ミケーネ文明時代にはディウォヌソヨ(Διϝνυσοιο)として登場してくる旧神である。陸神ゼウス・海神ポセイドンと共に、肉体に閉じ込められた神ディウォヌソヨとして崇められていた。
ディウォヌソヨは、肉の身体を持つ故に輪廻転生をする。生まれ、死に、生まれ、死に、を繰り返する。それが一年単位で、植え付けと刈り込みを繰り返す農業を連想させて、豊穣の神になっていった理由であろう。
ミケーネ文明は、きわめて早い時期からイタリア半島に届いている。もしかするとディウォヌソヨは、ローマ人たちがギリシャの神々を呼び込むより、遥かに早く同地へ届いていた渡来神かもしれない。そんな想像をしてしまう。
つまりなにが言いたいかと言うと。。
バッカス←ディオニュソス←ディウォヌソヨは、イタリア半島南方に渡来した神である。
この神に因んで、ネッビオーロ種に「霧の葡萄」という名前を付けるなら・・古代ギリシャ語の"霧"オミクレーomikhleを使用するはずである。Nebbioloにはならない。
・・・ははは(^^♪つまらないイチャモンだ。
ラテン語のネブラnebulaを語源にネッビオーロという名前が付いて、尚且つピエモンテの原種だと信じられてしまうほど昔から有った葡萄なら・・これはやはり最初に名付けたのは、ラテン人/ロンバルディア人だと僕は思ってしまうのです。
ならば。。
あのピエモンテ盆地を遍く覆う朝靄を、神の吐息と云うなら・・その神もまた北東から渡来した神のはずである。
ならば、その神はリーベル(liber)のはずだ。
リーベルはローマの旧神で豊穣の神・ワインの神である。古ラテン人の言葉を色濃く残す北方のロマン諸語の中には、長母音を使用せずにリベルという地方もある。いずれにせよ北方からインド・ヨーロッパ語族と共にイタリア半島を南下してきた旧神である。リーベルこそ、ネッビオーロを抱くのに相応しい神だと僕は考えてしまうのです。
ああ。でも先輩なら、こう言い返すでしょうな。
「ん。たしかにそうかもしれない。しかしリーベルは、ラテン人がローマ人となったときに、バッカスへ吸収合併されてしまった神だ。云ってみれば第一勧業、富士、日本興業の3銀行のシステムを、みずほ銀行としてシステム統合したのときの富士銀行のシステムの扱われ方と同じようなもんだ。雲散したんだ。」
そう言われると「でも・・だからシステム障害を起こした・・ですよね」と、僕は思わず言ってしまいそうだ。
そしたらきっと先輩は「ははは。そうだったな。」そんな風に笑うだろう。苦々しくね。
いいなと思ったら応援しよう!