
【書評】ロマン主義の音楽であるために、美学的に何が必要か
M.カッロッツォ、C.チマガッリ『西洋音楽の歴史 第3巻』(シーライトパブリッシング、2013)

ロマン派と現代音楽を扱う第3巻。前者に7章、後者に6章。章の前半は歴史、後半は考察。なお、本シリーズ第1巻の書評もあります。
「第7部 ロマン主義の美学的な必要条件」
本の前半は「第7部 ロマン主義の美学的な必要条件」。ロマン主義の音楽であるために、美学的に何が必要か。この問いの立て方がスリリング。
第32章「ジョアッキーノ・ロッシーニ」
第32章「ジョアッキーノ・ロッシーニ」はオペラ史におけるヴェルディの反措定と考えるとわかりやすい(ただし、ロッシーニのリズム重視は考慮に入れる必要があるし、またスタンダールがロッシーニを「ナポレオン」と呼んだほどの当時のヨーロッパ音楽界の支配者だったことも忘れてはいけないし、さらに音楽の流れを変えずに劇のテンポを変える天才的な技も持っている)。シェークスピア原作の「オテッロー」が、ロッシーニにおいてはおよそ悲劇と思えぬ作曲がなされているのに対し、ヴェルディは人間性の悲劇としてきちんと音楽劇化されている。背景にはヴェルディの文学とりわけシェークスピアに対する深い関心がある。そのことは第36章「19世紀のイタリアオペラ」で「台詞に重点を置いた演劇に極めて近づいた」とかすかな言及がある。奇しくも2013年はヴェルディ生誕200年だった。
第33章「ロマン派初期の世代:ヴェーバーとシューベルト」
第33章「ロマン派初期の世代:ヴェーバーとシューベルト」の考察部分でリートの基本構造は有節だと指摘される。有節は英語だとふつうは strophic という。すべての詩のスタンザが同じ旋律で歌われるもの。その反対の方法は通作(英語で through-composed)。シューベルトはどちらでも作曲している。なお、アイルランドのシャン・ノース歌唱をこれになぞらえて表現すると、基本的には有節だが、詩に応じて旋律や装飾音が変化するという意味では通作的要素も併せ持つ。本書の言い方なら、「ヴァリエーションを伴う有節リート」に似ている。その種のものともいえる「菩提樹」(Der Lindenbaum)の分析は興味深いが、トーマス・マンが「プロでない愛好家たちはこのリートを〔中略〕全体として有節形式で歌っていた」と『魔の山』(Der Zauberberg)の中で指摘していることはさらに興味深い。
第34章「ロマン派の3人の作曲家:メンデルスゾーン、シューマン、ショパン」
第34章「ロマン派の3人の作曲家:メンデルスゾーン、シューマン、ショパン」は1810年に生まれたシューマンとショパン、およびその前年に生まれたメンデルスゾーンとを扱う。なお、この年の前後にはほぼすべての有名なロマン派の音楽家が生まれている。1811年にリスト、1813年にヴェルディとヴァーグナー。
あまりにも恵まれた環境の中で軽やかに人生を送ったメンデルスゾーンに比べて、シューマンは自己分裂(Zerrissenheit 〔ツェリセンハイト、ツェリセンは「引き裂かれた」の意〕)の危機に直面した。興奮と憂鬱の二面性。これはある意味でロマン派の典型といえる。シューマンの場合は、さらに深い二面性に魂を支配された。社会での経済的成功を望むブルジョワ的「平凡な」志向と、全身全霊を芸術に捧げる「詩的な」願望との二つだ。これにとどまらず、音楽家として歩みだしてからも、シューマンは、ピアノと作曲というさらなる両極に引き裂かれる。こうした二面性は当然、彼の音楽に反映された。
ショパンについては、一般に知られる「鍵盤の詩人」の面とは別の、ある種の異国からやって来た「野蛮さ」の指摘が興味深い。そのあたりに関して「サルマーシアの野蛮人」(105頁)の記述があるのだが、これはどこのことだろう。ことによると、黒海北方のサルマティア(Sarmatia)のことか。この地域のことなら、知る限り、サルマーシアとはふつう表記されない。翻訳をする人がときに無用な英語音を使うことがある(「カソリック」など)が、歴史的には大いなる問題を引起すことがあるので注意が必要だ。ともあれ、ここをきちんと訳しておかないと、次段落の冒頭、「実際、フレデリック・ショパンは推定1810年の3月1日にポーランドに生まれた」の記述の意味がわからない。なにが「実際」なのか。ポーランドとサルマティアとの関わりは、その地域に関心のある人しか知らないことなので、いずれにせよ注(か解説的訳文)がほしい。
第35章「ベルリオーズとリスト:絶対音楽?」
第35章「ベルリオーズとリスト:絶対音楽?」はやや失望させられる。ベルリオーズを「フランスのロマン主義における最高の作曲家」と始めに規定した時点であまり論じる気がないという予感がする。読んでみるとその通りだ。これに対し、ベルリオーズの影響下にあるとは明記しながらも、リストのほうは3全音の音程の実験的使用のことを含め、短いながらも鋭い洞察をくわえている。リストの絶対音楽の例としては「ピアノソナタ《ロ短調》」をあげている。
第36章「19世紀のイタリアオペラ」
第36章「19世紀のイタリアオペラ」は、さすがイタリアのテクストだけあって、ここぞとばかりに詳しく記述される。ヴェルディの『リゴレット』の分析は圧巻。
第37章「リヒャルト・ヴァーグナーと楽劇」
第37章「リヒャルト・ヴァーグナーと楽劇」はイタリアオペラほどではないにせよ、しっかり記述されている。ヴァーグナーのポジションを「過激派」と定義するのはおもしろい。彼の作品について「オペラ」でなく「楽劇」が用いられることを彼自身は認めていなかった。むしろ、彼が考えたのは「未来の音楽」(Zukunftmusik)だった。この「ツークンフトムジーク」は、今日ドイツ語としてはヴァーグナーの芸術を揶揄して用いられるのは残念なことだ。考察の部分でヴァーグナーの『ラインの黄金』がたっぷり分析されている。ただ、気の毒なことに、巻末の索引ではヴァーグナーの名は「ワ」に配列されている。ヴェルディが「ウ」にあるというのに。
第38章「19世紀後半の交響楽:ブラームスからマーラーへ」
第38章「19世紀後半の交響楽:ブラームスからマーラーへ」になると、特にマーラーにおいて、「19世紀の翳り」あるいは「深い危機の萌芽」が見えてくる。だが、このあたりの記述はさらっとしたものだ。
「第8部 新しい音楽の道」
本の後半は「第8部 新しい音楽の道」。調性が消えて、音楽はどこへ向かうのか。道は一つではない。無調音楽を作曲したシェーンベルクを現代音楽の始まりとする従来の考え方に対し、時間芸術としての音楽の概念を否定するという画期的な考え方が注目されるようになる。「時間を超越した」音楽の概念だ。その結果、単独の音に特別な注目がされるようになる。つまり、前後の音との関わりから解放された音だ。さらに、音をオブジェとみなすことも行われるようになる。それは音楽から人間性を失わせることにもつながるけれども。
第39章「19世紀の音楽における愛国主義と写実主義」
第39章「19世紀の音楽における愛国主義と写実主義」は地理的範囲をひろげて論じる。ロシアや東ヨーロッパや北ヨーロッパが視野にはいってくる。リムスキー=コルサコフやヤナーチェクやシベリウスなど。悲しいことにアイルランドであげられるのは、チャールズ・ヴィリアズ・スタンフォードのみだ。
第40章「19~20世紀のフランスとイタリア」
第40章「19~20世紀のフランスとイタリア」ではドビュッシーの語法の現代性として、時間の流れを止めるような、単独の音に注目するような手法のことが語られる。考察のところではドビュッシーの有名なプレリュード『沈める寺』('La Cathédrale engloutie')がとりあげられる。もちろん、これはブルターニュの伝説の都市イス(Paris は「イスに匹敵する〔Par Is〕」が原義)に関わる曲だ。音の空間を瞬間ごとに埋める方法などが指摘される。「音が響き渡る聖堂」がいかに「浮上」し「再沈没」するか、音楽的にそれをどう表すか。非常にスリリングな分析が展開される。
第41章「ウィーン楽派」
第41章「ウィーン楽派」は3人のウィーン人、シェーンベルク、ベルク、ヴェーバルンの無調への道のりが語られる。ドビュッシーの革新性を見た後では、やや色褪せて見えるのは仕方ない。
第42章「ストラヴィンスキーと新古典主義」
第42章「ストラヴィンスキーと新古典主義」はたいへん刺激的な章だ。新即物主義(Neue Sachlichkeit)に始まり、コクトーの刻印を受けたサティの家具の音楽、ブレヒトの異化効果などをへて、「20世紀の音楽の真の柱」とされるストラヴィンスキーに至る。また、民族音楽の観点からは見逃すことができないバルトークについても語られる。考察のところでは、ストラヴィンスキーの『春の祭典』がそのリズム構造を含め、くわしく分析される。
第43章「ダルムシュタットと前衛派」
第43章「ダルムシュタットと前衛派」ではフランス人メシアンがドイツのダルムシュタットで書いた楽曲『音価と強度のモード』のこと、およびそれが投げた種がブーレーズらの総音列技法(音列の基準を音高だけでなく音長などにも適応させる)という芽を出す流れのことが語られる。さらに、ケージの偶然性の音楽にも触れられる。
第44章「電子音楽とその他」
最後の章、第44章「電子音楽とその他」ではついにチャールズ・アイヴズがごく短く登場する。
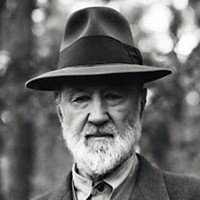
Charles Ives - The Unanswered Question
電子音楽では前の章で既に出てきていたシュトックハウゼンらのことが語られる。前の章で触れられたシュトックハウゼンの「群のテクニック」については、この章の考察部分で具体的に分析される。ここで「群」とはシュトックハウゼンによれば、「際立った特定の音の数」のことだ。この「数」のことといい、現代音楽に復活した微分音のことといい、古代ギリシアの音楽が蘇るかのごとき動きを瞥見しながら、本書は閉じられる。
