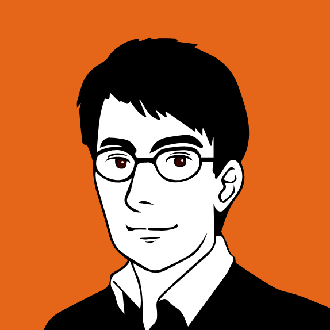すべてオンライン。
2015年から2017年の2年間ほど、ECシステムを提供している部門に所属して、ECカートシステムのプロダクトマネージャーや、UXリサーチ&コンサル事業の「おかいもの研究室」などを立ち上げたりしていました。
当時も今もEC界隈ではO2Oやオムニチャネルというワードは頻繁にでてくる言葉です。
O2O(オンライン・ツー・オフライン)
Online to Offline,とは、インターネットなどのオンラインから店舗などのオフラインへ消費者を呼び込む施策。
オムニチャネル
ネットだけでなく店舗などリアルの場を含めたあらゆるチャネルを連携させてお客さまとの接点を持って売上をアップさせる施策。
そんな中、2019年3月に以下の本が発売されました。
アフターデジタル オフラインのない時代に生き残る
≪目次≫
第1章知らずには生き残れない、デジタル化する世界の本質
第2章アフターデジタル時代のOMO型ビジネス~必要な視点転換~
第3章アフターデジタル事例による思考訓練
第4章アフターデジタルを見据えた日本式ビジネス変革
これ面白い!今年TOP3に入るおすすめ本です。
特に心惹かれたのがOMO(OnlineMergeOffline)、そしてリアルとデジタルを分ける時代の終焉の概念
オンラインとオフラインの境界線がなくなってきています。むしろオンラインがビジネスの基盤となり、拡張するオンラインプラットフォームがあらゆるリアルなビジネスを飲み込み、統合していく。これが元グーグル・チャイナの代表で、投資会社シノベーション・ベンチャーズを設立した李開復が2017年に提唱したOMOの世界です。
問いたい、語りたい。
第2章アフターデジタル時代のOMO型ビジネス~必要な視点転換~
この章の中から気になる部分
BtoC向けECサイトとそのロジスティクスを運営する「ジンドン」(京東、JD.com)の無人サービスの開発部署に質問した内容
問い
「オンライン企業である御社が、なぜオフラインの無人コンビニを展開する必要があるのでしょうか。O2O戦略があれば教えてください」
なあ
すると、次のような答えが返ってきました。
「もう020の時代ではありません。店舗というリアルチャネルであっても、ユーザーの行動のすべてをデータとして取得できる時代です。我々にとってはモバイルもPCもコンビニも、ただのユーザーインターフェースでしかありません。例えば、顧客がスマホで水を1本購入することも、無人コンビニで顧客が水を1本購入することも、誰がいつどこでどの柄を購入したのかがすべてデータとして分かるのであれば同じことですよね。顧客は水が欲しいと思った時、もしたまたま近くコンビニがあればそこで買うでしょう。わざわざスマホで購入して家に届けてもらうなんてことはしないはずです。顧客は『オンラインとかオフラインとか』といちいち考えておらず、その時最も便利な方法で買いたいだけなので、我々は様々な選択肢を提供することが大事だと思っています。そのために無人コンビニも展開しているのです」
さて、日本では、OMO(OnlineMergeOffline)を取り込めるのでしょうか?
個人的に私はオンラインゲーム業界で戦略・企画を担当してきたので、その経験を活かせると考えています。そしてOMOの世界を浸透させ、色々な人を巻き込んで何かしら形にしてきたいと考えている。
プロジェクトデザイナーとして。
---
Photo by Victoria Heath on Unsplash
:::::::
noteは年300記事程度の更新頻度。
「プランナー&デザイナーの思考、考え方」「リーダー育成」「新規事業開発」「プロジェクトマネジメント」「プロジェクトファシリテーション」を中心に書いていきます。興味のある方、是非フォローして最新記事を受け取って頂ければ幸いです。
運営サイト:良い問いを創る。yoitoi.com
いいなと思ったら応援しよう!