
#8 太宰治全部読む |未完のグッド・バイ
私は、太宰治の作品を全部読むことにした。
太宰治を全部読むと、人はどのような感情を抱くのか。身をもって確かめることにした。
前回読んだ『お伽草紙』では、既存の昔話や伝承を下敷きに、太宰のユーモアと想像力が絶妙にブレンドされた短編小説を堪能した。
第8回目の今回は、『グッド・バイ』という短編集を取り上げる。表題作の「グッド・バイ」は、未完の絶筆作品である。
太宰治|グッド・バイ
1948年6月13日、愛人の山崎富栄とともに、玉川上水に身を投げ、太宰は亡くなった。彼が自殺によってその生涯を閉じたことは、多くの人が知っているだろう。
しかしながら、彼が死の間際まで執筆し続け、自殺によって未完となった作品があることをご存じだろうか。それが今回取り上げる、「グッド・バイ」という作品である。
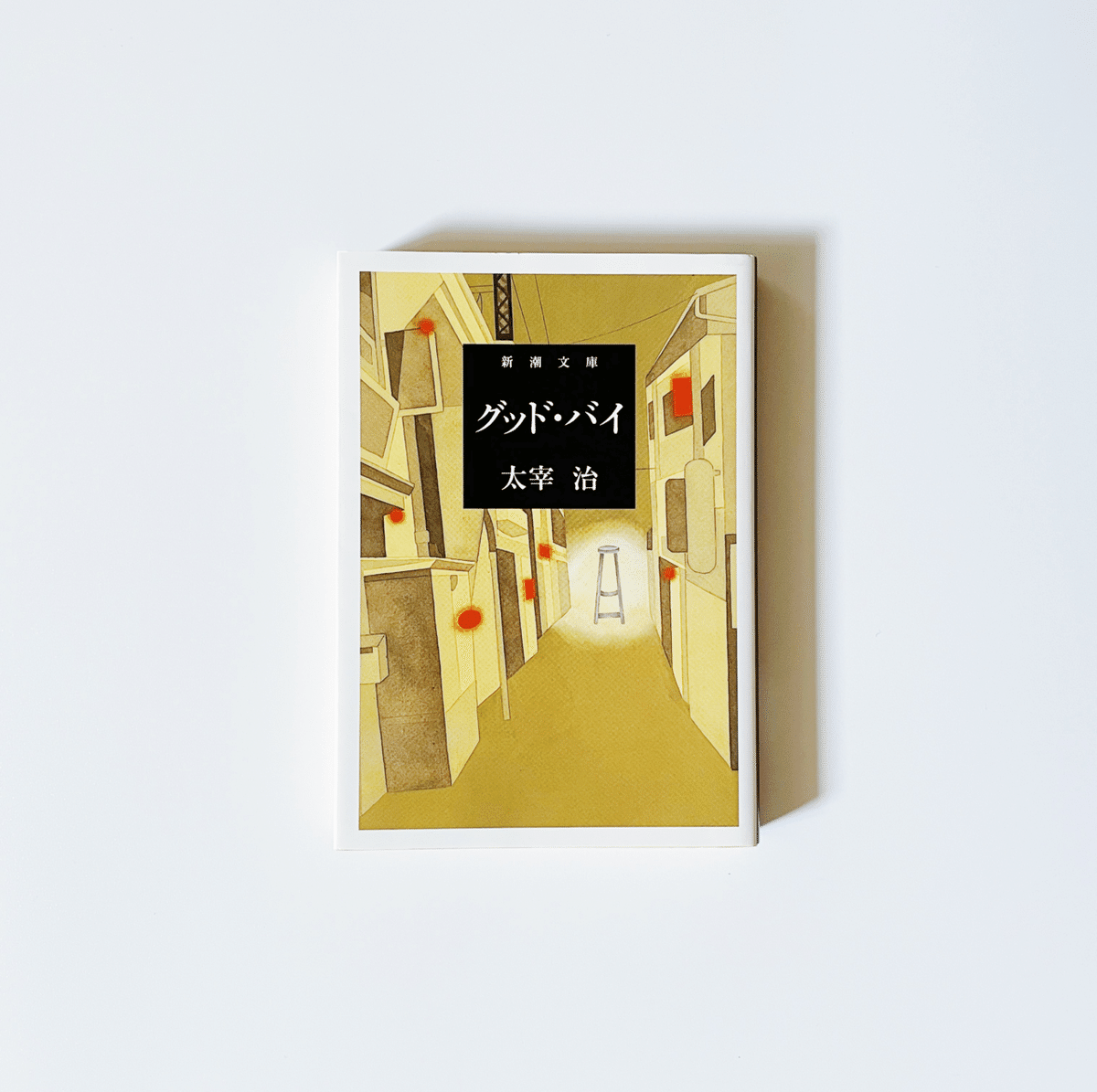
被災・疎開の極限状況から敗戦という未曾有の経験の中で、我が身を燃焼させつつ書きのこした後期作品16編。『人間失格』後の新境地を垣間見させる未完の絶筆『グッド・バイ』をはじめ、時代の転換に触発された痛切なる告白『苦悩の年鑑』『十五年間』、戦前戦中と毫も変わらない戦後の現実、どうにもならぬ日本人への絶望を吐露した2戯曲『冬の花火』『春の枯葉』ほか『饗応夫人』『眉山』など。
あらすじにもある通り、本書に収められている短編は、いずれも太宰の作家人生の後期に書かれたものである。第二次世界大戦の終結後、彼が入水自殺を遂げるまでの、3年間のうちに発表されたものだ。
以前読んだ『ヴィヨンの妻』の短編と、執筆時期が重複している。『ヴィヨンの妻』に収録された作品といえば、晩年の太宰の浮世に対する絶望が色濃く反映された、暗くて陰鬱なものが多かった。
果たして、『グッド・バイ』の収録作品はどうだろうか——。
今回は短編の数が非常に多く、いつもと同じ分量で感想を書くと長くなってしまうため、簡潔に書くに留めた。
薄明
空襲で家を焼かれた太宰が、眼の病に罹った娘のために奔走する小説。父親らしい太宰の一面が垣間見える、貴重な作品。
苦悩の年鑑
生まれから戦後までの太宰の思想変遷が、断片的に語られている。特定の思想を持たないが故の苦悩が、人生を通じてあったのだろう。
日本は無条件降伏をした。私はただ、恥ずかしかった。ものも言えないくらいに恥ずかしかった。
十五年間
『走れメロス』収録の「東京八景」という短編に続き、太宰の東京での執筆活動を回想する小説。
「上品で美しい」芸術家を嫌悪し、真の芸術家は醜いものだと断言する。そして、他ならぬ太宰自身こそが、糾弾すべき気取った芸術家であると自己否定する。
たずねびと
空襲の中、故郷津軽へ一家で疎開する道中で、食糧に窮した太宰に食べ物を恵んでくれた女性に向け書かれた小説。実際にこの短編は、女性に届いたのだろうか。その先にある物語に思いを馳せる。
男女同権
女性に理不尽な仕打ちを受け続けてきた男性の経験談。背筋が凍るような恐ろしい話だが、実はその男性が、被害者として都合よく解釈しているだけなのでは……という気もしてくる小説。
冬の花火
続く「春の枯葉」と並ぶ、太宰戦後の戯曲作品のひとつ。
敗戦後の日本の虚しさが、まざまざと描かれている。戦中の日本の狂乱的とも言えるような虚構を、「冬に上がる花火」に例えている。
春の枯葉
戦後の田舎で生きる人々の、どうしようもない鬱屈や不条理を描いた戯曲。
太宰の戯曲はかなしいけれど、どこか品の良さも感じられるから不思議である。
メリイクリスマス
疎開先の津軽から東京に戻り、最初に書いた短編。「太宰流・恋愛の極意」といった作品。最後の飲み屋のシーンが良い。
フォスフォレッセンス
現実世界よりも夢世界の方が真実であり、両方の世界は地続きであるという、夢に対する太宰独自の感覚が語られている。夢と現実を行き来するような、不思議な読み心地の短編。
朝
当時の太宰の暮らしぶりが伺える小説。今でいう、「ルーティーン紹介」といった作品だろうか。作家さんの「仕事部屋に通う生活」に憧れてしまう。
饗応夫人
戦争によって夫を亡くした女性の、悲しい物語。厚かましく家を訪ねてくる夫の友人とその仲間たちを、自身の身を削りながらも、手厚く歓迎・接待する。その異常なほどの饗応ぶりに、悲しみが誘われる。
美男子と煙草
ああ、生きて行くという事は、いやな事だ。殊にも、男は、つらくて、哀しいものだ。とにかく、何でもたたかって、そうして、勝たなければならぬのですから。
太宰が取材で上野の浮浪者たちと会見する小説。太宰自身も、いつ浮浪者になってもおかしくないという複雑な心情が語られている。
眉山
そそっかしい飲み屋の娘の笑い話……かと思いきや、最後に切ないオチがつく短編。再読すると印象が全く変わる、余韻を残すような作品だ。
女類
泥酔状態で、人類を「男類」と「女類」に分け、両者は分かり合えない存在と説く男。「女は金が好き」といった偏見を披露し、主人公を閉口させ、挙句周囲から非難を浴びる。
渡り鳥
軽薄な青年の語りを通じて、戦後日本の「模倣・ニセもの文化」を、見事に批判、諷刺している作品。
グッド・バイ
連載中に太宰が自殺を遂げたため、未完となった作品。
10人近い愛人を作っているダメ男・田島が、怪力で狡猾な美女・キヌ子と手を組み、愛人たちに別れを告げるため奔走する小説だ。
『人間失格』や晩年の短編にあるような鬱々とした感じはなく、滑稽さやユーモアに満ちている。太宰文学の新境地を感じさせるような作品だ。彼が自殺してしまったことが残念である。
未完の作品ということで、物語はこれから本格的に愛人に別れを告げていこうというところで、プツリと終わっている。
愛人たちに次々と別れを突きつけ、最後には自身が妻から別れを告げられるというオチが練られていたらしいが、本作が完結することはなく、正解を確かめることはできない。
太宰ファンは、本作がどのような展開を辿り、どのように終結する予定だったのか、それぞれに想像を膨らませて楽しむ。各々の太宰像が、異なる物語を創り出す。
伊坂幸太郎さんの『バイバイ、ブラックバード』という小説がある。
本作は、太宰の「グッド・バイ」の筋書きをもとに、伊坂さんが想像を膨らませて書いた小説である。余韻の残るラストが最高だ。
「グッド・バイ」と合わせて、ぜひこちらもお読みいただきたい。
第二次世界大戦中、太宰は空襲によって家を焼かれ、故郷の津軽へと疎開するという経験をした。
同じような境遇の人波に揉まれながら、永遠に続くかと思える長い列車の道中を、飢えをしのいで耐え忍ぶ。
戦争という非常事態に直面し、そして戦後も退廃的な生活を送る自分に失望して、死へと塞ぎ込んでいく太宰。
それでも、彼が小説を書き続けたことに感動するのは、私だけだろうか。
私は小説を書く事は、やめなかった。もうこうなったら、最後までねばって小説を書いて行かなければ、ウソだと思った。それはもう理屈ではなかった。
理屈を超え、魂を削るように書かれた小説。太宰の心境を想像すると、『グッド・バイ』や『ヴィヨンの妻』に収録された戦後の作品が、ギリギリの綱渡りで書かれた、貴重なものに思えてくる。
そして、未完の作品「グッド・バイ」。
「未完」と聞くと最後まで読めないことが残念に思えるが、むしろ未完でも貴重な作品を残してくれたことに、感謝しなければならない。
太宰が「グッド・バイ」を残したことで、伊坂さんの『バイバイ、ブラックバード』のように、後世で素晴らしい小説が生まれている。
不完全でも、太宰が残してくれたバトンを、今も誰かが受け取っては、先へと運んでいる。このバトンリレーは、この先もずっと続いていくだろう。
↓「全部読む」シリーズの続きはこちらから!
↓本に関するおすすめ記事をまとめています。
↓読書会のPodcast「本の海を泳ぐ」を配信しています。
↓マシュマロでご意見、ご質問を募集しています。
