
#16 太宰治全部読む |『晩年』から『走れメロス』へ、試行錯誤の過渡期
私は、太宰治の作品を全部読むことにした。
太宰治を全部読むと、人はどのような感情を抱くのか。身をもって確かめることにした。
前回の『津軽通信』では、太宰の短編の中でも戦争期に執筆された、”シリーズもの”作品たちを読んだ。「未帰還の友に」など、優れた短編も多く発見した。
16回目の今回は、『新樹の言葉』を読む。
「太宰治全部読む」も、ようやく終わりが見えてきた。果たして今回は、どのような作品なのだろうか。
太宰治|新樹の言葉
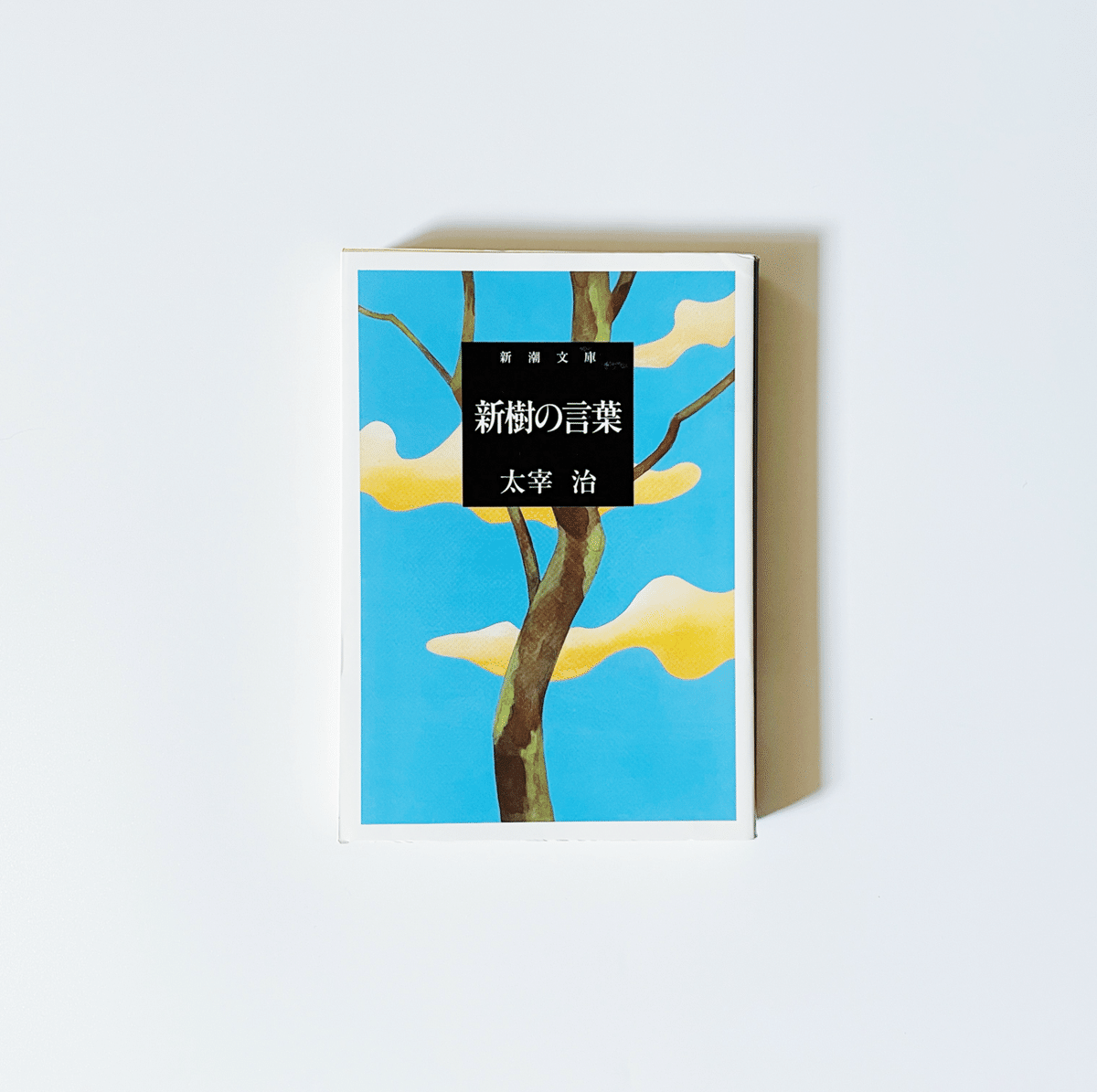
麻薬中毒と自殺未遂の地獄の日々から立ち直ろうと懸命の努力を重ねていた時期の作品集。乳母の子供たちとの異郷での再会という、心温まる空想譚のなかに再生への祈りをこめた『新樹の言葉』。”男爵”と呼ばれる無垢な男と、昔その家の女中で今は大女優となっている女性との恋愛譚『花燭』。ほかに『懶惰の歌留多』『葉桜と魔笛』『火の鳥』『八十八夜』『老ハイデルベルヒ』など全15編。
本作『新樹の言葉』は、太宰の作家人生では中期にあたる、1939〜1940年に執筆された短編15編を収録している。
前期の反逆的・前衛的な作風から脱却し、『走れメロス』のような比較的安定した自由な作風に至るまでの、試行錯誤の時期にフォーカスをあてた短編集だ。
試行錯誤の過渡期にフォーカス
太宰の小説は、冒頭部分に太宰自身の言葉で、その作品に関する解説や創作過程、時に言い訳めいた述懐などが書かれていることがある。
本作『新樹の言葉』に収められた短編は、それが顕著である。太宰の創作に対する試行錯誤が、作品によく表れていると感じた。
これまで初期・中期・後期と、あらゆる時代の代表的な作品を読んできた。
今回の『新樹の言葉』のように、各時代の空白期間を埋めてくれる、過渡期の作品を読むことができるのはとても楽しい。
今回も、特に印象的だった短編をいくつかご紹介する。
懶惰の歌留多
「懶惰の歌留多」は、「いろはにほへと」の頭文字で始まる題の掌編を並べた、カルタ仕立ての短編である。
新潮文庫版の解説には、『晩年』執筆時にボツとした掌編を救い出し、編集したものと書かれている。
太宰が自身の怠惰を嘆き、執筆が捗らない言い訳をくどくどと並べながら、その中に優れた掌編が差し込まれている構成が面白い。
苦しさだの、高邁だの、純潔だの、素直だの、もうそんなこと聞きたくない。書け。落語でも、一口噺でもいい。書かないのは、例外なく怠惰である。おろかな、おろかな、盲信である。人は、自分以上の仕事もできないし、自分以下の仕事もできない。働かないものには、権利がない。人間失格、あたりまえのことである。
この頃から、自身に対する「人間失格」の感覚が存在していたことが、上記引用箇所にも見受けられる。
締切に追われ、進まない執筆に頭を悩ませる太宰が、リアルタイムに伝わってくるような内容になっており、非常に面白かった。
火の鳥
「火の鳥」という短編は、長編小説として構想し執筆を始めたものの、途中で断念し未完となった作品である。「グッド・バイ」の他にも未完作品があることを、今回初めて知った。
高野幸代という女優を主人公に置き、心中を図り男性を死なせてしまった冒頭シーンから、女優としての初舞台を成功させるシーンまで書かれて終わっている。
太宰には珍しく、幸代の一人称視点(女性告白体の小説は、太宰の得意分野である)ではなく、客観的な三人称視点で書かれている点が特徴だ。
そのため、主人公の心中を吐露する語りの文章がなく、会話文を中心に組み立てられている。他の作家では当たり前に見られる手法だが、太宰にとっては貴重な作品である。
太宰の代名詞とも言える独自の一人称スタイルではないため、良くも悪くも「太宰らしさ」が薄い正統的な作品だが、これも太宰が創作の試行錯誤を重ねる中で生み出された結果と言えるだろう。
春の盗賊
最後に「春の盗賊」という短編。こちらは一転して、小説としての筋書きがほとんど見られず、ひたすらに太宰の心情が乱筆された作品だ。
以前取り上げた『二十世紀旗手』ほどではないが、間髪入れず次々に言葉が吐き出されて入り乱れ、独特なリズム感をもって読者を翻弄する文体は、「これぞ太宰」といった感じである。
このように、不安定な精神状態そのままに筆を走らせた短編から、作家として更なる飛躍を図る実験的・技巧的な短編まで、様々な顔が見られるのが太宰治の魅力だ。
◇「全部読む」シリーズの他の記事はこちら◇
◇本に関するおすすめ記事◇
◇読書会Podcast「本の海を泳ぐ」を配信中◇
◇マシュマロでご意見、ご質問を募集しています◇
当noteは、Amazon.co.jpアソシエイトを利用しています。
