
本は、自分と社会を(再)構築するナラティブとの出会い――渡辺由佳里『ベストセラーで読み解く現代アメリカ』レビュー
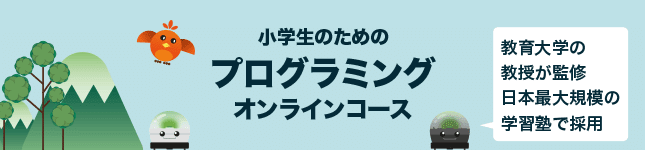
(※この記事は2020/08/24に公開されたものを再編集しています。)
「この本を抱きながら眠りました」
「この本を抱きながら眠りました」。あるエッセイについて友人と話していたときのことだ。「好きすぎて眠る直前まで読んでしまうんです」と語っていた。
似た事例が、九井諒子の短編マンガにも取り上げられている(『ひきだしにテラリウム』所収の「ノベルダイブ」)。散らかった部屋、たまった洗濯物、シンクには四日前の食器、ぼさぼさの歯ブラシ、住民票必須の手続きの案内、元恋人から結婚式の招待状――。あ゛―もう、わかってるって、仕事が片付いてからなんとかするから……と言い訳しながら、電灯を暗くして、そんなときでもやめられない趣味、ノベルダイブ――眠気と戦いながら物語に触れることで、夢と物語が混ざっていくのを楽しむ――をやろうとする、というのが短編の導入である。
自分以外の存在を「他者」と呼ぶことが許されるなら、本との出会いは、他者との出会いであり、他者との付き合い方も千差万別だろう。ほとんど本は読まないのに、特定の一冊をずっとテーブルの上に置いていて、時々パッと開いていると語る人にも出会ったことがある。Skypeでつないでいるときに、たまたま相手が読んでいた哲学の本を朗読してもらったという経験を聞いたこともある。
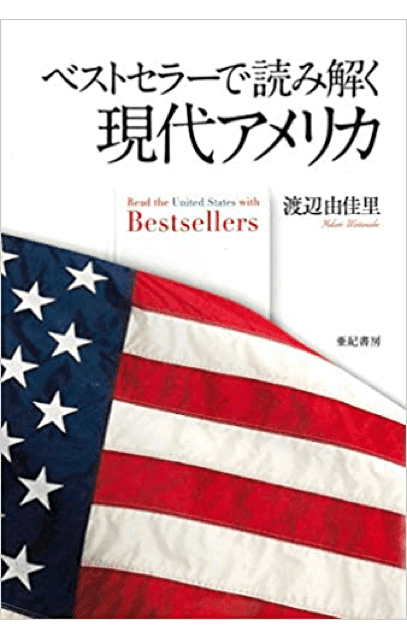
ベストセラーから読むアメリカ社会
今回取り上げるのは、渡辺由佳里の『ベストセラーで読み解く現代アメリカ』(亜紀書房, 2020年)である。渡辺が「ニューズウィーク日本版」のウェブサイトにて連載してきたものを中心にまとめた、書評集とでも言うべき内容である。
話題としては多岐に渡っている。小説のレビューがあれば、政治家の回顧録があり、社会学の本があるかと思えば、ビジネス書やノンフィクションもあるし、「まなびとき」でも幾度か名前を挙げたレベッカ・ソルニットの本、それから、近藤麻理恵や村田沙耶香の本の英訳まである。
レビューは、以下のようなテーマに従って並べられている。「Iアメリカの大統領」「IIアメリカの歴史」「III移民の国、アメリカ」「IVセクシャリティとジェンダー」「V居場所がない国」「VI競争社会の光と影」「VII恋愛と結婚」「VIIIアメリカと日本の読者」「IX民主主義のための戦い」。
本を評することは、社会を評すること
いずれも、書籍の一部を小気味よく紹介するだけでなく、著者がどんな人物で、元々どんなイメージが抱かれているか、出版のタイミングがどうか、どのように受け取られたのか、どのような社会的意義や影響力があるのか、といった事柄が合わせて解説されているのが、本書の特徴だろう。本の内容を読むと同時に、本の内容や影響を通して「アメリカ社会」を読むという姿勢が表れている。
全編を通して使われているキーワードはないけれども、その態度を象徴する言葉は本の前半に出てきている。ヒラリー・クリントンの『WHAT HAPPENDED:何が起きたのか』(光文社)を取り上げたときに用いた「ナラティブ」という言葉だ。
ユヴァル・ノア・ハラリの『サピエンス全史』(河出書房新社)を引いて人間のイマジネーションに言及しながら、共同性を生み出す装置としての「ナラティブ」について渡辺なりの説明を加えてはいるけれども、「現象を捉え、説明するフレームや理論」のことだと理解しておけばよい(pp.67-9)。これに基づいて、書評=社会批評エッセイを読み解いてみよう。

アメリカでうごめく無数のナラティブ
例えば、「まなびとき」のレビューでも取り上げた、カート・アンダーセンの『ファンタジーランド:狂気と幻想の五百年史』が書評されている。アメリカ建国の前史には、存在しない黄金への熱狂と、宗教的熱狂とがあることを踏まえ、アンダーセンは、そこで作られた「幻想に基づく熱狂というパターン」をアメリカ社会が幾度となく繰り返してきたのだというナラティブを編んだ。それは、新興宗教、疑似科学、政治的熱狂などとして反復されるのだが、それは、現代において、ドナルド・トランプという形で結実したとアンダーセンは読み解く。従ってこの本は、アメリカ社会のナラティブを書き換える試みでもあった。
他にも挙げておこう。政治家たちの選挙戦で用いられたフレーズやスローガン、支持者による動員合戦のレトリック、政治家の家族による回顧、専門家による大統領の分析や批判、閣僚による内情告発、“フェデラリスト”ハミルトンの描き直し、建国のナラティブの書き換え、各世代のフェミニズムの戦略や人物とラベリング、アメリカ先住民の苦悩、日系アメリカ人俳優ジョージ・タケイの収容所経験、移民をめぐる物語、ディストピア小説、ロマンティックな国際結婚、レイプ被害者と加害者と地域住民の加害をめぐる非対称的な語り、近藤麻理恵の全米での成功譚――。もちろん、このほかにもたくさんある。
アメリカに黒人として生きる親子の会話
「まなびとき」のコラムでも、ビリー・アイリッシュの発言とともに紹介したBlack Lives Matterに通じるアメリカ社会の現実についても、本書では扱われている。
黒人は、少しでも疑いがある行動をしたり、言い返したりしたら、肉体を破壊される可能性があるのだ。だから黒人の親はわが子に、「おもちゃでも銃は持ってはいけない。フード付きのジャケットを着てはならない。警官にどんなに侮辱されても言い返してはいけないと教えねばならない。黒人の大統領がいても、それがアメリカの現実なのだ。何の罪もない18歳の黒人青年マイケル・ブラウンを殺した警官が無実になった日、アメリカの正義を信じられる恵まれた環境で育ったコーツの息子は、その「夢」を失い、自分の部屋にこもっていた。それに胸を痛めながらも、父は息子の肩を抱いて「大丈夫だ。心配するな」と慰めはしなかった。なぜなら、彼自身が一度として「大丈夫だ」と信じたことがなかったからだ。(p.120)
これは、タナハシ・コーツという黒人ライターの『世界と僕のあいだに』(慶応大学出版会)を取り上げた文章の一節だ。
アメリカの平等と正義をめぐるナラティブが、実際には黒人を排除しているのだという現実を前に崩れ去っている。25-29歳の黒人男性の死因の6位が、警察からの暴力であり、その殺害に関わった警官のうち数%しか有罪になっていない。「黒人の身体を持って生きる」ことについての、それぞれのナラティブを生み出そうとする試み自体を評価することで、夢の壊れた重たい現実を生きていくことをコーツは促している。

反射的にインテリを批判しさえすればトランプは理解できるのか?
本書が好意的に取り上げるナラティブには、一定の傾向がある。それは、一概には言えない現実を覆い隠そうとする、単純化された批判への抵抗である。何かを切り捨て、単純化し、誰かを全き悪者にすることで自分自身を純粋なままに留め置いて安心しようとする人間の性向に、渡辺は批判的であるように思われる。いくつか事例を挙げよう。
トランプ大統領が誕生した衝撃的な選挙戦以降、マスコミや素人評論家たちは、型通りのトランプ支持者をやみくもに取り上げながら、返す刀でとにもかくにも都市部のインテリを否定しておくという一つの強固なナラティブを作った。インテリは見当違いのことを考えていると指摘することで、自分たちは「現実」を見ていると信じられるのだろうか。誰かがすべて悪いということになれば、それ以外の人間は、自分に責任を問わなくなり、内省しなくなってしまうのではないか。ヒラリー・クリントンの『WHAT HAPPENED』を取り上げた箇所で、渡辺はヒラリーとともに自問する。(pp.65-6)
近年、「純粋さのテスト(purity test)」という言葉が飛び交っていた。例えば、ヒラリーが共和党の家庭に育ち、高校生のときに共和党候補の支援活動をしたことが批判されたりしたことがある(p.363)。こうした純粋さへの過剰な希求について、レベッカ・ソルニットは、「あまりにも多くの人が完璧さを信じていて、そのために完璧ではないものすべてを貶めてしまう」と表現する(『それを、真の名で呼ぶならば』p.8)。
もちろん、「純粋さのテスト」のようなフレーズを、無思慮に他者批判のために使えば、自分を免責して話題の棚から遠ざけてしまう。純粋さのテストをあげつらう人ほど、自分を純粋で安全にしておきたがる人はいない。厚顔無恥になりたくないならば、こうしたフレーズは、他者でなく自分への戒めとして使用しておくべきだと言い添えておく。

単純化への抵抗と、ナラティブ未満の口ごもり
完璧な純粋さを求めて残りを切り捨てること、自分を棚上げして誰かを罵倒すること、つまりは、単純化するナラティブに渡辺は抵抗している。抵抗の半分は、別のナラティブの開発と普及を提案することによって遂行されている(pp.69-70など)。しかしそれは、2016年の選挙戦で、ヒラリーやトランプやサンダースが互いに言葉を投げつけ合ったような、広報とPRの問題だと言えるだろう。よりよいナラティブを流通させることで社会を変える戦略でもある。
こうしたイメージ戦略抜きに現代社会が成り立っていない以上、こうしたナラティブの広報的な側面は無視できない。しかし同時に、抵抗の残り半分は、何かもごもご言うことによって遂行されているように見える。それは口ごもりにすぎないので、何かを説明するフレームや理論とは言えず、ナラティブ未満のものだ。
フェミニズムを扱った小説において、第二派フェミニズムを若い世代が「中流階級の白人女性のフェミニズム」と批判する箇所を渡辺は取り上げた。批判自体は妥当だとしても、その批判のラディカルさに、渡辺は、率直な戸惑いや苛立ちを示す。その動揺は、2016年の大統領選挙において、ヒラリーをめぐって生じていた女性たちの分断を回想させた。「若い女性の多くがヒラリー批判の急進派につくか、無関心かのどちらかを選」び、「ヒラリー支持の若い女性(特に大学生)はピアプレッシャー(仲間からの圧力)で黙り込むしかなかった」(p.184)。
そういう箇所の渡辺は、動揺や苛立ちを率直に表現しながらも、その他の箇所に比べて、強く言い切ることができていないように見える。「そんなに単純化しなくても、いいんじゃないかなぁ」「割り切れないとこも、あるんじゃないか……」といった割り切れない感覚が、少し情熱的に言語化されている。
本書の魅力は、こういう箇所にこそあるのではないか、と個人的には思う。口ごもりには、もごもごと口の中で言葉を構成し直す作用もあるのかもしれないのだから。
渡辺由佳里『ベストセラーで読み解く現代アメリカ』(Kindleあり)

<参考文献>
九井諒子『ひきだしにテラリウム』(Kindleあり)
ヒラリー・クリントン『WHAT HAPPENED:何が起きたのか?』(Kindleあり)
タナハシ・コーツ『世界と僕のあいだに』
レベッカ・ソルニット『それを、真の名で呼ぶならば:危機の時代と言葉の力』
クリント・スミス「アメリカで黒人の息子を育てる方法」TED Talk
「Black Lives Matter、日本人が知らないデモ拡大の4つの要因」(News Week日本版)
<まなびときの関連記事>
・アンダーセン『ファンタジーランド:狂気と幻想のアメリカ500年史』のレビュー
「いかにして私たちは事実を捨てフェイクを望むようになったか:レビュー①」
「ポストトゥルースの時代は、”ワンチャン”への期待で溢れている:レビュー②」
・Black Lives Matterを取り上げた記事
「思考は謎から目をそらし、問題を忘れる:ビリー・アイリッシュの投稿から考える」
・『サピエンス全史』が登場する記事
「『見えない相手』と対峙する:想像の人類史」
2020/08/24
著者紹介
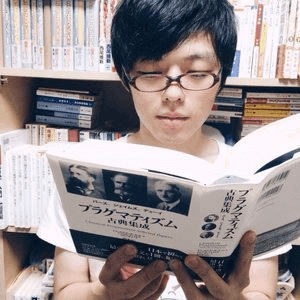
博士(人間・環境学)。1990年生まれ、京都市在住の哲学者。
京都大学大学院人文学連携研究員、京都市立芸術大学特任講師などを経て、現在、京都市立芸術大学デザイン科講師、近畿大学非常勤講師など。 著作に、『スマホ時代の哲学:失われた孤独をめぐる冒険』(Discover 21)、『鶴見俊輔の言葉と倫理:想像力、大衆文化、プラグマティズム』(人文書院)、『信仰と想像力の哲学:ジョン・デューイとアメリカ哲学の系譜』(勁草書房)、『ネガティヴ・ケイパビリティで生きる』(さくら舎)など多数。
