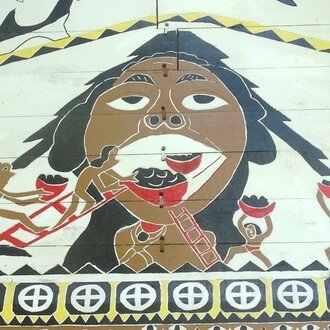『山の彼方の棲息者たち』 加藤博二
著者の加藤博二については、国有林を管理する森林官だったこと以外よくわかっていない。一九三〇年代から四〇年代にかけて『深山の棲息者たち』『密林の怪女』といった山奥に暮らす人々についての書物を発表している。本書は信濃や飛騨にいたサンカ、炭焼き、猟師、山稼ぎ人、箕売りの乞食婆などとの邂逅を書いた掌編集である。序文で東京・中野の寓居で彼らの面影を思いだすと書いているから、森林官の任にあったのは明治後期から昭和にかけての時代だろうか。
著者が原生林で迷い、サンカの未亡人の小屋に泊めてもらって、山うなぎの飯と呼ばれる蛇のご飯を勧められる「山女」や、松本近くの山中で炭焼き相手の薬売りと知りあい、岩穴に寝泊まりする「岩窟ホテル」は、近代まで残っていたサンカの風俗の貴重な報告である。深山の若い女たちの境遇を描かせたら、著者の右にでる者もいまい。
十三歳の少女を中年男に売りわたす芸者屋の話、娘を工場に売ってはさらい返してくる炭焼き村の話、野合と掠奪結婚の風習が花嫁を通せんぼする遺風になった部落の話など、いずれにも山奥に暮らす女たちの哀切が漂っている。その反面、「山の湯」では温泉村の女中たちが宿泊客との色恋において、生娘と見せかけるのに山蛭を使っていたことを暴いてみせ、女たちのしたたかさも描く。どれも実地で見聞しないと書けない話だろう。
民俗学は文字を持たない人たちに関する文学である。そのような意味では、本書は山地の常民を描いた第一級の民俗誌であり、その文体や筆致には瑞々しい文学的感性がみなぎっている。「飛騨の娘」は、山道で出会った十七歳の少女の家に泊まったときに、妻帯者でありながら彼女の純潔を奪ってしまい、後悔の末、翌年に娘の家を訪ねるという、民俗誌と私小説の中間にあるような掌編である。考えてみれば、森林官もまた「山の棲息者」のひとりなのだから、本書に著者自身の人生が描かれていても自然なのかもしれない。
初出:「北海道新聞」
いいなと思ったら応援しよう!