
美意識を鍛える
こんばんは。
ステイホーム中についポチりがちなSHOGOです。
いやー、ついやってしまうんですよね...
在宅の時間が増えたので、それに伴って自己研鑽に充てる時間も増えてきたのは良いことなんですが、その反動なのか、ついネットで買っちゃう回数も異常に増えました...
4月からの1ヶ月半で、10回以上は絶対に配達してもらっていますね。今までポチった商品の梱包用段ボール合わせれば、等身大のガンダムくらいは作れる自信があります。

配達員の皆さん、いつも本当にありがとうございます。
心から感謝しております。
そして、これからはなるべくまとめて注文します。ごめんなさいm(__)m
ちなみに、僕がポチったものはどれも最高のオススメ商品でした。皆さんにも紹介したいのですが、長くなってしまうのでまた今後にしたいと思います!
◆美意識を鍛える
今回は、『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』(著:山口周)を読み込んでのアウトプットです。
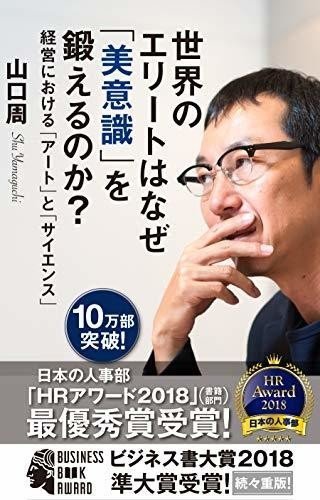
僕は学校の教科の中で「美術」が一番嫌いでした。
嫌いな理由はシンプルに、センスがなかったからです。
絵心や発想力が無いことを自覚していて、美術の成績も良くなかった僕は、
「将来、美術が必要になってくるような仕事はするつもりもないから、別にいらないでしょ。」
とばかり思っていました。
それが、自分が社会人になってビジネス書を読むようになってから気付いたのですが、ビジネスマンには「アート」としてのスキルが必要といった内容の本が意外と多いのです。
今回、山口さんのこの本を読むに至ったきっかけも、ずばり、なぜ「美意識」を鍛える必要があるのか?というタイトル通りの疑問をずっと持っていたためです。
・なぜ、ビジネスマンは「美意識」(「アート」の側面)を鍛える必要があるのか。
・どうやって「美意識」を鍛えれば良いのか。
今回はこの2つの目的を持って、本書を読み込みました。
◆なぜ「美意識」を鍛える必要があるのか
まずはじめに、本書での山口さんの主張を僕なりにまとめると、
世界のエリートが「美意識」を鍛える理由は、経営での意思決定において、これまでのような「論理」や「理性」を重視するだけでは、ビジネスで勝利するには限界があるから。
となりました。
このようにまとめると、会社内でのエリートや経営に関与しているトップだけが「美意識」を鍛えれば良いというように見えますが、ビジネスパーソンなら誰もが磨くべきスキルだと僕は思いました。
経営における意思決定では、いくつかの側面でのアプローチがありますが、大まかに「論理」「直感」「理性」「感性」の4つに区分けできると思います。
「理性」が「正しさ」や「合理性」を軸足に意思決定するのに対して、「感性」は「楽しさ」や「美しさ」が意思決定の判断基準になります。
「論理」と「直感」は何となくイメージできると思うので省略します。
そして、現在の日本人の多くが、ビジネスにおける意思決定では、「論理的」で「理性的」であることを、高く評価する傾向があるようです。
確かに僕も含めて大体がそうかなと思いました。
例えば、会社であるプロジェクトを立ち上げる企画をしている場面でも、初めにあらゆる分析を行って、ものごとの一貫性や整合性を担保してから意思決定を行うはずです。
その部分に関して山口さんは、「ちょっと待った!!」をしています。

山口さんは、軸足が「論理」と「理性」に偏りすぎた経営では、結果としてそのビジネスは停滞するよ。と警鐘を鳴らしています。
そして、経営の意思決定においては、「直感」と「感性」も高い次元でバランスよく活用することが重要だと指摘しています。
その理由としては、「時間」と「差別化」の2点を挙げています。
1つ目の「時間」は、「論理的」「理性的」にこだわって答えを出そうとすれば、時間がかかってしまい、停滞してしまうという意味です。
今後僕たちが向き合うであろう課題の多くは、「論理的、理性的だけではシロクロつかない問題」であると予想されます。
その課題に直面する度に、あれこれ無駄な情報を集めたりして「今は決められない」と立ち止まっているのは、ずっと同じところに穴を掘っているようなものです。何も出てきたり、生まれたりしません。
そこで、「直感」と「感性」に基づく意思決定が必要になります。
2つ目の「差別化」は、ビジネスというのは基本的に競合との差別化を追求するものですが、「論理的」「理性的」な考えだけでは、差別化は図れないという意味です。
多くのビジネスパーソンが論理的な思考力、理性的な判断力を高めるためにに努力しているので、その努力の行き着く先は「他の人と同じ答えが出せる」という終着駅になります。
論理的思考というのは、つまり「正解を出す技術」です。あくまでも一般的な正解を出す訳なので、周りにもたくさん同じ正解は落ちています。
なので、その正解の先を追求して、周りから抜け出した存在になるために必要なのが、「直感」と「感性」となります。
ここまで長文で、ダーーーーーッと書いてきましたが、要は
「直感」と「感性」、それを言い換えた「美意識」に基づいた大きな意思決定が重要だよ!ということです。
よく、「アート」と「サイエンス」の言葉が使われると思いますが、
論理的思考が「サイエンス」、直感力が「アート」と例えられます。
「アートのような意思決定」を説明するのは難しいところですが、
なんとなく、フワッと、これがいいかなと思って
というレベルの意思決定も重要になるということですね。
◆美意識の鍛え方
では、どうすればこの「美意識」を鍛えられるかと言うと、本書では次の4つが紹介されています。
1.絵画を見る
2.哲学に親しむ
3.文学を読む
4.詩を読む
特に「見る力」を鍛えることが大事だと書いてありました。
本当の「見る」というのはとても難しいもので、大人になったら、目に入ってくるものを基本的に意味付けして解釈してしまいます。
どういう事かと言うと、
例えば、次の2つの言葉を見て共通点を考えてください。
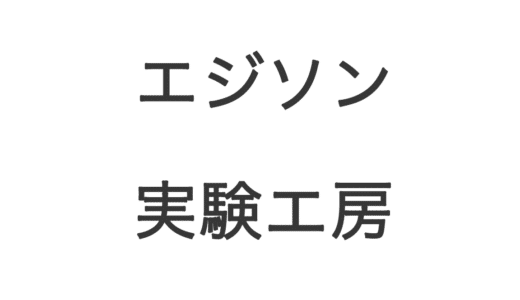
ヒントは、「読まずに、見る」ということです!
経験を積んだ大人にこの問いを出すと、恐らく
「両方とも『発明』が絡んでいる!」的なことを答えると思います。
ですが、これを何の思考も挟まずに、ただ「見る」ということに徹すると、
「どちらも『エ』が含まれている!」ということに気づくはずです。
もちろん、カタカナの「エ」と漢字の「工」ですが、ビジュアル的にはどちらも同じです。
大人は、「見る」ことよりも先に「読む」ことをしてしまいます。
純粋に「見る力」をつけることでパターン認識を回避して、新しい発想や着眼点を身につけることができるということです。
◆最後に
「美意識」を鍛えることは、仕事を進めていく上で欠かせないスキルになると思います。今後どうしても論理だけで判断できない場面に直面する可能性があります。その時の最終決定権は自分の「美意識」です。
この本を読んで早速、「よし、週末は美術館に行こう!」と考えた僕は、とんでもなく浅はかかもしれません。
でも、思い立ったことをすぐ行動に移すことが重要だと考えているので、まずは気軽に行ってみようと思います。
この本は、今まで美術や芸術には全く興味がなかった僕の価値観を180度変えてくれた、最高の一冊でした。
今回も長文となりましたが、最後まで読んでくださった方、本当にありがとうございます。
僕のアウトプットが他の人にとっても有益な情報になりますように。
人生を本気で成功させるために、
公務員を僕はやめる。
