
オススメ小説「あなたのための物語」著:長谷敏司【感想】
【オススメ小説】
タイトル:あなたのための物語
著者:長谷敏司
出版社:早川書房
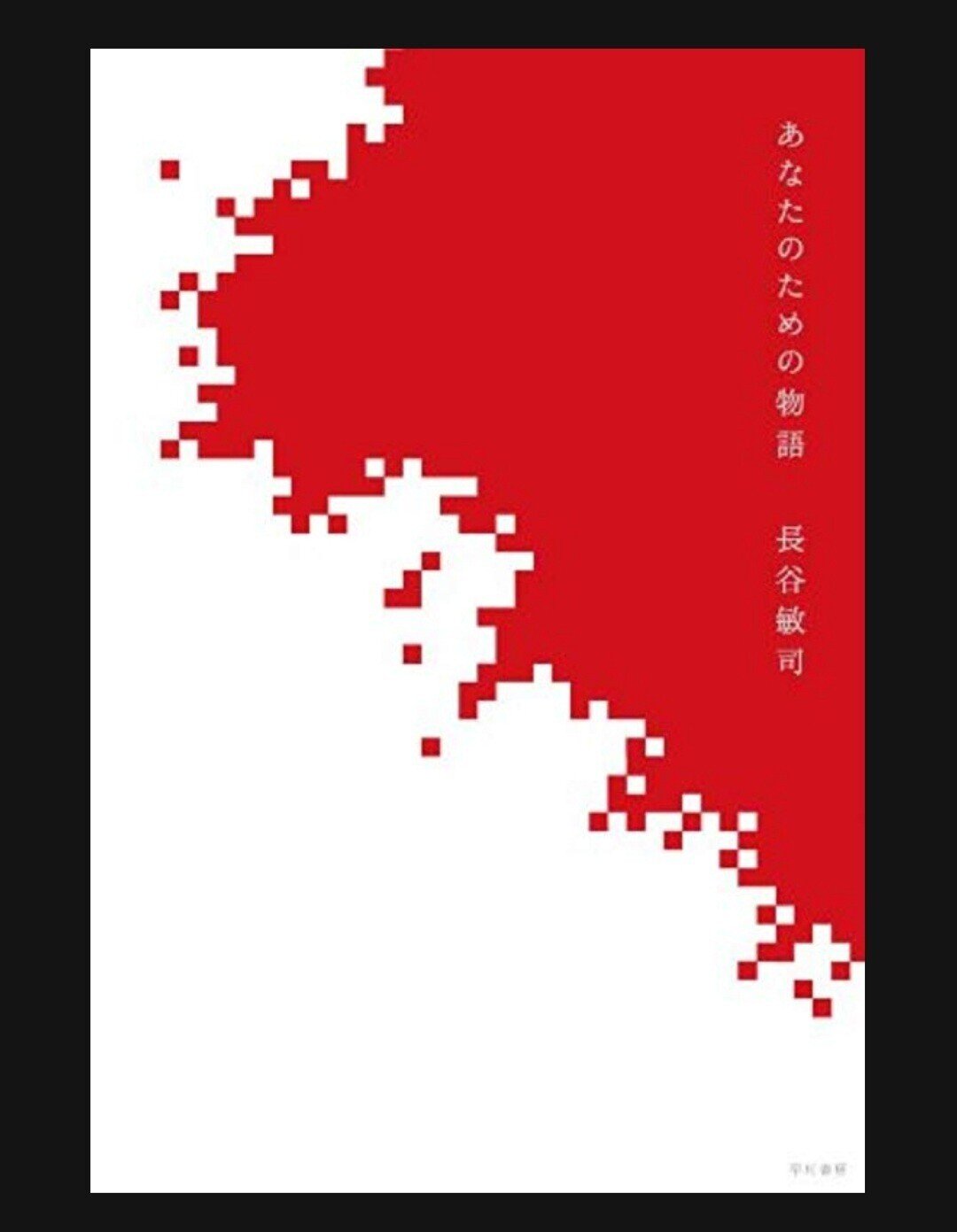
あらすじ
主人公の科学者「サマンサ」は今まさに死の淵にいた。恐怖は理性を殺し、意思と魂はその体から消え去ろうとしていた。痛みが波のように寄せては帰り安心と絶望が繰り返す。苦痛と怒りが全てを塗りつぶし、そして、尊厳も誇りもなく惨めに孤独に彼女死んだ。
サマンサは「NIP(ニューロン・インターフェース・プロトコル)」と呼ばれる人工神経の開発者であり、その発展形である「ITP(イメージ・トランスファー・プロトコル)の完成を目指していた。『wana be』というITPを利用した仮想人格を作り出し「wana be」に人間同様の想像力があることの証明として小説を執筆させようとする。
世界観の補足
「NIP」は脳内に擬似的に神経を発生させることで、脳に障害を負った場合でも問題なく義肢操作を行うことが出来る。「ITP」は前者を利用し擬似神経にAの感情、知識などを転写して、それをBの脳内に直接発生させることが可能となる技術である。つまり、Aの感情を言語や文章などを通さず直接Bへと伝えることが出来る。しかし、「ITP」には使用中において「世界が色あせてつまらない」ような感覚が続くという問題(感覚の平板化)があった。そこで「ITP」を利用した仮想人格に小説を書かせることで感情の平板化の原因を探ろうとする。
「彼」は、自らの価値の証明のために小説を書き続ける、実験の成否にかかわらずいずれ消去されることを知りながら。彼は自分の時間が死に向かっていることを自覚している。ゆえに、その時間が終了するまでに自らの価値の証明(創造性ある小説の執筆)をすることを目的として据える。
『wana be』とサマンサ、死の認識
『wana be』は自分の死について誕生した瞬間から理解している。人生を歩む中、死が理不尽に突然避けられぬ穴のように目の前に現れたサマンサと最も異なる点だ。だから死とは『wana be』にとってはある種の到達点であり、サマンサにとっては納得できない代物なのだ。
サマンサは死とその恐怖に科学を用いて徹底的に抗う。恐怖や苦痛を感じた際にITPを使用し、希望や楽しいという感情を脳内に生じさせる姿はあまりに哀れで無様ですらある。
追い打ちをかけるようにITP使用による感覚の平板化が彼女を襲う。それは恐怖、苦痛さえもありふれたつまらない体験のように感じさせ、彼女自身の体験が世界中にありふれた量産品で代り映えのない物だと、今自身が感じているものはお前だけの特別なものではないと言われているかのように思わせる。
自分に誇りを持ち生きてきたサマンサにとってそれは心をへし折るのに十分なものだった。
死をはじめから意識する『wana be』と、死を目前に否応なく突き付けられるサマンサ。『wana be』がサマンサの為に書いた物語は彼女にいったい何をもたらすのか?
なぜ物語を作り、なぜ物語を読むのか
人は生まれそして死ぬ。その間の状態を”人間”、その期間を”人生”と仮定する。人はその人生での出来事を大概記述可能な言語により記憶する。ある一定の出来事について言語情報により意味記憶することによりそれは”物語”となる。つまり”人間”と”人生”とは、それそのものが”物語”であるといえるのではないだろうか。(この段落は物語を人生に読み替えても読めます)
しかし、当然のことながら言語により表現できない物事も当然存在する。意味を伝達するために言語があり、言語は意味を記録するためにある。言語により表現不可な、いわゆる”抽象的”な出来事は正確に記録されず、いずれ記憶から薄れてしまう。
上記のような自ら作り上げた言語により縛られる状態に人はジレンマを抱えている。『wana be』は作中で人はその状況にストレスを感じているとし、言語を使って物語を書くことでそのストレスを分散していると言っている。
書かれた物語は大多数の人にとって非日常であることが多い。それは自らに足りない”物語”を埋めようとしているからであり、それを取り込むことにより自らの物語を補強したいからか、或いは自分の言語では表現できないものを他人の言語にもとめているからなのだろうか。
ストレスの原因そのものを用いてストレスを発散する様はまるで、暴力によるストレスを暴力により発散するのに似ている。それゆえ外部に対する発散行為である物語は他人を傷つけることもできる。
小説や物語が商品たりうるのは「言語を使い、相手の言語を奪うことが出来たから」とも『wana be』は言っていた。当然、物語を読むときは記述した人物の言語によって読むこととなり、その間は相手の言語に支配されるのだ。
だからこそ、自分の物語に既に存在し、他人の言語によらずとも良い物語(陳腐でありふれた物語)では商品たりえずその価値を見出せないのではないか。ノンフィクションなどはいい例で、実際の人物の物語だが読み手の物語や言語には存在しない体験や感情だから商品として存在するのだ。
『wana be』は死と物語について自らの目的との結びつきを見出すが、ネタバレになるのでここでの記述は避けます。
まとめ的な何か
普段何気なく行ってる読書という物語を消費する行為や、死という終わりがあるからこそ目的の達成を目指す、といった当たり前のことだが日常においてそれを意識することは少なかった。この小説を読んでからは文章を読むことに対して少し真面目になったし、自分の書いた文章を相手が読んでいるときは相手の人生の一部(主に時間=寿命)を奪ってしまうんじゃないかと思うようにもなった(じゃあ、こんな長い感想書くな)。
個人的には開始6ページが本編でオチなので気になった人は冒頭だけでも読んでみて下さい。そして興味を持ったらその続きもぜひ。
