
あをによし 光と影の道 その一【室生古道 佛隆寺】奈良あるき
まだ薄暗い朝6時、大慌てで起き、身支度して家を出るまで40分程。
その間、コーヒーを飲み、髪をちょちょちょと整え、顔はさっさかさと
やっつけ(どうせ大して整わないので)、いつもの山歩きスタイルに着替え
出発。
外の空気はキーンと冷え込んでいた。
慌てて出発したのは、奈良の公共交通機関事情あるあるで
1日数本のバスに乗るため。
近鉄榛原駅前7時53分発、これを逃すと次が12時頃になる。
予定通りのバス乗車。
これは夏に半夏生を見に御杖村へ行った時と同じバスで、
今回も乗客はワタシだけ、完全貸切だった。

先日、曽爾村に行った時とも同じルート。
川沿いを上っていく。

高井というバス停で下車。
今日は晴天!


かつて伊勢街道の高井関が置かれた宿場町だった。

バスを降りると、さらに冷たい空気が肌に突き刺さる。
陽の当たるところから蒸気が上がり、日陰はまだ真っ白の霜景色。


ここから室生古道へ。
伊勢街道から仏隆寺(赤埴・あかばね)を経て、唐戸(からと)峠を越えて西光寺、室生寺とを結ぶ道が室生古道。
ずっと訪れたいと思っていたお寺、仏隆寺参詣がまず今回の目的の一つ。
ここで是非拝見したいものがあり・・
そしてその仏隆寺は室生古道の道筋にあり、この古道も歩いてみたかった道。

仏隆寺を目指す。

山間の道はまだ陽が当たらずキンキンに冷えている。
寒いが気持ちが良い。







周りは杉林。
まっすぐまっすぐ清々しいほど伸びる杉の幹、好きだわ。





しばらく歩くと、杉並木を抜け明るく陽が当たる道へ。



気になるがまっすぐ進む



石段のゲートが閉まっていたので、脇の道から上がる。

仏隆寺(ぶつりゅう)
山号 摩尼山
宗派 真言宗室生寺派
開基 伝 堅恵(けんね)
創建 伝 850年
それ以前に奈良・興福寺の修円が創建したともいわれる
往時は七堂伽藍の大寺院だったとのこと。
室生寺の南門とは、正面の門として末寺の関係にあり、室生寺の宿坊または住職の隠居寺として重要な役目があったとされる。




本堂を開けていただき参拝。

十一面観音
聖徳太子作と伝わる

堅恵


ここは大和茶の発祥の地としても有名。
弘法大師空海の入唐に随行した堅恵が、唐の徳宗皇帝より「茶臼」と「茶の種子」を拝受し、寺内に「苔の園」という茶園をつくり、全国に普及したとされる。
その茶臼、かつては奈良国立博物館に出陳されていたそうだが
現在はここで寺宝として保管されている。
この茶臼をぜひ拝見したかったのです。




この金継ぎの謂れが
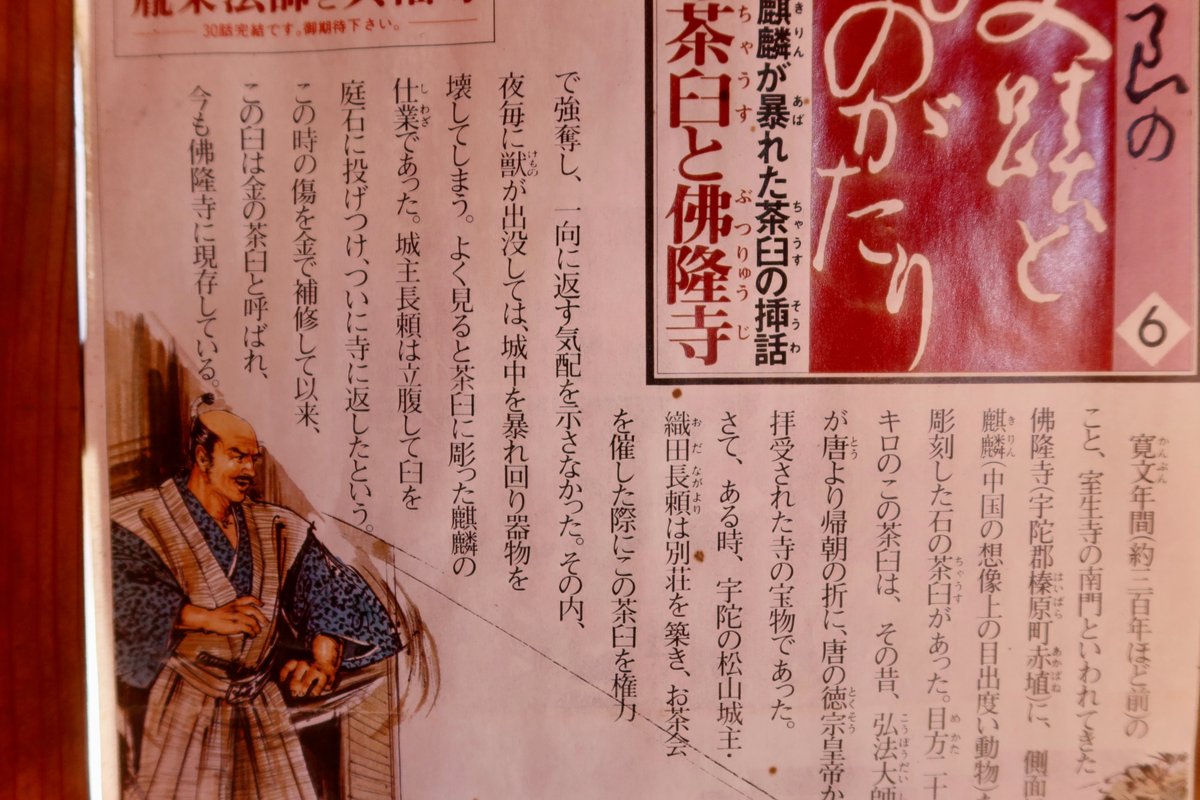

文章だけで、この茶臼の情報を得ていてどんな姿なのかとても楽しみだった。
想像はもっと大きく丸っこいものだったが、実物はとてもスッキリした
麒麟の彫刻がアクセントのかっこいい形。
木の取っ手のデザインが素敵。
本当に空海が唐から持ち帰ったものだとしたら、やはり感慨深いものだなぁ。
そして日本のお茶文化がここから始まった。
各流派の家元などがこの茶臼を観に来られるそうです。
早朝、9時前に訪れたにもかかわらず本堂を開けてくださり
色々ご案内いただいた奥様。
ご主人様の先代から世襲制の住職となったそうで、
それまでは室生寺から代々住職が務められていたとのこと。
息子さんで3代目になるが、お孫さんは女の子ばかりでと行く末を心配されている。
これだけの古刹を守り維持することは大変なことでしょう。
そんな奥様は愛知から嫁がれたそうで、どんな馴れ初めだったのかお聞きしたいところだった。

本堂でワタシの目が釘付けになった曼荼羅の軸
繊細で美しい色彩。
奥様に伺ったが、詳細は不明だった。



境内の奥にとても不思議な石の建造物があった。
宝形屋根を石で積んだ石室。
日本にまたとないものであり、大正3年に国宝の指定。

堅恵の廟

社務所前に戻ると、奥様がビニール袋を持って待っていらして
柿をお土産に下さりました。
「柔らかい一つはあとでおやつに、硬いのは少し置いてからね」
と5個もいただいた。
千年桜(推定樹齢900年のモチヅキサクラ)が有名なお寺だが
ナシの原種のヤマナシがあり、これはかなり希少なものとのこと。



春の桜、観てみたい。
高井のバス停から誰一人会うこともなく
仏隆寺でも一人ゆっくり参拝、拝観することができ
静かな静かな山とお寺の時間、大満足でもう帰ってもいいくらいだった。
が、今日はまだまだ先に続く目的地がある。
こちらもずっと気になっていたところ。

室生古道〜龍穴神社へ
つづく
いいなと思ったら応援しよう!

