
読書感想。『東京の空間人類学』
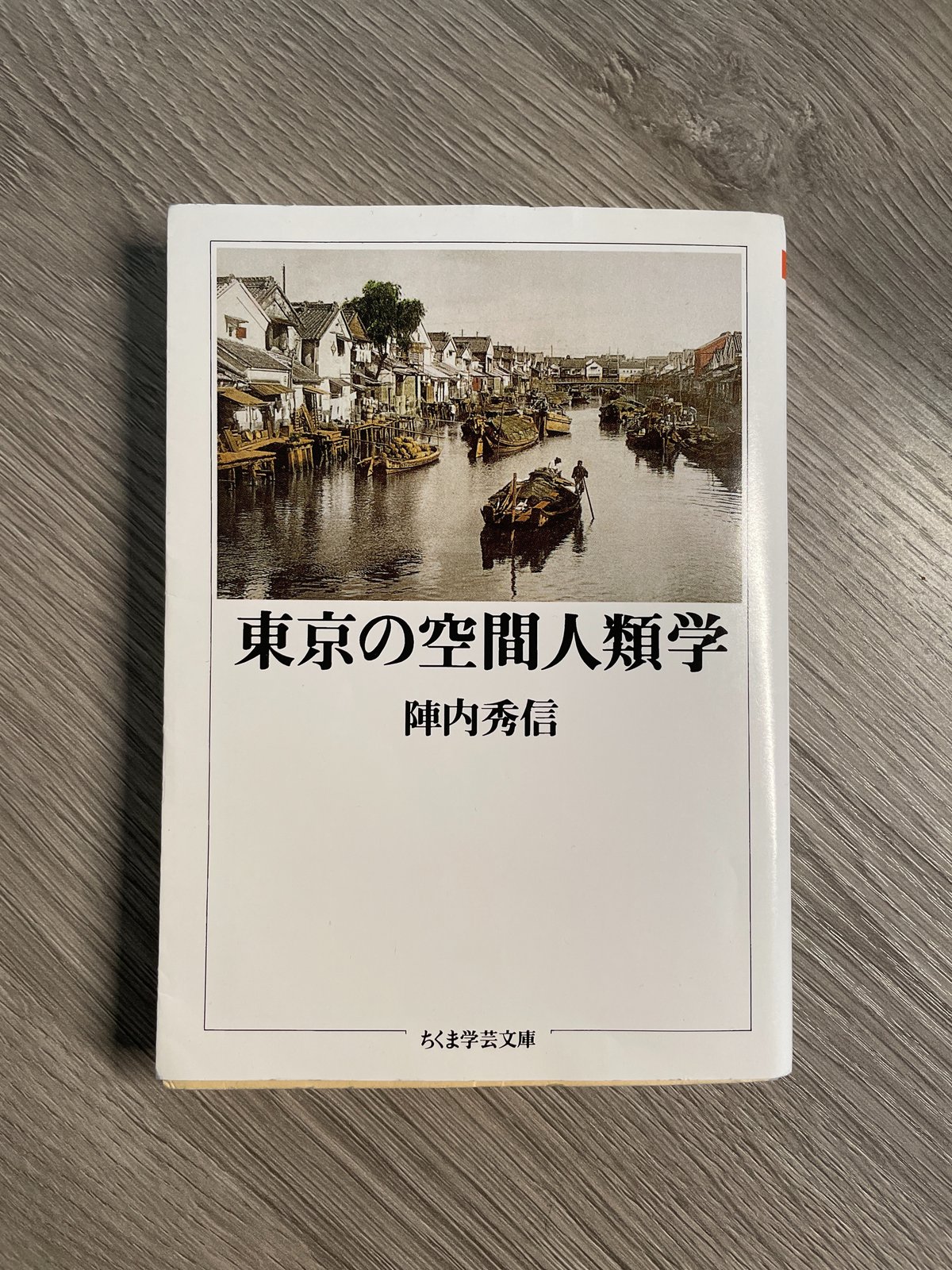
近代都市改造とともに除去され、あるいは地下へ封じ込められつつあるこのような都市民の慣れ親しんだ人間的スケールの賑わいに満ちた空間を地上の町のなかに息づかせていくことこそ、都市に魅力を与える最大の手段であると思われる。
金沢の21世紀美術館のお土産コーナーにて購入。旅行テンションで崇高な本を買ってしまった…と思ったけど、92年初版でそれほど古いわけでもなく、コツコツ読むことができた。
水路に恵まれた江戸の街づくりから、近代化が進み、震災と戦後を経て今の東京に至る都市構造の変遷を辿っていく、という内容。ちょうどヴェネチア旅行に行ったばかりなので、東京もかつては水の都だったという話を読むとワクワクした。ただ、訪れて改めて分かったことだけど、ヴェネチアは町中パッチあてまくり。歴史ある建物を丁寧に改修して21世紀に存在させていて、そこからメジャーバージョン2つ3つ上がった東京に住めているというのは、あの空気感を日常で味わえない悔しさより、安心が勝つ。。。
「有名な建築家が建てた見事な橋も、今や高速道路の陰に隠れてしまった。」というような、風情よりも生産性を優先した都市開発を嘆く筆者のお気持ちが散見するなか、文化や自然と調和する街づくりを目指す兆しが21世紀にはある -- と締め括られる。たしかにオフィスビルやタワマンが立ち並ぶエリアには植林や公園があって、きれいではある。一方で、年季の入った下町の商店街は取り残されるか、平らにリセットされてしまうのも目立つ。それこそヴェネチアみたくパッチをあて続けるのも限界があるし、耐久性の問題だってあるだろう。ただもっと温故知新というか、東京にしかない街づくりのコンテキストを活かしたプランも採れないのかな〜と素人ながらに思うのであった。
まぁ難しいことを考えてもしょうがない。せっかく東京に住んでることだし、本で紹介されている建築や橋を巡る散歩に出かけてみようかな。
