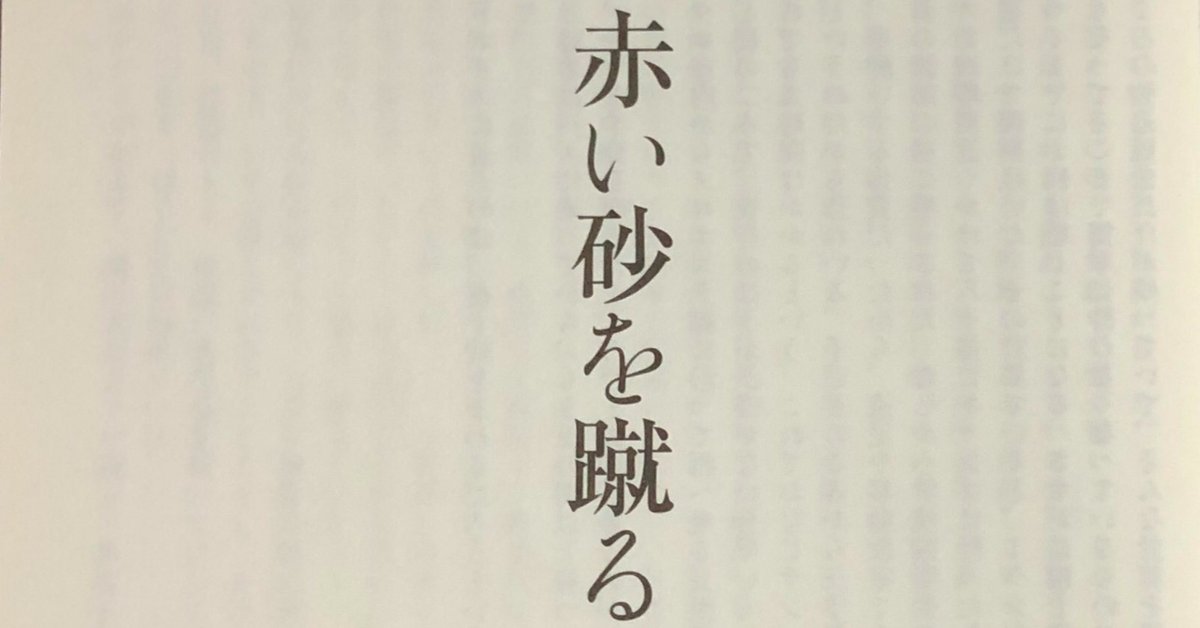
石原燃『赤い砂を蹴る』「文學界」2020年6月号【追記あり】
この作品は時系列が錯綜しているが、この錯綜が千夏の心理状態そのものを示しているのでこれは必要な構成なのだろう。
千夏と母の友人芽衣子がブラジルを訪ねるところが主系列だが、かなり多くの頻度で弟の大輝と母恭子の臨終のところを中心に過去に立ち戻る。これらを繰り返しながら、千夏と芽衣子の過去に対する態度の違いが次第に鮮明になりつつ最後を迎える。
父親の不在が共通項でありながら、それに基づく過去の災難を受け入れるにあたって、千夏はそれをはねよけようとし、芽衣子は寛容でそれらを切り抜けようとする。
結局この二人の過去に対する見解の相違は埋められることなく終わることになるが、この2つの立場が相まみえるたときには寛容のほうが上回るのだろう。
さらに千夏が、収支のバランスが取れないほど、芽衣子に救われているにも関わらずそのことに自覚がないだけでなく、時には芽衣子の義母や旦那に対して虐げられてれながらも我慢していることを、それとなく批判したりする一方、芽衣子には個人的に抜き差しならない事情を抱えていることを知っているのに、千夏が危機に瀕したときには躊躇なく相談したり、付き合ってもらったりしている。
挙句の果てには母や弟がなくなったことも、芽衣子と親しくなったきっかけになったと合理化しようすらしている。
女性差別、外国人差別、DV、アルコール依存症、偏見など様々な要素が作品の中をかめぐる中、それでもこの千夏の無自覚なところを描くのが、隠されたテーマではないかと思った。芽衣子という存在があったから、そうなのだろうと私は思った。
【追記】
上記まで書いて、なにか書き足りないと思ったことがあったので以下に追記。
とはいえ千夏の心の叫び、「一般論」に対する怒り(作中では恭子にたいする偏見)と、防衛本能から外からの抑圧に鈍感になろうして結果、自分は周りの悲しみついても感じ取れていないのではないかという思いが、特に母に対して激しい後悔の思いが募るようになる。
またこのことが、芽衣子の優しさについても、千夏は鈍感というか、気づかなくなってしまたということだと言えるのかもしれない。
また千夏は医療機関や公的機関に対する不信、並びに主に手続きに対する不満が作中でいくつか出てくる。最初このことが、千夏の「一般論」に対する不満と全く同じレベル、すなわち千夏の中のステレオタイプ的な不満だと感じていた。というのもこうした態度は、恭子が誤解されているのと同じレベルで、千夏が医療従事者を誤解している可能性があるからだ。なのでこれは作者が意図していたかどうかはわからないけれども、その可能性に思いが至らないことが、千夏の稚拙さを表していると考えていた。
しかしよくよく考えてみると、千夏の中にある社会への不満は、社会から押し付けられた一般論に基づく偏見によって、不本意に生み出されたものである。つまり負の連鎖の真っ只中にあり、それは千夏もある程度自覚しているものの、じつはそれ以上に支配されているように思えてきた。
そうるすると、この作品は負の連鎖の真っ只中にある人物から描かれた物語だと捉える直すことができ、この作品の、時系列が錯綜する構成の意図も、こうした観点から、やっとつかめたと感じた。
その上でもう一度芽衣子と千夏の並べて考えてみると、千夏が感じた(あるいは感じないようにした)ことは、千夏にとって不可抗力的であって、千夏に責任はないと千夏自体が感じるようになる。しかしそうした態度が千夏をなにかから開放することはない。ましてや芽衣子の過去に対する再解釈は、千夏から見れば敗北のように感じてしまう。しかしこの敗北したくないということが、負の連鎖そのものなのであって、敗北したくないということの裏返しは、何かに勝利したいということだから、またそれは別の敗者を生み出すことになるからだ。
しかしこの作品の価値は負の連鎖の真っ只中を描いたということなのだろう。芽衣子をあるべき姿として提示すること以上に、作品を読みながら千夏の思考回路を共有して、負の連鎖の怖さを感じることが、この作品の最大の魅力だと感じた。
