
マイナー好きなあなたのためのロンドン観光8選
【訂正加筆:2024年5月6日】New Covent Garden Flower Marketへの小売り客アクセスができるようになっていたようです。
下記に訂正をいれています。
みごとにnoteの世界に帰ってきてくださったローローさんのこのエントリを読んで、ちょっと真似したくなりました。
かといって、もう私の知っているトーキョー地図は古すぎる。
かといって、誰もきっとミネソタ州セントポール市の観光案内はいらなそう。ウィスコンシン州の小さな大学町の観光案内なんてもっといらなそう。
となれば、やはり今暮らすロンドンか。
ということで、マイナー好きなあなたのためのロンドン観光8選。
1.高いところからはじめてみよう
高校生の頃、大好きなデートスポットは浜松町にある貿易センタービルの展望コーナーだった。
なぜなら、高いところが好きだから。バーッと目の前に景色が広がるのが、好きだから。
東京タワーは高いし(値段が)、そもそも東京タワーに登ったら、象徴である東京タワーが見えない。
だから貿易センタービルだった。
スカイツリーが開業したときにはもうロンドンにいたし、登ったこともない。
けれど、映画「Perfect Days」のラストで東京にふり注ぐスカイツリーからの朝日を観た時。
高いところから眼下に広がる東京の街並みを見おろし、自分がなやむアレコレなんてたいしたことないんだと言いきかせていたころの自分を思い出した。
その気持ちはロンドンに来てからも同じ。
高いところは、自分を解放し深呼吸するのにぴったりだ。
だから、高いところから始めてみたい。
シャード
ロンドンで高い建物といえばシャード。

開業した2013年のふれこみは、確か「ヨーロッパで一番高い」だったけれど、今調べたら、すでにヨーロッパで8位になっていた。
展望台に登るには£35くらいするみたい。強気な値段設定。
ちなみに、ロンドンの絵に必ず登場する観覧車「ロンドンアイ」も£30くらいするようだ。

同じお金を払うんだったら、好きなだけいられるビルの上のほうがいいような。
でも£35も払いたくないでしょう?
そんな方におすすめなのが、52階にあるバーGONG。
安くないけど、ただ高いところにいるために£30〜35も払うんだったら、それを飲み物代に使うほうがいいと思う。
ものすごく狭くて、だからこそ、ああ、あの円錐形の一番上の方にいるんだなあと実感できる。
私は、同じシャングリ・ラ内のレストランで食事をした後、そこからバー使用をリクエストして予約した。
スペイン人の仕事仲間たちと、東南アジア出張で溜まったシャングリ・ラのポイントが期限切れになるまえに使おうという企画だった。
自分のお金を払って、もう一度行くか、といわれたらちょっと考えてしまう。
けれど、自腹だったとしても一回くらい行ってみるのは絶対にアリだと思う。
ガーキン (30 St Mary Axe)
高い建物はシティやカナリーワーフといった建築規制の少ないエリアに集中しているロンドン。
古くからのシティの象徴といえばガーキンだ。

その名の通り、どうみてもシティの町に突き刺さったキュウリ。
正式には30 St Mary Axeというらしいが、その名で呼ぶ人は誰もいない。
建築家は、ロンドン市庁舎やウィンブレースタジアム、ミレニアム・ブリッジをデザインしたのと同じ、イギリスが誇るノーマン・フォスター。
東京タワーが、スカイツリーの登場でなんとなく影が薄くなってしまったのと同じで、それまでシティの、いやエリザベス・タワー(ビッグベンを要する時計塔の名前)と並んでロンドンの、「象徴」だったガーキン。
最近では新参者のビルたちに埋もれてしまっていて悲しい。
ウォーキートーキー(トランシーバー)と呼ばれるSky Garden。
チーズグレーター(チーズおろし器)とよばれる122 Leadenhall Street。
そんな並み居るシティの新参高層建築のなかに建っていても、やっぱりガーキンのチャーミングさは一番だ。
建築ラッシュが続くシティだが、新聞記事に「このままじゃガーキンが埋もれちゃうよ」と書かれるくらい、みんなに愛されているビルなのだ。

ビル風すごそう。
そして、その最上階にあるHelixレストランは、いかにもガーキンの中にいると感じる鉄骨構造の中にあり、上まで気持ちよくガラス張りになっている。

ご飯もなかなか美味しかった記憶がある。
あえてクラシックに「昔から有名な高いビル」を訪ねるのもいいかもしれない。
◇
ハムステッドヒース
建物を離れて、高いところ、というと、ハムステッド・ヒースがおすすめだ。
ヒースとは、平坦地の荒地のこと。
また、そこによく生えている草(エリカなどににている)のことも示す英単語。
つまり、なんのことはないハムステッドにある巨大な草地。
なのだが、シティの北側に位置しているので、ここから見渡すロンドンのスカイラインはなかなかのもの。
向かう途中でサンドイッチや飲み物を買って、のんびりと天気の良い午後にピクニックしにいくのに最適。

2.水辺もなかなか悪くない
ロンドンといえば、テムズ川。
ロンドンを西から東に流れている…のではあるが、とにかくぐねぐねと蛇行しているので、川を基準に東西南北を判断しようとすると大変な目にあう。
イギリスで長年放送されている連続ドラマ「イーストエンダーズ」のオープニングはロンドンを俯瞰した地図から始まるが、それをみるとテムズ川のぐねぐねぶりがよくわかる。
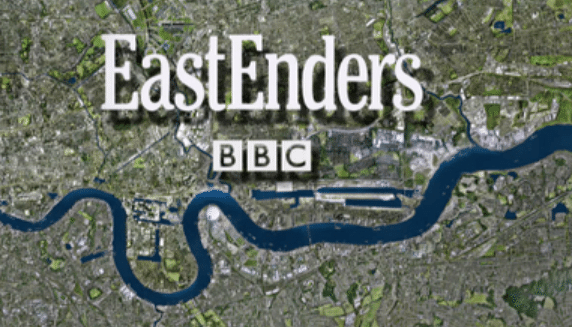
ロンドンといえばついついチューブ(地下鉄)や二階建てバスに乗ってしまいがち。けれど、テムズ川からロンドンを眺めるのも、視点が変わってとてもよい。
特に地下鉄や駅にほとんど冷房設備がないロンドンで、猛暑の日に移動するなら風を切るボートは最適だ。
テムズクリッパー
もちろん観光目的の遊覧船もでているけれど、私がおすすめするのはテムズクリッパー。
今はUber社がネーミングライトを持っているので、Uber Boatと呼ばれている。
これのいいところは、価格が遊覧船に比べて安いこと。
地下鉄やバスと同じ交通機関扱いなので、オイスターカードでも乗れる。
この「オイスターカード」。
いわば、SuicaやPasmoやIcocaのロンドン版だ。
最近は日本のクレジットカードもコンタクトレス対応になってきたので、オイスターカードを持たずに済ませるひとも多いかもしれないが、数年前までは、ヒースローですぐ買いなさいというくらいロンドン観光には欠かせないカードだった。
話がそれるけれど、最初に世界で非接触型決済を使用した交通カードは1997年の香港。
ソニーが開発したFeliCaを使った「オクトパスカード」である。
その後ロンドンに来たら、交通系カードの名前は「オイスターカード」。
なんせタコに牡蠣なのだ。
私はイギリス領の交通カードは鍋物の具材からつけるのかと思った。
後からわかってみたら、香港の「オクトパス」は中国語で繁栄するという意味をもつ「8」からきていた。
そしてロンドンの「オイスター」は英語の慣用句 "The world is one's oyster (望めばこの世界は思い通り)"から来ていた。
そもそもこの慣用句は、シェクスピア書いた「ウインザーの陽気な女房たち」の一節、"The world is mine oyster, which I with sword will open. (世界はおれの貝。剣で開けて中身を頂戴するさ)" に由来するので、もしシェイクスピアがあさりやムール貝を使っていたら、カードの名前も違っていたかもしれない。
そんなオイスターカードで、あるいはコンタクトレス対応カードで。
気軽にテムズ川を行き来してはいかがだろう。
あの有名な跳ね橋、タワーブリッジを下から眺める体験もお手軽価格でできる。

テムズリバーボート
もしも何回目かのロンドン訪問で、もう少し遠出を、あるいは毛色の違う観光をというのなら。
私のおすすめはウェストミンスターから西ロンドンにあるハンプトン宮殿までの船の旅。
メジャーな観光船はウェストミンスターを出発するとタワーブリッジを通るためか、ほとんど東に向かう。けれど、この定期船は暖かい時期のみ運航だけれど、かなりの距離を西に向かう。
何がポイントかというと、隅田川の川下り船と同じように、個性様々の橋をくぐっていくところだ。

1番のハンプトンコート橋から25番のウェストミンスター橋を通るうえに
リッチモンドとテディントンの閘門も通る
アルバート橋
チェルシーとバタシーをつなぐアルバート橋はお菓子のようなピンク色。
夜にもなれば電飾がついてディズニーランドのように愛らしくなる。

ハマースミス橋
ハマースミス橋もまた美しい吊り橋。
私が勝手に「ハロッズグリーン」と呼んでいる、あの典型的なモスグリーンの色に塗られている。

関連があるのかわからないけれど、ハマースミス橋川下側の南岸にはハロッズの家具倉庫(Harrods Furniture Depository)だった建物が残っている。
ハロッズの手は離れているけれど外装はそのまま残されている、美しい建物だ。

もうひとつハマースミス橋といえば、この写真。
ダニエル・クレイグが演じた最後のボンド映画である「No Time To Die」のなかでボンドとMがこっそり落ち合うスポットがハマースミス橋脇だった。

場内の観客がみなハッと声を出したのが面白かった
3.日帰りインド旅行はいかが
「イギリスで一番美味しいものは?」
「インド料理」
というやりとりは、定番のジョークで(本来の回答は「イングリッシュ・ブレックファスト」なのだが)、もちろん元植民地であるインドからの人口の多さがあいまってのことである。
ちなみにインド生まれのひとが多いベスト3はロンドン(約26万人)、レスター(約4万人)、バーミンガム(約3万人)となっている。
セントラル・ロンドンにもたくさんのインド料理レストランはある。でも、まるで日帰りインド旅行をしたような気分になれるエリアがいくつかある。
サウスホール(Southall)

サウスホールはロンドンで一番大きなシーク教徒のコミュニティだ。
シーク教徒はインドのパンジャーブ州に多い。だからサウスホールの町にあるインド料理レストランもほとんどがパンジャーブ料理だ。
シーク教徒の男性といえば髪と髭が伸びていて、その髪の毛をぐるぐる巻きにしたうえにターバンを巻きつけているスタイルが典型。
もしもターバンを巻いていないシーク教徒だとしても、鉄製の腕輪をつけているのですぐわかる。
そんなひとたちが街中を闊歩している。
パンジャーブ州は北インドにあり、冬にきっちり寒くなる。
だからクリームやギー(バター)、パニール(チーズ)、ヨーグルトが使われた料理が多い。
また小麦が多く取れる地域なので米食よりも小麦を使ったパン類がメイン。
料理法としては窯焼き料理であるタンドーリが有名だ。
つまり、釜で焼いた小麦のナンにたっぷりギーを塗ったもの、なんてまさにパンジャーブ料理ということになる。
菜食も、非菜食もあり。
タンドーリラムやタンドーリチキン、そして美味しいのがタンドーリフィッシュだ。
スパイスに漬け込んだ鯛やスズキを窯焼きしたタンドーリフィッシュは本当におすすめ。ぜひ一度食べてみていただきたい。

アルパトン(Alperton)
アルパトンはサウスホールからすこし北にある。
グジャラートのひとたちが多い地域。
グジャラートといえば、グジャラート・ターリ。
ターリとは定食の意味だ。
大きなお皿の上にプーリ(揚げパン)あるいはロティ、そして小さなカップに入った色とりどりのカレー、スープ、ヨーグルト、数種のご飯、バターミルクなどが盛られている。

グジャラートにはジャイナ教のひとが多い。
ジャイナ教は肉、魚、卵、そして根菜を使わないので、完全菜食。
でも、お皿の上はスパイスのおかげで色彩とバラエティに富んでいる。
しかも食べ放題。
というか、どれかを食べ終わると、まるで見張られていたかのようにすぐウエイターの若いお兄ちゃんが笑顔で新しいものに入れ替えてくれる。
わんこ蕎麦のような感覚だ。
ピカデリー線アルパトンの駅をでて、イーリングロード(Ealing Road)に沿って左に進むと、道がややカーブし三叉路になる。そこまでは普通のイギリス。
が、その交差点を越えたとたん、左右がもうインドになる。
その展開もおもしろい。
ウインドウの中のマネキンが着ている洋服はカラフルでビーズのいっぱいついたサリーやボリウッド映画のおじさんみたいな上下服。
キッチン用品店の前には山のようにターリに使う銀色の皿やカップ、ティフィンボックス(お弁当箱)を積み上げてある。

そして屋台で、ダベリやパニプリが売られている。
ダベリとは、おしゃべりすること、ではなく、言うなればインド版ハンバーガー。
じゃがいもを潰してスパイスをいれ焼いたあるいは揚げたものがハンバーグ代わりになり、それをパンに挟んで、チャツネ(野菜ベースの甘くないジャム状のソース)がかかっている。

パニプリとは、ボール状で中が空洞になっている小さな揚げパンの中に、ジャルジーラという謎の緑の液体を入れて、染み出したり割れたりしないうちに大慌てで一口で食べる、という要テクニックのスナックだ。
この謎水ジャルジーラはクミンやらなにやらが混ざっていて、最初にたべたときは、ぐへえと思ったのだが、なぜだかこれが不思議にクセになる味。

普通はこんな素敵にでてこない。
もしもあなたがメチャクチャな甘党ならば、道の脇で作っている揚げたてのグラブ・ジャムンに挑戦してもいいだろう。
小さなドーナツを砂糖、カルダモン、サフランなどが入ったシロップの中に漬け込んだもの。キーンと頭がいたくなるほどに甘いドーナッツだ。

インドぽい商店街を抜けた先には、Shree Sanatan Hindu Mandirというヒンドゥー寺院がどーんと建っている。ここで日帰りインドプチ旅行の気持ちはさらに高まる。

ちなみに、このアルパトンの商店街にあるFruity Freshという八百屋さんは、ガーディアン紙だかタイムズ紙だかが選んだロンドンの八百屋ベスト10に入っていた。
アジア野菜から西洋野菜まで。さすがベジタリアンのニーズに応える品揃え。なかなか見つからない日本ぽいナスも、ここだと手に入る。
4.市場へ行こう
ロンドンで市場へ行こうと書いてあるのを見て、あ、ボロマーケットでしょと思ったアナタ。
違います。
確かにボロマーケットは10年前まではオイスターを買ったり、他のヨーロッパからの変わった野菜やチーズを手に入れられる市場だった。
でも。
最近は観光地度が高すぎる。
そしてその結果、生鮮食料品を扱う店よりも、飲食店が増えてしまった。
だから、週末のランチどきなど、もう行列がすごくて身動きがとれない。
そればかりか、パエリアだのハンバーガーだのを手にもってキョロキョロ歩く人が多すぎて、洋服にぶつけられそうで怖くてしかたがない。
魚市場(Billingsgate Market)
と、いうことで、まずは魚市場から。
ビリングスゲイトマーケットはイーストロンドンにある。
火曜から土曜日の朝4時から8時半までの営業だが、6時半過ぎには片付けが始まっている印象だ。

ロンドンは魚や貝類がとても高い。けれど、ここにいくと当然ながらフレッシュでしかも安く海鮮が手に入る。
特に、サイズが小さいから5尾いくらという感じで皿に積み上げられたロブスターや、一尾まるごとで売られているカツオ、ドーバーからきたヒラメにアサリなど。種類も豊富でお買い得。
足元はびちょびちょなので、できれば水に強く滑りにくい靴を履いていったほうがいい。
肉市場(Smithfield Market)
ビリングスゲイトマーケットが魚市場なら、このシティのすぐ脇にある市場は肉専門。

ただし、東京の築地市場と同じで、シティ近くのあまりに好立地にあるためビリングスゲイトマーケットとともに、移転が予定されている。
すでに鳥類の市場は閉鎖してしまった。
肉市場はまだ健在。
いまのところ2028年までは、これまで通りヴィクトリア時代の建物で商いを続けるということなので、クラシックな建物のなかで取引される肉たちを見に行きたい方は、どうぞお早めに。
こちらは月曜から金曜日が営業日で取引は深夜から朝7時まで。
ビリングスゲイトとは違って、週末は開いていないのでご注意を。
花市場(New Covent Garden Flower Market)
ロンドンにいくつかある花市場のうち、一番大きなものはNew Covent Garden Flower Marketという。
そもそも花市場は、いまや劇場街の真ん中に位置する観光名所コベントガーデンにあった。

それが名前だけはそのままにテムズ川の南岸、バタシー地区に移転したものがNew Covent Garden Flower Marketである。
ロンドンどころか英国一の大きさを誇る規模なのだ。
ロンドンの花屋の75%がこの市場を経由した花を取引しているという。

ただ、ここは小売も、観光客向けの開放もしていない。ロンドンに住む華道家の方とお話していたところ、New Covent Garden Flower Marketでの小売り開放の情報をうかがった。
平日は朝4時から10時まで、土曜は朝4時から9時まで。日曜はお休みでだれでも入ることができるようになったとのこと。
値札はついていないので、お店の人に直接価格を訊き、20%の消費税を加えた額を支払う仕組みだそうだ。
とはいえ、観光目的でぶらぶらするのに、おすすめなのは、やはりこちらのColumbia Road Flower Marketだ。
花市場(Columbia Road Flower Market)

毎週日曜日の朝8時からだいたい午後2時過ぎくらいまで、東ロンドンのコロンビアロードの路上で開かれている。
この市場の歴史は19世紀に遡り、近所の人々が手作りの工芸品や自分の庭で採れた草花をもちよって取引していたのが始まりだという。

そんな歴史もあいまって、こちらは業者向きマーケットではない。
とはいえ売っているものが植木や花なので、観光客というよりも、広くロンドンのいろんなに住むひとが、自分の庭や家の中に飾る植木や花を求めてやってくる感じ。
近年ではその知名度があがったことで、花を売る屋台だけでなく、おいしいパン屋さんや趣味の良い雑貨や洋服屋などもたくさんできた。
通りの名前を意識してか、南米コロンビア産のコーヒーを扱うお店があったりして、花を買わずともなかなか魅力的な時間を過ごせるだろう。
5.点心をお試しあれ
ロンドンまで来て点心?と思うかもしれないけれど、旅行中いちどくらいはあなたも醤油が恋しくなるはず。
さすがに和食をたべるのは忍びないと思うのなら、ぜひ中華を食べていってほしい。
ロンドンにはおいしい四川や上海料理もあるけれど、やっぱりおすすめは点心だ。
Dim Sum Duck (Kings Cross近く)
たいていの点心レストランは予約を取らない。Dim Sum Duckはその中でもかなりの激戦の店。行列は長いし、店は狭い。

寒くない日、雨じゃない日なら張り出したテントの下で食べるのもありだけど、それでもお店のキャパシティはかなり狭い。
特に店内でゆっくり食事したいという人には向かないお店。
できれば、仲の良い、ずっと話し続けられる友達といって、行列を待つ間から楽しくおしゃべりするのがいいだろう。
Royal China
行列といえば、日本人には「ロイチャ」と呼ばれるRoyal China。
中華系オーストラリア人も、中華系マレー人も、そして香港系イギリス人の友達もみんなロイチャがいいというので、やっぱり一番認められているお店だ。
Baker Streetの店は開店の30分ほど前には行列ができはじめる。でもここはお店の広さが半端ないので、開店と同時に入れる人数もとても多い。それに回転もとてもよいので、大勢で行くとしても安心できる。
Queenswayのお店は残念ながら閉じてしまったけれど、行列はいやだな、という方はFulhamにいけば並ばずに食べられるかもしれない。
Dragon Castle (Elephant & Castle)
南の方にお勧めなのはDragon Castle。お店の雰囲気もいいし、行列もいらない。点心の種類もなかなか豊富で、おいしい。
Wing Tai (Brent Cross)
北ならやっぱり巨大中華スーパーWing Yipのレストラン。
あれ、この点心、さっき冷凍コーナーに売ってなかったっけ?という気もするけれど、まあそれはご愛敬。
Mandarin Kitchen (Queensway)
おなじQueenswayにあったRoyal Chinaが閉店してしまってからはここくらい、になってしまった。点心もある、けど、やっぱりここは「ザ、ロブスターヌードルの店」ではある。
6. PYOを楽しもう
PYOとはPick Your Ownの略。
Pick (収穫)Your Own(自分で)ということで、日本でいう「XX狩り」がごった煮になっている農園だ。
日本だったら冬から春にかけてのいちご狩り、秋のぶどう狩り、といったところだけれど、イギリスにおけるPYOは夏が勝負。


たいていのPYO農園は6月から9月くらいまでの期間限定。
その間にどんどんと採れるものが変わっていく。
ロンドンから気軽に行けるのはサリー州にあるGarson Farmだろう。
友達家族と一緒に行ったときは、ちょうどいちごとグリーンピースの収穫期。小学校にあがるか、あがらないかくらいの子供たちにとっては、収穫とはすなわちそのまま口に入れること。
いちごとグリーンピースの甘さは子供にはご馳走だ。
どう考えたって全部お腹の中ですよね、というくらい指も口の周りも真っ赤にしまくった子供たち。
大人もこっそり「味見」しつつ、でも、楽しく収穫して帰った。
そんな子供たちを見ても、計量小屋のおじさんは「おいしかったかい?」とニコニコだった。
なによりも採れたての野菜たちのおいしいこと!
とくに新玉ねぎの甘さ、アスパラガスのシャキシャキぶりには本当に感動させられた。
7.終点を訪ねて
子供のころ、渋谷駅も、目黒駅も、蒲田駅もみんな終点だった。
電車が「X」の印までゆっくりとスピードを落として近づいていき、プシューッと停車するあの感じ。
終点には、なんというか、ロマンがある。
モネだってそう思ったからこそ、きっと、サン・ラザール駅を何回も描写したのに違いない。

このサン・ラザール駅や北駅にパリのターミナル駅が代表されるように、パリには「パリ駅」や「セントラルステーション(中央駅)」といったものはない。
同じようにロンドンにも「ロンドン駅」や「中央駅」はない。
ミュンヘンの「München Hauptbahnhof」やニューヨークの「Grand Central Terminal」がドーンと中央駅として鎮座するのとは対照的だ。
19世紀、数多くの鉄道が首都ロンドンを目指して敷かれていった。
それぞれが競うようにロンドンへ到達した場所にターミナル駅(終着駅)を作ったので、イギリスのどの方角と繋いでいるかによって、それぞれの「ロンドン」がバラバラになった。
そういう意味では、東京も少し似ているかもしれない。
「東京」という駅はあるし、新幹線などは各方面へでるようになったけれど、昔ならば山梨方面には新宿、東北方面には上野といった個別の終点があった。
いまや相互乗り入れが進んだけれど、それぞれの私鉄の終点は、浅草、池袋、新宿、渋谷、品川と分散している。
ロンドンも、南イングランドへはヴィクトリア駅。
ウェールズなど西方面へはパディントン駅。
スコットランドや、イングランド北部のヨークやニューキャッスルへ向かうにはキングスクロス駅。
大陸へ向かうユーロスターはすぐとなりのセントパンクラス駅からといった感じだ。

それだけに終点もたくさん。
そしてその景色もさまざまなのだ。ここにいくつかおすすめをあげたい。
セントパンクラス駅
セントパンクラスの美しさはなんといっても鉄骨構造。
そして、新しさと古さが交錯するところ。
ユーロスターでロンドンに帰り着いた時の、「ああ終点まで着いた。ただいま」という気持ちで見上げる巨大時計はここならでは。

キングスクロス駅
そのすぐお隣のキングスクロス駅は、セントパンクラスのきらびやかさとは対照的な、質実剛健で地味な終点。

キングスクロスの良さは、ちょっと離れた目線のほうがよくわかる。
入線が真っ直ぐすっきりと終わっていて、広場があって、その先に主要道路が走っている。
頭上にガードなどがないので、その構成がとても整頓された美しさだ。

ちなみに本論とはまったく関係ないが、ここにいくと、ついでにハリーポッターの気分で壁に突入することもできる。
パディントン駅
ウォータルー駅やヴィクトリア駅など、増築などの影響で構造がゴテゴテになってしまっているターミナル駅も多いなか、エリザベス線などの新路線の延伸にもめげずその美しさを保っているのがパディントン駅だろう。
西側には乗り換え用の跨線橋がかかっているので、ぜひ。
そこから見下ろすと、売店やチケット売り場の高さからでは分かりづらい全体が見通せとても気持ち良い。

1番線のプラットホーム側にあるトイレの手前には、この駅で拾われたがゆえに駅の名前にちなんで名づけられたくまのパディントンが鋳物のベンチに座っている。
駅構内を離れて、運河へむかえば、青いパディントンも立っている。

パディントン駅で拾われたときには
まだダッフルコートを買ってもらっていなかったはずだけどね。
ウインザーリバーサイド駅
厳密にはロンドンから離れてしまうけれど、ウインザー城のおひざ元で、私の大好きな終着駅を。
ウインザーにはウインザー&イートンセントラル駅と、ウインザー&イートンリバーサイド駅いう二つの駅がある。
セントラル駅はその名の通り、街のど真ん中。ウインザー城の真正面に位置している。

でもその先かなりいかないと電車にはたどりつかない。
ずっとお店が続く。
美しいエントランスがある立派な駅のわりに、路線としてはスラウ駅からの支線が到着するだけ。
それに対して、ロンドン・ウォータルー駅からの直行電車が到着するリバーサイド駅は、路線として圧倒的に便利だけれど、到着するのは丘の下。
駅自体、いい意味でとても地味。
地に足がついている終着駅なのだ。


文字通りウインザーイートン橋のすぐ横、テムズ川のほとりにあるので、逆にイートン側の観光もすませて帰るにはとても便利な場所にある。
終着駅なのに大仰すぎないところが、とてもイギリスらしくて好ましい。
8.人生の終点。素敵な墓地たち
ロンドンに来て、驚いたことのひとつが、「散歩しに墓地に行く」というひとが結構いること。
親戚のお墓参りにいくわけではない。ただ墓石のあいだを歩いて、そこに刻まれたメッセージなどを読みながら歩くのが、いいらしい。
なにしろロンドン内の7大墓地のことは「マグニフィセント7(壮大な、素敵な7つの墓地)」なんて呼ぶほどだ。
Abney Park Cemetery
Brompton Cemetery
Highgate Cemetery
Kensal Green Cemetery
Nunhead Cemetery
Tower Hamlets Cemetery
West Norwood Cemetery
この「マグニフィセント7」はヴィクトリア朝のゴシック様式で作られた庭園型の墓地たちで、すべてセントポール大聖堂から直線約9キロの位置に計画的に作られたものだ。
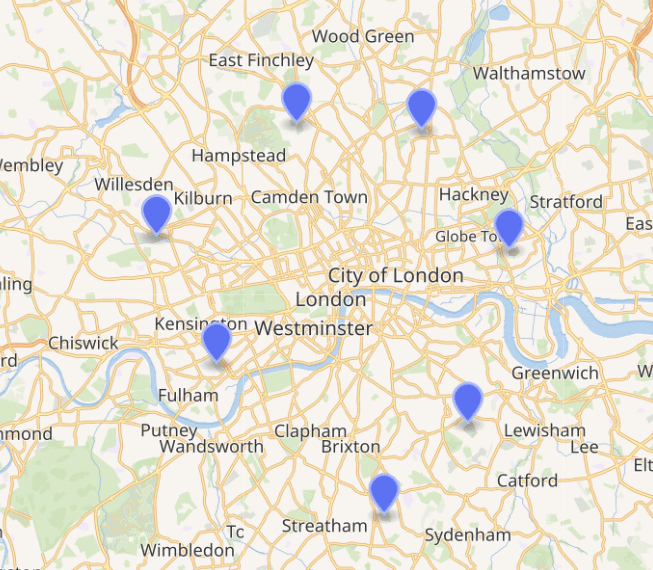
結果として、ロンドンの好立地なロケーションに、みっしりと茂る樹木や低木地、そして草原が広がる数少ないエリアを維持確保することになり、それが同時に野生動物の憩いの場にもなっている。
そんな中でも、お勧めなのはこの3つ。
ケンサルグリーン墓地
ロンドンで一番古く、いちばん広いのは1832年にひらいたケンサルグリーン墓地。
崩れかけた霊廟、緑におおわれた石像、傾いた石碑。
ヴィクトリア時代の劇作家や技術者などが葬られている
ハイゲイト墓地

ハイゲイト墓地は、ケンサルグリーンのすぐあと、1839年に開いた墓地。ここにもヴィクトリア時代のゴシック様式や、エジプト趣味が感じられる霊廟や墓石がある。
あまり日本人にはなじみはないが、哲学者カールマルクスのどーんと巨大な顔がのった墓石などがあることでも知られている。
でも、今はおそらく「ファンタスティック・ビースト」の撮影に使われたというほうが有名だろう。
ブロンプトン墓地

ブロンプトン墓地はWest of London and Westminster Cemeteryとして1840年に建造された。イギリスが世界経済の覇者であった1840~70年代の黄金時代を象徴し、装飾的な墓が作られ瀟洒な彫像などが飾られている。
そしてブロンプトン墓地だけは、王立公園のひとつとして王室が保有し開放している。
そういえばパリに行った時も、ヴィンセントが「せっかくだからモンパルナス墓地に行こう」といいだし、小雨の中散歩した。
そんな少し変わったところをめぐるロンドン観光も、時にはありかもしれない。
ということで、マイナー好きなあなたのためのロンドン観光8選。
ありきたりじゃつまらない!
もうロンドンは何度も行って、飽きてきた。
そんな方のために、どこかでお役に立てば、さいわいである。
いいなと思ったら応援しよう!

