
安いのに贅沢な気分が味わえるものとは?
昨年度末に転職をした。
もともとは学校の先生をしていた。
教室に行けば生徒たちとくだらない話で盛り上がり、とても楽しかったことを覚えている。
一方。
職員室はいつも居づらかったため、
目立たぬよう背中を丸く、
文句を言われぬよう無難なワイシャツを着て、
上司のつまらない話にも声を上げて笑い、
ああ、何が楽しくて毎日12時間労働をして週6日働いているんだろう
と、自分をなくしていった。
趣味と言えるものもなく、(作ったところで楽しむ時間などないのだが)
恋人と言える人もいない(家と職場の往復は何も生まなかった…)
「子どもが好きな人しか続かない」
「先生になりたいと強い願いがない人じゃなきゃ続かない」
どちらも自分のことだと思ったが、
心はすり減るばかりだった。
今は転職して、
超ハッピー!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
週休2日だし、給料は少し下がりはしたが割りに合うし、休憩時間も1時間きっちりくれるし、残業もない!!!!!!!!!!!!!!!!!
神ぃ~!!!!!!!!!仏ぇ~!!!!!!!!!!
ありがとうぉうぉうぉうぉう!!!!!!!!!!!!!!!!
といった感じだ。
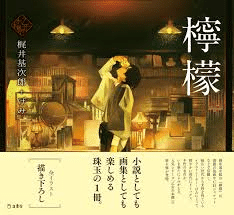
『檸檬』梶井基次郎著
【こんな人におすすめ】
〇 漢字で「レモン」って書けない人
〇 毎日が不安でたまらない人
〇 高校時代読んだけど「レモンが爆発した」こと以外覚えていない人
〇 仕事終わりに、安いもので贅沢を楽しんでいる人
〇 夢ならば?どれほど?よかったのでしょう?あれ?これってまさか…??梶井基次郎の『檸檬』のこと…!?の人
〇 高校時代この作品の伏線を回収しきれなかった人
これは以前わたしが学校の教材として毎年扱っていた作品。
「えたいの知れない不吉な塊が私の心を始終圧えつけていた」
とは有名な書き出しで、今でもわたしはこの表現を喜んで日常生活で使用する。
「えたいの知れない不吉な塊」
なんとなく…嫌な予感がする…なんか…わかんないけど…
みたいなとき、誰でもあると思う。
わたしはよくある。
先ほどもバニラアイスにチョコレートのリキュールをかけて食べようと意気揚々とカップのアイスをお皿に出そうとしたら、ぶちまけた。
なんとなく嫌な予感はしていた。泣いた。
とかそういう話ではなく、ここでの主人公は常に心に不安を抱えた状態で生きていた。
曰く「結果した肺尖カタルや神経衰弱がいけないのではない。また背を焼くような借金などがいけないのではない。いけないのはその不吉な塊だ」と書かれているが、文章をそのままの意味で捉えるのはなんだかナンセンスな気がする。
現実逃避。
不安になる理由はわかっているのにそのせいにはしたくない。
言葉では言い表せない「不吉な塊」のせいにする。
「二銭や三銭のもの――と言って贅沢なもの」
つまり「安いのに贅沢な気分が味わえるもの」を、ここでの主人公は好んだ。
でも、塵も積もればなんとやら。小さな贅沢が積み重なったらいずれ手に負えないほどの出費になる。
借金が増えていく。
そうやって主人公は心の中に不吉な塊を宿した。
癒されるのは件の果実。のちの「爆弾」。
「丸善」と「檸檬」が主人公にとってどのようなものを意味しているのか、巧みに比喩が使われているところがわたしは好きだ。
さらに最後の最後の一文。
「そして私は活動写真の看板画が奇体な趣で街を彩っている京極を下って行った。」
「京極」とは京都のこと。
現実逃避をし、丸善を爆発したことによって自身の心の中に始終あった「えたいの知れない不吉な塊」を解消した主人公は、再び「えたいの知れない不吉な塊」の元凶である京都に帰っていくというのがまた何とも言い難いほど、いい。
ハッピーエンドでないところがグッとくる。
「はぁ~すっきりした!!さて、新しい檸檬でも買ってレモンサワーでも作るか!!」とはならないところがいいとは思わぬか。
伏線やメタファーはいくらでもある。
梶井基次郎が意識していようといまいと、深堀りするのは面白そうだ。
ちなみにデジタル・ミニマリストへの道 第何日目かは忘れた。
最近はスマホにあまり触れていないので、仕事の休憩中にスマホを確認するのを忘れていた。本読まなきゃな~という頭しかなかった。
でもYouTubeは観たい。すっごく観たい。
下唇を噛みしめながら必死に我慢するとしよう。
