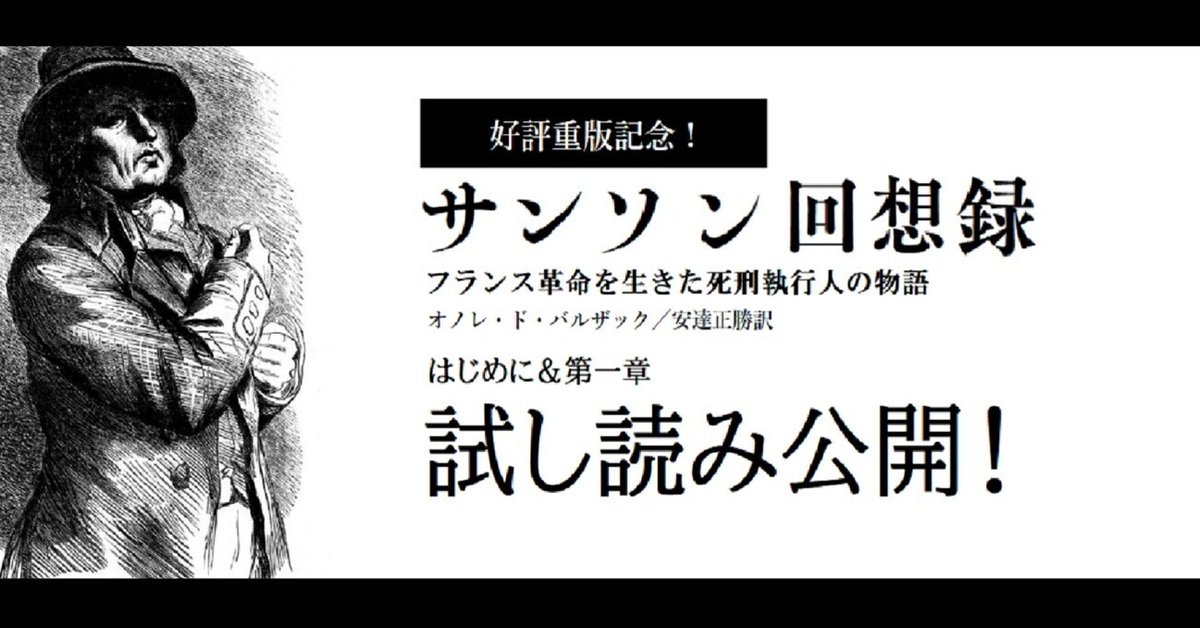
【ルイ十六世の処刑人、その数奇な運命の物語】『サンソン回想録 フランス革命を生きた死刑執行人の物語』試し読み(オノレ・ド・バルザック/安達正勝訳)
フランス革命時代、死刑執行人としてルイ十六世やマリー・アントワネットらを手にかけたシャルル‐アンリ・サンソンの数奇な運命を、フランス文学史上最大の文豪バルザックが描いた物語『サンソン回想録 フランス革命を生きた死刑執行人物語』(オノレ・ド・バルザック/安達正勝訳)の好評重版を記念して、本文試し読みを公開します!
訳者安達氏による「はじめに」と、本文第一章「死刑執行人の宿命」をお読みいただけます。
処刑人サンソンがバルザックの筆を通じて語る、己が辿った数奇な運命と職業への思いと、晩年に皇帝ナポレオン一世と出会う衝撃的な幕間の物語……とくとご覧下さい。
シャルル‐アンリ・サンソン(Charles-Henri Sanson 1739-1806)
フランス革命期の死刑執行人。処刑人一族サンソン家に生まれ、4代目当主として、1778年から〈ムッシュー・ド・パリ〉の称号を得て、ルイ16世、マリー・アントワネット、ロベスピエール、サン‐ジュスト、シャルロット・コルデら、のべ3000人余の人々を処刑したと言われている。多くの人を手にかけながらも死刑制度に反対し、その廃止を訴えていた。
はじめに
この『サンソン回想録』は、フランスの文豪バルザックが、四代目サンソン家当主シャルル‐アンリに成り代わって書いたものである。四代目サンソンはフランス革命期にパリの死刑執行人を務め、ルイ十六世やマリー‐アントワネット、ロベスピエールやサン‐ジュスト、ダントンらの処刑を担当した。いわば、フランス革命の影の主役、といった人物である。
バルザックがこの本の執筆に取りかかった頃、四代目サンソンはすでに亡く、五代目アンリ・サンソンの時代になっていた。サンソン家には歴代当主たちが残した手記、日誌、公文書、手紙など、多数の資料が伝えられていた。さらに、こうした文書資料の他、一族内で語り継がれてきた口伝の伝承もあった。バルザックはサンソン家からそれらの資料の提供を受け、五代目当主に会って話を聞き、自分でも独自に資料を収集し、『サンソン回想録』を執筆した。
この本を翻訳するにあたってまず最初に突き当たる困難は、バルザック自身によって確定されたテキストがない、ということである。
なぜ、そんなことになったのか、事情を説明する。
最初、1830年に『サンソン回想録』が二巻本で出版されたときは、バルザックとレリティエ・ド・ランという人物による共著であった。その頃、バルザックはまだ三十歳、新進気鋭、売り出し中の作家であったが、その後数多くの傑作を世に送り出し、押しも押されもせぬ大作家となった。つまり、時の推移とともにバルザックと共著者の評価に格段の差が生じ、共著者には気の毒だが、彼の書いた部分はあまり価値がないとみなされるようになった。
バルザックの死後、ある出版社がバルザック全集の出版を企画したが、『サンソン回想録』については、バルザックが書いた部分と共著者が書いた部分を振り分けるという困難な作業に直面しなければならなかった。この出版社はマルコ・ド・サンティレールという人物にこの作業を依頼した。サンティレールはバルザックとも共著者とも知り合いで、二人の執筆過程をよく知っていた。サンティレールは、バルザックが書いた部分とそうでない部分を見事に振り分けて見せた。以後、バルザック著『サンソン回想録』はこの選定にしたがって出版されてきたが、後の研究者たちから若干の異論が出るのは避けがたかった。
今回、私はコナール版とプレイヤッド版を参照した。コナール版が出たのは1935年、プレイヤッド版が出たのは1996年と、プレイヤッド版のほうが六十年ほど新しい。この本で「第十章」に相当する部分以外は、両者とも収録内容はまったく同じと言っていいほど、ごくわずかな違いしかない。解説、注に関しては、プレイヤッド版のほうがずっと優れている。
私は、プレイヤッド版を常に参照しつつも、基本的にはコナール版を底本とした。その理由は、コナール版はバルザックが書いた部分を「第一章」から「第十四章」までに整理し、バルザックが書いた部分だけで一冊の本にしようと努力しているのに対し、プレイヤッド版はバルザックが書いた部分を「第一巻第何章」「第二巻第何章」というふうにバラバラに羅列しているだけだからである。ただし、収録内容が大きく異なっている「第十章」相当部分に関しては、プレイヤッド版のほうが正しいと思ったので、こちらを採用した。
コナール版もプレイヤッド版も原著(最初二巻本で出された本)の注を踏襲しているが、表記がより詳しいコナール版では「原著編者注」「原著著者注」「原著注」の三種類に分けている。「原著注」と他の二種類の注との違いについての説明はないが、コナール版の表記に従った。この三種類の断り書きのない注は、すべて訳者による注である。また、章タイトルは、第八章以外は訳者がつけたものである。小見出しはすべて訳者による。
コナール版のタイトルは『不可触賤民の思い出』、プレイヤッド版のタイトルは『サンソン回想録』である。私はもともとのタイトルである後者を採用した。『サンソン回想録』のフルタイトルは『フランス革命期の刑事判決執行人サンソンによる、フランス革命史に貢献するための回想録』である。邦訳にあたり「フランス革命を生きた死刑執行人の物語」という副題を付した。
◆
第一章 死刑執行人の宿命
◆司法制度と世間の常識
◆ナポレオンに会う
司法制度と世間の常識
世の中には、どんな人生をたどるのか、あらかじめ定められている人たちが存在する。最初から最後まで、こうした人たちの人生はまっすぐな線をたどる。昨日行なったことを今日も行ない、明日もまた行なうだろうし、これからもずうっと同じことを行なうだろう。社会的にあらかじめ定められた人生とは、すべてこうしたものである。子供たちは先祖が定めた決まりに従うが、それというのも、社会が現状をよしとし、個人に対して固定した枠組みを設定するからである。その一方、社会によって枠組みを設定されない個人も存在する。
この地上に、どれだけの呪われた人々がいることだろう! そしてまた、どれだけの特権的人々がいることだろう! 高貴さの元を成すのは何なのかを誰が私に明かしてくれるのだろうか? そして、排斥は何に基づいてなされるのかを誰が私に教えてくれるのだろうか? 私はこうしたすべてのことを考えてみなければならなかった。私は、この世で名誉とされていることと恥辱とされていることについていろいろと考えを巡らせてみたが、考えるたびごとにいつも苦しい思いがつきまとった。
可哀相な不可触賤民よ、なにゆえにおまえの階級は社会から締め出されているのか? なにゆえにおまえの美徳をもってしても原初の汚(けが)れから救われないのか? おまえは生まれたときから汚辱の中に閉じ込められてきたが、父親は名誉ある人間だったと父親を誇りに思ってもきた。そして、息子としてのこの尊敬の念がおまえを一族に結びつけるさらなる絆となっているが、これはおまえにとって愛(いと)おしい絆であり、たとえこの絆を断ち切ることが許されたとしても、おまえがこの絆を断ち切ることはないだろう。おまえはどこへ行こうとしているのか? おまえはこれからどうなるのか? おまえは母親、弟姉妹を後ろに従えて共に生きてゆくのか? それとも、彼らを否認するのか? おまえは彼らの間に留まるがよい。彼らはおまえを愛し、おまえを求めるだろう。他の者たちはおまえを拒絶するだろう。孤立、それは死に等しい。
私は思うのだが、ここから数千里も離れた場所、中国の辺境、万里の長城近辺を除いては、どこでもユダ一族の末裔は唾棄嫌悪され、国民の埒外に置かれている。彼らは普通の市民になることができず、町では敵対的扱いを受ける。立法者は彼らの社会的境遇を改善しようとするが、偏見が彼らを突き落とす。理性は一つの声しか持たないが、偏見は千の声を持っていて、こちらのほうが影響力が大きい。大多数の者は闇であり、少数の者だけが光である。いちばんいいのは、自分に満足し、誰にも不満を持たないことだ。それが人間の条件のすべてであり、社会的条件以上のことだ。ともかくも、自分の良心に安んじることができれば、それで十分だ。
ヨーロッパのすべての国において、ボヘミアンはさ迷い、放浪し、恥辱にさらされている。哲学は、ボヘミアンに定住するように推奨する。しかし、偏見は「歩け、立ち止まるな」と叫ぶ。ある日、飢えと疲労にうちひしがれて、一休みする。そして、人を殺す。すると、今度は法律がそのボヘミアンを殺す。なぜ、法律はボヘミアンを殺すのか? それは、法律は哲学に由来するのではなく、偏見に帰着するものだからだ。
法律は思索の産物である。法律の基礎となるのは利害関係だが、しばしばピラミッドは頂点を下に逆立ちし、基礎がひっくり返されている。偏見の源(みなもと)を探るには、感情にさかのぼらなければならない。反感と嫌悪が産み出される根本には、何かしら真実めいたものがあることが多い。今日、真実と誤りを見分ける術(すべ)を誰がわれわれに教えてくれるのだろうか?
医師団の協議結果にしたがって、身体を救うために壊疽(えそ)になった部位を切除する外科医は、宮廷に迎えられ、もてはやされる。外科医は王侯の誕生の際に呼ばれ、死の際にも呼ばれる。外科医は王侯からありあまるほどの恩典を授かり、宮殿内を頭(こうべ)を高くして歩き、身分の高い人々から挨拶を受ける。外科医は、責任を問われることはなく、学識ある医師たちの意見に従っているだけだが、にもかかわらず、そうした医師たちと同等の敬意をもって遇されている。手先が器用でさえあれば外科医は非の打ち所がないとされ、たとえ器用さに欠けることがあっても、誰からも忌み嫌われることがない。手術が成功しようが失敗しようが、外科医は隠れはしないし、人から避けられることもない。体が接触するのを嫌って、通りすがりに身をかわされることもない。
判決を最終的に実行する死刑執行人も、あるべきこととあってはならないことを計る天秤を持っていない。人は彼に言う、「剣をとれ。裁判官たちを裁く至高の審判者の前において、流された血の責任を負うのは刃(やいば)ではない」と。なのに、なぜ、判決を執行する人間は司法官が着用する長衣を身にまとっていないのか? なぜ、彼はエゾイタチの毛皮で飾られた服を着て歩かないのか? それは、おそらく、社会というものは不滅なものだからであり、社会の一員を亡き者にする必然性は明白でないばかりでなく、証明され得ないからでもあろう。そしてまた、おそらくは、社会よりも聡明な人間の本性が抽象的なことのために現実の人間を消滅させることに憤慨するからでもあろう。社会は手でさわることが出来ないし、全構成員が一枚岩でもない。社会を構成する一個人が忌むべき存在になったからといって、それで社会が崩壊するわけでもない。司法の行為によって一構成員が排除されることは、団体・組織全体に関わることでもあり、それゆえにこそ、いつの時代にも「汝(なんじ)、人を殺すなかれ」が律法となってきたのである。
それに、何らかの悪事が犯されたからといって、それがどんなに重大なことであろうと、そのことによって社会全体が病むわけではない。ただ一時的な不調を来すだけであり、殺人に対して殺人を求める一般の声は、取るに足りない慰めしか社会にもたらさない。殺人によっては、問題は何も改善されないのである。カトリック信仰の中で育った私は、聖体秘蹟のパンをもらうために祈禱台の前に跪(ひざまず)くとき、いつも心が恐ろしく締め付けられるのを感じた。私はキリスト教の崇高な真実を信じてきた。固く信じてきた。けれども、その一方、告解の場で私に与えられる許しをそのまま信じていいものかどうか危ぶんでもいた。神父は、神の慈悲は尽きせぬものだと私に請け合ってくれたが、神父の寛容さあふれる言葉にもかかわらず、神父が赦免できない罪もあるのではないかと私には思われた。つまり、神父は私の迷いを取り除いてはくれたが、迷いの念は心引き裂く後悔のように何度となく戻ってきたのである。「汝、人を殺すなかれ」という戒律は、守れはしなかったものの、常に私の念頭にあった。禁じられているにもかかわらず、いつもそれを犯している、という思いがいつも私につきまとった。意思に関しては私は無垢であり、やむをえない「同意」を嘆きさえした。けれども、私は「そのこと」を遂行するように命じられ、それは遂行されるのであった。
ピラト〔*ピラトはローマ帝国の時代にユダヤ属州の総督を務めた。イエス・キリストの裁判に関与した人物として『新約聖書』に登場する。〕が宣告を下した後に手を洗い、もはや宣告のことなど気にもとめず、民衆に「このことについて考えるのは諸君の任務だ」と言っていた例に私も倣うことはできよう。しかし、私は自分でもこれについて考えてみざるを得ない。ピラトが自分が下した宣告を気にもかけずにまどろむことができるのは、法により近い立場にいるからだ。私が眠ることができないのは、剣により近い場いるからだ。ピラトにとっては毎夜毎夜が静謐(せいひつ)なものだが、私の夜は長く、安らかなものではない。ピラトの場合は、目覚めると賛辞に取り囲まれ、敬意の貢ぎ物がもたらされ、玉座の足下でも敬われる。私の場合は、太陽が輝き、陽を受けても、孤独が際立つだけであり、しかも、周りに人がたくさんいるがゆえに、この孤立感は恐ろしいものである。人々は、私を目にして身を震わせる。私は遠ざかり、暗闇に避難するが、私を取り囲む暗闇はさらにいっそう恐るべきものだ。暗闇の中にあるのは恐怖だけであり、死者たちとともに過ごすことになる。それは、私が内に抱える亡霊の世界である。私は、自分で自分が怖くなる。叫び声、嘆きの声が聞こえる一方、殺人を渇望する残酷な群衆の騒がしい声がする。燃えるような熱が私を襲い、体中の血が沸きかえり、息が詰まる。ひしめく群衆の怒号、騒々しい群衆の蠢(うごめ)きが、私に目眩(めまい)を起こさせる。私の神経は緊張と弛緩を繰り返す。私は目を背けるが、殺人は実行されてしまう。私は戦慄し、立っていられなくなり、足が萎(な)えるのを感じる。そして、私がうちひしがれて立ち去ろうとするとき、この上もなく残酷な苦しみに耐えているとき、その目が死の光景をむさぼろうと求めていた人々、満ち足りた人々、もし恩赦があったなら不満を感じたであろう人々は、自分たちが追い求めていた情動の下劣さを私に投げ返す。つまり、卑しいのは私であり、私の存在は唾棄すべきものとなる。私は、赤い雲の上に永遠の劫罰の言葉を見る――「さあ、今や、おまえは、受け入れるために口を開いた大地からさえも呪われるであろう……」
私は恐怖の対象なのだ。私を目にするやいなや、馬は耳をぴんと立て、狼が近づいてきたかのようにいななく。犬は私の服の臭いを嗅ぐと尾をたれ、田舎の住人が不吉な前兆と見なす遠吠えを天に向かってしながら離れてゆく。あらゆるものが私に敵対する。神はあらゆる生き物に生存本能を付与しているが、私はこの生存本能が予感する災い、災害のようなものなのである。私は恥辱と困惑に満たされた空間を抜け出る。やっと、終点にたどり着く。「汝、人を殺すなかれ」という言葉がもう一度耳に響く。私は家に駆け込む。子供たちが私に腕をさしのべる。私は、子供たちの愛撫を押し返す。子供たちの微笑(ほほえ)みが私を狼狽させ、うるさく、いらだたしく感じられ、うんざりさせられる。しかし、少し後には、それはなんと甘美なものになることか! 私の傷口に注がれる香油となるだろう。それでも、今日のところはとても耐えきれるものではない。
私の家の奥には神秘的な隠れ場所がある。一種の墓のようなところであり、子供たちが近づくことは禁じられている。私はそこに、明日にならないと魂を取り戻さない死体を埋葬するのである。つまり、明日には、苦しい夢を見ただけだということにしたいのである。こうして一晩寝ずに過ごすことが、私の日々を暗いものにする。私は、それが夢であったということにしたい。そうでなければ、とても生きてゆけるものではない。私は、生を、死を、疑いたい。私はこの世に存在しているのか、していないのか? そして私は、もう自分を嘆く必要がなくなるように、自分を無にしようとまでする。
あらゆる人生の中で最悪なのは、常に自分自身を忘れるように追い込まれる人生である。これが、社会が私に用意した状態である。不幸な状態であり、排斥は永続し、一族に世襲される。まるで正統性が王家に引き継がれるかのように。それでは、私は下層社会の王だとでも言うのか? そうならば、下層の王と至高の王とを隔てる距離はなんと大きいことか! 私はテミス〔*テミスはギリシャ神話の法・正義の女神。片手に秤を持ち、もう一方の手に剣を持っている。目隠し姿で表現されることが多い。〕の錫杖(しゃくじょう)は持っているが、その聖域にあるはずの玉座がない。裁判所は私の仕事を恥ずべきものだと思っているが、私は裁判所によって産み出されたのではないのか? 私は手に触れるすべての物を汚(けが)す。油のしみのように、世代から世代へと汚れはどんどん広がってゆく。伝統の糸が切れない限り、汚れは子孫に受け継がれてゆく。私の手が汚辱を印すわけだが、それは法の名のもとに下される個人への罰だ。だが、社会は汚辱を伝染させ、不治の癩病にする。社会は罰する術も自浄する術も知らない。社会は復讐し、身を汚す、というだけのことだ。社会は私の境遇に冷酷だが、そもそも、私の境遇は社会が不条理で無慈悲であることから生じている。社会を情け深いものにするのは私の仕事ではない。もともと、社会には憐憫の情などない。しかし、社会の過酷さの担い手であることがどれほど大変なことかを余すところなく社会に示すことによって、そうした過酷さは不必要だと思い知らせ、その思いを強化し、広めることには貢献できるだろう。
もし犯罪判決の執行人が忌み嫌われるならば、もし彼がすべての人間の中でだれにとってもいちばん忌まわしく嘆かわしい人間であるのならば、もし彼の同胞が身内の中にしか存在しないのならば、もし世論が彼を社会関係の外に放逐するのならば、現今の刑罰制度はどうにも正当化され得ないということであり、刑法学者が目指す目的とはまったく正反対の結果になっているということである。
世間に代わって復讐する人間を見つけるために、思考する存在を無感覚にすることを思いついた最初の者は、もっとも恐るべき罪を犯した。その者は、天地創造の傑作である人間を堕落させ、神に対してもっとも大きな侮辱行為を行なった。というのは、その者は、卑しめるために神の創造物を選んだからである。殺人を職業として確立させ、社会の復讐者に永遠の自殺の苦しみを付与し、生涯にわたって世間のさらし者にしようというのは、地獄のような考えだ。
私は六十歳を越えている。私の苦しみは長くつらいものだったが、私の後に続く子孫たちも同じ苦しみを味わうだろうと思うとそれが心底堪(こた)えて、私の苦しみはさらに増大する。たとえヒューマニスムが勝利を収める日が来ても、それは遅きに失するであろう。フランス革命の嘆かわしい経験以前にも、ヒューマニスムを果敢に説く人々はいた。フランス革命は過ぎ去ったが、革命が陥った深淵から崇高な思想は生じなかった。どんなにひどい悪弊も、慣習の恐ろしさを白日の下にさらすには十分ではなかった。つまり、死刑制度は廃止されなかったのである。大勢の人間が処刑されたが、犠牲者の数を加算することは行なわれず、あれほど多くの嘆かわしい犠牲者が倒れた哀悼の野が壁で封じ込められることもなかった。法は今も人間の犠牲を求めている。法は、生け贄を産み出す人たちの終身的中立性を保証し、保護する存在であり続けるために、人間を犠牲にしている。未来がどうなるかは私の知りうるところではないが、もし、凶悪な犯罪に対して下される死刑判決がいったんわれわれの法体系から駆逐されたならば、どんなに過激な政治的主張も救済手段として死刑制度を復活させようとすることはないのではないか?
あの不運なルイ十六世は、自分を裁く者たちの前で無実を訴え続けた。しかしながら(告発者たちの言葉を借りて述べるのだが)自白ないしは共犯者の告白を引き出すために執拗の極みに達したにもかかわらず、ルイ十六世を拷問にかける提案がなされるまでには至らなかった〔*ルイ十六世の裁判は裁判所ではなく、国民公会で行なわれた。裁判官の役割を担ったのは国会議員たちである。ルイ十六世は、フランス革命前に、それまで裁判の一環として行なわれていた拷問を王令によって禁止していた。だから、ルイ十六世を拷問にかける提案はなされ得なかった、したがってルイ十六世が拷問禁止にとどまらず、死刑廃止にまで踏み込んでいたならば、死刑の提案もなされなかったのではないか、というのがサンソンの論調である。〕。どうしてルイ十六世は処刑台を覆しておかなかったのだろうか? そうしておけば、ルイ十六世の不可侵性があらゆる攻撃を退けたことであったろう。死刑制度を廃した君主に対して、暴君的考えを抱いていたという非難を試みた者はだれであれ、満場一致の嘲笑にさらされて面目を失ったことであったろう。このときに忌むべき刑罰を復活させようという動議を出すには、どれほどの信じがたい卑劣さが必要であったことだろう! このようなイニシアティヴを担うことを引き受けた人物に対して、どれほどの悪辣さが想定されたことだろうか! 国王に対して科すべき刑について国民公会が論議していたあの時に、たとえば、ブルボット議員が立ち上がり、フランスを取り巻く状況の深刻さを理由に、死刑の必要性を声高に主張したとしよう。もし、この刑罰が、国王によって採用され布告された真にキリスト教的な体系の唯一の例外として提起されたとしても、議会内においてもフランス全土においても、この種の提案を退けるためにどれほど大きな怒りが渦巻いたかしれないこと、間違いない。ブルボットの声はヤジにかき消され、寛容な哲学を総動員しても、常軌を逸した人間の振る舞いと見なされることによってしか、彼は許されなかったことだろう。しかし、残念なことだ! この点に関しては私以上に嘆いている者はいないが、ルイ十六世は自分の心の思うところにしたがわなかった。ルイ十六世は、数々の困難に見舞われた時期に自分を救うことになったであろう唯一の息吹にしたがわなかったのである。
私が今述べている考えは、思索することができるようになって以来、一貫して変わらない考えである。私の長い職業生活の全過程において、私はいつでも同じ願い、同じ信念を抱き続けてきた。まだ半年もたっていないが、非常に得がたい邂逅(かいこう)を利用してこうした考えを表明する機会があった。
ナポレオンに会う
私はマドレーヌ寺院の境内にいた。法令によって、この寺院が何に捧げられるべきものか変更されたばかりだった。建物の周囲を整理する作業が始まっていた。私は何頭かの馬を持っていたが、何の用途にもつけずに飼っておくほど裕福ではなかったので、この工事に雇われている荷馬車引きに馬を貸していた。この男が馬を荒っぽく扱っているという報告を私は受けていた。事実を自分で確かめようと思ったが、相手に見られるのは嫌だったので、雑然とした工事現場に立っていた石柱の陰に身を落ち着けた。私は本を開き、土木作業人たちが仕事をしている場所にたまに目をやっていたが、そのうち読書に没頭してしまい、心地よいある種の幻想に身をゆだねていた。『ローマの夜』という詩集のある章に夢中になって我を忘れ、もうここにやって来た目的のことはすでに考えていなかったその時、私は騎馬の一団の物音によって夢想から現実に引き戻された。騎馬の一行は、通りに沿う板囲いの入り口のところで止まった。やがて、急ぎ足で歩く三人の人物が私がいるほうへとやって来るのが見えた。彼らは何か話していたが、会話は大いに盛り上がっているように見えた。
「作業現場は、いったい、どこなんだ?」と三人の中でいちばん小柄で質素な服装をした男が言った。「大変な混雑ぶりで、石切場全体がここに移されたという話を聞いたんだが」
「のこぎりの音が聞こえませんか?」
「一つ、二つ、三つ、四つ、それ以上ではないな。建築業者諸君は、いったい何を考えているんだ? パリの人々にとってはこれほど甘美な音楽だというのに!」
「工事現場に石がある間は、パンはけっして高騰しないものだ」
こうした会話の間、話し手たちは歩いていて、私はと言えば、ごく自然な好奇心に駆られて彼らと平行に歩いて後を追っていた。四角い柱列を支える巨大な花崗岩の傍を私は注意深く歩いた。
「見たまえ」と、作業員たちが巨大な石塊をコロに乗せようとしている現場のすぐ近くを通りかかったときに、小柄な男が鍔(つば)の広い帽子を目深にかぶり直しながら言葉を継いだ。「あの連中はやり方を知らんな。連中の中には砲兵は一人もおらんようだ。やれやれ! 一つ教えてやる必要がある」
「お怪我をなさるといけません」と、一行の中でいちばん若い男が言った。
「何も心配するな」と小柄な男は答えた。「力仕事のやり方は覚えている」
「大事なお体を危険にさらすのをわれわれは見過ごせません」
「建てようとしているのは、栄光の殿堂〔*マドレーヌ寺院は「栄光の殿堂」となる予定だった。〕ではないのか? フランスのだれもが手を貸すべきだ」
こう言うと、小柄な男は作業員たちに近づいていった。
「やあ諸君、難儀しとるようだな? 地面に板を敷くんだ。そして、コロの数を減らすんだ。そうすれば、摩擦が少なくなる。それと、人員配置の仕方もよくないな」
「どうだい、俺が言ったとおりだろう」と、作業員の一人が軍隊式に敬礼しながら満足げな様子で叫んだ。その男は片足が木の義足だった。
「あなた様は軍隊経験がおありですね?」
「そのとおり。で、あなたもですね? どんな部隊にですか?」
「砲兵部隊、ちび伍長〔*ナポレオンはかつて、兵士たちから親しみをこめて「ちび伍長」と呼ばれていた。〕の連隊ですよ」
「私もですよ。で、あなたはエジプトに行きましたか?」
「何ですって、私がエジプトに行ったか、ですって! 私はマルタ島を見ましたし、アレクサンドリア、ピラミッド、ポンペイウスの柱、ジョゼフの井戸、聖母の家も見ました」
「私もですよ」
「で、私はブラックで片足を失いました。そこの暑かったことといったら、ひどいものでした」
「皇帝はちゃんと報いてくれたんでしょうね?」
「はい、二百五十フランの年金をいただいています。大した額ではありません。それだけですと、女房と子供たちがいる場合は、ツルハシを振るわなくてはなりません」
「お子さんたちは男の子ですか?」
「女の子なんていうのは、どうにもなりません。男の子、いつだって男の子じゃなくっちゃ! 男の子は大きくなったら、父親のようにするでしょう。国に仕えるでしょう。もし砲弾が飛んできら……」
「あなたは十字勲章を申請すべきです」
「ああ、そうですね、申請するんですね。で、だれに申請するんです?」
「皇帝にです」
「それはダメですよ。私にもう一本足があれば、できますが。だって、そうじゃありませんか、十字勲章はなお戦える人たちのものです」
「ご存じないようですな。戦傷者用の十字勲章というのもあるんです」
言葉を奇妙に強調しながら小柄な男は言った。それから、一緒にいた二人の人物の一人のほうに振り向いた。
「アレクサンドル」と彼は言った。「この砲兵の名を書き留めておきなさい。お名前は?」
その質問は義足の男に向けられていた。
「ジャック・フォワサックと申します。コレーズ県出身です」
「素晴らしい県だ、兵士と鉄の産地だ」と小柄な男は叫び、急いで付け加えた。「私はナポレオンに少し顔が利(き)く。彼は私を知っているんだ。明日、パレードの時間に来たまえ。廃兵院の傷痍軍人二十五人にレジオン・ドヌールの鷲が授与されるんだ。あなたも隊列に加わりなさい。われわれがあなたを推薦しよう」
「大変ありがとうございます、大尉殿、大佐殿、将軍様……」
「よろしい、よろしい」
「何という恩義を負うことになるのでしょう! ああ、仰せのことを忘れることはないと請け合います。軍服は正装がよろしいですか、それとも略装のほうが?」
「お好きなように」
「私はあなた様のご命令に従いたいのです、元帥閣下。と申しますのも、私をご覧になっておわかりでしょうが、私は軍服をまだ持っています。それは新品どころではありません」
「火薬の臭いがするのではありませんか?」
「はい、そうなんです。われわれ全員が好きな臭いです。丸刈りのちび〔*「丸刈りのちび」も親しみをこめたナポレオンのあだ名。〕のことは何もおっしゃいませんね。あの方は火薬の臭いが好きなんです。あの方に私のために話してみてください。きっと、私のことを思い出すでしょう。砂漠の真ん中で、あの方は私の水筒から水を飲んだんです。まあ、なんと喉が渇いていたことでしょう」
「思い出すでしょうよ」と、小柄な男は感動の様子で言った。
「そうでしょうとも、みんな喉が渇いていましたから。喉がからからだった、私も他の人も。でも、私はあの方に水をあげたんです。このフォワサックがいなかったら……」
「思い出すでしょうよ」と、小柄な男は繰り返した。
言葉に幾分か力がこめられていたが、そこには自己非難から生ずる居心地の悪さが混じっているように私には思われた。この後、小柄な男は記憶をたどる人間が見せる不動の姿勢のまま無言でいた。それは一分ほど続いた。それから急に腕を後ろに回し、背中で腕を組んだ。
「さあ、諸君」と彼は言った。「散歩を続けよう。この人たちの仕事の邪魔をしてはいかんからな」
彼は数歩歩いて、また立ち止まり、チョッキのポケットを探り、何かを取り出して匂いを嗅ぎ、厳粛な調子で次のような考えを述べたが、それは私を考え込ませた。
「諸君も聞いたことがあるだろうが、皇帝は流すべき血がない軍人を見捨てると主張する者たちがいる。もしこんな意見が一般に信じられたなら、危険なことだ」
「栄光の殿堂は、戦死者のためのものです」と、三人の中でいちばん年上の男がすぐに応じた。
「この殿堂は生きている者たちを感化するでしょう」
「そのとおりだ。だが、いつ完成するんだ? 五十年後か。いつまでたっても、だめかもしれん。建設費用はたっぷりある。栄光の殿堂には銀行家がついている。イタリア、オーストリア、オランダ、プロシアだ。ところが、建築家たちときたら吞気なもんだ。連中のやり方で行くと、法令で決定された殿堂は計画倒れになる恐れもある。それに、これから先は……」
私は聞き耳を立て続けていたが、いくら注意深くしても無駄だった。強く吹き始めた風が逆向きになったのである。時々音を拾えるだけだったので、はっきりと見える唇の動きから類推し、想像力を働かせて意味のある文章にしようとしたが、ダメだった。私はじりじりした気持ちで会話の場所が変わるのを待った。すると、大変嬉しいことに、三人は一種の納屋のようになっている方へと移動した。そこはヴォージュ県の大理石を切る石工たちの作業場になっている場所だった。誰か親切な人がこの作業場のドア代わりになっている粗末な荒布を持ち上げると、小柄な男は急いで真っ先に入っていった。荒布がまた落ちると、私にはもう何も見えなかった。そこで私はだれにも気づかれずにまた近づき、そのテント小屋のようなところの中に私自身もいるのと同じくらい明瞭に問答を聞き取れるようになった。やさしいけれども重々しく威厳ある声から、質問しているのが誰かはっきりとわかった。
「ここには何人いますか?」
「六人ですが、明日は三人しかいなくなるでしょう」
「いったい、なんということだ! 工事の進み具合が遅いのも当たり前だ。エジプトのピラミッドはほんのわずかな資金で作られた。この国では山のような金貨が投じられているのに何もせんというわけだ。我が国の建築家たちは、取り壊しに精通しているだけだ。いかさま師だ。連中は、城を解体しては金を儲ける。クレジュス〔*クレジュスは巨万の富を有したリディア王。〕のような連中だ。――ところで、諸君、何か不満はないか? ちゃんと鶏肉は食べているかね? 賃金はいくらくらい?」
「場合によります」
「ああ、わかった、出来高払いだな。その場合、どれほど稼げるのかね?」
「七フラン、八フラン、いい仕事で、ワインが高いときには、十フランまで稼げることもあります」
「十フランとは、ずいぶんいいじゃないか。大隊長の給料と同じということをご存じかな?」
「高すぎるとお思いですか?」
「そんなことは言っていない。まったく逆だよ。汗は報いられなければならない。職人は、望むときに家族を持ち、余裕を持てるようでなければならない」
「それは、あなた、しっかり稼いだ報酬ですよ。私は思う存分寝るというふうにはいきません。朝の三時から夜の九時まで仕事です。まったく、冗談じゃない。犬のような生活です。少しは楽ができればいいのですが……。いつも座って腕を動かす、これに耐え続けるには鉄の胃袋が必要です。そして、吸い込む埃、これが命を縮めるんです。私がノコギリに水をかけられるようにと、わざわざご親切にもお越しくださったんですか?」
このとき、私は誰かに肩を叩かれた。振り向くと、髭をはやした大男の顔が目の前にあった。その男は私の喉元に摑みかからんばかりに近づき、トルコ風の短剣の切っ先を私の胸に突きつけた。同時に、外国人訛りのその見知らぬ男は恐ろしい呪詛の言葉を投げつけながら私を人殺しと呼んだ。
「来い、俺について来い」と、その男は言った。「もしご主人様が望めば、おまえの首、切る」
私は引っ立てられたが、相手は完全武装していたので抵抗はしないようにした。
「悪党め、おまえ、ご主人様、殺そうとした」と彼は言葉を続けた。「悪党め、おまえ、もう終わりだ。おまえ、俺のご主人様、殺す、おまえ、死ぬ!」
告白するが、私は恐ろしかった。そうあって、当然だろう。私が何をしたというのか。私にはやましいことは何もなかった。しかし、私と同じ仕事に携わっている人間の中に、突然の恐怖を感じることがないほど強い人間はいない。それは幻影のせいか、それとも、不吉な影、怒った死者たちの魂のせいか? 消滅した王政の「聖なる場所〔*聖なる場所とは、ルイ十六世とマリー‐アントワネットが処刑された場所のこと。〕」が近いことが私を恐怖ですくませた。王家の人々を手に掛けたのは、この私であることが、改めて想起された。しかしながら、まだ昼だった。それでも、まったく思いもかけない出来事だったし、とても異常な状況だったので、私は混乱し、すっかりわけがわからなくなった。いかなる宿命によってかはわからないが、私は死を恐れてはいなかったので、人間の復讐という考えは浮かばなかった。しかし、私を捕らえて放さない悪魔の爪の下で、私は準備なしに神の前に引き出されるのをひどく恐れていた。数々の贖罪の意識が一斉に私に襲いかかり、恐るべき混乱の中に私は落ちていった。
私の理性がこうした苦悩に陥っているときに、ある動きがあり、そのおかげで私は正気に返ることができた。人々が駆け回り、私から遠くないところで「皇帝だ! 皇帝万歳!」という叫び声がわき起こり、何度も繰り返されたのである。これで私はすべてを理解した。どのような順路で高いところから降りてきたのかわからないが、私はいつの間にか地面に立っていた。私は、まったく予期していないときに小柄な男の前に連れて行かれた。彼が微笑んでいるのに私は気づき、それはいい前兆であるように思われた。彼の目の中に陽気な煌(きら)めきが見て取れた。
「諸君のおかげで目が回りそうだよ」と彼は周りを囲む人たちに叫びかけていた。「よろしい、よろしい。もう十分だ。諸君にナポレオン金貨百枚進呈し、私は祝杯をあげるとしよう」
歓呼の声が倍加した。まだだれも私にまったく注意を払っていなかった。しかしながら、私はみんなに見せるべき捕虜だった。建築資材で雑然としているところに私がいたことは、たぶん何らかのミステリー、何らかの犯罪的陰謀を隠しているのだろう。私は統率者のところに連れて行かれた。私を見て、彼は気むずかしい馬のように身を震わせ、額を曇らせた。私のほうは、冷静で、すっかり落ち着きを取り戻していた。良心に一点の曇りもないことが私の顔に表われていたと確信する。
「この男はだれだ?」まだ私がかなり離れたところにいるときに皇帝は尋ねた。「たぶん、ふくろう党〔*ふくろう党はフランス西部で反乱を起こしていた王党派反革命集団。〕か、イギリスから送られた殺し屋だろう。――ルスタン〔*ルスタンはサンソンを連行した人物。エジプト遠征時にナポレオンに服したマムルーク。〕、おまえの捕虜をよく見張ってろ」
「逃がしはしない。―― 動くな、さもないと、俺、首切る!」
そして、この恐ろしい命令をしながら、ルスタンは着ていたたっぷりとした外套の下からマムルーク風のサーベルを取り出し、それを勝ち誇ったように振り回した。皇帝と一緒にいた高官たちは急いで私の身体検査に取りかかった。高官たちというのは、アレクサンドル・ベルチエ公と宮廷侍従長ジェラール・デュロックである。彼らは疑いを抱かせるような何物も見つけられなかった。小冊子『ローマの夜』は、何か手がかりになる紙でも挟まれていないかと、非常に念入りに調べられた。私には、型どおりの尋問がなされるだろうということがわかっていた。すでに説明しようと試みたが、口を開こうとするたびに、マムルークが「黙れ、さもないと、俺、首、切る」と言って私を黙らせた。
私はほとんど裸同然だった。この状態では何も危険はないとわかって、皇帝は私から四歩のところにやって来た。
「名前は?」権力者の計算ずくの冷たさをこめて言った。
「サンソンと申します」
彼は首を肩に引っ込めながら眉をしかめた。私の名前が特別な印象を与えたことは明らかだった。
「私がここへやって来たとき、あなたは何をしていましたか?」
「本を読んでいました」
彼は幾分か機嫌を直し、心配げな額の曇りが消えた。
「あなたは何者ですか?」と言葉を継いだ。
「犯罪判決の執行人です」
口に出して言ったというよりは、思わず漏らしたようなこの言葉に、幕僚長は急激な嫌悪感に駆られて手に持っていた本を投げ捨て、私のすぐ傍にいた宮廷侍従長は恐ろしげに後ずさった。このときマムルークがどういう心境だったのかは知らないが、私に対する態度はもはや敵意あるものではなかった。彼は好意をこめて微笑み、アジア人的賛嘆の表情を浮かべて私を眺めていた。
皇帝陛下は動揺して身をひきつらせ、それを隠そうと努めていたが無駄だった。
「私はジャファで癩(らい)病患者に手を触れたことがある……」と彼は小声でつぶやいた。
私が登場しているこの場面は、私にとってまったく屈辱的なものでしかなかったのだから、陛下は私を好人物だと思ったようだと言っても、それは虚栄心からではない。
「この老人は、しかしながら、人の好さそうな顔をしている」
「どうやら、デュロック、彼はあなたを怖がらせたようだな? ――彼を離してやれ」と皇帝はすぐに私の番人に命じた。
それから、すぐに考えを変え、
「ちょっとお尋ねするが、サンソン、あなたはいつから仕事に就いていますか?」
「一七七八年からです」
「すると、あなたですか、九三年に……?」
彼は終いまで言わなかったが、以前墓地があった囲いを私に指し示した。私は目が曇り、涙を拭くためにハンカチを取り出した。
「ああ! あなたなのですね」と言葉を継いだ。「それでですね、もしまた国民公会のようなものができて、彼らが不遜にも……?」
「陛下」深々とお辞儀をしながら、私は答えた。「私はルイ十六世を処刑いたしました」
頭を上げたとき、私は皇帝陛下が恐怖にかられている兆候を認めた。目が固定し、唇が震えていた。まるで、最後の瞬間の死刑囚のようだった。皇帝は身動きもできずに立ちすくんでいた。
「彼はわれわれ全員をギロチンにかけるだろう!」とヌーシャテル公〔*ヌーシャテル公とは、アレクサンドル・ベルチエのこと。〕が叫んだ。
「行こう!」茫然自失の状態から抜け出したナポレオンが言った。
そして、彼らは立ち去った。
私は強力な一撃を与えたはずだった。私が意図的にした返答から生ずるであろう考察に、私は大いに期待した。冠をかぶったナポレオンの頭の上に私が吊したのは、単なるダモクレスの剣ではなかった。私が吊したのはずっと重い剣で紐につながれているが、ひとたび政治的混乱が起これば、その紐はだれの頭上でも切れ、結び直されてもいつ切れるかわからないものなのである。私は楽観的に期待していた――皇帝は知恵を働かせ、味わった恐怖心から有益な考察を引き出し、この鋭い剣を急いで打ち砕くだろう、と。この鋭い剣は、哲学と宗教に反して野蛮な法制度が法典の要約、社会基盤の要として維持してきたものだ。死刑制度、そして君主を殺害するように運命づけられている人間の役職を永続させる危険が、われわれの会見の結論として出てこないのは不可能だ、と私には思われた。
ナポレオンは、実際、茫然自失として立ち去っていった。しかし、日々の生活においては次々に新しい印象が生じ、急速に入れ替わるものだから、直ちに決断に変わる考えのみが有効である。私は、『モニトゥール』紙〔*『モニトゥール』紙は政府系の新聞。〕に次のような言葉で記された法令が出るのを待ち受けていた─ 死刑制度は最後的に廃止された。
その後、私の率直さはただ一つの結果しか生まなかったことを知った。つまり、翌日表彰されることになっていた二十五人の傷痍軍人の昇進を忘れさせたという結果である。そしてまた、あの律儀なフォワサックになされた約束も忘れられた。あの人物は記憶に留められるべき価値があったというのに。つい最近、彼は勲章を帯びることなく死亡し、栄光の殿堂の階段には雑草が生えている……
〔*「栄光の殿堂」は途中で建設が中止された。〕
〈続きは書籍版へ〉

オノレ・ド・バルザック
『サンソン回想録 フランス革命を生きた死刑執行人の物語』
(安達正勝訳)
2020/10/16刊行
四六判 ・総336頁
ISBN978-4-336-06651-0
定価:本体2,400円+税
装幀:コバヤシタケシ(Surface)
【著訳者紹介】
オノレ・ド・バルザック
フランス文学を代表する作家の一人。1799年生まれ。ロマン主義・写実主義の系譜に属する。現実の人間を観察することが創作の出発点だが、創造力を駆使して典型的人間像を描きあげる。歴史にも大きな関心を持ち、歴史的事実から着想を得ることも多かった。様々な作品に同じ人物を登場させる「人物再登場法」という手法を用い、膨大な作品群によって「人間(喜)劇」と名づける独自の文学世界を構築しようとした。代表作は『谷間の百合』。豪放な私生活も伝説的に語り継がれている。1850年没。
安達正勝 (あだちまさかつ)
フランス文学者。1944年岩手県盛岡市生まれ。東京大学文学部仏文科卒業、同大学院修士課程修了。フランス政府給費留学生として渡仏、パリ大学等に遊学。執筆活動の傍ら、大学で講師も務めた。著書に『物語 フランス革命』『マリー・アントワネット』など。
■話題沸騰の『Fate/Grand Order』シャルル=アンリ・サンソン特装オビ付き版も、好評出荷中です!(2021/1/18現在)


サンソンマスターの方は、お見逃しなくどうぞ!

※こちらの画像↑を保存または印刷して書店員さんにお見せいただくと、スムーズにご注文いただけます。
■キャンペーン詳細→『サンソン回想録』FGO特装帯キャンペーンのお知らせ
担当:国書刊行会編集部(昂)
