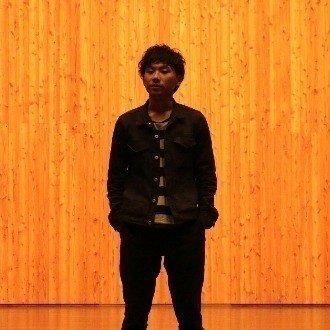【建築学生へ!】設計弱者の私が 1位 を取った8つの手順 0:設計の手順 その伝えかた
【「0」と「1」のみ期間限定で全文無料公開中】
こんにちは、高橋向生です。
今日紹介するのは、建築学生がいちどは悩む。設計課題への取り組みかたです。
基本的な考えかたや、設計を考える手順、コンセプトの考えかたなどを紹介していきます。
全体で8部構成されていますが、読みごたえがある記事なんで、ゆっくり読んでいってください。
今日の記事は「目的」と「設計手順」を話して、サラっと終わります。
目的
僕の目的は全国の大学で設計課題のレベルアップが目的です。
お恥ずかしい話、僕は設計が得意じゃありませんでした。
やる気だけが空回りして、みんなと違うことを考えたく、いっつも変な言葉と変わったコンセプトで設計に挑んでいました。
まあ当然、そんなので設計がよくなるわけもなく、苦悶の日々をすごしてきました。
そんなある日に、どうやってコンセプトを考えるかという視点ではなく、
なんでそのコンセプトなのかという根源を考えるようになりました。
そう思ったときに今まで自分が
「こうなったらいいなぁ」
「この提案面白いんじゃね」
「この敷地には、こんな問題点があるから、それを解決させるこのコンセプトでいこう」
といった表面的な薄っぺらい提案や、それっぽい敷地調査の問題点からコンセプトを考える程度の、浅はかな考えで設計していることに気付きました。
なぜそのコンセプトなのか。なぜそれが問題なのか。なぜその問題を取り上げるのか。なぜプログラムはそうあるべきなのか。
と、なぜを繰りかえすうちに、建築の本質とは、機能の本質とは何なのかを考えていくようになりました。
そのときに、本質から設計をかんがえること。それを順序よく分かりやすく伝えることの大切さを知りました。
それら二つを重視して設計課題をこなすうちに、段々とあいてが理解をしめすようになり、設計のレベルもあがっていきました。
これをマニュアル化して、広められたら建築学生全体のレベルアップにつながると思い、今回noteで書くことにしました。
ただ、あくまでこれは僕の設計手順です。
全員が全員、そのやり方で成功するとは思っていません。
なので、それぞれが建築の本質を見極め、それぞれの考え方で設計手順を考えていけたらなぁ、と思います。
設計を考える大まかな手順
今回は設計を考える手順だけを話しておわります。
細かい内容は次のコラム「建築の機能(プログラム)の本質」についてお書きします。
1 本質:建築の機能(プログラム)の「本質」を見抜く。
2 問題:それに対し、本質からずれた「社会問題」を提起する。
3 調査:社会問題が起きている計画地の関係性などを「敷地調査」する。
4 動機:社会問題を解決させる可能性(動機)を計画地から探る。
5 概念:計画地の可能性を発揮させる概念(コンセプト)を決める。
6 構成:コンセプトを形にするため、どうやって形づくるか。
7 計画:構成に基づいた配置計画、動線計画など、大まかな図面を描く。
8 設計:計画された図面に寸法や数値を入れ、具体化させる。
9 模型:完成された図面を元に、模型に起こし、三次元で認識させる。
これらは、設計を考えるときの手順ではありますが、相手に伝える手順でもあります。
この順番で、小説をかくように、ストーリー展開を意識して話すと伝わりやすくなります。
話を1本の線でつなぐように、前後の話が連結して話すと分かりやすいです。
最初の本質については下の「1 建築の機能(プログラム)の本質」をお読みください。
建築設計の実力を付ける勉強法も紹介しております。
一度は調べてみたい建築家を100人以上 一覧にしました。
自分の好きな建築が見つかる記事になります。
サポートして頂いたお金で知識を蓄え、より良い記事を書けるよう頑張ります!