
2024年読んでよかった本
センスの哲学
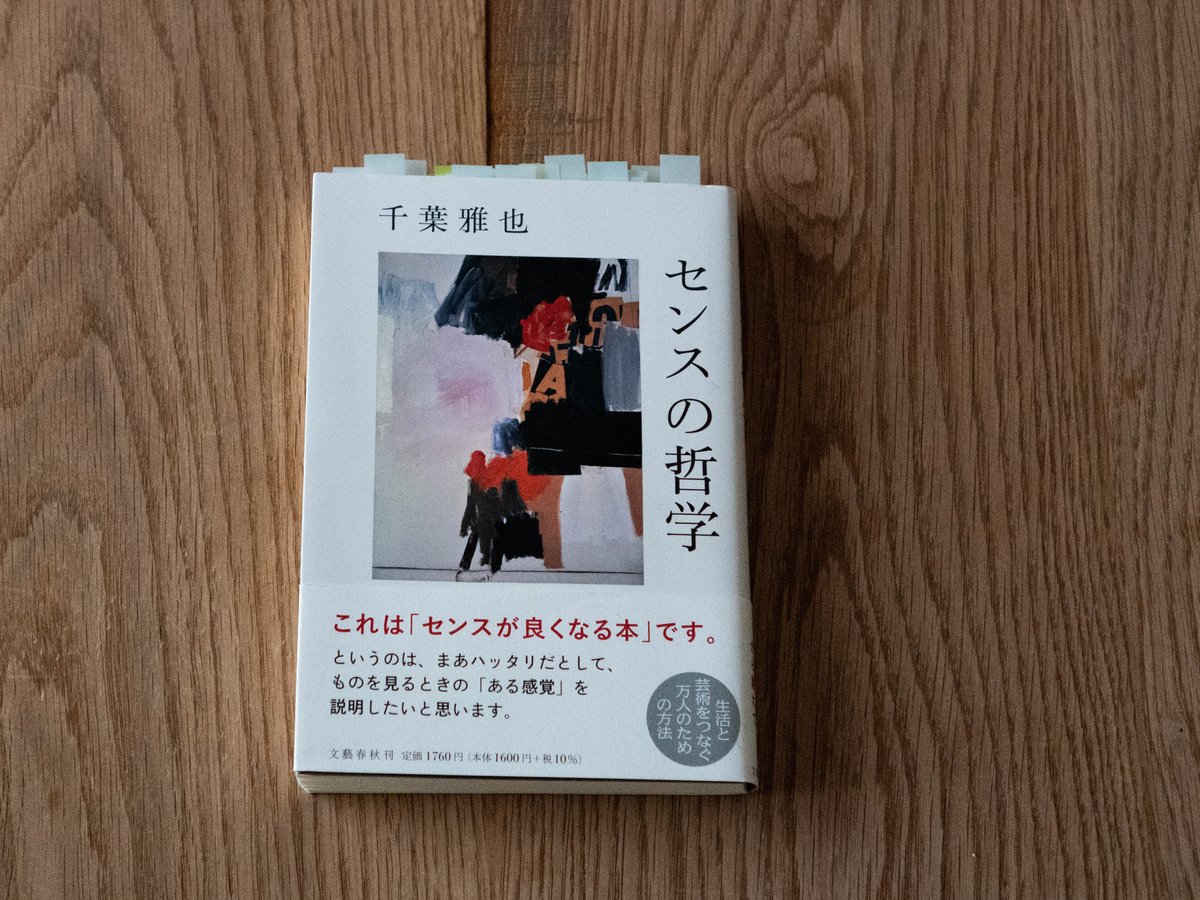
発売されてまずすぐに読んだ。そのあと1年通してずっと目につく本棚に置いて手にとった。そして年末の大整理を経て2025年の今も本棚のスタメンに堂々といる。読んだり寝かせたりを何度も繰り返している。読むたびに自分に染み込んでくるような感覚がある。この先ずっとお守りのようになる本。
何かを(映画や本や音楽や料理など色々)を見る時感じる時、今までは『めっちゃ感動した』とか『泣けた』とかその時感じた直球の感情しか言葉にできなかった。だけど一旦落ち着いて引いてみることを意識できるようになったのはこの本のおかげだなと思う。ライブハウスに行って前方で見るのをやめて真ん中くらいで見るようにもなった。
自分は食べることとか食べもの周りのことが好きですごく興味がある。映画や本や写真を見たときに出てくる料理やスタイリング、キッチンに置いてある小物とか冷蔵庫に貼ってあるものとかから人物を想像したり作り手の意図を想像したりするのが好きなのだが、なんかそれがただの食いしん坊みたいで恥ずかしく思っていた。
でもそう見方こそ無自覚に出てしまう自分らしさというか自分にしかできない視点なのだろうなと思い大事にするようになった。
(10月に読んだ『青山真治アンフィニッシュドワークス』での田村千穂さんの青山さんの映画に出てくるフライパンの論考がものすごく面白くて、そういう視点で見てもいいのだなという気持ちになったのもある)
そういう自分しかに視点を大事にしようと思ったら、他者の無自覚に出てしまっているその人らしさみたいなものも気になってそこを見るようになったし今までは『なんかそれはダサくないかい?』も『おうおう、これがその人らしさじゃないかー』だと肯定できるようになった。
あらゆることは今起こる

この本は『あーそれわたしだわ』と思う部分が多すぎて笑い泣きのように何度もなった。著者は同じ世代なので見てきたもの(テレビやゲームなど)が同じというのもあるかもしれない。『それでよかったんだ』『それでいいんだ』と子供の頃の自分と今の自分とがと同時に励まされてる感じがある。
本を読んで著者の行動に共感した人はコンサータってすごいんやなー、気になるな、飲んでみたいなと思ったはずだが(思っちゃったけど?)、わたしもそんなひとり。実際はなんにもしてないし相変わらず自分で自分に振り回されているけど(たぶん自営業だからなんとかなってる)受診するほどじゃないんだよなーな日々を今も送っている。
そしてエピローグにある『日常』から自分にとっての『日常』についてよく考えるようになった。著者は『日常』とは不安定さと結びついていると書いている。
わたしは著者とは逆で『日常』は何も起こらない穏やかな凪のようなゆるやかな時間がただただながれていくイメージをもっていたし今もそのようなイメージが強い。
だけどここ最近はその『日常』とわたしが勝手に名付けたもののハードルが高いことがなんと多いことかと感じる。自分ごと、子供ごと、夫ごと、さらに災害や戦争やどうにもならない他者ごと。
『凪の日常』があまりに少なすぎる。わたしの中で勝手に名付けてきた『凪の日常』を乱すような些細な事件が毎日ありすぎるなと思っていた。もう日常=凪ではないのでないかと思い始めていた。
著者の書いている通り日常はいつも不安定、だけど日常というものが続こうとする強靭さと、そこでおきたことがふるびてたちつづける家屋のように影響しているのなら、何があっても自分が戻るところが日常で、それは今で過去で未来で、自分はそこからしか生まれてこなかったし、生まれないし、どんなに不安定だとしても日常を大事に生きていくのだという覚悟ができた。ような気がする。
最後に
2冊ともどちらも自分を肯定してくれたような気持ちになってすごく救われた。
お二人とも自分と年齢が近くてそれもミッドライフクライシスをいきていく勇気みたいなひらきなおりみたいな堂々といきていくぞという気持ちが整ったのでよかった。
本を読むにあたって、新しい考えと出会うためというのもあるけどやっぱり『そうだよね、だよね』と共感したいという気持ちが強いのかもしれない。
