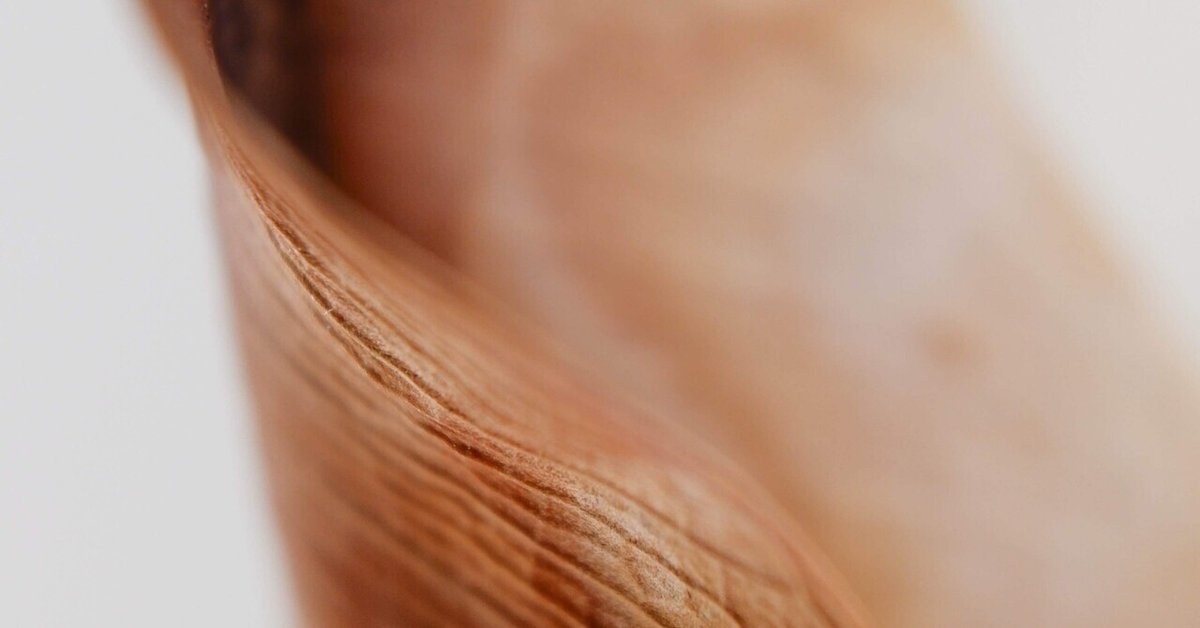
日本が世界に誇る「うま味(UMAMI)」の功罪
今から遡ること1世紀余りの1908年2月、東京帝国大学の池田菊苗(いけだきくなえ)教授は昆布に含まれる未知の味覚成分がL-グルタミン酸であることを世界で初めて突き止めた。その発見によってそれまで甘味・塩味・酸味・苦味の4種と考えられていた人間の基本味に第5番目の「うま味」が加えられ、5年後には同大学の小玉新太郎研究生が鰹節から新たにイノシン酸を、1960年にはヤマサ研究所の國中明博士が干し椎茸などに含まれるグアニル酸がうま味物質であることを特定した。後に三大うま味成分と呼ばれ、今や世界において「UMAMI」という共通語で通じるようにもなったそれら全てが日本人科学者によって発見されたことは、古くから海産物中心の出汁文化に慣れ親しんできた我が国の面目躍如といったところだが、その偉業がこれまで人類の食文化にどのような影響を与えてきたかについては余り言及されることがない。
挙げるとすればそのひとつは調味技術への貢献だ。日本料理の出汁、フランス料理のブイヨンやフォン、中国料理の湯(タン)など、うま味の発見以前から経験則的には知られていた世界の様々なうま味の利用法を体系的に発展させ、より明確な技術的アプローチを出来るようになった点は大きい。また、2種類以上のうま味を組み合わせる(※)ことで、うま味をより強く感じるという相乗効果(最大6~7倍とされる)の発見(国中明.1960年)は、一般に料理を減塩した際に感じられる味の物足りなさを体感上うま味で補うことが出来るという機能性や健康上のメリットも生み出した。
※アミノ酸系のうま味(A) ✕ 核酸系のうま味(B)
1909年の味の素社による世界初のうま味調味料(L-グルタミン酸ナトリウム※)の製品化も外せない。これは手間とコストのかかる出汁の抽出行程を丸ごと飛ばして、誰でも簡単に必要な量だけ「うま味」を料理に添加できるという正に世界の食卓事情を一変させてしまうほどの画期的な商品であった。事実、同社を世界トップクラスの調味料企業へと押し上げた屋台骨商品でもあるが、そのサクセスストーリーが必ずしも順風満帆ではなかったことには一応留意したい。※よく勘違いされるがL-グルタミン酸ナトリウムは加工品であり純粋なうま味ではない。
1968年5月16日、世界で最も権威ある総合医学雑誌の一つであるニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシンに寄稿された1本の記事が同社の命運を分けたのである。実際には科学的検証を欠いた編集宛の手紙レベルだったとされるが、その内容を要約すると「中華料理を食べると15~20分後に首の後ろが痺れ、それが次第に両腕や背中に広がり、全身の脱力感、動悸を発症する」といったものだ。俗に言う「チャイニーズレストラン・シンドローム(中華料理店症候群)」である。それが寄稿者の意図によってかよらずか同誌の記事として米欧を中心に瞬く間に世界の衆目を集めることとなり、その安全性を疑問視する声と共に専門家や国家政府をも巻き込んだ激しい公開討論へと繋がったのである。その結果、原因の主犯格として中華料理に多用されるうま味調味料=L-グルタミン酸ナトリウム(以下、MSGという)に白羽の矢が立ったというわけだ。
当時の検証では因果関係が証明されるに至っていないにも関わらず、その余波の大きさたるや2023年の本稿執筆現在でもアメリカ人の10人に4人がMSGを意識的に避けているという実態調査(IFIC・国際食品情報協議会調べ)があるほどだ。なお、味の素社内外の継続的な検証により、今では適量の範囲内でMSGの安全性が科学的に立証されていることも申し添えておきたい。
筆者はこの顛末に思いを馳せる時、消費者のみならず叡知の徒たる科学者すらも惑わせるフード・ファディズムの時代を越えた影響力の大きさに憂慮の念を禁じ得ない。今後同じような新しい価値が世に広く普及する時代の転換点に差し掛かったとき、一般消費者が何を信じれば良いのかという指標そのものが個々人の責任において求められ始めたというある種の警告にも思えるからだ。
新たな価値観というものが確実に浸透するまでには多少の紆余曲折が付き物だ。うま味に関しては発見以前から概念そのものがある程度我々の生活に根差していたと考えられるが、それが科学によって改めて定義されたことで思わぬ角度から弊害に繋がっているという視点を持つ者は意外に少ない。
元来うま味とは、食材中に遊離しているものを除けば、調理者の相応の経験則を拠り所として、一定の手間暇をかけて食材の風味と共に抽出される間接的な成果物としての味わいだ。しかし、うま味物質の発見および簡易な調味料としての普及をきっかけにその「相応の経験則」や「手間暇」、「間接的」といった垣根が一挙に取り払われたことで、まさしく堰を切ったように食業界に「うま味の氾濫」が起きてしまったのである。
特に商業目的利用の場面への負の波及効果は座視できない。例えば加工食品の一括表示に見られる「調味料(アミノ酸等)」などの表記はその食品に化学的に合成または抽出されたうま味が添加されていることを表しているが、昨今の食市場に溢れかえるのは過剰に強調されたうま味、無益に繰り返される冗長なうま味、風味全体の中で孤立する場当たり的なうま味、味の調和を自己破壊する不必要なうま味などだ。タガが外れて独り歩きを始めたうま味が生み落とす異形な味わいの数々は、「人間はうま味を足してやれば満足する」とでも言わんばかりの万能主義的な「過信」と「野放図ぶり」を象徴している。
チャイニーズレストラン・シンドロームの一件も、その問題の根幹は、発見されて高々100年ちょっとの新入りに等しいうま味という一介の味覚要素が持つ体系化の未熟さと不釣り合いな有用性の高さ、量産化のブレイクスルーによって獲得した「手軽さ」という強みを未だ持て余していること、またその手軽さゆえに風味や栄養価とは脈絡のない利用が横行しつつも半ば放置されてきた怠惰な現状にあると筆者には思えてならない。
うま味の発見者・池田菊苗教授の研究当時の想いは、「滋養に富んだ粗食をおいしく食べられるようにする調味料を発見・工業化することが日本の栄養不足解消に繋がる」という崇高なものであった。悲願でもあるうま味調味料の一般普及が皮肉にも滋養を軽視した無秩序なうま味の濫用が蔓延る商業主義の温床を産み出す遠因になろうとは氏も想像だにしなかったことであろう。
