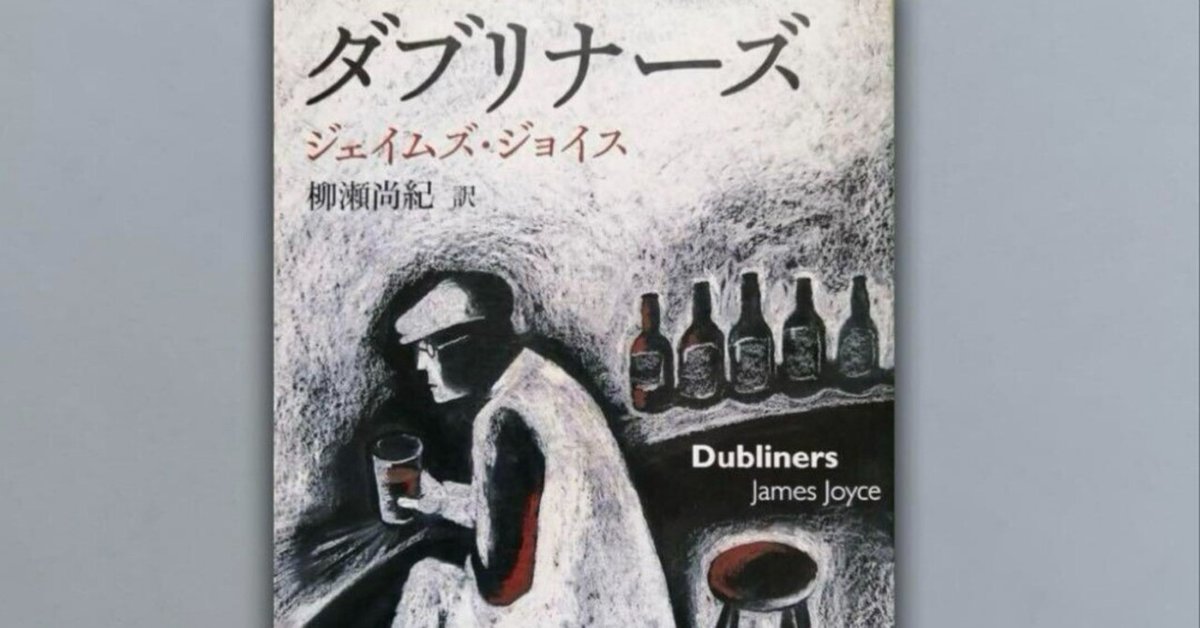
ジェイムズ・ジョイス『ダブリナーズ』(1914)柳瀬尚紀訳 - 感想
*
2024/9/3〜11/8(計15日間)
海外文学のラスボス(の1人)、ジェイムズ・ジョイスの小説はだいぶ前に『若い芸術家の肖像』(集英社文庫)の冒頭を読みかけてすぐに放り出したのみで、読み通したのは今回が初めてです。
短編集の最後を飾る「死せるものたち」をいちばん初めに読んで、あとは冒頭から順に読みました。以下の感想もその順番です。
9/3(火)
9/4(水)
死せるものたち
The Dead
大晦日の社交パーティ
登場人物が多すぎる! これ家系図・相関図を描かないと分かんないや
20ページ過ぎても誰が主人公なのか分からない。群像劇?
人物の外見や仕草の描写が精緻なのは19世紀小説(バルザック?ディケンズ?)の流れを汲んでいるのか。にしても異様さを感じる。登場人物全員を露悪的に見ているというか、変な執着があるような。
社交界を風刺する短編としては最近読んでたリスペクトルを連想する。
「西部イギリス人」というアイルランド人への蔑称。イギリスかぶれの非国民ってことか。
アイルランド語の存在を恥ずかしながらよく知らなかった。いちおう公用語なんだ。都市ゴールウェイ、ゲールタハトという西側地域(イギリスから遠い地域)では比較的話者が多いと。
9/5(木)
ゲイブリエルの圧巻のスピーチ 保守的な、アイルランドの伝統のもてなしと、主催者である叔母たち3名を誉めそやす内容。
正月の親戚の集まりの賑やかさとほの哀しさがよく表現されている。
読み終わった!
これは……傑作! すげ~~~小説がうめぇ~~~~
80ページほどの短編だが、ラスト20ページの展開がすごい。それまでは誰が主人公で何の話なのかもよく分からないほどなのに、最後に一気に「小説」になる。
三角関係モノだとは聞いていたので、冒頭から、誰と誰と誰の話なんだと気にして予想しながら読んでいたが、ゲイブリエルの妻グレッタに、ラスト9ページで唐突に生えてくる両想いだった幼馴染(享年17)……そういうことか…………
まぎれもない三角関係モノであり、ヘテロ幼馴染モノであり、「幼馴染」という歴史的な概念についての小説であり、人(他者)の歴史について、他者の過去と未来、生と死についての話である。
そして、精神的なNTR(寝取られ)モノであるというか、BSS(僕が先に好きだったのに)ならぬBAS(僕があとに好きだったのか)………… これはこれでより一層、失恋エモとしての旨みは強いかもしれない。
ようするに、じぶんの性癖の ""核"" を見事に打ち抜いていった作品だった。
死者を含む三角関係モノとしてまず自分のなかで思い出すのは重松清『十字架』。ただ、「死せるものたち」が生者↔死者の両想い(死別)であるのに対して、『十字架』は死者→生者の片想いであり、生者→死者の向きの好意は無い(がゆえに遺された生者は死者の死後に好きでもない人間の存在を引きずって生きなければならなくなる)というのが、やっぱりめちゃくちゃ凄いことを描いていると思う。まさかジョイスを読んで重松清の評価が上がるとは……
「生者→死者」つまり「好きだった人が死んでしまった」という要素は、それだけで悲劇的なドラマチック性を持っており、物語にとって都合がいい。だからこそ、それを排して、「死者→生者」の片想いをなすりつけるような独りよがりで暴力的な死(自殺)のうえに、「物語」をつくった重松清の才覚が光る。
閑話休題。
『十字架』は置いといて、この「死せるものたち」もまた、わたしのような失恋エモ厨、感傷マゾヒスト、自分のものにできたと思っていた「女」がするりと「男」の腕のなかを抜けて歴史を持った《他者》として立ち現れる物語がド性癖の人間にとっては、最最最高の小説だった。
グレッタとマイケル・フュアリーの幼馴染関係は言うまでもなく、妻グレッタから夫ゲイブリエルへの「愛」もすごいと思う。かつて心底愛していた(愛し合っていた)男のことを、こんなにもハッキリと、情熱的に、夫の前で言ってしまえるということに、夫への無限の信頼と愛情とを感じる。
だから、これは三角関係モノではあっても、決して「NTR」ではないのだ。死者を通じて、究極の夫婦愛を描いた短編でもあるのだ。現在のグレッタのフュアリーへの愛/執着は、浮気でもなければ不倫でも夫への裏切りでもない。死んだ両想いの幼馴染という彼女の人生の核にある秘密を夫に教えてしまえる、そのことに、いかにグレッタが夫を愛していて感謝しているかが表れている。
むろん、「たぶん、すべてを打ち明けたのではない」p.374 とゲイブリエルが考えるように、グレッタの「秘密」は彼の前にすべて明らかにされたわけではないだろう。しかし、マイケル・フュアリーの存在を伝えた時点でグレッタは夫を「承認」しているとはいえるだろうし、この文で重要なのは、本当にグレッタがすべてを打ち明けていないかどうかではなくて、「すべてを打ち明けたのではない」とゲイブリエルが考えていることのほうだろう。彼の慎み深さはすごい。
そう、グレッタ側のゲイブリエルへの愛だけでなく、ゲイブリエル側のグレッタへの優しさと慎みもかなりのものだと思う。
寛大の涙がゲイブリエルの目にあふれた。己自身はどんな女に対してもこういう感情を抱いたことはなかったが、こういう感情こそ愛にちがいないと思った。
とあるが、このゲイブリエルの「寛大の涙」こそが「愛」なのだとわたしは思う。たしかに、グレッタ→フュアリーのような情熱的な愛とは質が異なるが、ゲイブリエル→グレッタの、妻のかつての想い人の存在を知って「寛大の涙」を流すゲイブリエルの寛さ(ひろさ)も「愛」でなくてなんだろうか。NTR漫画で、寝取り男に "堕ち" た彼女の変わり果てた姿に、それでもだからこそ「好き」だと思う寝取られ男の境地に似ている(NTRではないんじゃなかったのかよ!)。
妻の「幼馴染」という《歴史》を目の当たりにして、ゲイブリエルは精神的NTRを通り越して達観してるんだよな。書かれている通り、生と死の境界を超越している。「死せるものたちがかつて築き上げて住った堅固な世界そのものが、溶解して縮んで」p.375 いる。
自分のおめでたい姿が目に浮ぶ。叔母たちの使い走り、神経質な人の好い感傷家を演じ、俗物どもに演説をぶち、己の道化じみた情欲を理想化し、鏡でちらりと見て取れたなんとも憐れむべき独り善がりの間抜け者。
むろん、前半でさんざん描かれたように、ゲイブリエルは基本的に「俗物」で滑稽で憐れな人物ではあるのだけれど、ゲイブリエルをそうした間抜けな寝取られ男(コキュ)で終わらせないのがすごいところ。
二人の叔母も大笑いになった。ゲイブリエルの心配性はいつも笑いの種なのだ。
──ゴロッシュなんです! とコンロイ夫人。つい最近はそれ。道がぬかるむときは、あたし、ゴロッシュを履かなければならないんです。今夜だって履かせたがって、でもいやって言いました。次は潜水服を買ってくれるでしょうね。
彼女が自分のものであることが嬉しくて、優雅さと妻らしい身のこなしが誇らしかった。
彼女の不可解な気分を征服したくなった。
マイケル・フュアリーのことを打ち明けられるまで、ゲイブリエルはグレッタのことを所有物であるかのように認識していた。男の父権的で女性蔑視的な「愛」。叔母たちに笑い話にされる、妻への過剰な気配り(「心配性」)もその裏返しである。
彼女は身をふりほどいてベッドへ駆け寄り、ベッドの柵上へ腕を十字に投げ出して顔をうずめた。ゲイブリエルは一瞬、呆然と立ちつくし、それからあとを追う。姿見の前を通るとき、自分の全身が見えた。
──今でもくっきり目に浮ぶ、と、ちょっと間をおいて彼女は言った。すてきな目をしてたわ、大きな黒い目! とっても表情があった──表情が!
そんなゲイブリエルの父権的な権威が、妻の「幼馴染」という秘密によって徹底的にコケにされ解体される。この意味で本作は非常にフェミニズム的であるが、単にそうして家父長制に入り浸った「男」の失墜を痛快に描いて終わるのではなくて、失墜した「男」側の自嘲、達観、赦しと解放までをも射程に入れているところが更にすばらしい。(無論これらも「フェミニズム」の範疇である。)
ゲイブリエルは片肘をつき、妻のもつれた髪と開き加減の口を憤りもなくしばし見つめ、深い寝息を聞いていた。そうか、そんなロマンスの過去があったのだ。一人の男がこの女のために死んだ。夫たる自分がこの女の人生でなんとも哀れな役割を演じてきたものだと考えても、今、ほとんど苦痛を感じない。
そしてその頃、初々しい少女の美しさの当時、彼女はどんなふうだったのだろうと思い浮べるうちに、不思議な友情にも似た憐れみが心の内にわいてきた。
その赦しや解放とは、とうに亡きマイケル・フュアリーの影のとなりに、彼だけではない「死せるものたち」を視ることで為されるものである。
涙がなおも厚く目にたまり、その一隅の暗闇の中に、雨の滴り落ちる立木の下に立つ一人の若者の姿が見えるような気がした。ほかにも人影が近くにいる。彼の魂は、死せるものたちのおびただしい群れの住まうあの地域へ近づいていた。彼らの気ままなゆらめく存在を意識はしていたが、認知することはできなかった。
叔母もまた、じきに影となり、パトリック・モーカンやあの馬の影といっしょになるのだ。
自分の身の回りのものもいずれ死ぬ、ということに想いを馳せること。これは普遍的な気分であるが、こうした構成で提示されるとものすごい喰らってしまう。
ラスト20, 10ページまでに数十ページ「伏線」というか「溜め」を仕込んで最後に昇華させる構成ではあるものの、それは文字通り、各人の人生の「構成」そのものの暗喩となっているし、(読んでないけどおそらく)この『ダブリナーズ』という短編集の末尾にこの短編が置かれている理由も、そういうことなのだろう。それまで精緻に描いてきたダブリンのまちの人々の生をすべて包み込んで終わらせるような、強烈な「死」とその超越の物語。
小説的な技法としては、p.360の、雪道を帰る妻の後ろ姿に感傷的になり(=性的に興奮して)ふたりの出会いからを回想して勝手にひとりエモくなるゲイブリエルのくだりは、映画的なフラッシュバック演出だなぁと思った。
二人だけの秘密の生の一瞬一瞬が、星のごとくきらめいて記憶に弾ける。
この時代って「映画」はまだそこまで一般的じゃなかったんだっけ じゃあ逆輸入?
あとは、晩餐会で演劇が話題にのぼるけれど、まさに舞台演劇っぽい空間設計や人物の立ち位置・移動のつくりになっていると感じる箇所が幾つかあった。「オーグリムの乙女」を階段の踊り場で聴く妻を見るところとか、ホテルで明かりを持った老人の後ろをついて階段を登るときに立ち止まるシーンとか、あとはホテル室内の窓から差す光に沿った動きの描写など。
外の街灯の不気味に青ざめた明りが、一条の光となって一つの窓から扉まで伸びている。
妻は鏡からゆっくりと離れて、光芒づたいに歩み寄ってきた。
9/6(金)
姉妹
The Sisters
若い「僕」の一人称小説
近所の、「気がおかしくなった」と思われている元神父の老翁によくしてもらっていたが、亡くなった。世間の大人からは疎まれてるけど、子供の自分だけには良き師、良き友人でいてくれる大人との関係というのは児童文学でもありがち。
なんだ、最後の「死せるものたち」だけじゃなく、最初から「死」始まりなのね。葬式から始まる小説は定番。
亡くなったフリン師ときょうだいである2人の老女がタイトルの「姉妹」なのだろうが、なぜこれが題になっているのかはよく分からない。
階段の踊り場や部屋の光、そして老人が着ている服についての細やかな描写などは相変わらず。
9/9(月)
出会い
An Encounter
ザ・少年時代! 初夏の冒険! スタンドバイミー! ノスタルジーがすごい。好きだなぁ 手持ち無沙汰な放浪の情景描写がいい。
学校をサボって友達と旅に出た先で、話しかけてくる変なおじさんに出会う。このおじさんの語りの描写がまた良い。前作と同様に、子供にとっての大人、がひとつの主題となっている。子供のもつある種の「大人」への幻想を終わらせ、同時に牧歌的な子供時代から目を醒めさせるきっかけともなる哀しい大人。なんか重松清『きみの友達』っぽさを感じた。児童文学!
インディアンとか、新教徒(メソジスト)とか、そうした「他者」に関する記述が散りばめられている。子どもの排外主義。「緑色の目」を探すってどういうことだろう。最後のおじさんは深緑色の目をしてるらしいけど。
ピジョンハウスって火力発電所のことか。最初に写真が掲載されていた。
こういう、ひとつの都市・町をスケッチ的に郷愁を込めて描く短編集って本作が嚆矢なのかな。スチュアート・ダイベック『シカゴ育ち』なんかを思い出す。
9/10(火)
アラビー
Araby
うおおお少年の異性愛の目覚め! 淡い初恋という一大事! これも子供を描いた小説として好きだなぁ。主人公の「僕」は何歳なんだろう。高学年〜中学生くらい?
アラビーとは、気になっている友達の姉の名前ではなくてバザーの名前なのね。
お姉さんの描写が良すぎる。逆光に立つ姿が浮かび上がるシーンは「死せるものたち」で音楽を聴く妻が階段の踊り場の暗がりに浮かび上がる場面を連想する。
初恋に振り回されてる子供のおはなしはなんぼあってもいい。かわいい。
序盤だけ「僕ら」という複数形を何度か使う。「マンガンの姉」への恋の話に本格的に入ると、友達連中は後景化する。
初恋の高揚を「東洋の魔法」と呼ぶ素朴なオリエンタリズム。終盤のバザー店舗の壺も「東洋の番兵」に喩えており、なにかそういう裏テーマがあるのか。てか「アラビー」ってアラビアと関係ある? そもそもバザーがペルシア語なのでそっちの文化圏か。じゃあ「東洋の魔法」で何も問題ないな。
今のところ読んだ4編すべて終わり方がダウナーというか、挫折や気まずさ、人生の苦味……みたいな着地をしている。
やっぱり文章も小説も順当にうまい。スタンダードな上手さの頂点、といったところ。ちゃんとした小説などその気になればいくらでも書けるからこそ、前衛的な作品に挑戦していったのか。ピカソみたいな。
エヴリン
Eveline
三人称。19歳の女が、船乗りの男とブエノスアイレスへ駆け落ち結婚する直前に、家のなかでこれまでの人生を振り返る。
抑圧的な父親。どれだけ「ここ」から解放されたくても、離れられない。退屈で残酷な故郷への憎悪と執着。
もはやこの終わりは予定調和だろう。
カーレースが終って
After the Race
二十代後半の「若者」たちの、カーレース後の浮かれた夜の一幕。フランス、ハンガリー、イギリス、アメリカなど色んな国の男達が出てくる。アイルランド人がそうしたビジネスパートナーや知人たちにいいように溶け込もうとしてカードギャンブルでこっ酷く負けるのは、そういう国際政治勢力図の隠喩なのか。
9/12(木)
二人の伊達男
Two Gallants
三人称叙述。
レネハンとコーリー。ふたりの三十過ぎの「若い男」が女と逢引きして金を稼ごうと道をぶらつく。といっても、片方レネハンのほうは、そろそろこうした「青春 youth」から卒業して身を固めたいとも漠然と考えている。
うろつき回ることにも、あくせく生きるのにも、一時しのぎや策略にも、もううんざりした。十一月には三十一歳になる。いい職にはつけないものか? 家庭をもつことも無理だろうか?
青春期の終わり。若者から大人へ。現代日本でいえば、恋愛工学に飽きてきた男の話みたいな。結局こういう人々って男同士の絆(ホモソーシャル)に囚われているので、「成功」オチもそういうものへの執着だと解釈できるか。
主人公の設定ゆえにミソジニーがきつい。
「流し目みたいなあの女の口」p.91 というが、どんなだよ。顔のパーツを顔の別のパーツで喩える。なんとなくわかるけど。
ジョイス一流の、シニカルかつ精緻な人物描写がおもしろい。p.82のコーリーの描写など。
10/7(月)
下宿屋
The Boarding House
自分にとって、娘の失った名誉の埋め合わせになりうるものは、たった一つの償いしかない。つまり、結婚。
19歳の娘の純潔を、下宿させている35歳の男に奪われた母親が、責任を取って結婚してもらおうとする。
現代日本とは貞操観念も結婚観もまったく異なるので、償いが結婚だとか、結婚したらもうお終いだと独身男が嘆くのとか、そうなんだ〜と面白い。
文章がとてもうまい。模範的。人間の心理に分け入った描写をするすると読ませる。
マダムと娘の駆け引きのところが良い。
ラストに娘が一転してなぜかポジティブになるところ(彼が結婚してくれると直感したから?)はなかなか咀嚼が難しい。
小さな雲
A Little Cloud
10/10(木)
上京してビッグになった旧友が地元へ久しぶりに帰ってくる。彼を自慢に思い、自分も何者かになれるのではと妄想する32歳の詩人ワナビー既婚男チャンドラー。痛い
イギリスへ素朴に憧れるダブリン市民
旧友とバーで再会するが、生きる世界があまりにも違うことに嫉妬し、退屈な女に引っかかって結婚生活に縛られている自分を省みて、友もこちら側に引きずりこもうとする。
そして帰宅後、乳児を抱き抱えながら妻の写真を見ていらだち、バイロンの詩を読もうとするが子に泣き喚かれ、思わず怒鳴りつけてしまう父……
これは……凡庸な男性のホモソーシャルとマッチョイズム、ミソジニーなどなどが混じり合った愚かしさを見事に抉り出している短編だなぁ。「死せるものたち」といい、こういう「ふつう」の男性のなかに潜むどうしようもない幼稚さと有害さについて書くのが得意なんだなぁジョイスって。『ユリシーズ』もたのしみ😊
10/11(金)
写し
Counterparts
嫌いな男上司に反抗して仕事をクビになるダメ男。金を質屋で工面して仲間と飲んだくれる。
11/15(火)
仲間に奢りまくって素寒貧になり、おまけに腕相撲で負けた腹いせに息子へ暴力を振るう…… マジで最初から最後までクズな男の最悪な1日の話だった。
10/16(水)
土くれ
Clay
原題と「くれ」で韻を踏んでる?
老女マライアが、かつて乳母として育てた男性の家庭のハロウィンパーティへ赴く。ほっこりとしたぬくもりが感じられるやさしい短編。
10/17(木)
痛ましい事故
A Painful Case
ひゃっほーぅ! 不倫小説だ〜〜!!!
ダブリン郊外で世俗から離れた慎ましい暮らしをする銀行勤めの独身中年男性ダフィー氏は、ある日コンサート会場で娘を連れた知性的な既婚女性シニコウ夫人と出会い、惹かれあって何度も逢瀬を交わすようになる。しかし夫人から身体的な接触を迫られたダフィー氏はそれを拒絶し、別れることにする。4年後、酒浸りになったシニコウ夫人が夜中に列車に轢かれて亡くなったことを新聞で知り、自分の品位をも落とされたと憤るが、その後に彼女を拒絶してしまったことを後悔し、真の孤独を噛み締める……
プライドの高い孤独に酔った男の自意識文学としてかなりスタンダードに完成されている。「死せるものたち」の前身っぽさも感じる。
「人生の饗宴から放逐されたのだ」p.191 という言い回しは使い勝手が良さそう。
彼は己の肉体からちょっと距離をおき、己の行為を疑わしげな横目で見るという生き方をしてきた。妙な自伝癖があるために、ときおり頭の中で、己自身のことを三人称の主語と過去形の述語を用いて文章に記す。
序盤にこの記述があるせいで、どうしても、この三人称過去形の短編小説をそういうものとして読まざるを得なくなるギミック。
あらゆる絆は、と、彼は言った。悲しみへつながる絆です。
ここもいつかエピグラフに使いたい。
10/25(金)
委員会室の蔦の日
Ivy Day in the Committee Room
選挙運動人として雇われている男たちが寒い雨の日に暗い部屋で酒を飲みながら語らう。登場人物が多くて誰が誰だか混乱した。
部下に裏切られて殺されたアイルランド国王パーネル?の追悼の死で締めくくられる。史実? 背景が理解できないのでよく分からずに終わった。
暗い室内の情景描写はさすが。
この人か〜
11/7(木)
母親
A Mother
ピアノを弾ける娘が出演する4日連続の音楽会の企画運営を手伝う母親、カーニー夫人。しかし音楽会が1日少なくなるなど、聞いていた話と違うことに憤った夫人は、契約通りの報酬金を払ってもらえない限り娘を出演させないと宣言する。しかしそのせいで音楽会自体の進行が滞り、他の出演者や観客に迷惑をかけ、夫人は周りから非難される。
……え、これどっち? カーニー夫人が、いわゆるモンスターペアレントであって、こういう迷惑な母親・女性いるよね〜ってことなのか、それとも彼女をぞんざいに扱う周囲の男たち・世間をこそ風刺的に批判しているのか……。カーニー夫人の娘・キャスリーンも、最初の出番のときには母を振り切って舞台に自ら歩み出たが、最後には母が外套で包んで退散させられるのにされるがままとなっており、どういう心境なのかよく分からない。
文章がやっぱり上手い。脇役の人生をさらっと一段落で描写するのとか。
夫人は中央郵便局を信頼するのと同じように、大きくて安全で動じないものとして、夫を信頼していた。夫の才能の乏しいことは承知しているけれども、男性としての抽象価値を尊重しているのだ。
バスのダッガン氏は細身の青年、まばらな黒い口髭をはやしている。市内のある会社の玄関番の息子だ。子供の頃は、そこの響きのいい玄関ホールで低音を伸ばして歌っていた。
ヒーリー嬢が目の前に立ち、しゃべったり笑ったりしているからだ。彼女が愛想よくする理由は察しがつく年輩にはなっているものの、この機会を利してやろうとする気の若さはある。彼女の肉体の温みと芳香と色艶が五感を刺激した。見下ろす視線のもとでゆっくりと起伏する胸がこの今は自分のためにゆっくりと起伏している、笑いも芳香も媚びた眼差しも自分への貢物だ、と、彼は心地よく意識した。
ここやばい 男性の愚かさ、気持ち悪さを描くのがうまい
11/8(金)
恩寵
The Grace
夫婦生活25年の中年男性カーナン氏がある夜、酔っぱらってバーの階段から転げ落ちて頭や舌を怪我する。彼の長年の友人のパワー氏らは、カーナン夫人に頼まれて、彼を更生させるために画策する──カトリック・イエズス会での静修をみんなでやろうと誘う。
題名通りとても宗教的な話で、やはりいまいち掴めなかった。
しかし、と、神父は聴衆に語った。自分にはこの一節が、俗世の生活を送る運命にありながら、それでも俗人のようにはその人生を送るまいと願う人びとのための指針として。とくにふさわしいものと思われる。これは商売人と職業人のための一節なのである。
ラストの神父の説教・講和では、商人などがその世俗的な生活のなかで信仰を保つための一説が語られる。これは、ここまでダブリン市民の世俗生活を活写してきた本作全体の意義を肯定している風にも読める。
まとめ
おわり!!!
アイルランドの歴史とキリスト教に関する知識がないとよく分からないところはあったが、ジョイスの「正統的」に上手い文章技術・小説技法はよくよく堪能できた。
若くしてこれだけの上手さがあってこれだけの文学空間を作り上げてしまったら、あとはここからそれをどう崩していくか、に一生を捧げるのもきわめて妥当であると納得する。
「死せるものたち」はダントツとして、他に「出会い」「アラビー」「小さな雲」「痛ましい事故」が特に好きだった。
