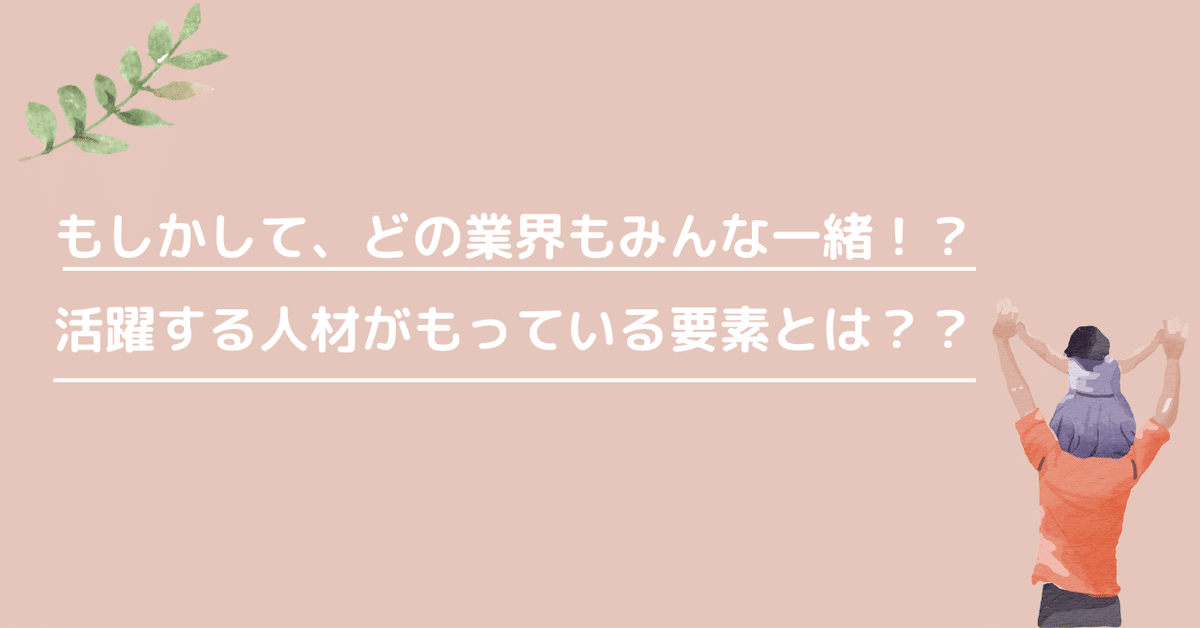
最近、どこの人材育成担当者と話をしても、結局、同じところにたどり着く、今後求められる要素
先日、某駅前のルノアールの中で、私を含めて3人で、これからの人材育成について話をするという機会をいただきました。
お相手は、某プロスポーツチームの人材育成担当の方と、以前、某国際協力機関でさまざまな国の教育計画について考えていて、今は大学で教員養成に取り組んでいる方になります。
プロスポーツチームの人材育成担当の方は、複数のチームを渡り歩いてきている方でした。誰もが知っているレジェンド級の監督を支えていたこともあるのだそうです。
海外とのネットワークも広くもっていて、欧米を中心に、中南米までも含めて、さまざまな国の選手の発掘や国との交流の仕事も担当されています。
話に登場する人物がことごとくトッププレイヤーや有名選手ばかりで、裏話を聞かせてもらうと、それらの選手の外から報道されている姿勢と重なる部分と意外な部分とか明らかになっていき、なんと贅沢な時間だろうかと思いました。
今は多くの過去のトッププレイヤーや指導者達の言葉から学んだことや、最新のデータを駆使しながら、プロアスリートやチームのビジネスサイドの人材育成に取り組んでいるということです。
もう1人の国際協力機関で働いている友人は、統計を用いて教育領域で活動している人です。
彼の場合は先進国から後進国まで、世界中の教育施策の成果を分析したり、ローカルの学校に入り込んだりしながら、さまざまなデータを取っては、国の教育政策に落とし込む支援を仕事にしていました。
国連機関の本部と、ローカルの学校を行き来するという、これまた非常に興味深い領域で活動されていました。想像するに、出会うのは、知的に非常に優秀で、かつまた思いやりなどのEQも高い方ばかりだったことでしょう。
一定の方面においては、世界中の人材の中でも、トップレベルに優秀な人たちに囲まれていたと言って良いのではないかと思います。
そして、その時に聞いてなるほどと思ったことがありました。
それは、国際協力機関で働くというのは、プロスポーツ選手と同じようなところがあり、過酷な環境にある現場の最前線で、ずっと仕事を続けていくというのは厳しいものがあるのだということです。
彼の場合は、40になるというタイミングを契機に拠点を日本に移し、これからは、日本で人材育成や教育者の指導に取り組むことにしたという話を聞かせてくれました。
今回お話をさせてもらった二人は、どちらも世界のトップオブトップの人材が集まってくるような領域でプレイヤーとして働き、また育成に携わってきているという共通点があります。
こんな人たちと人材育成をテーマに話をするとなると、どんなことが話されていくのでしょうか。私から提案し、この場をセットさせてもらったわけですが、話をする当日はワクワクが止まらないという状態でした。
結果、蓋を開けてみたら、もともと持っていた想像を遥かに超えて、非常に面白い時間でした。気がついたらあっという間に3時間が過ぎ去っていたという感じです。
帰りの電車の中や、寝る直前のベッドの中、また当日の朝起きた時も、あの場でのやりとりを反芻しながら、今回得られた知見の豊かさを噛み締めておりました。
その際、ふと1つの考えがよぎりました。
あの時の場とともに、今週、入った複数の商談でクライアントと話をしていたことを振り返っていたら、ふと、あそこで話をしていたことって、日頃、私がさまざまな企業の人材育成担当者さんと話をしていることと、結局、ほとんど一緒かもなということに気がついたのです。
もちろん、国内外のトップオブトップのプレイヤーと、日本のさまざまな職場で働いているごくごく一般的なビジネスパーソンでは、求められる程度には違いがあるでしょう。
でも方向性としては、同じことを言っているのが本当に面白いなーと思いました。
今回、得られた私の発見は、多くの人にとって参考になるのではないかということと、大きく言う分には問題ないであろうということから、私があの場を思い返しながら、さまざまな業界の人材育成の担当者さんたちが「今後の人材育成においては、結局、ここがポイントだよね」と語っていた点を3つにまとめて共有したいと思います。
ポイント① 自分の所属している環境をよくしていこうという意欲をどれだけ持てているか?
企業や組織の中にある部署でも、プロスポーツのチームでも、学校の中でのプロジェクトでもそうなんですが、能力はもちろん大事ではあるものの、それ以上に大事なものがあるのではないかという話を、誰と話をしている時も、気がついたらしていたなと思います。
「能力以上に大事」とされるのが何かというと、それが意欲です。
どこの世界でも、何かを始めていきなりうまくいくなんていうことの方が少ないものなのでしょう。継続して取り組み、課題を解決していく姿勢が必要不可欠です。
そのためには、意欲がないことには何も始まらないですし、多少は動いたとしても、最終的には何も生まれていなかったということになっていきます。
意欲って、ほんと大事ですよねーということに、最近どこの現場の担当者さんと話をしてもなっていくように思います。
ポイント② 自分の成長に対してどれだけ貪欲に学習に取り組めているか?
学習する内容については、組織から求められる要素と、自分自身で必要と感じたり、それを身に付けたいという自分から生まれる要素と、どちらもあるかなと思います。
どちらもできるというのが理想的ではありますが、せめてどちらかだけでももっていることが本当に重要になってくるよねと、毎回のようにそんな話に展開していきます。
この「時間とともに学び、成長していける姿勢」は、できれば、その量は大いに越したことはないだろうなと思います。
逆に、これが「全くない」ないし、「あってもちょっとしかない」となると、その人材と一緒に仕事を進めるのは厳しいとなっていくことでしょう。
ポイント③ 自分が改めるべきポイントを素直に受け入れ、修正できるか?
修正とありますが、修正のポイントについては、「A=他者から指摘されて」というケースもあれば、「B=置かれている状況から察して」というケースもあれば、「C=自分自身の在り方を見つめて」というケースもあるかと思います。
Aが起こる状況というのは年齢を重ねるほどに生まれ難くなってくるので、生涯に渡って主となるのはBとCの部分でしょうか。
もちろん、Aが起こった際は、状況的にかなり深刻な状況であることも想像されるため、そこでの在り方はさらに重要になってきます。
ここで自分を改めて良い方向に修正できる人は活躍しやすいですが、いつまでたっても変わらない、修正が効かない、という人は本当に厳しいよねという話になっていきます。
3つの要素がいつ必要なのか?
この3つ、教育を受ける機会の多いであろう10代、20代に限らず、30代でも40代でも完全にそうだなと思いますし。
むしろ40代、50代、60代と年齢を重ねた時ほど、重要な姿勢になってくるかもしれません。
よく、人間の能力をテストの成績などで計測できる認知能力と、計測するのが難しい非認知能力とで分けて考えていきますが。
ここ最近、どこの業界、領域で人材育成に携わる方々と話しても、見事なまでに同じようにこれらの非認知能力の重要性の話に展開していくなということを感じます。
「スキルは後からどうにでもなるが、この在り方の方をなんとかするのは本当に難しい」と。口々にみなさん、そう語ります。
これらの三つ、もともと小学校の先生の時に、さんざん言っていたことばかりだなということに気がつき、思わず苦笑してしまう瞬間もあったのですが。
でも自分自身を振り返ってみても必ずしもできている場面ばかりでもないので、人のことは言えたものではありません。
考えてみると、子供の教育について話をしようとすると
「何歳から塾に入れてうんぬんかんぬん」
「うちの子の成績がうんぬんかんぬん」
「どこの国の教育がうんぬんかんぬん」
と展開することがありますが。
ここ最近携わるどこの領域の人材育成の担当者さんとのやりとりを思い返していくと、実は一番良い教育、学習環境は、小さいころから大人になってまで、ずっとこれらの点について意識を向けてくれ、振り返りの機会とフィードバックを与えてくれるところなのかもなということを思ったという話です。
こういった話は、まだまだ十分なデータが集まってきている領域ではないこともあり、現時点では、私があちこちで聞いている話をまとめた状態でしかないのですが。
今後、長い期間働くことが前提となり、そこからデータが集まっていた時や、これまでには測ることが難しかった部分まで何らかの形で計測できるようになったりすると、どこかのタイミングでそのエビデンスが見つかるような予感がしています。
はてさて。その時が来た時に、どんなことが明らかになるのか。今からそれがとっても楽しみです。
ということで、今日も素晴らしい学びの機会をどうもありがとうございました。
いいなと思ったら応援しよう!

