
皆で語り合う
令和7年度から使用される中学校国語科の教科書。教科書発行会社の4社が、中学3年生の教科書の中に取り上げている物語や小説は、次のとおりです。
『形』 (菊池寛)
『故郷』 (魯迅)
『最後の一句』 (森鴎外)
『風の唄』 (あさのあつこ)
『握手』 (井上ひさし)
『温かいスープ』 (今道友信)
『高瀬舟』 (森鴎外)
『坊ちゃん』 (夏目漱石)
『線は、僕を描く』 (砥上裕將)
『私』 (三崎亜記)
『バースディ・ガール』 (村上春樹)
私が中学校の国語科の教師として長年授業を行ってきて、一番優れた教材であると考えるのが、この中にある『握手』(井上ひさし)です。中学校の最終段階において、ぜひとも読み味わわせたい上質のものがあふれています。読み応えがある作品であるということです。
『握手』は1984年に書かれ、『ナイン』(講談社)に収録されています。よかったら、手にしてみてください。

この記事では、物語・小説をあつかう授業について、この『握手』を教材にして記していきます。
まず、この教材での「読むこと」の指導内容(中3)は、次のとおりです。
・表現上の工夫に注意して読むこと
・場面や登場人物の設定の仕方をとらえ,内容の理解に役立てること
・構成や展開,表現の仕方について評価すること
ただし、これは指導者サイドのことであって、子らにとって学び取りたいことは、物語や小説の読み進め方です。これから先の人生の中で、物語や小説をどう楽しみながら読んでいけばよいかについて学ぶことです。自分の足で歩けるようにする学びです。
そこで、物語・小説の読み進め方について、学習のはじめに次のように示し、①から④の流れで進めていくことを確かめます。
物語や小説の読み進め方
① 「はじめ」の主人公と「おわり」の主人公の姿を読み取る
② クライマックスで、なぜ主人公は変わったのかを読み取る
③ おもしろかったか?
④ ③のことについて、交流する。語り合う。
さて、『握手』をあつかった授業。
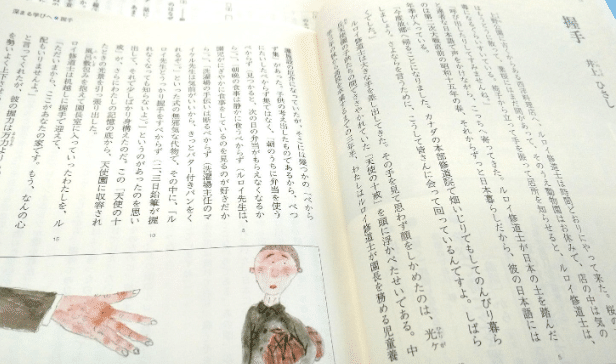
この作品には、3つの握手の場面が描かれます。
時系列で次に並べてみます。
「はじめ」の「わたし」
★ルロイ修道士から「わたし」への出会いの力強い握手
握手に込めた思いは、
「なんの心配いりませんよ
(ここがあなたの家です) 」。
(天使園での「わたし」のこれからをとらえて)
クライマックスへと向かうきっかけ
★ルロイ修道士から「わたし」への再会の穏やかな握手
ルロイ修道士の不調(!?)に気づくきっかけ (伏線)
「おわり」の「わたし」
★「わたし」からルロイ修道士への別れの力強い握手
握手に込めた思いは、
「なんの心配いりませんよ
(あなたは、何十年も神様を信じてきたのですから) 」。
(「死」に臨むルロイ修道士をとらえて)
この作品には、ルロイ修道士の独特の「指のしぐさ」が登場します。その「指のしぐさ」がルロイ修道士とのエピソードを回想させていくという構成になっていることから、指導者もその意味をとらえることにとびついてしまいがちです。しかし、やはり注目すべきは、この3つの握手なのです。
私の授業では、この3つの握手の場所だけを確かめた後、次のような「問い」を子らに示しました。
3つの握手。1つだけ他の握手とはちがうものがありますね。
どの握手ですか? 考えてみましょう。
おわかりのとおり、ある観点から比べれば、どの握手も他のものとは違う、と説明ができます。みな正解。これが、ミソです。例えば、出会いの握手か、別れの握手か。例えば、力強いか、そうでないか。5つくらいの比較の観点があります。比較のなかで3つの握手がそれぞれどんな握手であるかを読み取らせるのです。「表」にするのもよいでしょう。
再会の握手が作品を動かし、出会いの握手と別れの握手とのみごとな呼応、シンクロ。よく計算されたとてもすぐれた構成です。「わたし」とルロイ修道士とのあたたかな関係性とあいまって、私たち読者の心を強く打ちます。この作品の題名が『握手』であることの深い意味が、学習後に子ら理解されていかねばなりません。
続けましょう。
物語や小説の読み進め方の「③」で示したように、私たちは物語や小説を楽しむために読みます。よって、「おもしろかったか」「おもしろくなかったか」を確かめることがとても大切です。
そして、すぐさま「④」へ。
読み終えた後、「感想文を書く」というお決まりの活動よりももっと大切なことは、「仲間と感想を交流し合うこと」「語り合うこと」です。「わたしは、こんなふうに読んだけれど、あなたは、どう?」「わたしは、ここがよかった」「ぼくは、こんなところがおもしろいと思ったよ」と自由に語り合う時間をたっぷりととることです。感想文にまとめさせる必要はありません。「大人」になったときに、感想文なんかにまとめることなどめったにないのですから。それより「語り合い」です。
皆との語り合いを心から楽しいなあと感じさせることができれば、子らは次の作品へと自ら手を伸ばし、読書を生涯にわたって楽しんでいけるはずです。
読書の秋です。
最初に紹介した11の作品。
中学生に戻って、読んでみてはどうでしょうか。
そして、語り合えたら、なお楽しいですね。
