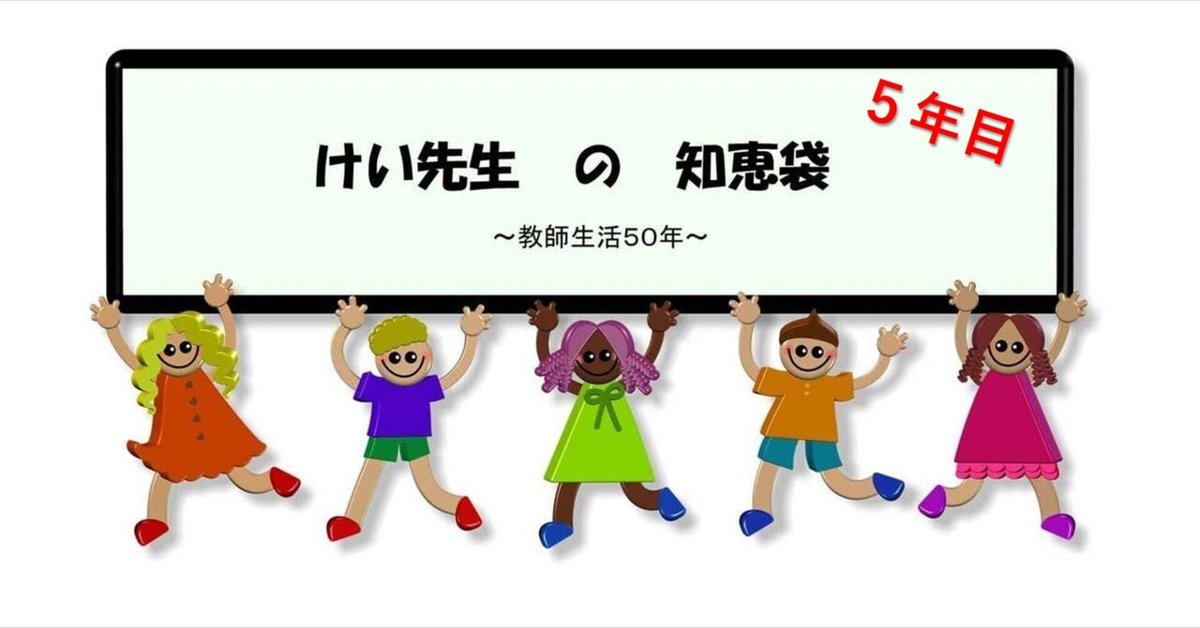
不登校(5)【255限目】
2025.2.13
不登校については【189限目】【201限目】【202限目】【240限目】と、4回記載してきました。不登校の理由は人それぞれ違いますが、少しでもこちらのnoteがヒントになればと思います。
【240限目】では、不登校になったお子さんに、担任の先生や家族がその子の話をよく聞き、無理やり学校に行かせず見守ることにし、焦らず、無理をさせず、その子のペースで生活することを優先することにしました。
学校に行くときは、保健室登校から始まって少しずつ生活のリズムが出来たようでした。
先日、電話をしたときは、学校に行きたくない日もあるけれど、そんな時は休ませて子どもの気持ちを尊重する生活を続けていったら、休んだ次の日は学校に行くというような生活になったとのことです。
今は、たまに休む日もあるけれど、友達もできて、その日は友達とバレンタインのチョコレートを作ると言って出かけたそうです。学校の中でも、安心できる居場所ができたようだと言っていました。
不登校の状態でも、子どもは本人なりにいろいろ考えて成長し、学校で学ぶ代わりに、自分の内面を見つめなおし、じっくり考える時間になったと思います。
【Dearにっぽん】もういちど、学校〜玖珠町立くす若草小中学校〜不登校経験者が安心して学べる新しい公教育モデルとは? を見て
(NHK 2025.2.13)
文部科学省の調査によりますと、日本の不登校児童生徒は年々増加しています。
そんな中で、大分県、玖珠町の山間に開校した新しい公立小中一貫校の紹介が、NHKの放送でありました。ここは、従来の学校とは違う教育モデルを採用し、不登校や登校しぶりを経験した子どもたちが安心して学べる公立の学校です。
先生たちは一般の学校から赴任した先生が中心になっている学校なので、今までとはちがった新しい公教育だということに私は驚きました。
私が勤めていた市には、不登校や行き渋りの児童生徒は、教育委員会が設置する教育支援センター(文部科学省のデータでは全国で1142ケ所)があり、そこが、居場所や学びの場所になっています。
学校とは違って、現役の先生が指導するのではなく、退職された先生方(多くは管理職経験者)が指導されている施設になっています。
くす若草小中学校(小中一貫校)とは
全国的にも珍しい、くす若草小学校は、小学1年生から中学3年生までが通う義務教育学校で、従来の学校と違うユニークな教育スタイルを実践しています。
・在籍する児童生徒数22名(全員が不登校や登校しぶりを経験)
・教員数10名(一般学校から赴任した先生が中心)
・特徴的な点、校則なし、宿題なし、決まった行事なし
・登校率、開校以来、平均8割(不登校経験者にとって高い数値)
この学校の教育方針は「無理に学校へ行かせるのではなく、子どもたちが安心して過ごせる場所を提供すること」にあります。
日々の授業や学校生活も、決まったカリキュラムがあるわけではなく、児童生徒の興味や意欲を尊重しながら柔軟に組み立てられるのが特徴です。
校則や宿題がなく、決まった行事もないこの学校は、「なぜ学ぶのか?」「どうすれば自分らしく生きられるのか?」といった根本的な問いに向き合いながら、新しい学校の在り方を模索しています。
この学校が設立された背景には、全国的に増加する不登校の児童・生徒の課題があります。
柔軟な学習環境と独自の教育スタイルを実践するために、以下のような教育方針が実践されています。
・自由な通学スタイル
・個別の学びを重視
・探究活動を重視した授業
・異年齢学級による学びの多様化
・「対話」を重視した教育
その結果子どもたちに起こった変化と成果
・昨年まで100日以上欠席していた生徒が、現在は一度も休まずに通っている。
・以前対人関係が苦手だった子が、サークル対話を通して積極的にコミュニケーションをとるようになった。
・学校に行くこと自体がストレスだった子どもが楽しそうに学習に取り組む姿が見られるようになった。等。
「学校に来なければならない」と、言う義務ではなく「ここに来ると楽しいことがある」「自分の居場所がある」と、感じられることが、子どもたちの一歩につながっています。
この番組を見て
子どもが不登校や行き渋りになったとき、無理に学校生活をさせるのではなく、自分の好きなことや出来ることから学校生活になじんでいき、友達と過ごす時間を増やしながら、子どものペースを大切にすることで、学校に行きたいという気持ちになれたと思います。
10人の先生たちが、22人の子どもたちへのサポートや日常の教育現場での挑戦の成果です。寄り添い話を聞くことで子どもの心を開き、先生たちと子供たちとの触れ合いが、心を癒してくれたと思います。
学校に戻る過程は、一人ひとり違うので、子どもの気持ちを尊重しながら、子ども自身が「行きたい」と思える環境づくりが大切です。
不登校という課題に対して、公教育の可能性を玖珠町が提示した新しい学校モデルで学んだ子どもたちが成長し、自分らしく生きていくことができれば、今後の公教育の未来を考えるヒントになるかもしれないと思いました。

【今週のけい先生】*担当:夫(父)
立春が過ぎて10日が過ぎましたが、雪交じりの寒い日があり温かい日差しを感じる日もありました。けい先生は庭に出て、梅の花が咲いた!種から育てたビオラが初めて咲いた。喜寿の色の紫色の花が咲いた!と、何度も庭に出て、喜んで眺めていました。
次は、バラの剪定と植え替えをすると張り切っていました。
【編集担当より】
今日は、バレンタインデーです。チョコレートの甘い香りが街の中に漂っているように思います。チョコ好きとしては、つい百貨店に足を延ばしてみようかと思います。
女性の多い職場で働いていましたので、義理チョコをいただいた際のお返しにいつも頭を悩ませました。ありきたりでも面白くないけれども、あまり気合の入ったお返しも良くない。ギリギリのラインが難しいものです。
色々と考えた結果、フロアの数少ない男性に声をかけて、みんなでホワイトデーにケーキを買ってくることにしました。会議室でみんなで食べるみたいな感じで、結構よい方法だったかと思います。
この時期になると、本命チョコについてや今のトレンドについて、義理チョコが減ったなどなど、バレンタインにまつわる話をよく目にします。なんだかんだみんなイベントが好きですよね。
イベントごとは、乗っかったもの勝ちが信条ですので、帰りに自分へのご褒美チョコでも買いましょうか。
