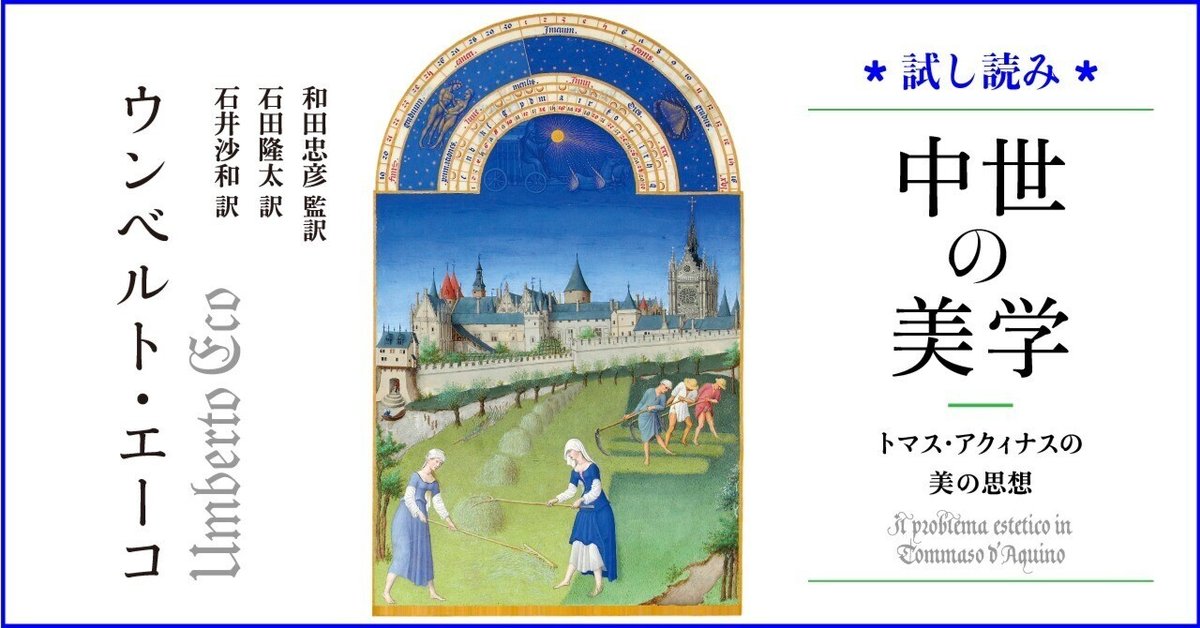
【試し読み】ウンベルト・エーコ『中世の美学――トマス・アクィナスの美の思想』(和田忠彦監訳、石田隆太・石井沙和訳、解説=山本芳久)
日本にもファンの多いウンベルト・エーコ(1932–2016)。彼が20代前半で執筆し、初めて出版したのは「中世の美学」に関する本でした。このたび満を持してその邦訳を『中世の美学――トマス・アクィナスの美の思想』として刊行します。
エーコと言えば、中世の修道院を舞台にした小説『薔薇の名前』(1980)が世界的大ベストセラーとなり、86年には映画化もされました(ジャン=ジャック・アノー監督、ショーン・コネリーとクリスチャン・スレーター主演)。エーコの本や映画を通して、西洋中世の世界に魅了された方も多いのではないでしょうか。私もその一人です。

今でも版を重ねるロングセラーの王道である。
とはいえ中世は一昔前まで「暗黒時代」と呼ばれていました(これについては、ウィンストン・ブラック『中世ヨーロッパ ファクトとフィクション』平凡社、2021年など参照)。エーコが『中世の美学』を執筆した当時、学問の世界でも「中世に美学はない」というのが定説でした。その定説を覆し、美の思想の鉱脈を切り拓いたエーコの原点たる本書の成り立ちについては、ここで公開する監訳者和田忠彦さんのあとがきをご覧ください。トマス・アクィナスについては山本芳久さんが分かりやすく解説してくれています。ちなみに好評のカヴァー装画は、《ベリー公のいとも豪華なる時禱書》から「6月」の一葉を選びました(装丁は小川順子さん)。ベリー公の「コレクション」は本書にも登場するので、読んでみてくださいね。

***
物語作者エーコの原点を知るために
訳者あとがきにかえて
和田忠彦
『トマス・アクィナスにおける美学の問題』(Il problema estetico in Tommaso d’Aquino)には三つの版が存在する。初版1956年(Edizioni di Filosofia 社刊)、第二版(本書)に第八章「結論」と併せて書かれた序文を添えた1970年(Bompiani社刊)の版。そして第三の版は2012年、『中世思想論集』(Scritti sul pensiero medievale, Bompiani 2012)に収載された本稿冒頭に序文を附し、修整短縮した第八章「結論」を添えた版である。
だが本書第一章冒頭で示した仮説、つまり美学をバウムガルテンあるいはクローチェ的な意味でとらえる哲学であるとすれば、「中世人には美学的な関心がなかったことになる」が「美しさの価値、その定義や機能、その生み出し方や楽しみ方といったさまざまな関心におよぶ分野だと理解するなら、中世人はたしかに美学について語っていた」(10頁)とする二二歳から二四歳にいたる青年エーコが立てた仮説は、その後一貫して揺らぐことがなかった。
美学とは芸術についてあらゆる点から考察することであるなら、哲学や神学を含む中世の議論には美学の問いが溢れている。
事実、2005年のミラネジアーナでの講演「美しさ」においても、若き日の仮説(に寄せる信頼)が変わらないことをこんなふうに述べている。
わたしは一九五四年、トマス・アクィナスについての小論ではあったが、美をめぐる問題をタイトルに組み込んだ卒業論文で美学の学位を取得した。(中略)五〇年もの歳月を経て、その間何度も美の概念について考えたのに、答えは当時とまったく変わらないことに気づく。まさに、時間とはなにか、と尋ねられたアウグスティヌスが答えたとおりなのだ。「誰にも尋ねられなければ答えは分かっている。だが、それを尋ねる者に説明しようと思うと、それができない」
一九七三年に(中略)ディーノ・フォルマッジョの芸術の定義を読んだとき、自分のもっていた不確かさが慰められた。そこにはこう書いてあった。「芸術とは人間が芸術とよぶすべてのものである」。だから、わたしもこう言おうと思う。「美とは人間が美とよぶすべてのものである」
「美しさ」
あるいは、1996年に発表した自伝的エッセイ「どのように書くか」(『文学について』2002年刊収載)においてもこう述懐したうえで、じつはこの仮説への一貫した信頼が自身の物語ることへの執着と希望に結びついていることを告白している。
トマス・アクィナスの美学的問題について書かれた卒業論文の口頭弁論を行った際、わたしは二番目の指導教官(その人物こそアウグスト・グッツォ教授です。といっても後になって、わたしの文章をそっくりそのまま出版してくれはしましたが)に反駁されるという憂き目に遭いました。要するにその場で言われたのは次のような事柄です。君は自分の研究のさまざまな側面を何から何まですべて俎上に載せ、それでいてまるでひとつの探究を行っているかのように論じている。実を結ばぬ思考の軌跡、後になって放棄してしまう仮説までも書き留めながら。ところが、成熟した学者というのはそうした経験を一度すべて味わいつくした後、公に(最終稿のかたちで)出すのはその結論だけなのだと。わたしは自分の論文がまさに教授の言うとおりのものであることを一応認めはしたものの、それが限界だとは感じていませんでした。逆にそのとき、確信したのです。あらゆる研究はこのようなやり方で「物語られる」べきなのだと。そしてのちにわたしが書く批評作品はどれもみな、まさにそのようにしてつくりあげられたものだと思っています。
そのようなわけで、わたしは物語を書かずとも穏やかでいられました。その実、語りへの情熱を別のやり方で満たしていたのですから。そしてのちに物語を書くことになったときでさえ、それらはある探究の編みなおしであるほかなかったのです(語りの世界ではそれを冒険とよぶまでのことです)。
この述懐から思い浮かぶのは、小説第一作『薔薇の名前』のカヴァー袖に添えられた作者エーコ自身による惹句「理論化できないことは物語らなければならない」だろう。それは、卒業論文を書いたときから自身のなかに絶えることなく息づきみずから実践を重ねてきた信念が、長篇小説というかたちで読者の前にあらわれたことを意味していたのだと確認できるあきらかな痕跡でもある。しかも、物語の舞台は中世の修道院―もっとも馴染みのある世界、もっとも蓄積のある資料を活かすことのできる時代と舞台―それはごく自然な選択だったと、作品発表後繰り返し述べていたエーコにとって、ここに引用紹介した卒業論文の副査アググスト・グッツォの指摘がどれほど貴重なものであったかは言を俟つまでもあるまい。
だが、中世との出遭い、トマス・アクィナスの美の思想との出遭いを準備したのは、エーコがまだ故郷アレッサンドリアで送った高校時代の出来事である。
高校の哲学教師ジャコモ・マリーノから受けた影響の大きさは、「いま読みなおしてみても師の授業中にとったノートは現代的である点において何の遜色もない」と最晩年「知的自伝」(Autobiografia intellettuale)(Library of the Living Philosophers, Open Court, Chicago 2017)で述懐するほどのものであったことがうかがえるからだ。とりわけトマス・アクィナスについての授業の魅力は、エーコをはるか遠く、卒業論文にはじまり小説『薔薇の名前』にいたるまでの長い道程を支えつづけ、『中世美学における芸術と美』(1959)以来の中世に関する1300頁を優に超える著作を生みだす原点となったようにみえる。
暫しこの「自伝」を傍らに、若き日のエーコの足跡をたどってみることにしよう。
高校時代のエーコは、当時の流行を反映してと言うべきか、クローチェの著作にもふれるにはふれたが、後年『カントとカモノハシ』(1997)でも言及するように、クローチェは「あまり芸術が分かっていないという印象を受けた」ので、トリノ大学に進学してから読んだジョン・デューイの『経験としての芸術』(1934)が殊更「正真正銘の解放」として魅力的に映ったと回想している(前掲「知的自伝」)。そしてそのトリノ大学の教師陣には、現象学のルチャーノ・アンチェスキ(ボローニャ大学)とエンツォ・パーチ(パヴィア大学)のふたりを除く、主だったポスト観念論哲学者のほぼ全員が集まりつつあったという偶然も、青年エーコをさらに哲学へと向かわせる大きな要因だったと言えるかもしれない。なかでも中世研究者カルロ・マッツァンティーニとの出遭いなしに、エーコの中世への愛着、さらにはトマス・アクィナスにおける美の概念についての関心を深めることはなかったと前掲書の回想からうかがうことができる。
そうして深まりつつあったトマスへの美学的関心に決定的な影響をあたえる存在が大学二年次に登場する。美学者ルイージ・パレイゾンが着任したのである。その講義はどれも、「〔パレイゾンの恩師アウグスト・〕グッツォのような劇場型でも、〔ニコラ・〕アッバニャーノの懐疑的でアイロニカルなものでもなく魅力的で、明晰かつ卓抜な細部へのこだわりに満ちた殊の外厳格なもの」とエーコの眼には映ったようだ。やがてエーコは、パレイゾンのもとでトマス・アクィナスの美学的問題について卒業論文を書く決心をする。
以上が青年エーコの、そして本書初版の基となる卒業論文の主題をめぐる前史である。
こうして本書の基となる卒業論文が生まれ、さらに四半世紀以上を経て、中世を舞台にした小説が生まれ、夥しい著作のなかに、1300頁超の中世論が脈々と書き継がれ纏められていくことになるのだ。
エーコにとって物語世界とは「真実のモデル」であって、現実世界ではない。
物語世界はやり直しや矯正がきかない、だから神でさえ手出しができないのだ、と繰り返しエーコは述べている―そんな物語への揺るぎない信頼に、本書を起点とする中世とトマスの美の思想にたいする一貫した主張が重なってみえるとしても、それはけっして強引な類推ではないだろう。
物語作者エーコの原点はトマスのなかに美の思想をもとめた若き日の著作にあるのだから。
ところで故郷アレッサンドリアの人びとの懐疑的な姿勢には常にユーモア精神が潜んでいる。それはすぐれて建設的な姿勢なのだ―そうエーコが話すのを幾度か聞いたことがある。逝ってから六年余、思い返してみると、故郷の人びとの特徴を悉くエーコ本人が体現していたことに気づく。その特徴は、晦渋にすぎると2012年版の序文で述べていたこの最初の著作においても、じつは随所に潜んでいるとみるのは、牽強附会にすぎるだろうか。
* * *
最後に、ご多忙のなか、迂生のような初学者にも全体を見通すための示唆に富んだ解説を寄せてくださった山本芳久さんに心から感謝を申し上げる。かねてより平明にして深いお仕事に多くを学んできた。本訳書の刊行にあたって、当初から是非にと願っていたこともあって、はじめて拝読したときの歓びは忘れがたいものであった。拝読しながら、半世紀ほど前、だだっ広い閑散とした教室で聴いていた山田晶先生の講義を思い出した。いつも腰からぶら下がっていた手ぬぐいのことも。
さて訳出にあたっては、まず石井沙和が暫定稿を作成し、それを石田隆太が専門研究者として徹底的に見直し完成稿とし、最後に和田が確認を行い確定させた。そのいずれの段階においても、慶應義塾大学出版会編集部の片原良子さんが細やかにして緻密な作業を惜しまず継続してくださらなければ、本書は完成に漕ぎつけられなかったであろう。ここにあらためてお礼を申し上げたい。
二〇二二年九月
***
↓本書の詳細はこちらから

#中世の美学
#ウンベルト・エーコ #エーコ #トマス・アクィナス
#和田忠彦 #石田隆太 #石井沙和 #山本芳久
#慶應義塾大学出版会 #KUP #keioup
