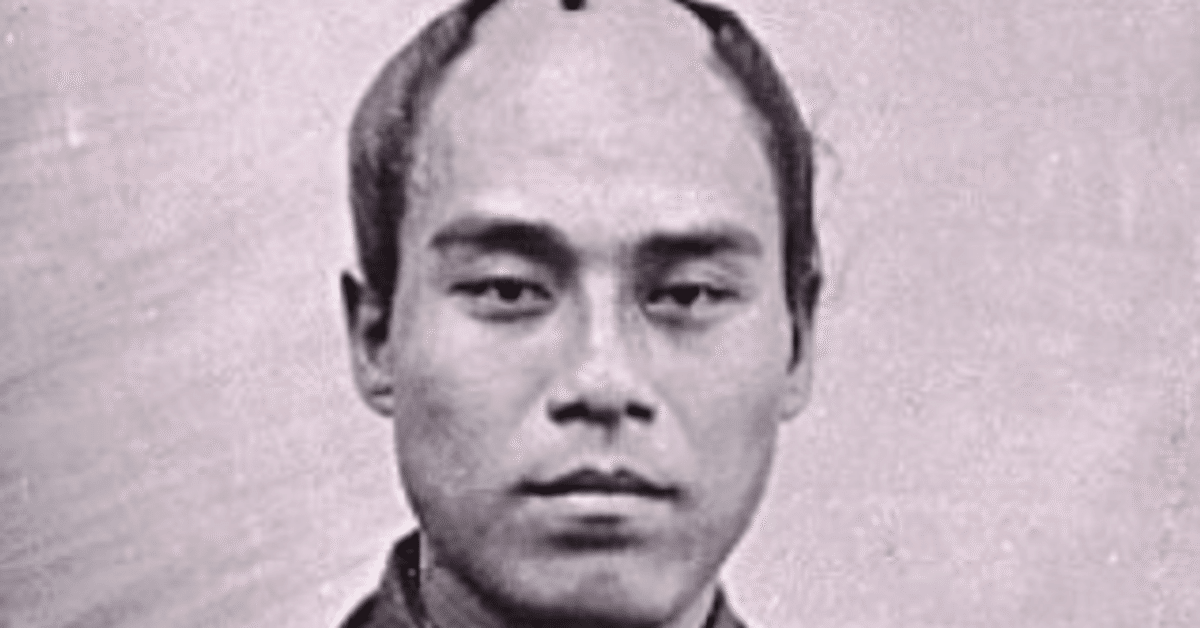
福沢諭吉「中津留別の書」前半~個人の自由独立と男女の平等
「中津留別の書」は1870(明治3)年、母と兄の娘を東京に迎えるために中津を訪れた際、故郷の有志者に対して書き残した福沢のメッセージである。明治になったとはいえ、中津を含め各地には江戸時代の封建的な価値観が根強く残っていた。後に発刊される『学問のすゝめ』の原型となる重要なテーマが述べられている。
要約
人は、一身独立をはかり、一家の生計を立ててこそ、はじめて万物の霊(あらゆる生物のなかで一番優れていること)というべきである。
自由とはわがままという意味ではなく、他人を妨げない範囲で自分の心のまま物事を行う意味である。個人の自由独立は大切なもので、これを誤解せず、自由の分限を守れば、一身独立して一家独立し、一家独立して一国独立し、一国独立して天下も独立すべし。
人の守るべき道(人倫)の根源は夫婦にある。男女は平等である。だが、日本や中国には妻以外に妾を複数囲う習慣があり、婦人を下女のように扱っている。主人が妻を軽蔑すれば、その子はこれに倣って母を侮り、その教えを重んじない。主人は外に働きに出て家にいることが少なく、これでは子供の教育はままならない。
論語に「夫婦別あり」という言葉があるが、これは2人ずつ夫婦の区別を正しく定めるという意味であるべきだ。だが実際は妾がおり、そうなっていない。世の男性はもし婦人と逆の立場になったら婦人に仕えることが出来るのか問いたい。
現代語訳
人は万物の霊であるというのは、ただ耳目鼻口手足をそなえ言葉を話し、寝食することを言うのではない。その実は、天道に従って徳を修め、人の人たる知識見聞を広くし、物に接し人と交わり、自分の一身独立をはかり、一家の生計を立ててこそ、はじめて万物の霊というべきである。
古来より中国・日本人はあまり気付いてこなかったことだが、人間には生まれつき自主・自由という道がある。ひと口に自由というと我がままのように聞こえるが決してそうではない。自由とは他人を妨げずに自分の心のままに物事を行う意味である。父子・君臣・夫婦・朋友、たがいに妨げず、各々その持ち前の心を自由自在に働かせ、自分の心を持って他人の身体を制さず、おのおのが一身の独立をなせば、人の生まれながらの性質は正しいゆえ、悪い方へは行かないだろう。
もし勘違いした者がいて自由の分限を越え、他人を害して自分を利そうとする者があれば、それは人間の仲間に害ある人ゆえに、天が罰するところ、人が許さないところ、身分の上下・長幼の差別なく、これを軽蔑してかまわず、これを罰しても差し支えない。このように、人の自由独立は大切なもので、この意味を誤った時は、徳も修めることができず、知識を開くこともできず、家も治まらず、国もたたず、天下の独立も望むことは出来ない。一身独立して一家独立し、一家独立して一国独立し、一国独立して天下も独立すべし。士農工商が互いにその自由独立を妨げてはならない。
人倫の大本は夫婦なり。夫婦ありて後に、親子あり、兄弟姉妹あり。天が人を生み出した、世界の始まりの時も一男一女であったろう。数千万年の長い年月を経たが、その割合は同じである。また男も女も、等しく天地の間にいる一人であり、その価値に差別があるべき道理はない。
今も昔も中国・日本の風俗を見ると一人の男子が多くの婦人を妻と妾にして、婦人を下女のように、または罪人のように扱い、これを恥じる様子はない。浅ましきことではないだろうか。一家の主人が妻を軽蔑すれば、その子はこれに倣って母を侮り、その教えを重んじない。母の教えを重んじなければ、母がいてもいないようなものである。ましてや主人は外で働いて家にいることが稀なので、誰がその子どもを教育するのだろうか。哀れと言ってもいいきれない。
『論語』に「夫婦別あり」と書いてある。別ありとは、分け隔てがあるということではないだろう。夫婦の間には情こそがあるべきである。他人のように分け隔てがあっては、家庭は安定しがたいだろう。それゆえ別とは区別の意味で、この男女はこの夫婦、あの男女はあの夫婦と、2人ずつ夫婦の区別を正しく定めるという意味であるべきだ。しかし現在、大勢の妾を養い、本妻に子どももいて、妾にも子供がいるときは、兄弟同士で父は1人で母は異なる。夫婦に区別あるとは言えないだろう。男子に2人の女性を妻として迎える権利があるならば、婦人にも2人の夫を作る権利がないといけない。天下の男子に試しに聞いてみよう、妻が別の夫を愛し、一婦二夫、家にいることがあれば主人はこれを受け入れてその婦人に仕えるか?
また『春秋左氏伝』(孔子編纂とされる『春秋』の注釈書)には妻を交易することも書かれている。孔子様は世の風俗が衰えるのを憂いて『春秋』を著し、夷狄だの中華だのと、やかましく人を褒めたり、けなしたりされているが、妻を交易することはさほど心配しなかったのだろうか、素知らぬ顔をして咎めていない。あるいは「夫婦別あり」も他に解釈しようのある言葉だろうか。儒学者の先生方も説明すべきだろう。
考えたこと
① 個人の自由独立は男女平等に
明治3年にすでに福沢は男女平等を主張している。これは当時としてはかなり進んだ女性観と言える。その後も福沢は1880年代に『日本婦人論』などを著して女性の地位向上や男女平等を発信し続けました。特に儒教にもとづく男尊女卑思想を批判し、江戸時代に書かれた貝原益軒の『女大学』を批判し、自ら新しい女子教育のあり方や、男女平等の原則に基づく男女関係、父母が手本を示し団欒を大切にする家族関係、などを記した『新女大学』を著しています。
② 夫婦間の対等性が子どもの教育においても大切
これは保護者面談をしていて感じます。子どもが精神的に不安定だったり、他人に対して攻撃的な子だったりする時、すべてではないですが、夫婦間の関係がこじれていたり、家庭の教育においてどちらか一方が極端に力を持っている場合が多いです。
これも習慣の力が成せるものです。例えば、夫婦の間で悪口を言い合っていれば、子どもも人の悪口を平気で言うようになります。どちらか一方が相手の意見を全く尊重しないような関係であったら、相手の意見を尊重しない態度が子どもにも移ります。これは子どもの前で親が直接それらをやっているという意識がなかったとしても、子どもに何かしらの形で伝わります。
家庭教育というと親子間の関係にどうしても目が言っていますが、その前提となるのが、夫婦間の関係といっても過言ではないでしょう。「人倫の大本は夫婦にあり」、夫婦円満が良い教育の秘訣でもあります。
