
まちづくりにおける、子育て空間のデザインについて、幼児施設を600件以上設計してきた建築家の日比野拓さんと考える
進む一方の少子化と、老朽化が進む園舎。
建て替える財源もなければ、そもそも子どももいなくなるし。。
でもこのままだと建物も危ない。保育士はいないし。。
都農町に限らず、全国の地方、特に過疎地において切実な課題をテーマに、「つの未来会議」第6回を開催しました。
ゲストとして、日本全国から海外まで、幼児・福祉施設に特化した建築家であり、自らも保育園やカフェダイニングを経営する日比野拓さんに都農町までお越しいただきました。
町長をはじめ保育・幼稚園関係者、町役場、町民の方々と、理想的な子育て空間について、200枚以上の設計実績を見ながら話し合いました。


1.なぜ、子どもの空間は大切なのか
日比野さんが子ども施設をデザインする際のアイデアの源泉は、いまだに3歳のころの実家にあった空間の記憶。
アメリカの研究科学雑誌でも発表されていますが、
「空間認識能力」は「言語能力」や「数学力」に匹敵するほど重要
複雑な空間を探索したネズミの海馬はそうではないネズミの4万倍も多くの神経細胞を持ち、海馬組織は15%増加し、高い空間認識能力を持つ

・私の3歳のときの実家の写真。父も建築家でした。
・3歳の記憶がいまだに強く残ってます。
・窓を遊具として開け閉めしたのでしょっちゅう壊れた。
・与えられた遊具でなくても自分で見つける
・30センチもない段差は貴重な遊び道具。
・とびおりたときの達成感、椅子になって腰掛けて話したこととか。
・だんだん高いところからとびおりようとステップアップ
・椅子のメーカーのシールが裏にはられてたことを今でもおぼえてます。
・隙間があったのでどうしても入りたくなって覗き見した。
・子どもしか見えない景色をいまだに覚えている。
2.遊具はいらない
ニューズウィーク誌で『世界でもっとも前衛的な幼児教育』と評されたイタリアのレッジョエミリアの事例も共有、園庭に遊具はほとんどなく、自然に勝るものはないと。
・レッジョエミリアを見て、遊具がないことに気づく。
・豊かな自然の木々や芝生、高低差。
・日本では芝生にするとはげるよね、となりがち。
・イタリアでははげる理由を学べばいいじゃないかと
・はげたところにも虫がいて探すのは楽しい
・落ち葉は清掃が面倒だけど、子どもにとっては気づきや学びになる。
・子どもにとっては図鑑の世界。
・園庭に出るところに虫や花の図鑑がおいてある。
・大人はその探求を手伝うだけ。

3.色やキャラクターはいらない
これはぼくも感じるところ。
日本の子ども向け施設は、どうしてこうパステルカラーとか虹色が多いんでしょうね。
中国でも同様なことを感じました。
キッザニアの設計をする際にも、大人と同じ色彩感覚でつくったことを思い出します。
虹とか雲とか色とりどりに塗ってある園舎もありますが、虹や雲は空に出たときに観ればよいですね(笑)
動物の顔をしたバスも、遊園地に任せておけばいいですね(笑)
犬とか猫は本物が一番ですね(笑)
この写真は面白かった。
雨が降ったほうが、滑りやすくなるので子どもたちは泥だらけで遊びに夢中。大事なことは大人が止めないことだと。

・環境をつくるときに大事にしているのは、色を使わないこと。
・主役は子ども
・日本の子育て施設は遊園地のようにデザインしがち
・ディズニーランドだったら、ミッキーやミニーが主役だけど。
4.本に触れられる環境が大事
次のテーマは『本』
日比野さんから、本と学力の関係を踏まえて、どう本を読みたくなる空間をつくるかについてお話がありました。


・本をテーマにした保育園。
・低いところは子どもが読める本
・高いところは大人が読み聞かせしてあげたい本があります。
5.食の空間
5歳児の肥満時は過去最高だそうです。
結論は「ジャンクフードの食べすぎ」「運動不足」と日比野さん。
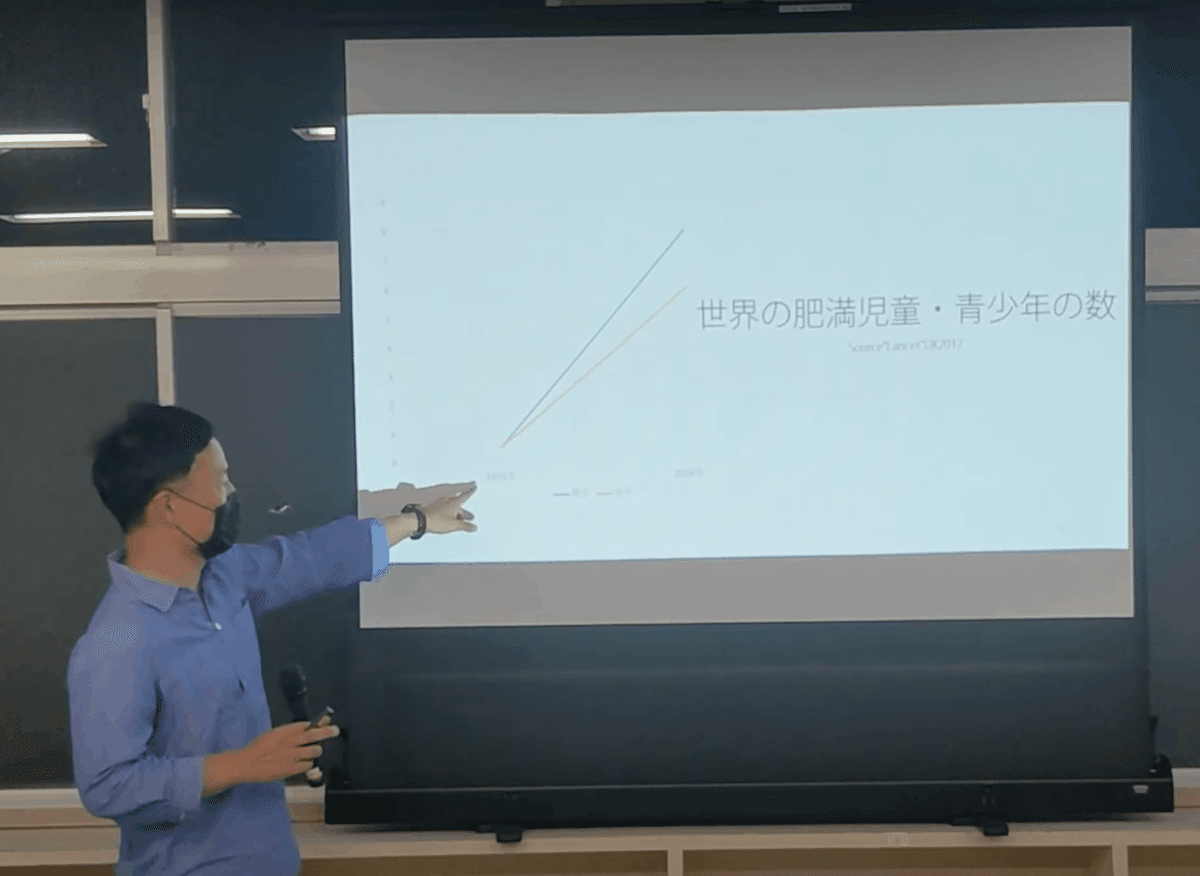
・幼児施設の設計で特に食空間を大事にしています。
・食の空間を外につなげることをよくやります。
・大人もオープンなカフェで食べると気持ちがいいですよね。一緒です。
・外とのつながりがある食の空間は食べる量も増える
・子どもが参加する仕掛けも。
・子どもが食に近づいていくことが大事。

6.身体を動かす遊びを増やす
山梨学院の中村和彦教授によると、幼少期に子どもが経験すべき動作は36あるそうです。
・たとえば「掘る」はスポーツではできない動作。
・動作の多くは日常の中で身体を動かす遊びにある。

日比野さんが都農町に到着してから、都農町内をまわったのですが、外で遊んでいる子どもをほとんど見かけられなかったのが残念だと。
これはぼくも最初に来た頃、同様の印象を持ちました。

7.意味のある段差
日比野さんは、幼児施設の設計で、積極的に段差を取り入れてます。
もちろん、保育士や保護者からすれば「危ない」と反対されることを承知でチャレンジしています。

段差は、保育士も保護者も心配。
でも、段差は飛びたいものですよね。
自社で経営する保育園は3年間、一人も怪我をしていません。
自分のスピードで、自分ができる範囲を覚えていくものです。
園庭の事例紹介では、もともとの土地の形状をいかして、高低差のある園庭にしたことで、いつでも子供達はかけまわっているそうです。楽しそう!

日比野さんから最後にまとめのメッセージ
・ちょっと危ないが大事
・失敗から成長、怪我から成長
・遊具がなくても、ちょっとした段差や勾配で子どもは遊ぶ
・過保護にならないこと
・好奇心を奪わないこと
・失敗する事を恐れないこと
・挑戦すること
・答えを与えるのではなく、考えたり創造して、行動する機会を与える

8.遊びの導き役
1時間近く、日比野さんから200枚以上の幼児施設のスライドを見た後で、参加者同士で話し合い、質問がポストイットで集められました。

町長も交えてパネルディスカッション。
盛り上がったテーマは「公園は必要?」

都農町は自然豊か、都会に比べれば公園面積も広い。
にもかかわらず、町民、特に子育て世帯からは子どもを安心して遊ばせる公園が欲しいという声をよく聞きます。
町長が子どもの頃は、神社や川や畑をかけずりまわって遊んでたそうで、今、環境は変わらないはずなのに、なぜ遊ばなくなったのか?
子どもの変化というより、大人の変化かもしれませんね。
いまの大人たちが子どものころは、近所のお兄さん、お姉さんと遊んでたから自然と危険を教えてもらえたように思います。
そのあたりの環境変化で、自然があっても遊べないんでしょうね。
自然を活かした遊びができるプレイリーダーが必要。
自然って一歩間違えれば、命を落とすんだよってある程度の導きが必要
9.小さな町だからできること
最後は、参加者一人ひとりが、「都農町の未来への提案」
理想の子育て施設を考えて発表しました。




参加者のみなさんからいただいた「アンケート」と「未来への提案」
建て替え、移転の必要性も高まってきた町立保育園をはじめ、これからの都農町にとって、子育て施設をどうしていくかは重要課題。
今後の企画の参考に、積極的に取り入れていきたいと思います。
【日比野さんの話で一番印象に残ったこと】
・大人が子ども達の可能性を信じる
・子どもの頃の体験の必要性を改めて学んだ
・あえて子育て支援センターと名乗らない
・他の人がハンデと思う事をプラスに捉える
・子どものころ、飛べる段差と飛べない段差を見分けていた
・子どもが主役
・子どもをリスペクトしているのがわかる
【都農町の理想の子育て施設】
・農の都らしいこども園・保育施設
・畑がフィールド!自然の中で遊び道具をつくる
・大人が変われる子育て施設
・幼保小中(高)が一貫した学び(体験・創造・コミュニケーション)
・大丈夫です!と言い切る
・中央保育所はいまどきの施設になってほしい
・自然の中でのびのびと育てる自分で考えることができる施設に
・親が不安を吐き出せる
・年上、年下が多く関わり互いに学べる
・インクルーシブ&ダイバーシティ
・町民全員が参加できるクリエイティブな環境
・36の動きができる施設
自分の可能性を伸ばしていけるか、開花させてあげれるか。
ものごとをゼロからつくりあげていく力をつけるのに遊びは重要。
小さい町は、やる気になって変革しようと思えば早いので大きな行政にインパクトをあたえることができるよう、地域をあげて子育て空間の仕掛けとしくみをつくっていきましょう!
