
#2024年の本ベスト約10冊
今年は自分の感性を守って耕すための読書を意識した。そのせいか、物語の力をつよく信じた一年だった。
思えば幼少期から今日までずっと、読書は私にとって世界ともっとも深くふれあう方法だったような気がする。生きるとはどういうことなのか、心とは何か、人はなぜ異なり、奪われ、傷ついて、愛するのか、物語は問いかける。その問いの中を登場人物と泳ぐとき、ことばも何ものも介さずに大切なものを共有した、という気持ちになる。物語はことばでできているのにね、なんでそう思うんだろう。
伊藤紺『気がする朝』

レモンイエローの装丁のように爽やかで感覚的な情景。シンプルな言葉えらびには一切の背伸びや飾りがなくて、読むだけで高校生のころの自分の感性に戻らされる。今年いちばんのリフレッシュ本!
僕らいっせいに喜び合って生きものは愚かなほうがきれいと思う
野口裕二『ナラティブと共同性』

臨床社会学の世界でナラティヴ・アプローチを研究してきた著者が、オープンダイアローグ(OD)や当事者研究の世界に衝撃を受け、そこから新しいナラティヴの課題と可能性をひらいてゆく。ときに研究は、凌駕する存在に出会ってしまうものなのだ、研究者を尊敬する。
自己の物語はわれわれの人生を支えてくれる一方で、人生を立ち行かなくさせることもある。そんなとき新しい自己語りの方法が必要になり、ODの独自技法はその効果が注目されている。ODでは、参加者それぞれがどのような物語をもっているかをお互いに理解しあうことを大切にする。多様な声が尊重され響きあう関係性、すなわち共同性を育てていく。その響きあいにより結果としてそれぞれの心に流れる愛の感情を重要な治療的要素とするところも特徴である。このロジックなき理論、2025年は本格的に学べたらいいなと思う。
エマニュエル・レヴィナス『全体性と無限』

レヴィナス(1906-1995)は、西洋哲学の文脈で「他者」を本格的に論じた哲学者。(これ以降は私の理解なので違ってたらほんとにすみません)
哲学とはスーパー平たくいうと「この世界とは何なのん」の学問で、古代から「世界は火でできてる」とか「水でできてる」とか、「世界とは神だ」とか、色々な研究がされてきた。近世になると「我思う故に我あり」に代表される「世界とは私による認識だ」という認識論が浸透する。しかし、本当にそうなのか?世界が私による認識であるとする場合、この世界に存在する他者は私の認識の範囲内の存在になってしまう。レヴィナスは、私が何をどうがんばっても把捉しえない〈他者〉があると考え、そもそも「私」は他者への関係によって初めて位置づけられる、という論で〈他者〉の絶対性を打ち立てた。
主著『全体性と無限』では上のような話に加えて、レヴィナスのオリジナルな概念である「顔」の議論が山場なのだけれど、私はその先の最後の章にある「愛」についての話がいつも気になる。卒論でもそれを取り扱ったけど、8年経った今でも「?」が多くて苦戦している。他者は何をどうがんばっても分からない存在なのだけれど、レヴィナスの言う愛は分からないまま肯定することや、ただ近づこうと手を伸ばすことだけではないようなのである。私はそれをずっと知りたい。
ともあれ8年ぶりに上下通読できてよかった。
コリーヌ・ペリュション『レヴィナスを理解するために』

この本は2018-2019年にフランスの大学で哲学科修士終了の学生たちとケアに携わる人々向けに行われたセミナーの記録で、こんな素敵なものが5年足らずで日本語訳出版されることに本当に感謝。今の日本のレヴィナス研究者の活動量と、レヴィナスの哲学が倫理・政治・医療と幅広い領域の人びとに響くものであることのおかげだろう。今年前半はレヴィナスの『存在の彼方へ』オンライン読書会に参加していた(のちに資格勉強のため断念)けれど、そのときも学生はもちろん牧師さんや医療従事者の方など色々な方が参加していた。
私は真の意味では他人と接近できないが、この他人が他者に対し責任を負うよう私に強いるからである。私が何もせず、他人についての話を聞こうと欲していなくても、私は他人に応答し、このようにして私は自分が何者であるかを語っているのである。
チョ・ヘジン『ロ・ギワンに会った』

ただ生きるため、脱北してブリュッセルへ逃げてきた青年ロ・ギワンの物語と、彼の足跡を辿るある記者の物語。
命がけで国境を越え、最愛の人を失い、生きるためだけに見知らぬ国へと流れ着いたここまでの道のり。それが何の意味もなかったことを受けいれなければならない、氷のように冷たい時間。彼は、懐かしさだけで故郷を思い出す甘い時間は、自分には今後いっさい訪れないだろうと悟った。
まさにこの「それが何の意味もなかったことを受けいれなければならない、氷のように冷たい時間」が終始流れる。地下鉄のにおい、病室のにおいがする。ギワンの視点描写が詩的でありながら手ざわりを与えてくる。失意と懺悔と後悔を胸に塗られながら、長く苦しみながら読んだ。あなたもロ・ギワンに会ってほしい。
小川洋子『密やかな結晶』

その島では、ある日突然何かが消滅してしまう。住民はその存在を思い出せなくなり、痛くも苦しくもなく、淡々と消滅した世界に順応して生きていく。やがてあらゆるものが消え去って…
夜の特急列車の中で涙が止まらず手を震わせて読んだのを覚えている。この物語には、人間にとって普遍的なものが描かれている。現実世界にも溢れているが、これをこのように伝えるのは「物語」でなくてはならないと思わせる確からしさがあった。感動した。
今年のなかから1冊だけ選ぶとするなら、この本だと思う。
寺尾紗穂『天使日記』
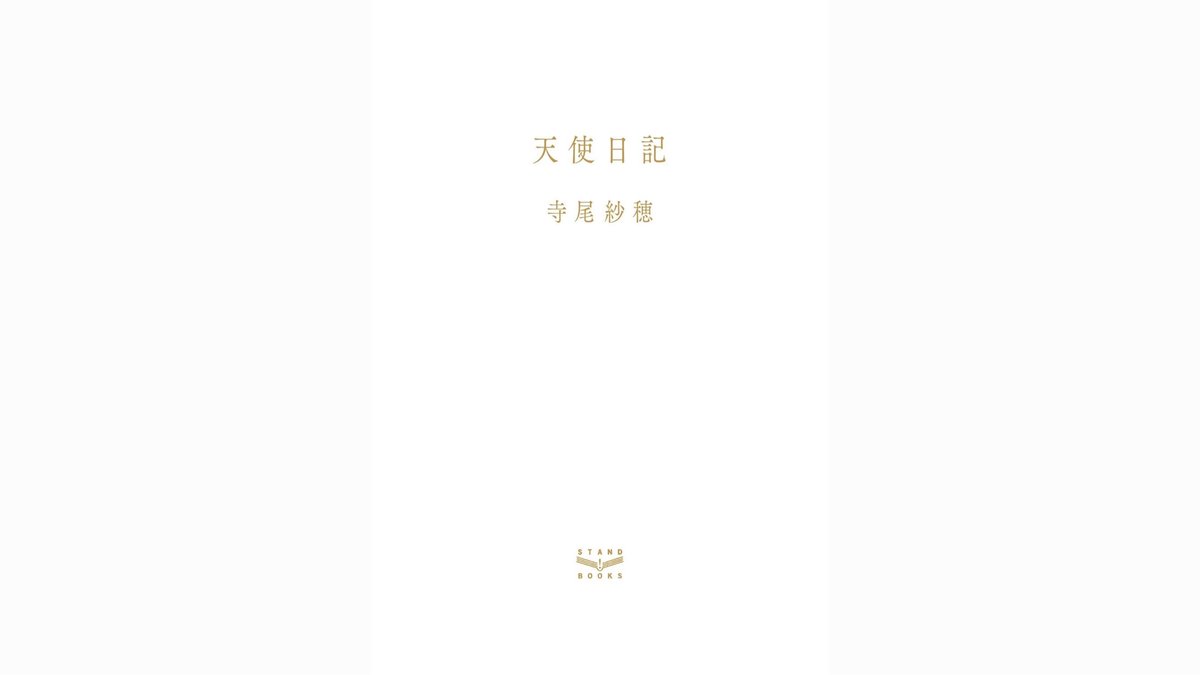
ミュージシャンであり文筆家である寺尾紗穂さんのエッセイ。今年の初め、人類学者の猪瀬浩平さんとのトークイベントで初めて寺尾紗穂さんにお会いした。ミュージシャンとして素敵な方だとは元々存じていたけれど、ご自身で調査研究活動をしていることをそこで初めて知った。このエッセイでは、娘ちゃんに天使が見える日々や調査の日々が綴られている。天使が見えることをそのまま受け取り信じることと、パラオまで自費で赴きご高齢の当事者へ取材することとは、彼女の中では地続きだ。人を愛し、世界に問い、ことばを信じる。研ぎ澄ませた精神で実直に取り組むさまがかろやかに綴られている。
平田基『居心地のわるい泡』

終末感のある世界の中で、くじらのところへ水の器を探しに行ったり、森が横断歩道を渡ったり、体が春になったりする漫画。世界へのパースペクティブを自由にしてくれる最高の作品。装丁も美しく全体として完成度が高すぎる。シンプルかっこいい。
バッシュ・シャーム/ギーター・ヴォルフ『世界のはじまり』

ターラー・ブックスをご存知だろうか。南インドのチェンナイにある独立系出版社でハンドメイド本やビジュアルブックを中心に児童文学や教育、社会問題など幅広いジャンルの本を出版している。ハンドメイド本は古布を原料にした手漉きの紙にシルクスクリーン印刷、糸かがりの製本で表紙も手張りで、一冊ずつ丁寧に仕上げられる。手にとって分かる、ものとしての強度のある絵本だ。ボローニャ国際絵本原画展で受賞した『夜の木』が有名だけど、私はこっちの方がおすすめ!中央インドのゴンド民族の世界のはじまりの神話。泥や種子や輪廻の話。ほんわりミステリアスな表紙の印象とは違いパワフルで楽しい絵と刺さる深淵な言葉。小学生のころ、この本で育ちたかった!ターラー・ブックスを訪ねるのが最近の夢。誰か一緒行こや〜
ユリイカ2025年1月号 特集 ハン・ガン

2024年10月10日、ストックホルムでハン・ガンの名が呼ばれ、ノーベル文学賞に選出された。私は仕事に慌ただしくしていて、数年前『回復する人間』を共有した親しい友人からの連絡で、夜更けに知った。
思い出したのは、5月のことだ。『別れを告げない』刊行記念のオンライントークイベントが白水社で催されて、その質問コーナーで「他者を理解することはできると思いますか」と尋ねさせていただいたときに、ハン・ガンさんが答えてくださったのは「理解することはできないと思っている。けれども、知りたい、教えてほしいと乞う姿勢をやめないことだ。」というような内容だった。そのときの彼女の人柄の滲み出た顔を思い出した。
ハン・ガンは「痛み」の作家だと思う。パーソナルな痛みから、戦争などの集団としての痛みも分け隔てることなくひとつの同じ「あなたが痛いということ」として扱う。その静謐でありながら正面から向き合うこと以外を赦さない筆致が唯一無二である。読めば、物語を生きたように痛く苦しく、物語が身体に伝わってくる感覚を覚え、次第にヒリヒリと癒されて自分のものになっていく。そんな作品だと私は思っている。
ハン・ガンの作品をすでに世界中の多くのひとが読み、痛み、傷つき癒されてきたという事実、そして賞をもらって今後一層広く訳され読まれていくことは素晴らしい。ハン・ガンの問い続ける営みが世界的に評価され、より多くの人が同じ問いに直面することが、心からうれしい。自らのなかの暴力を退けることはできるのか。暴力的な世界の中で生きることの理由は。ひとはなぜひとに酷いことをするのか。苦痛の限界はどこにあるのか。愛はどこまでゆけるのか。「理解することはできないと思っている。けれども、知りたい、教えてほしいと乞う姿勢をやめないことだ。」
ユリイカはハン・ガンへのインタビューから始まり斎藤真理子さんはじめ訳者陣、クオン社の方、トラウマ研究の宮地尚子さん、などと非常に豪華な内容で、皆様のハン・ガンへの信頼と感謝に溢れており必読の特集。
おまけ:2024年の音楽ベスト
今年は贔屓の1曲×12か月の形式で。
