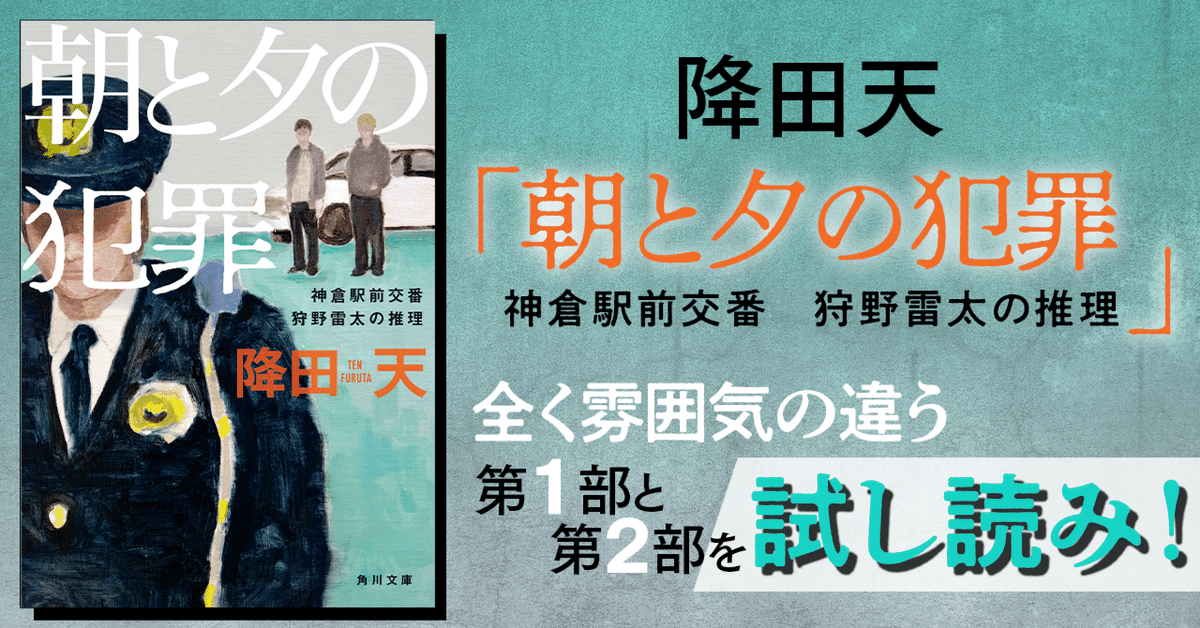
【試し読み】降田天『朝と夕の犯罪 神倉駅前交番 狩野雷太の推理』第1部・第2部の冒頭を特別公開!
降田天さんの傑作長編ミステリ『朝と夕の犯罪 神倉駅前交番 狩野雷太の推理』(角川文庫)が、2024年9月24日(火)ついに発売!
『偽りの春 神倉駅前交番 狩野雷太の推理』(角川文庫)に連なる「狩野雷太」シリーズ最新作であり、犯人視点から描かれる「倒叙もの」のミステリ小説です。
長編小説でありながら、第1部「朝と夕」と第2部「夜と昼」で雰囲気の異なる読み味が楽しめるのも、本作の魅力のひとつ。
そこで本記事では、第1部と第2部の冒頭を特別公開! それぞれの読み味をぜひ確かめてみてください。
あらすじ
マンションの一室で元刑事の警察官・狩野雷太は衰弱した男児と、傍らで餓死した妹を発見する。母親を取り調べるものの、その本名や、なぜ子どもたちを置き去りにしたのかは不明のままだった。しかし、彼女が過去に巻き込まれた誘拐事件が明らかになり、アサヒとユウヒという兄弟が捜査線上に浮かび上がる。彼らがこの誘拐を企んだ理由とは。2つの事件を結ぶ糸は何か? ハラハラが止まらない、心揺さぶる傑作長編ミステリ!
『朝と夕の犯罪 神倉駅前交番 狩野雷太の推理』試し読み
第一部 朝と夕
大事なのは誰から生まれたかじゃなく、
誰といっしょに飯を食ったかだ
セルバンテス『ドン・キホーテ』
1
黄色は「進め」だ。
それが“お父さん”からはじめて教わったことだった。
赤は止まれ。青は進め。黄色は全速力で突っ込め!
2
ビーッ。鋭いクラクションを響かせて、車が目の前すれすれを通過していった。風圧でネルシャツの裾がはためき、ドアをこすったのではないかと思ったほどだった。横断歩道の向こうに見える信号は赤だ。目に入った青年に気を取られ、注意がおろそかになっていた。一歩下がったアサヒの前を、色も形もさまざまな車がひっきりなしに流れていく。大学の最寄り駅のロータリーはいつも交通量が多い。
普段は長すぎると感じる待ち時間が、今は長いのか短いのかわからなかった。車道の信号が黄色になって赤になり、車の列が停まる。横断歩道の縞が向こうの端まですっかりあらわになる。青になった信号の下に立っている青年の姿が、再び視界に現れた。ずたずたのジーンズとナイキのごついスニーカー。金に近い色の髪に、いくつものピアス。ワンショルダーのバックパックを背負っている。
その青年をアサヒは知っていた。もう長い間、顔を見ていなかったが、ひと目でそうと気がついた。向こうもこちらに気づいているのかどうかはわからない。見覚えがあるような、というところだろうか。アサヒが彼を見つめているように、彼もアサヒを見つめているが、ほとんど無表情だ。
駅へ向かう学生や会社員に交じって、青年が足を踏み出した。アサヒはわずかに遅れ、駅から吐き出された群れに包まれて歩き出す。アサヒと彼とは互いを見つめたまま近づいていき、双方あと三歩ですれ違うというところで、急に彼がニカッと笑顔を見せた。二重まぶたの明るい瞳に、やんちゃな少年の面影が表れる。いたずらが成功したとき、ユウヒはいつもこんな顔をした。
「なんだ、そっちも気づいてたのか」
「ひと目でわかったよ。兄ちゃん、変わってないな」
「おまえは……」
秋晴れの空をバックに輝く金髪を見上げる。会わないうちに身長を抜かれてしまった。
「いや、おまえも変わってないか。だからわかったんだ」
「急いでる?」
ユウヒが信号に目をやって尋ねた。そうでもないとアサヒは答えた。講義までにはまだ時間があるし、間に合わなくてもべつにかまわない。ユウヒが引き返す形で、ふたり連れ立って横断歩道を渡った。ロータリーの中心にはちょっとした広場があり、待ち合わせスポットになっている。
「なんで歩行者用の信号には黄色がないんだろうな」
点滅する青信号を見てユウヒが言う。その横顔をアサヒはちらりと見たが、他意はないようだ。
「いくつになった」
「えー、たったひとりの弟の歳、忘れる?」
「正確には知らないから」
「冗談だって。十九。誕生日は結局わかんなくて、八月一日ってことになった。兄ちゃんは二十歳だよな。大学生?」
「政経学部の二年」
「かっけー。頭よかったし、真面目だったもんな」
「おまえは?」
「ラーメン屋のバイト店員。高校のときから続けてんだ」
進学はしていないのか。高校は卒業したのか。突っ込んで尋ねるのははばかられた。
「今日もこれからバイトなんだ」
「このへんなのか?」
「いや、神倉。今日は友達に会いに来てたんだ。美容専門学校行ってて、この近くに住んでんの。でもまさか兄ちゃんに会うなんてなあ。東京に住んでんの?」
「ああ、世田谷に」
「『ああ、世田谷に』」
ユウヒはアサヒの口まねをして、頭のてっぺんから足の爪先までじろじろと眺めた。特徴のない黒い髪や、地味なTシャツとネルシャツや、無難なメッセンジャーバッグを。
「東京住みのわりには垢抜けてなくない?」
「ほっとけ」
「そうだ、連絡先、交換しようよ」
言いながら、ユウヒはもうパーカのポケットから携帯電話を取り出している。アサヒもバッグから携帯電話を取り出した。
「あ、兄ちゃんもフツーのケータイなんだ。iPhone4Sとかスマホとか気になるけど値段がなあ」
最新機器に興味はなかったが、「だな」と話を合わせた。経済事情については進路のことより訊きにくい。
考えてみれば十年ぶりの再会だった。横断歩道を挟んで偶然に互いを見つけ、それから五分たらずでこうしていつでも連絡を取り合えるようになったのだと思うと、とても奇妙な感じがした。
「いろいろ話したいけど、バイトだから行くわ。改めて会おうよ」
「ああ」
「なるべく早くな。メールする」
じゃあなと別れて歩き出したとたん、背後から「兄ちゃん」と呼びかけられた。振り返ると、ユウヒは後ろ歩きで横断歩道を渡りながら、いっ、と口を横に広げて歯を見せた。
「いいじゃん」
アサヒは行儀よく並んだ自分の歯列を舌でなぞった。
3
「その歯、きれいにしましょうね」
アサヒを引き取って家に連れ帰る車のなかで、母は言った。助手席に座った彼女は、乗り込んでからずっと前方か窓の外に顔を向けていたので、後部座席のアサヒには、白い耳たぶの下で揺れるピアスしか見えなかった。透明な宝石はダイヤモンドだろうと思ったが、そもそもアサヒは他に宝石の種類を知らない。揺れるダイヤモンドのピアスが、記憶にある最初の母親の姿になった。その前に児童相談所で対面したはずなのだが、何も覚えていない。
「それなら任せてくれ。パパは歯医者さんだから。矯正は早いほうがいい」
ハンドルを握る男がルームミラー越しにアサヒを見た。パパという言葉に対する反応をうかがったのだと、そのときにはわからなかった。アサヒが黙っているのをどう受け取ったのか、新しい父親はぴかぴかの眼鏡の奥で目を細め、「僕のことは好きなように呼んでね」と優しく言った。アサヒははっとして、急いで「はい」と答えた。
「そんなにかしこまらなくていいんだよ」
「かしこまる、なんてわからないわよ」
言葉の意味はなんとなく知っていたが、黙っておいた。“お父さん”がよくラジオを聴いていたから知っている、とは言うべきでない気がした。
これから暮らす家は、東京の世田谷という地域にあり、〈こづか歯科〉と看板のかかった煉瓦色の建物の後ろに建っていた。医院よりもずっと新しそうな二階建ての白い家で、広いバルコニーと芝生の庭と車二台分のガレージがある。ガレージを寝床にしているのはBMWとフォルクスワーゲン、お父さん流に言えば「金持ちの乗るガイシャ」だ。「金持ちの家」に「金持ちの庭」に「金持ちのワン公」。
小塚家ではオスのトイプードルを飼っていた。焦茶色だからココアと名づけられたそいつは、新参者の人間の子どもが家のなかで何番目の地位にあるのかを見極めようとしていた。
いちばん偉いのは五歳の彩だ。それまで小塚夫妻のひとり娘だった彩は、突然登場した兄に反発した。だからココアも歯をむいてうなっていた。けれど三十分もしないうちに彩は敏感に察知した。この子にパパとママをとられる心配はないと。
兄を受け入れたとまでは言わないにしろ、彩がアサヒにあからさまな敵意を示すのをやめたことで、両親はほっとしたようだ。家族が増えたお祝いだと言って、父はホールケーキを買ってきて、とっておきだというワインを開けた。ココアのためのケーキもあった。アサヒはケーキを貪るように食べ、口や手やテーブルや床までをもクリームでべたべたにした。
「飲みすぎよ、パパ。明日も仕事でしょ。しっかり働いてもらわないと」
「はーい。彩ぁ、ママに𠮟られちゃったよ」
父は七歳下の母に頭が上がらないように見える。でも、ひと切れのケーキと一杯のワインをおなかに収める間に、母は「ありがとう」と「おいしい」を数えきれないほど連呼した。食器を片付けたあとにも、またありがとうと告げた。
「なんだよ、大げさだなあ。そうだ、日曜日は家族みんなでどこかに出かけよう。ディズニーシーなんてどうだ。オープンしたら行きたいって言ってたろ。ママとアサヒと彩とで相談しといて。それから歯の矯正の話だけど、なるべく早いほうがいいから、知り合いの矯正医に話してみるよ」
「そうよね、お願い」
車のなかで自分をパパと呼んだときと同じく、新しい息子を呼び捨てにしたときにも、父はアサヒの反応をうかがっていた。アサヒはケーキの残りがしまわれた冷蔵庫を未練がましく見ていたが、彼の視線と、それに母の緊張した視線も、はっきりと感じた。
その夜、生まれてはじめて与えられた自分の部屋に向かって階段を上る前に、アサヒは両親に告げた。
「おやすみなさい……パパ、ママ」
慣れない呼称は、口に入れたものの大きすぎた飴のようだった。
足元を嗅ぎまわっていたココアが、すいと離れていった。
4
あのケーキを食べていたとき、母がどんな顔で自分を見ていたか、今ならありありと想像することができる。かつてお父さんの妻だった彼女は、生まれたばかりのアサヒを置いて出ていったと聞いていた。とっくに縁を切ったはずが、十年もたって戻ってきた息子。二十二歳の自分から送りつけられた荷物。アサヒにウェットティッシュを差し出しながら、母は思ったかもしれない。夢なら覚めて、と。
「きれいに食うなあ」
ちゃぶ台を挟んで畳にあぐらをかいたユウヒが、惣菜のからあげを箸でつまんだまま、まじまじとアサヒを見て言った。
神倉市内にあるユウヒのアパートだ。高校を卒業してからひとり暮らしをしているとのことで、気兼ねなく話せるからと誘われ、ユウヒのバイト先の定休日に訪ねてきた。アサヒのほうは夕方まで大学だったので、それから神倉まで足を運ぶのは億劫な気もしたが、それよりも現在のユウヒの生活を見てみたいという思いのほうが勝った。
神倉に来たのは人生で二度目だ。小京都と呼ばれる古い町は観光地としても人気だが、にぎやかなのは駅前の通りや有名な寺社など一部の場所だけで、ユウヒの住まいは生活のにおいがするありふれた住宅地のなかにあった。黄葉を待つイチョウが黄昏の空を彩っていて、ぎんなんのにおいが充満している。
アパートは木造らしく、さびだらけの階段がむき出しになった二階建てで、各戸のドアの横に洗濯機が並んでいた。ユウヒの部屋は一階の端で、六畳の和室にキッチンとユニットバスが付いている。片付いてはいなかったが、物が少ないせいで汚いというより殺風景だ。冷蔵庫や組み立て式のパイプベッドなど最低限のものしかなく、それらの色やスタイルには統一感がない。しょぼい部屋だけど風通しだけはいいんだとユウヒが言うとおり、あせた畳はさらりとしていた。
「食べ方はだいぶ直されたから」
言いながら、ユウヒが焼いてくれた餃子を口に運ぶ。バイト先のラーメン店で余ったのをもらって冷凍してあるのだそうだ。キッチンには包丁やまな板や炊飯器があって、簡単な料理はしているという。
正直、ここへ来るまでは、すさんだ暮らしをしているんじゃないかと不安に思っていた。外見も派手だし、悪い仲間とつながって悪いことをしているかもしれないと。しかし、そんな雰囲気は感じられない。
「直されたって、今の親に?」
「そう」
食卓につく姿勢、茶碗の持ち方、いっぺんに口に入れる量、文字どおり箸の上げ下ろしに至るまで、食事のたびに細かく注意された。一時は食べること自体を嫌いになりかけたくらいだ。
「へえ、ちゃんとしてる」
それはまさに母がアサヒに望んだことだった。この子をちゃんとした子にする。ケーキを食べさせたとき、もしくは十年ぶりに会ってがたがたの黄ばんだ歯を見たときから、決意していたに違いない。
「うまいな、この餃子」
「だろ。うちの自慢なんだ。ラーメンもうまいから、今度食べにきてよ」
「高校のときからそこで働いてるって言ってたな」
「高二から。学校はときどきサボったけど、そっちは無遅刻無欠勤。性に合ってんだろうな。卒業して就職っていうのもぴんと来なかったし、うちみたいなバカ校出て就ける仕事なんてたかが知れてるし、だったら続けようと思って」
ユウヒは発泡酒の缶を手に取り、あ、という顔になった。もう空になったらしい。未成年のはずだが、缶から直接ごくごくと喉に流し込む様は慣れたものだ。
「兄ちゃんも二本目いくだろ」
「いや、俺はいいよ」
「酒弱い?」
「どうかな。あんまり飲む習慣がない」
「大学生って飲み会ざんまいじゃねえの?」
「人によるよ」
アサヒはそういう場が好きではないし、誘われることもほとんどない。
ユウヒは立ち上がってキッチンへ行き、二本目の発泡酒を飲みながら戻ってきた。ぷはっと息を吐き、手の甲で口元を拭う。
「で、何だっけ。ああ、就職の話か。それに就職したら時間がなくなるって聞くからさ。俺、児童養護施設の手伝いしてて、そっちに時間を割けなくなるのは嫌なんだよ」
「児童養護施設?」
「同じ市内にある〈ハレ〉ってとこ。俺も入ってたとこだよ。うちの父さんはそこの職員で、俺が高校に上がるタイミングで里親になったんだ。早くにヨメ亡くして独身なのに、子ども引き取るなんてよくやるよな。おまけに俺は厄介なガキで、職員時代からそこらじゅう頭下げて回らなきゃならなかったのに。いちばんやばかったのは、中学で先輩殴って鼻の骨折ったとき。ほんと物好きだよ」
自分とユウヒとのやりとりは、まるで波のようだと思う。アサヒの言葉はそろそろと引いていく波で、ユウヒの言葉ははじけるように打ち寄せる波。勢いもテンポも色も異なる。昔からそうだったが、これほどに違いが顕著だっただろうか。
「今さらだけど、何ていうんだ、おまえの名前」
「ああ、そうだよな。いろいろ調査したけど本当の名前はわかんないままで、結局、新しく戸籍を作ったんだ。今の俺は、マサチカユウヒ」
思わず手が止まった。
「……正近ユウヒ」
「そう、下はユウヒのまま。苗字は“お父さん”のをもらった。漢字は今の父さんが考えてくれて、雄々しく飛ぶで雄飛。悪くないだろ」
正近雄飛。声に出さずに復唱してみる。
「兄ちゃんは?」
「コヅカアサヒ。小さいに貝塚の塚、旭川の旭」
「カイヅカ?」
「土へんに家みたいな」
「兄ちゃんもアサヒのままなんだな」
「俺は戸籍がそうだから」
「アサヒとユウヒのまんまだ」
うれしそうなユウヒに、そうだなとほほえみ返す代わりに、アサヒは餃子を口に運んだ。小塚家の食卓に出されるものに比べて味が濃い。母の考えでは、こういう味つけは素材本来のよさや料理におけるちょっとしたひと手間を台無しにしてしまう。
ふいに自分の境遇も話さなければという気持ちに駆られ、口を開いた。
「うちは父が歯科医で母は専業主婦、あと妹がいる」
「へえ、妹いくつ」
「十五、中三。それと犬を一匹飼ってる」
「『金持ちのワン公』?」
ユウヒがいたずらっぽい目つきになった。つられるようにアサヒもにやりとしたが、すぐに笑みを引っ込めた。お父さんの思い出を持ち出す弟の真意が読めない。何のわだかまりもなく、ただ素直に懐かしんでいるだけなのか。自分もそうしていいのか、笑っていいのか、わからない。
「俺はひとりっ子だよ。犬もいない。まあハレでチビたちに囲まれてると、父さんとふたりきりの家族って感じしないけど。兄ちゃん、何学部って言ってたっけ」
「……政経」
ユウヒに大学の話をするのは、後ろめたいような気がした。ましてアサヒが通う大学は、難関校に分類される私立だ。
「政経って何すんの。理系?」
「政治と経済。文系だよ」
こづか歯科は彩が継げばいいと意思表示するための進路で、父も母も反対しなかった。
「そっか。なんか兄ちゃんの人生がうまくいってるみたいで安心したよ」
うまくいってる。そのとおりだろう。
「恵まれてると思うよ。……おまえは?」
「まあ、普通じゃない? 中学のときに一回ハレを脱走したことがあるけど、戻ってよかったと思うし。……ただ」
コン、と音を立ててユウヒが缶を置いた。
「今は問題がある」
こちらを見つめるその顔は、アサヒの知らないものだった。屈託のない子どもの面影は消え、厳しい目をした青年がそこにいた。
頭のなかに黄信号が灯った。小塚旭になってから何度も見た光。自分が岐路に立っていることを知らず、進むべきでない道に足を踏み入れようとしている場合に灯る光だ。黄色は止まれ。無視してしまったときは、いつも悪い結果が待っていた。たとえば両親の機嫌がひどく悪くなったり、教室で冷や汗をかく羽目になったり。
話を聞かずに立ち去るべきだ。だが、アサヒはそうしなかった。ユウヒのまなざしがそれを許さなかったし、アサヒ自身がそうしたくなかったからだ。
弟を見返して言葉を待つ兄に、ユウヒはいくぶん表情をやわらげて「食後にコーヒーでも飲む?」と尋ねた。短い話ではないのだろう。もらうよとアサヒは答えた。ユウヒはキッチンに立ち、電気ケトルで湯を沸かし始める。インスタントらしい。
「コーヒー飲んだりするんだな」
「煙草やめてから、たまに」
「やめたのか」
吸っていたことは意外ではなかった。
「ハレのチビにくさいって言われちゃってさ。あそこじゃ一回も吸わなかったんだけど」
こちらに背を向けて手を動かしながら、ユウヒはちょっと言葉を切った。アサヒの頭のなかには依然として黄信号が灯っている。
「震災のとき、兄ちゃんの周りは大丈夫だった?」
「震災? ああ、知り合いに死者が出たり、家が倒壊するようなことはなかったよ」
今年の三月十一日に発生した東日本大震災。急に話題が飛んだと思ったが、そうではなかった。
「よかったな。こっちはハレの建物がやられちゃってさ」
「えっ」
「倒壊まではいかなかったけど、壁の亀裂とか床の傾きとか雨漏りとか。もともと老朽化してたしな。それでも手当てしながら使ってたんだけど、夏に市の職員が調査に来て、安全性に問題があるから使用を中止すべきだって」
「中止したらどうなるんだ」
「とりあえず子どもらには県内の他の施設に分散して移ってもらった。でもどこも満杯だし、やっとなじんだばっかって子もいたのに。泣いて嫌がるのとか柱にしがみついて動こうとしないのとか見ると、こっちもつらくてさ。ったく、雨漏りなんか今に始まったことじゃねえっての」
「戻ってこられないのか?」
「建物がどうにかなればな。砂糖とミルクは?」
「え、ああ、どっちもいらない……いや、やっぱりミルクだけくれ」
ブラックで飲むことが多いが、たまにミルクが欲しくなる。疲れているときや、緊張しているときに。
「やっぱ砂糖はだめ? うちにあるのはスティックシュガーじゃなくて、料理用の砂糖だけど」
アサヒは黙って弟の背中を見つめた。声音はごく普通だが、どんな顔でそれを言っているのか。
「じゃあ、今は移転先を探してるのか」
「なかなか難しいよ。普通の家を見つけるみたいにはいかないからさ。元の建物を建て直すか大々的にリフォームできればいちばんなんだけど、それにはやっぱ金がかかるじゃん。児童養護施設って国と自治体からの措置費ってやつで運営されてんだけど、かつかつで修繕費まではとても手が回らない。補助金には条件が合わないし、寄付金集めもうまくいってない。融資も検討したけど、理事長はもう歳で、病気してるのもあって、借金してまで経営を続けたいとは思ってないんだ」
「大変なんだな」
「でも、俺はハレを存続させたい。父さんもそうだし、何よりも子どもたちがそれを望んでるんだから。問題は金なんだ。あと五百万あれば、理事長を説得できるかもしれない。いや、してみせる」
何と言ったらいいのかわからなかった。私立大の文系学部で四年間にかかる学費が、たしか四百万くらいだったはずだ。父が去年買い換えたばかりのBMWは六百万ちょっとだったか。
電気ケトルがぐつぐつ鳴って湯が沸いた。運ばれてきたマグカップはひとつだけで、金髪ピアスの男には似つかわしくないハローキティのイラスト付きだ。
顔を上げると、ユウヒの真剣な顔が目の前にあった。
「協力してよ」
コーヒーの香りが鼻腔に届く。頭のなかの黄信号が激しく点滅している。
「……協力?」
「五百万を手に入れる」
「どうやって」
「俺の知り合いに金持ちの娘がいるんだ。その子を誘拐する」
目を逸らさず、まばたきもせずに、ユウヒは言った。
やっぱりだ。黄信号を無視したら、ろくなことにならない。
アサヒは唾を飲み、それから思い出してコーヒーを口に運んだ。舌を火傷しそうになった。
「変わってないな、そういうとこ。おまえはよく真面目な顔でとんでもないこと言って、俺が慌てふためくのをおもしろがってたよな。得意げに『うっそー』ってばらすときの、あの憎たらしい態度といったら」
笑えていないのが自分でもわかる。兄のいじましい悪あがきを、ユウヒは冷静な目で見つめている。アサヒは熱さにかまわずコーヒーをがぶがぶ飲んだ。
「心配しなくても、本当の誘拐じゃない。誘拐する相手も了承済み、仲間なんだよ。狂言誘拐ってやつ」
「冗談なんだろ」
「違うよ。狂言だけど冗談じゃない。遊びでもない。その子の親に身代金を要求して、千五百万円を手に入れる」
「千五百万? 五百万じゃないのか」
「俺に五百万、誘拐される仲間に五百万、兄ちゃんに五百万」
ユウヒは落ち着いている。そして、決めている。
マグカップを傾けたが、もう空だった。
「おかわり、いる?」
「犯罪じゃないか。犯罪だぞ、それ」
「だから兄ちゃんに頼んでるんだ。兄ちゃんにしか頼めないから。友達も、父さんや他の職員も、ハレで一緒に暮らしてた仲間も、誰もこのことは知らない」
「ばかなことはやめろよ。何か他の方法を考えるんだ」
「他の方法って?」
即座に切り返されて言葉に詰まった。
「だけど……犯罪だぞ」
また同じことを口にしてしまう。
「うまくいくわけない。捕まるに決まってる」
「やりようだよ」
「もし、もしうまくいったとして、金の出どころをどう説明するんだ」
「説明なんか必要ないよ。金は『伊達直人』として寄付する」
漫画『タイガーマスク』の主人公の名前で児童福祉関連施設などに寄付を行う、いわゆるタイガーマスク運動が、去年のクリスマスを皮切りに日本各地で報告されていることは、もちろんアサヒも知っている。
ユウヒは空のマグカップを持ってキッチンへ行った。
「俺さ、小学校四年生から学校に通い始めたんだ」
「……俺は五年生からだった」
それまでまともな教育を受けたことはなく、基本的な社会通念さえ教わらずに暮らしていた。いや、あれは暮らしと呼べるものではない。家もなく、けちな盗みを重ねて、かろうじて食いつなぐだけの日々。
ずっとあとになって知ったことだが、住民票があるのに乳幼児健診を受けていなかったり学校に通っていなかったりする子どもは、行政による調査の対象となる。しかし住民票というものは、その自治体に居住実態がないと判断されたら削除される。住民票がなければ調査の対象にはならない。その子どもは所在も生活実態も不明となり、消えてしまうのだ。
「勉強ができなくて、給食は犬食いで、泳げなくて、はやりのゲームやテレビも知らなくて、そりゃいじめの恰好の的になるよな」
おまえもか、という言葉を吞み込む。自分の経験を語りたくはない。
「こっちも慣れない環境にいらいらしてて、ちょっとしたことで椅子を振り回したり牛乳をぶっかけたりしたから、お互いさまってとこもあるけど。いじめられて泣くタイプじゃなかったし、何かやられたら、たいてい体でやり返してた。俺、昔からけんかの才能はあったみたいなんだよな。おかげでそのうち誰も手出ししてこなくなったけど、やっぱ学校は敵ばっかって気分が抜けなくてさ。だけどハレにいるときは、楽しかったし安心していられたんだ。仲間もいたし、父さんみたいに信頼できる大人もいた。あのころ、もしハレを追い出されてたら、俺はどうなってたかわかんない」
ユウヒの声がしだいに熱を帯びていく。
「今、子どもらはよその施設に移ってるけど、そのまま追い出すようなことはしたくないんだ。ただでさえ親や社会からいろんなものを奪われてきた子たちから、これ以上、何も奪いたくないんだよ」
「よその施設でだって幸せに暮らせるかもしれないじゃないか」
「それならいいよ。でも、帰りたいのに帰る場所がないって状態にはしたくない」
アサヒは自分のバッグを引き寄せた。「できないよ」
ユウヒが振り返ったようだったが、アサヒは下を向いていたので確認することはできなかった。
「兄ちゃん」
「協力はできない。話も聞かなかったことにする」
立ち上がりかけたアサヒの前に、ユウヒは静かに二杯目のコーヒーを置いた。砂糖はなしで。
「砂糖がだめになった理由、ばらしちゃってもいい?」
協力を拒まれることを最初から予想していたような落ち着きぶりだった。アサヒははっと顔を上げた。ユウヒと目が合ったとたん、胸に芽生えた疑念がたちまち根を張って確信になる。
「最初から、脅して協力させるつもりだったのか」
「兄ちゃんが自分から協力するって言ってくれたら、そんな必要なかったんだけど」
「ロータリーで再会したのも偶然じゃなかったんだな。俺のことをすっかり調べた上で接触したんだ」
小塚旭という名前。世田谷の住まい。通っている大学と通学経路。おそらく素行や性格も。そして、こいつは使えると判断した。
「犬を飼ってるのは知らなかったよ」
中途半端な中腰のままで、アサヒはユウヒをにらみつけた。血のつながりはない、けれど血よりも濃いものでつながっていたはずの“弟”を。
(気になる続きは、ぜひ本書でお楽しみください)
第二部 夜と昼
なるほど悲しみってものは人間のために
あるもんで、獣のためじゃあねえ。
だけんど、人間もあんまり悲しむと
獣になっちまうよ。
セルバンテス『ドン・キホーテ』
1
うだるような夏の日だった。
神倉駅前交番に勤務する狩野雷太は、住民からの通報を受け、部下の月岡とともに自転車で現場に向かっていた。現場は駅の西側に建つ集合住宅。通報者はそこの住人で、隣の部屋から聞こえていた子どもの泣き声が聞こえなくなり、異臭が漂ってくるので、様子を見てほしいという。
二十数戸のすべてが単身者向けのマンスリーマンションだった。こざっぱりとした三階建てで、問題の部屋は三〇二号室だ。共同玄関を入ってすぐのところにある郵便受けに借り主の名はなく、のぞいてみると、チラシがあふれんばかりに溜まっている。建物の中は薄暗く、しんとしていた。平日の午後は留守の部屋が多いのだろう。
階段を急いで上る。三階に着いた時点では、異臭は言われてみればという程度だった。しかし三〇二号室の前に立つとはっきりと感じられ、さらにドアについている新聞受けを指で開けると、強烈なにおいが漏れ出してきた。何かが腐ったにおい。
月岡が呼鈴を押し、警察ですと呼ばわりながらドアを叩く。応答はなく、ドアに耳をつけても物音ひとつ聞こえない。開けますよと声をかけてノブをひねる。鍵がかかっている。隣の部屋のドアがわずかに開いて閉じた。
すぐにマンションの管理会社に連絡して鍵を開けてもらった。担当者はひどくうろたえていて、鍵がなかなか鍵穴に入らなかった。
ドアを開け、月岡とふたりで中へと踏み込む。
目に飛び込んできた惨状に、狩野は言葉を失った。
窓もカーテンも閉め切ったワンルームの部屋。フローリングの床に散乱するごみ。そのなかに埋もれるようにして、小さな子どもがふたりいた。ひとりは仰向けに倒れ、もうひとりはぐったりと壁にもたれて座っている。どちらも下着一枚しか身につけておらず、むき出しの体は骨と皮ばかりだ。
倒れているのは女児だった。すでに事切れていて、遺体の腐敗が始まっている。
座っている男児のほうはまだ息があり、屈み込んで大声で呼びかけると、閉じたまぶたがうっすらと開いた。ひからびた唇がかすかに動き、何かつぶやいたようだが聞き取れない。
「みっちゃん、救急車と応援要請!」
茫然と立ち尽くしていた月岡が、電流に打たれたように動き出した。
2
神倉市のマンションの一室で、女児の遺体が発見され、衰弱した男児が保護された。神奈川県警は神倉署に捜査本部を設置した。
県警捜査一課に所属する烏丸靖子は、現場のマンションの前に立ち、情け知らずの太陽をにらみつけた。正面玄関の脇に供えられた花はしおれ、ジュースやお菓子のパッケージが日差しを乱反射している。
「あっちぃ……」
若いころは暑さにも寒さにも強かったのだが、四十を越えてからこたえるようになってきた。パンツスーツなんか着ているから余計に暑い。
顔をしかめてマンションに入っていく烏丸に、群がったマスコミがいっせいに反応する。フラッシュがたかれ、マイクが突きつけられる。捜査の状況は。母親は犯行を認めてるんですか。保護された男児の容態は。日常的に虐待が行われていたんでしょうか。この調子でマンションや近所の住人、手を合わせに訪れた人に詰め寄っているらしく、なんとかしてくれと警察に苦情が来ている。
「はいはい、どいてくださいねー」
取り合わずに素通りし、エレベーターはないので階段で三階へ上がる。廊下の端にある小さな窓が開いているのは、においを逃がすためか。
三〇二号室。立番の巡査にごくろうさまと声をかけ、黄色いテープをくぐって中へ入る。悪臭がむっと鼻をつく。
鑑識はすでに作業を終えたあとで、ごみの散乱する室内は無人だった。敷金礼金保証人不要、契約は月ごとのマンスリーマンションだ。備え付けの家具や家電に住人の個性はないが、壁には子どもが描いたらしい絵がたくさん貼られている。馬に乗って槍を持った騎士に、ドレスを着たお姫さま。拙い文字が添えられたものもある。『ママ いつもありがとう』──あれは母の日に描かれたものか。『おにいちゃん 7さい おめでとう』──あれは男児の誕生日に。『ママ ゆうや まひる』──三人でにこにこと手をつないで、どこへ出かけていくのだろう。赤ちゃんの人形や児童書もあった。子ども用の食器も、歯ブラシも。
ごく普通の家庭だ。仲むつまじい母と子どもたち。少なくとも、独身で子どももいない烏丸の目にはそう見える。
だが、子どもたちはここに置き去りにされていた。窓が閉め切られエアコンも稼働していなかったため、昨日、八月五日に発見されたときの室温は三十五度を超えていたという。ふたりは暑さのあまり服を脱いだのだろう。
女児の遺体は司法解剖に回されている。保護された男児は神倉市立病院で治療中だ。室内の状況からして、ふたりは食べ物を求めて冷蔵庫や戸棚をあさったらしい。買い置きのカップ麺やレンジで温めるだけの冷凍食品、菓子などが尽きると、生の野菜をかじったりマヨネーズやケチャップを吸ったりして、それも尽きると水道水を飲んで飢えをしのいでいたようだ。
マンションの管理会社によると、部屋の借り主は、吉岡みずきという女だった。二十三歳の会社員で、入居したのは半年前。書類上は単身ということになっており、子どもが同居していたことを管理会社は把握していなかったという。
この吉岡が二児の母親と思われたが、所在がわからなかった。契約書に本人が記入した勤務先は実在せず、部屋にあった名刺から実際はデリバリーヘルスで働いていることが判明したものの、七月二十六日から無断欠勤が続いていて連絡が取れないとのことだった。マンションの契約の際にもデリヘルの面接の際にも本人確認は行われておらず、こうなると名前や年齢さえでたらめという可能性もある。
「烏丸さん」
呼ばれて振り向くと、黄色いテープの外に西がいた。中学生のころから捜査一課の刑事になりたいと思っていたそうで、三十半ばでやっと念願が叶って張り切っている。鼻の下に指を当てて眉をひそめていた西は、目が合うなり「うお」と軽くのけぞった。
「なんすか、その顔」
「ご挨拶だね。この部屋に来たら誰でもこんな顔になるだろ」
悲惨な現場はそれなりに踏んできたが、今回は格別だ。
「ほんと胸くそ悪いっすよね」
唾でも吐きそうな西とともに、烏丸は隣の三〇三号室へ向かった。通報者であるそこの住人から話を聞くためだ。
斎藤という五十がらみのその女は、自身は神倉市民ではないが、神倉に住む親が市内の病院に入院しているので、世話をするためにこのマンスリーマンションを借りているとのことだった。先が見えないまま毎月の更新を続け、もうじき一年になるという。あらかじめ連絡してあったためすんなり会うことができたが、刑事たちを部屋にあげようとはしなかったので、烏丸と西は狭い靴脱ぎに立っていなければならなかった。
「まあね、半年前にあの人が入居したときから、子どもがいるんじゃないかってことには薄々気づいてたんです。子どもの声とか足音って、どうしたって漏れてくるじゃないですか。とはいえ、そういうことはまれで、たいていはとても静かだったんですけどね。姿を見たことも一度もないですし」
「でも、ここは単身者用のマンションですよね」
「噓ついて入居したんじゃないですか。ここの管理会社、かなりいいかげんだと思いますよ。こっそりペット飼ってる人とか同棲してる人もいるみたいだし。私もどうせ仮住まいだと思って我慢してることがたくさんあるんです」
「吉岡さんと交流はありました?」
心外だとばかりに斎藤は顔をしかめた。
「いいえ、まったく。前に挨拶したのに無視されて、それからはすれ違っても会釈もしません。人と関わりたくないような感じでしたよ。だから名前も知りませんでしたし。明らかに男ウケを狙った恰好で夜出かけて朝帰ってくるから、水商売の人なんだろうとは思ってました。あとは、スーパーやドラッグストアの帰りらしいところを何度か見かけましたけど」
「異変を感じたのはいつごろですか?」
「七月二十五日です。私、日記をつけてて、見返したら二十五日のところに書いてありました。隣から『死ね』と怒鳴る声が聞こえてきて驚いた、って。朝、お茶を淹れようとしてたときだったから、こぼしそうになったのを覚えてます」
「『死ね』? 吉岡さんがそう言ったんですか?」
「さあ、あの人の声かどうかは。絶叫っていう感じでしたし。ただ、そのあと乱暴に玄関ドアを開け閉めする音がして、子どもの泣きわめく声が聞こえてきたんです。ママとか、ごめんなさいとか、言ってるみたいでした。それ以降、そういう声が一週間くらい断続的に聞こえてて。気にはなってたんですけど、交流もないですし、私も親の世話で忙しくて、それに正直に言えば関わり合いになりたくないという気持ちもあって、そのままにしてました」
烏丸は乾いた唇を舌で湿した。
「その間に吉岡さんの姿を見たことは?」
「ありません。でも、もともと生活時間帯が違いますから」
「通報したときの状況を教えてください」
「八月に入って、子どもの泣き声が聞こえなくなったんです。正確にいつとは言えないんですけど、そういえば聞こえないなって。なんだか異臭も漂ってくるみたいだし、怖くなって、迷った末に一一〇番しました。もっと早くそうしてれば……」
斎藤はうなだれ、節の太い指で目頭を押さえた。
聴取が終わって三〇三号室のドアが閉まったとたん、西が憤懣をぶちまけるように息を吐いた。
「七月二十五日に子どもたちを置いて家を出て、それきり十日以上も帰ってないってことですかね。無断欠勤は二十六日からってことでしたし。ろくな食べ物もなしにそんだけほっといたら、死んじゃうのはわかってただろうに。しかも『死ね』って。こいつは殺人ですよ」
保護責任者遺棄致死か、殺人か。
育児放棄の結果として死に至らしめた場合、殺意の有無が問題となる。この母親は故意に娘を死なせたのだろうか。
「まだわかんないよ」
そう言ったものの、烏丸も同じことを考えていた。子どもが描いた「ママ」の笑顔が、頭のなかでぐにゃりとゆがむ。
事件発覚の翌日未明、吉岡みずきなる女は、交際相手の男性宅にいたところを神倉署の捜査員によって発見された。子どもたちの母親であることを認め、任意同行の求めにおとなしく応じたが、取り調べに対しては黙秘している。事件についてはおろか、自分の名前すら答えない。発見されたとき、本人確認ができるものはいっさい所持していなかった。神倉市に住民登録はされておらず、家宅捜索でも身元のわかるものは見つかっていない。
黙秘を続ける吉岡は、非協力的な態度から逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、まずは男児に対する保護責任者遺棄罪で逮捕となった。子どもの父親や知人に保護を依頼していたという可能性もないではないが、交際相手や職場の関係者にも子どもの存在を隠していたことから、そうは考えにくいと判断された。
そのタイミングで、烏丸が取調官に任命された。当初は神倉署の刑事課署員が事情聴取に当たっていたが埒が明かず、やはり同性のほうが聞き出しやすいだろうとの理由で白羽の矢が立ったらしい。神倉署の面々はおもしろくない様子だったが、そんなことをいちいち気にしてはいられない。
取調室ではじめて対面したとき、吉岡みずきの両目は乾いていた。視線を下げてマリンカラーの爪をいじる様は、授業に退屈している学生のようだ。緩く波打つ茶色の髪を首の後ろで結わえ、貸与品のグレーのスウェットを身につけている。袖口からのぞく細い手首には、いくつもの古い傷跡があった。色白の美人だが、店のホームページに載っていた写真とずいぶん印象が違うのは、化粧の有無や服装の違いというより表情の違いのせいだろう。
吉岡の身柄を確保した捜査員によると、娘の死を知らされたときもこんなふうだったらしい。涙も見せずうろたえもせず、ぼんやりと捜査員を見て、そっかあ、死んじゃったかあ、とつぶやいた。何度も反芻しているその言葉を、烏丸はまた思い出す。
押収した吉岡のスマートフォンには、子どもの写真や動画が大量に収められていた。親子三人、くっついてアップで写っているものもたくさんあった。あんなに幸せそうに笑っていたのに。
司法解剖の結果、女児の死因は脱水と栄養失調、平たく言えば餓死だと判明した。また、死亡したのは八月二日ごろだということもわかった。子どもたちが発見されたのは八月五日だから、男児は女児の遺体とともに三日間ひとりで過ごしたことになる。他に重大な身体的虐待の痕跡、たとえば火傷や骨折の痕などは見られなかったものの、だからといって恒常的な虐待がなかったとは言えない。男児は病院で治療を受け、もう会話もできるはずだが、今のところいっさいの質問に対して口を閉ざしているという。衰弱は激しいものの、体に深刻な後遺症が残る心配はないということだけが救いだった。
「まずはあなたの名前を教えてくれる?」
烏丸の質問に、吉岡は沈黙で応えた。沈黙というより無視だ。
「それじゃ、あなたの子どもたちの名前は?」
吉岡はやはり答えない。
「ゆうやくんと、まひるちゃん、だよね。貼ってあった絵に書いてあったよ。どういう漢字を書くの。それともひらがな? お兄ちゃんと妹で、ゆうやくんは七歳なんだね。まひるちゃんはいくつ? 五歳くらいだろうって医者は言ってるけど」
七歳なら小学校一年生か二年生のはずだ。しかし部屋にランドセルはなく、ゆうやが小学校に通っている様子はなかった。近隣の保育園や託児所への聞き込みでも、ゆうやとまひるらしき子どもの情報は得られなかった。烏丸もマンションの住人に尋ねて回ったが、子どもの存在に気づいていなかった者がほとんどだった。
「七月二十五日の朝に、あなたの部屋で『死ね』と叫ぶ声を聞いた人がいるの。続いて部屋を出ていく物音も。それはあなた?」
少し間を空けて烏丸は続ける。
「同じく七月二十五日、あなたは交際相手である杉浦さんの家に転がり込んだ。その日は約束してなかったのに、急に訪ねたんだってね。そしてそのまま警察に発見されるまで居座った。それまではどんなに遅くなっても泊まらずに帰ってたから、杉浦さんは帰らなくていいのかと訊いた。するとあなたは、帰れないと答えた。『帰れない』ってどういう意味?」
子どもがいることを知らなかった杉浦は、吉岡が別の男と暮らしていると思っていたそうだ。だから必ず帰宅していたが、この日、その男に追い出されたのだと。だからそれ以上は追及せず、好きなだけいていいと言った。
「あなたはひとりで子どもたちを育ててたの? 父親は?」
殺風景な取調室に烏丸の言葉だけが積もっていき、同じだけのはがゆさが心のなかに積もる。記録を取っている西がいまいましげにこちらを見ている。
「あなたが話してくれないと、まひるちゃんをきちんと弔ってあげることもできないよ」
解剖はオールマイティではない。被疑者や被害者の口から新たな事実が出てこないとも限らない以上、早々に遺体を焼いてしまうわけにはいかない。あの小さな体は事件の証拠なのだ。
吉岡の目がはじめて烏丸を捉えた。だがそこに宿る感情を読み取る前に、またすぐに伏せられてしまった。
「もっかい訊くよ。あなたの名前は?」
吉岡みずきは偽名だと、烏丸は確信している。
名なしの女は沈黙を続けた。
(気になる続きは、ぜひ本書でお楽しみください)
書誌情報

書名:朝と夕の犯罪 神倉駅前交番 狩野雷太の推理
著者:降田 天
発売日:2024年09月24日
ISBNコード:9784041147276
定価:946円 (本体860円+税)
ページ数:400ページ
判型:文庫
発行:KADOKAWA
★全国の書店で好評発売中!
★ネット書店・電子書籍ストアでも取り扱い中!
Amazon
楽天ブックス
電子書籍ストアBOOK☆WALKER
※取り扱い状況は店舗により異なります。ご了承ください。
