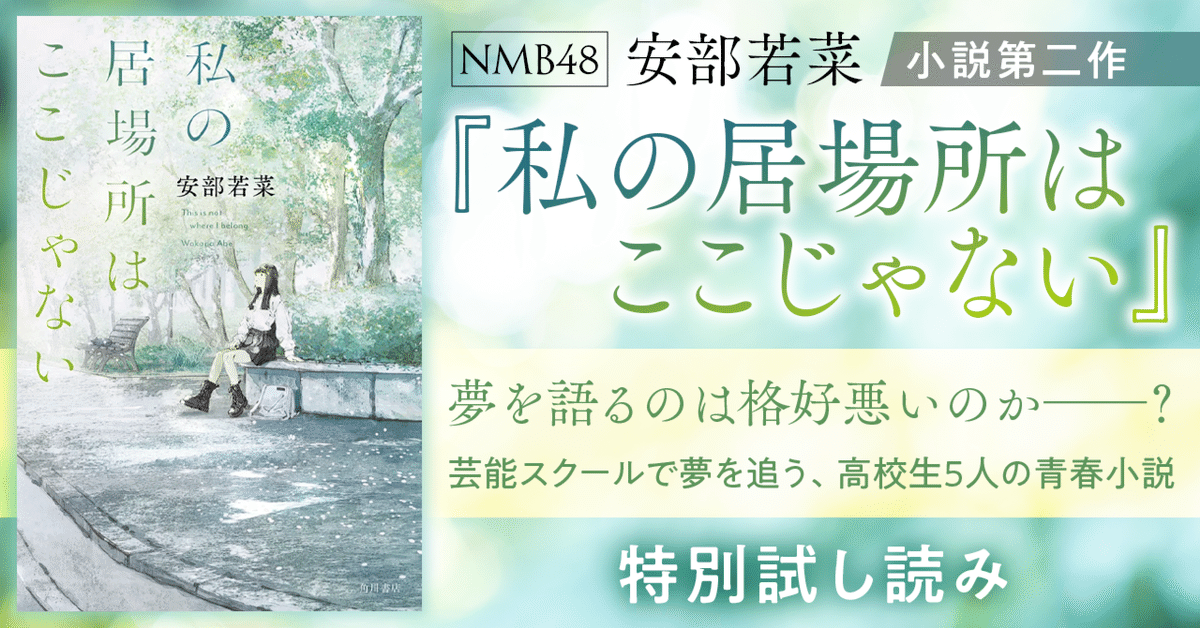
【試し読み】安部若菜『私の居場所はここじゃない』冒頭特別公開!
現役アイドルが〈アイドルとオタクの恋愛〉を描き話題を集めた、『アイドル失格』の著者・NMB48の安部若菜さん。
衝撃のデビュー作から2年、ついに小説第2作『私の居場所はここじゃない』が発売!
本作のテーマは「夢」。夢を語るのは格好悪いのか? 努力するのはダサいのか? 現役アイドルの著者が問う、芸能スクールで夢を追う、高校生5人の青春小説です。
刊行を記念して、冒頭の試し読みを特別公開します。どうぞお楽しみください!

あらすじ
舞台は大手事務所主催のエンターテイメントスクール。3月にある事務所所属をかけたオーディションに向け、高校生5人はレッスンに励んでいた。
友達と一緒に応募したオーディションで特別に声をかけられ、成り行きでアイドルを目指すことになり、当たり前だった「青春」や友人関係に息苦しさを感じ始める莉子。
亡くなった母の期待を背負い、結果を残したいと焦る、ダンスボーカルグループ志望の冬真。
「子どもを産まなければモデルになりたかった」という母の言葉で将来の夢を決め、SNSの活動を頑張るモデル志望の美華。
「普通」「真面目そう」と言われ続けてきたことにコンプレックスを抱き、「特別」になりたいと強く願う俳優志望の純平。
いじめが原因で自ら芸能活動を辞めたが、もう一度自分の居場所を求めて入学を決意した、元天才子役のつむぎ。
嫉妬や葛藤を乗り越えて彼らが最終オーディションの舞台に立つとき、どのような"光"を放つのか――。
『私の居場所はここじゃない』試し読み
プロローグ
私の居場所はここじゃない。
いつからか頭をもたげたそんな考えが、べったりと黒いシミみたいにこびりついて離れない。
くらくらするような暖房の熱が明るい部屋中に満ちている。吐き出す声が、クリーム色をした防音の分厚い壁に吸い込まれて消えていった。
「しっかり腹式呼吸を意識して! 口もちゃんと開けて、体全体を一つの楽器だと思って!」
あ、え、い、う、え、お、あ、お。
意味のない音を繰り返し発音する。青春まっさかりの中高生十数人が、何も疑わず、必死に声を出している。鏡に映ったそんな自分たちが滑稽で、またいつもの考えに取り憑かれた。
私の居場所はここじゃない。何か運命的な出会いがあって、夢中になれる何かを見つけて、ずっとそこにいてもいいと思えるような居場所が、きっといつか見つかる。
「莉子、腹式呼吸が全然出来てない。基礎の基礎すら出来なくてどうするの? これが出来なきゃスタートラインにすら立てないよ」
「すみません! 頑張ります!」
「あとつむぎ、声が小さい! 経験者でしょ?」
「すみません」
経験者だからって皆から距離を置かれても、ひっつめ髪の先生に叱られても、立ち向かって頑張ろうと思えるような場所が、きっと見つかる。
「これは皆共通だけど……。どんな風に時間を過ごしても、その日は絶対平等にやってくる。だから悔いのないように時間を使いなさい」
「はい!」
ぴかぴかで、シミ一つ無いようなビルの中、その希望に影が差さないよう、私も皆に合わせて大声を出した。望んで来たはずのこの場所も、今じゃ水の中みたいに息苦しい。
でも4ヶ月後、3月25日に開催されるオーディションに合格すれば、きっと新しい居場所に出会える。それまでは、ただこの空間をやり過ごせばいい。耐えて、耐えて、練習して、もう一度新しくやり直そう。
でも、それも自分の居場所じゃなかったら?
頭をもたげた闇をかき消すように、渇いた喉に冷たいペットボトルの水を流し込んだ。
丸山莉子
『応募書類を拝見させて頂きました。丸山様には非常に才能を感じておりまして、ぜひ直接会ってお話しさせて頂ければと思います』
放課後、そんな詐欺みたいな電話をかけてきたのは、紛れもなく大手芸能事務所『スターターズ』だった。心愛と真奈と、いつものように駅前のハンバーガーチェーン店で駄弁っていた時、見知らぬ番号から電話がかかってきたのだ。
「ねえ今の電話『スターターズ』からだったんだけど」
興味津々といった様子でテーブルに身を乗り出して聞き耳を立てていた2人にそう告げると、きゃあっ! と花が咲いたような歓声を上げた。特に真奈は前に3人でライブに行った時と同じくらいのはしゃぎっぷりで、ゆるく巻いて低い位置で2つに結んだ髪をぶんぶんと揺らす。
「すごい! 莉子、オーディション受かったってこと? 3人で送ったのに莉子だけじゃん! うちらも電話来たりするのかな?」
「心愛が応募してあげたお陰じゃない?」
4人がけのテーブルできゃいきゃいとはしゃぐ私たちをうるさそうに見る隣のテーブルの女性と目が合ってしまった。気まずくてすぐに視線を落としたが、その視界の端で女性が席を立ったのが分かった。
「で、どういう電話だったの?」
そんなことに気づきもせず一層テーブルに身を乗り出す真奈に意識を戻す。少しだけアンバランスなテーブルががたんと傾いた。
高校に入学して仲良くなれた、いわゆる「一軍」の2人。真奈とは中学のバド部で一緒だった。真奈は部活でも目立つグループであまり話したことはなかったけど、新しいクラスに同じ中学出身の子が私しかいなくて、真奈から話しかけてきてくれた。自然と2人でいたら、気づいたら心愛も一緒になっていた。
2人といる時間は高校生活最初の秋を迎えても楽しいことばかりだった。新しいブレザーに袖を通して、3人お揃いのキャラメル色のカーディガン(本当は明るい色は校則違反だけど)を羽織って、寒くてもスカートのウエストは2回折る。中学の時は特別目立つ方でもなかった私がこうして2人と一緒にいられて、憧れていた以上の高校生活、夢見ていた「青春」だった。そこにこの知らせだ。
「いやほんと、私なんかが受かるなんて……。でも電話自体は、とりあえず来てみたいな感じでよく分かんないの」
何それ、意味分かんなすぎない? と2人は笑い転げる。楽しいな、とポテトを一口食べて思う。店内に流れるカフェミュージックに体が揺れる。
「スターターズのアイドルオーディションに応募したんだから、そういうことだよね? 莉子アイドルになるの? やばくない?」
真奈は私よりもはしゃいでころころと表情を変える。人懐っこくてミーハーなところも愛嬌があって真奈の可愛いところだ。心愛はクールな表情を崩さず、つやつやと波打つ髪をいじりながら相槌を打っている。毎朝わざわざ髪をセットするなんて私には真似出来なくて、いつもおしゃれな心愛を本当にすごいと思う。
心愛は情報にも早くて、2週間くらい前、ネットで大手事務所『スターターズ』の新アイドルオーディションを見つけてきた。その場のノリで写真を撮って「小さい頃からアイドルになるのが夢でした!」なんて噓を並べて3人とも応募したけど、まさか私が受かるなんて夢にも思わなかった。
「いやいや、まだ審査とかあるだろうし……」
いつも2人の後を追っているのに、今日は自分が話題の中心にいるのも嬉しくて、つい口元が緩みっぱなしになってしまう。お店の2階席に差し込む夕陽に目を細め、私は少しだけ2人から顔を逸らした。近くを走る電車が地面を揺らす。
真奈からの「莉子もロング似合いそう!」って一言に影響されて春から伸ばし始めた髪もすっかり胸まで伸びた。怒られるのが怖くて私だけまだ黒いままの髪も、今が染めどきなのかもしれない。この間まで暑かった気がするのに、駅の周りに遠慮がちに伸びる木はすっかり赤や黄色に色づき始めている。
真奈の手がポテトの最後の1本に伸びた時、私は胸の奥にあった重大なことを口に出す。
「……スターターズってさ、B5が所属してるとこだよね」
その一言にまたひと盛り上がりして、そのまま話題は今私たちが夢中の男性アイドルグループ『B5』に移り変わる。
B5は高校生を中心にすごく流行ってるって心愛に教えてもらって、動画で見たレオ君のウインクにすぐに撃ち抜かれた。ドームライブも奇跡的にチケットが取れて夏休みに3人で行ったし、韓国っぽい曲や雰囲気がたまらなくかっこいい。
同じ事務所なら、推しのレオ君に会えるかも。話すようになって仲良くなって……。オレンジに染まる店内で、そんな妄想がシャボン玉みたいに浮かんでは消えていく。夢から醒めないまま、約束の週末はすぐにやってきた。
鏡に映る私は、いつもよりちょっと可愛い気がする。リップも新しいのを買ったし、あれから数日はお菓子も我慢した。パパが珍しく持って帰ってきたケーキは食べちゃったけど。
でも数秒ごとに不安になる。私って可愛いのかな? 今まで容姿を褒められるようなタイプじゃなかったし、心愛や真奈は綺麗な二重だけど、私はそうじゃない。心愛に教えてもらったアイプチでの二重の作り方を、もっと練習しておくんだった。
余裕を持って準備を始めたのに、結局時間ギリギリに家を飛び出した。11月になってもまだ20度を超えていて、夕方でも東京は薄着の女の子ばかり歩いている。私も、真奈の「絶対脚出した方がいいよ!」という言葉通り、ミニのニットワンピースにショートブーツを履いて、動画を見ながら頑張って髪も巻いた。心臓が飛び出しそうなくらい緊張するけど、スカートを揺らす風が気持ちよくて、アップテンポなB5の音楽に心が弾む。5人の存在がどんどん近づいている気がして、自然と口角も上がった。
駅から少し離れたところにある大きなビルの前に立ち、小さく息を整える。入り口の両脇には、出迎えるみたいにまだ細い木が植えられていた。
脇の下は汗ばんでいるのに手先はやたらと冷たくて、火照った頰に手を当てると気持ちが引き締まる気がした。今更湧いてきた現実感に少しだけ引き返したくなる。
時間にはまだ5分ほど早く、躊躇いつつ外から様子を窺った。ガラス張りの1階は暖色のキラキラした照明に照らされている。ぎゅっとカバンの紐を握りしめ突っ立っている私の側を、黒のスキニーパンツを穿いたスラリとした綺麗な女の子がコツコツとヒールを鳴らして歩き去っていった。やっぱり私なんかが来るところじゃないのかも。鏡の前で何とか作った自信が一気に消えていく。
『入る前から超芸能人みたいな人いる……無理かも……』
『莉子なら大丈夫! 1番可愛いから!笑』
真奈からのメッセージと、心愛からのグッと親指を立てたスタンプがすぐに返ってきた。いつも通りの2人に少し和み、スマホをしまって気持ちを落ち着かせる。そうだ。これで胸を張って2人に並べるんだ。
一歩踏み出し、自動ドアをくぐってエレベーターに乗り込む。1人っきり、エレベーターの鏡で顔を念入りにチェック。集合場所の6階はレッスンスタジオのようで、ガラス張りの大きなダンススタジオが目に飛び込んできた。清潔感溢れる白い壁に、色んな角度で照らすオレンジがかった照明、おしゃれな観葉植物に期待と緊張はピークに達する。ニットの下で、背中につうっと汗が流れた。
「丸山莉子さんですか?」
丸眼鏡の、30代前半くらいの男性に声を掛けられた。柔らかい色のゆったりとしたシャツ姿で、カフェでバリバリ仕事してそうな感じがすごくかっこいい。その男性は、ぎこちなく頷く私に優しく微笑んで、紳士的に案内してくれる。
「お待ちしておりました。こちらへどうぞ」
通されたのはテーブルと椅子だけの部屋で、やっぱりガラス張りだった。外を歩く同い歳くらいの子が時々通りざまに覗いている。
出された温かい紅茶を片手に、私はすっかりのぼせ切っていた。紅茶に砂糖を入れていた時に丸眼鏡の男性が話し始め、慌てて姿勢を正す。
「この度は、書類審査にご応募頂きありがとうございました。私、スターターズ事務所の佐藤と申します」
滑らかな動きで差し出された名刺を何度もお辞儀しながら受け取る。名刺の受け取り方も調べておくんだった。受け取った名刺をカバンに滑り込ませる。
「本来であれば、2次審査ではグループ面接、3次審査では歌唱やダンスとなるのですが、今回は、そのアイドルグループとは別枠でのご相談になります。
単刀直入に申しますと、新しいアイドルグループのオーディションとしては、残念ながらご希望に添うことが出来ませんでした。しかしこうして特別に個人的にお呼びしたのは、丸山様に多大な才能を感じたからで……」
頭が真っ白になる。アイドルに受かった訳じゃない? 特別? 才能って? オーディションに受かるよりも良いの? 疑問符だらけの溶けきった頭では、その後に続く男性の話をすぐには理解することが出来なかった。
「……すみません、もう一度いいですか?」
「丸山様を、是非弊社の運営するスクールにお誘いしたいと思っております」
一度目と全く同じ文言を繰り返したのち、男性はにっこりとした顔のまま話を続けた。
「私ども『スターターズ』では『スターターズスクール』という芸能スクールを運営しております。スクールと申しましても、一般的なスクールとは違い、芸能事務所へ直結するオーディションがあることを売りにしていまして、入学にも厳しい審査を必要としております」
ぽかんとする私をよそに、男性は言い慣れた説明であるかのように一息で言い切ると、1冊のパンフレットを取り出してきた。準備されていたそれに、私は心の中で膨らんでいた風船がどんどんとしぼんでいくのを感じていた。昨日1時間かけて塗ったピンクのマニキュアは粗だらけで急に恥ずかしく思えて、テーブルの上で指先を丸める。佐藤さんはお構いなしに勧誘を続ける。
「本来であれば4月のオーディションに合格した、中学生から高校生の十数人の皆様にご入学いただき、翌3月に開催される弊社のオーディションに向けて1年間のレッスンを行っております。ですが丸山様には特待生として途中参加に加え、入学金もゼロにさせていただきたいと思っております」
そこからお金の話とかオーディションの話が延々と続いたけど、今日芸能人になれる訳じゃないと分かった以上心は離れていく一方で、早くこの狭苦しいガラスの部屋から解放してほしかった。このことを2人になんて言えばいいんだろう?
「とにかく、丸山様には才能を感じております。ぜひ前向きな御検討をよろしくお願いいたします」
特待生だとか、そんなことを言われると悪い気もしないけど、結局、今回呼ばれたのがいいのか悪いのかも分からないまま、1階の自動ドアの外まで見送られていた。
ウイーンと自動ドアが開くと、さっきとは全く表情を変えた空気の冷たさに驚く。空が急激に暗くなるのをかき消すように、街は昼間以上の明るさを放ち出している。室内にいたのは30分くらいだったのに、頭は催眠術をかけられたようにぼんやりしていた。
数歩進んでチラリと後ろを見ると、佐藤さんがずっと頭を下げていたから、気まずくて小走りで建物から離れる。姿が見えなくなって息を大きく吸ったら、自然と大きな欠伸が出た。
駅の方向も分からないまま歩き出し、スマホを手に取ろうとカバンをまさぐる。スマホの四角い感触に、今日の結果の催促で溢れていそうな画面が頭に浮かび、反射的に手を引っ込めた。親のことを思うと真っ直ぐ帰る気にもなれず、あてもなくふらふらと歩き続けた。夜風に吹かれ、少しずつ頭がクリアになっていく。
芸能人になれる! とはしゃいだ手前、スクールの勧誘をされただけなんて恥ずかしくて2人に言えない。やっぱり、私なんかがアイドルになれる訳がなかったんだ。望んだ訳でもないのに、勝手に突きつけられた現実に息が苦しくなる。
脇に見えた公園に吸い寄せられ、水の止まった噴水のへりに腰掛けた。葉の擦れる音とベンチで寄り添うカップルの笑い声だけが聞こえる雰囲気は、心愛が好きなバンドの曲がよく合いそうだ。足元からにじり寄る寒さに、昼間暖かかったからと上着を持ってこなかったことを後悔する。
醒めきった心で、さっき渡されたA4サイズのパンフレットを取り出してぱらぱらと開いてみた。吹き出しで経験談を語るぱっちりした目の女性に、また一つ、小さな自信を失う。
特待生だなんて言っても入学金以外は払わなくちゃいけないし、実はこんなのよくある勧誘なのかもしれない。本当に事務所に入っちゃうようなこの人たちと私とじゃ、きっと住む世界が違うんだ。言い聞かせるようにめくる美男美女の笑顔と期待に満ちたページの最後、「卒業生からのメッセージ」の欄に見覚えのある顔を見つけ、吸い込まれるようにその文字を追った。
「僕の人生を変えてくれた場所です! ここでの出会い、経験が今の活動に繫がっています。迷ってるなら一歩踏み出そう!」
推しである、B5のレオ君だった。たった数十文字だったけど、1文字ごとに目が開かれていくような思いで、食い入るように何度も読み返した。レオ君があの空間にいた。あのダンススタジオで踊り、あの部屋でミーティングを重ねたかもしれない。
吹きつける風で髪が乱れても、視界にはそのパンフレットの一角しか映っていなかった。『一歩踏み出そう』ありきたりな言葉だけど、レオ君の声で再生された途端、今日スターターズに向かった時のようにまた心臓が高鳴り始める。自分でも笑えるくらい単純だけど、推しの存在は一瞬で私の心を奪った。私もレオ君がいた所にいたい!
それに、ここに通っていれば2人にも言い訳が立つし、最後のオーディションにさえ合格しちゃえば認めてもらえるかもしれない。呆れるほど前向きになった私は、しゃらしゃらと葉の擦れる音にも背中を押されている気がした。
「まあいいんじゃない? 部活もバイトもやってないんだから習い事の一つくらい」
パパの明快な一言で私の『スターターズスクール』通いが決まった。翌日スクールに電話をすると、3月のオーディションまで時間がないので、と次の月曜のレッスンから見学がてら参加することになった。習い事は小学校の頃に少しやっていたピアノくらいで、今から始めるなんて不安しかない。検索履歴は『高校生から習い事 遅い』『ダンス 未経験者』そんな言葉で溢れた。
質問の回答者も両親も「高校生から始めて遅いことなんてない」って口を揃えて言うけど、高校生って何かを始めるにはそんなに若くないと思う。それでもスマホの壁紙にいるレオ君のことを考えていれば期待も不安と同じくらい高まっていった。
そしてあの日、家に帰ってから恐る恐るスマホを見たけど、2人からの連絡は特になかった。
「とりあえず今日からレッスンを受けることになったの」
翌週の学校でようやくそう切り出せたのは5時間目の終わりだった。
「すご! まじで頑張ってね」「がんばれー」
変わらず応援してくれる真奈はともかく、心愛はスマホをいじったままで興味がなさそうだ。心愛は最近少し不機嫌な気がする。何かしちゃった? 自分の行動を必死に思い返してみても心当たりはなくて、ただ教室の隙間風にぎゅっと体を縮こめることしか出来なかった。
絶対に、オーディションに合格しよう。そうしたら今度こそ胸を張って2人に並べる。
学校が終わって、18時からのレッスンのため、制服のまま電車を乗り継いでスタジオに向かった。朝のニュースで本格的な冬が来ると言っていた通り、スカートを吹き抜けていく風は数日前よりうんと冷たく、這い上がるように太もものつけ根まで冷やされていく。
持参するよう言われた運動着と室内履きでパンパンの紙袋を提げて、再びあのビルの前に立った。陽が沈んでより存在感を増すその明るさにぎゅっと荷物を抱えてしまったけど、何度もイメトレした通り、エレベーターから降りてすぐ、受付の女性に元気に挨拶した。
「こんばんは! 丸山莉子です!」
黒のタートルネックを着た女性は「よろしくお願いします」とにこやかに案内してくれる。長い髪をヘアクリップで緩くまとめていて、気取っていないのにすごくおしゃれ。はらりと肩に落ちた数本の毛束さえも計算みたいで、素敵な大人の女性になんだかドギマギしてしまった。
施設のことやルールをざっくり説明してくれる背中をピッタリと追う。あちこち見たかったけど、キョロキョロしたらみっともないと思って目線だけで偵察した。「着替えはこちらです」と案内された女子更衣室では5人が着替えている最中で、すれ違いざまに視線を感じた。
「これ、名札です。レッスンの時は毎回つける決まりになっているので、卒業までなくさないように気をつけてくださいね。じゃあ着替えて準備が出来たらダンススタジオに来てください」
渡された名札は、クリアケースに入った名刺サイズの紙に『丸山莉子』と書かれていて、首から掛けられるよう黄色い紐が付いていた。
4桁の暗証番号付きのロッカーに荷物を置き、家にあったB5のライブTシャツと、左腿の付け根に『丸山』と名前の入った体操服の青いジャージに着替える。家にあった運動着はこれくらいしかなくて深く考えずに持ってきたけど、周りの子たちがピッタリとしたヘソ出しのトップスを着たり裾のたっぷりとした「ダンスっぽい」パンツを穿いているのを見て、検索履歴の「遅い」の文字が頭に蘇る。
今日は90分のダンスレッスンだ。ガラス張りのスタジオでは、十数名がストレッチをしていた。同じく透明なガラスの扉をそうっと開けて中に入る。この「総合アーティスト養成コース」は倍率も値段も1番高く、中学生から高校生まで通えるらしい。入学出来るだけでもエリート! なんて記事も前に見かけて悪い気はしない。
周りの面々が直接でなく鏡越しに、見定めるようにこちらを窺っているのが伝わる。緊張や不慣れが伝わらないように、壁にかけられた時計を眺めながら適当に首を伸ばしたり、足首をブラブラさせたりしながら開始時間を待った。
室内履きとして持ってきた体育館シューズの紐を両足とも結び直したとき、ダンスの先生らしきチャラい男性と、さっきの受付のお姉さんが入ってきた。目線がそちらに集中したところで、お姉さんが私を手招きしてこう切り出す。
「今日から参加することになった丸山莉子さんです。皆さんは是非先輩として色々教えてあげてくださいね」
「よ、よろしくお願いします」
しんとした広い部屋に、空調の音が大きく聞こえる。何の準備もしていなかったから、それだけ言って頭を下げるのが精一杯だった。突き刺さるような視線が痛い。
「じゃあアイソレからやっていきましょう。莉子は今日は適当に真似してみて」
30代くらいの、キャップを被った「いかにも」ダンサーな先生は、息の詰まる張りつめた空気を打ち消すかのようにパンパンと手を叩きレッスンを始めた。
後から知ったけど、アイソレっていうのはアイソレーションの略で、首とか胸とか、体の一部だけを動かすダンスの基本動作らしい。そんなことも分からないまま、ヒップホップの音楽に合わせて皆が「いつもの」練習を進めていく。私はとにかく必死に動きを真似するけど、やっぱり初心者の私が追いつけるわけもなく、焦りで視界はどんどんと狭くなっていった。
ふいに、体育のダンスの授業でうまく踊れずテンパっていたクラスの女の子を思い出す。言い出したのは、いつも通り心愛だった。
(続きはぜひ本書でお楽しみください)
書誌情報

書名:私の居場所はここじゃない
著者:安部 若菜
発売日:2024年12月06日
ISBN:9784041152867
定価:1,760円 (本体1,600円+税)
ページ数:208ページ
判型:四六判
発行:KADOKAWA
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322404001145/
★全国の書店で好評発売中!
★ネット書店・電子書籍ストアでも取り扱い中!
Amazon
楽天ブックス
電子書籍ストアBOOK☆WALKER
※取り扱い状況は店舗により異なります。
